突然の動悸や息苦しさに襲われ、「このまま倒れてしまうのでは」と感じた経験がある場合、それはもしかすると不安障害による症状かもしれません。
不安障害は過度な不安によって心身にさまざまな影響を及ぼす精神疾患で、動悸はその代表的な身体症状の一つです。
この記事では、不安障害で起こる動悸について詳しく解説します。
動悸が起こる原因や対処法、病院での治療方法などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
不安障害とは

不安障害とは過度な不安が長期間続き、日常生活に支障をきたす精神疾患の総称です。
誰にでも不安を感じる場面はありますが、不安障害ではその感情が強く持続し、心身にさまざまな症状を引き起こします。
代表的なものとして、『パニック障害』『社会不安障害』『強迫性障害』『全般性不安障害』などがあり、これらは厚生労働省など公的機関でも分類されています。
ここではこの4つの不安障害について解説しましょう。
パニック障害
パニック障害は、突然理由もなく強い不安に襲われる『パニック発作』を繰り返す病気です。
発作時には激しい動悸や息切れ、めまい、吐き気といった症状が10分以内にピークに達することが多く、命に関わるのではないかという強い恐怖を伴います。
一度発作を経験すると「また発作が起こったらどうしよう」と常に不安を抱えるようになる『予期不安』を抱えるようになります。
予期不安の影響で人混みや電車、エレベーターなど発作時に逃げられない場所を避けるようになり、生活の自由が大きく制限されるのもパニック障害の特徴です。
社会不安障害
社会不安障害は、人前に立つことや注目される状況に対して強い不安や恐怖を感じる障害です。
人と話す、視線を浴びる、食事や字を書くなどの場面で極度に緊張し、赤面や発汗、震え、吐き気といった身体症状が現れることがあります。
「恥をかくのでは」「失敗して笑われるのでは」といった恐れから、外出や人との接触を避けるようになり、次第に学校や職場に行けなくなるケースもあります。
放置すると自尊心の低下や学力低下を招くのみでなく、うつ病や引きこもりなどに発展することもあるため注意が必要です。
強迫性障害
強迫性障害は、「しないと不安」「確認しないと落ち着かない」といった強い不安から、同じ行動や思考を繰り返さずにはいられなくなる精神疾患です。
典型的な例として、手洗いを何度も繰り返す、火元や鍵の確認を何度も行う、数字や順番に強くこだわるなどがあります。
これらの強迫行為は本人も不合理なものだと理解していても、不安を和らげるために繰り返してしまいます。
その結果、日常生活や学業、仕事に支障をきたすことも多く、周囲の理解が得られず孤立することも珍しくありません。
全般性不安障害
全般性不安障害は、特定の出来事に限らず、あらゆることに対して過剰な不安や心配が6か月以上続く状態です。
例えば「病気になるのでは」「家族に何か起こるのでは」など、現実には起こっていない出来事に対しても強い不安を感じ、日常生活に支障をきたします。
不安感に加えて、落ち着きのなさ、疲労感、集中力の低下、イライラ、筋肉の緊張、不眠といった症状もよく見られます。
こうした症状の影響で、学校や仕事が続けられなくなることもある精神疾患です。
治療においては、認知行動療法や薬物治療が効果的とされています。
不安障害で動悸がする原因

不安障害では、強い不安や緊張が心と体に大きなストレスを与えることで、動悸といった身体症状が現れることがあります。
特に人前で話すことや外出、混雑した場所にいることに対して不安を感じると、自律神経のバランスが乱れ、交感神経が過剰に働く状態になります。
この交感神経の過剰な活動によって心拍数が急激に上がり、動悸として感じられるのです。
パニック障害では、突如として強烈な不安が襲い、同時に激しい動悸が起こる『パニック発作』がみられます。
また、「また動悸が起きたらどうしよう」という予期不安が強まり、さらにストレスが増して動悸が悪化するという悪循環に陥ることもあります。
ただし、動悸の原因がすべて不安障害とは限りません。
カフェインやアルコールの摂取、睡眠不足、または循環器疾患や内分泌疾患でも同様の症状が出る場合があります。
そのため動悸が頻繁に起きる、強い不快感を伴う、ほかの身体症状(息切れ、胸痛、めまいなど)もあるといった場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。
正確な診断を受けることで、不安障害による動悸かどうかを見極め、適切な治療に繋げられます。
不安障害で動悸などの症状が起きたときの対処法

不安障害で動悸などの症状が起きたときの対処法として、以下が挙げられます。
- 深呼吸をしてリラックスする
- 休息をとる
- 腹式呼吸をする
- リラクゼーション法を取り入れる
- 誘導イメージ法を試す
- カフェインやアルコールの摂取を控える
- 精神科や心療内科を受診する
ここでは上記7つの対処法についてそれぞれ解説します。
深呼吸をしてリラックスする
動悸や不安を感じたときは、まず深呼吸を意識してみましょう。
ゆっくりと呼吸を整えることで、過度に働いている交感神経の興奮を抑え、副交感神経を優位にする効果が期待できます。
深呼吸のポイントは鼻から大きく息を吸い込み、数秒間息を止めてから、口からゆっくりと息を吐き出すことです。
このとき自分の呼吸に意識を集中することで、不安にとらわれていた思考が一時的に遮断され、落ち着きを取り戻しやすくなります。
深呼吸は特別な道具や広い場所を必要とせず、どこでも実践できる簡単なリラックス法です。
動悸が始まりそうなときや不安を感じた瞬間にすぐに実践できるよう、日常的に練習してみてください。
休息をとる
動悸や息苦しさなどの不調が出たときは、無理に活動を続けず、まずは体と心を休めることが大切です。
座ったり横になったりして安静にすることで、自律神経の興奮が和らぎ、不快な症状が軽減しやすくなります。
また不安障害は慢性的なストレスや疲労の蓄積によって悪化する傾向があるため、日頃から意識的に休息をとることも大切です。
しっかりとした睡眠、食事の見直し、趣味や好きなことを楽しむなど、自分自身を労わる時間を確保することが不安の予防にもつながります。
自分の心と体の状態に目を向ける習慣をつけ、調子が悪いと感じたら早めに休むことを心がけましょう。
腹式呼吸をする
腹式呼吸は、不安症状の緩和に効果的な呼吸法の一つです。
これは胸ではなくお腹を使って呼吸する方法で、副交感神経が優位になり、心身をリラックスさせる効果が期待できます。
やり方は簡単で、まず背筋を伸ばして楽な姿勢になり、鼻からゆっくり息を吸いながらお腹を膨らませます。
その後、口から時間をかけて息を吐き、お腹をへこませるように意識しましょう。
この動作を数回繰り返すことで、心拍数の上昇が緩やかになり、不安感も軽減しやすくなります。
特に動悸が強く出たときや気分が高ぶっているときには、腹式呼吸を数分間行うことで落ち着きを取り戻せることが多いです。
日常的に練習しておくと、発作時に自然と取り入れられるようになります。
リラクゼーション法を取り入れる
不安障害の症状を和らげるためには、リラクゼーション法を取り入れるのが効果的です。
代表的な方法には漸進性筋弛緩法やアロマセラピー、軽いストレッチ、音楽、マインドフルネス瞑想などがあります。
特に漸進性筋弛緩法は、緊張状態にある筋肉を意識的に緩めることで、心身ともにリラックスしやすくなります。
こちらもやり方は簡単で、部位ごとに力を入れて数秒間保持した後、ゆっくりと筋肉を緩めて脱力感を感じるというものです。
これのみでリラックス状態へと移行しやすくなるため、症状が出た際には試してみるとよいでしょう。
また香りや音楽は脳に直接働きかけるため、気分転換や不安の軽減にも役立ちます。
自分に合ったリラックス方法を見つけて、日々の生活の中に取り入れていくことが重要です。
誘導イメージ法を試す
誘導イメージ法は、不安や緊張を和らげるためのリラクゼーション技法の一つです。
静かな環境で目を閉じ、心地よい風景や安心できる場面を想像することで、心身の緊張を解きほぐします。
例えば森の中で鳥のさえずりを聞きながらそよ風に包まれるイメージや、波の音が心地よく響く海辺にいるシーンなど、自分にとって安心できる情景を思い浮かべるのがポイントです。
イメージと呼吸を組み合わせることで、副交感神経を優位にし、動悸や焦燥感を落ち着かせる効果が期待できます。
初めはうまくイメージできないかもしれませんが、練習を重ねることで自然と心が落ち着きやすくなります。
カフェインやアルコールの摂取を控える
不安障害のある方は、カフェインやアルコールの摂取をなるべく控えることをおすすめします。
カフェインはコーヒーやエナジードリンク、紅茶などに含まれているもので、交感神経を刺激し、心拍数の上昇や不安感の増幅を招く可能性があります。
特に動悸が出やすい方にとっては、症状を悪化させる要因となり得るため、過剰摂取には注意が必要です。
またアルコールは一時的にリラックス効果をもたらすように思われがちですが、代謝が進む過程で自律神経が乱れやすくなり、かえって不安感や睡眠の質の低下を引き起こすことがあります。
これらの飲み物を習慣的に飲んでいた場合は、ノンカフェイン飲料やノンアルコール飲料への切り替えも検討してみてください。
精神科や心療内科を受診する
不安障害の症状が長期間続いている、または動悸や不安によって日常生活に支障をきたしている場合は、専門の医療機関を受診しましょう。
精神科や心療内科では、問診や必要な検査を通じて、不安の原因や重症度を正確に判断します。
治療には薬物療法や認知行動療法などがあり、症状の程度や本人の状態に合わせたサポートが行われます。
自分では「まだ大丈夫」と感じていても、つらさを抱えたまま放置していると不安がさらに悪化し、うつ病などの二次的な疾患につながる恐れもあるため注意が必要です。
また不安の感じ方には個人差があるため、つらいと感じた時点で早めに相談することが大切です。
専門家のサポートを受けることで、より効果的で安心できる治療が受けられます。
不安障害の病院での治療方法
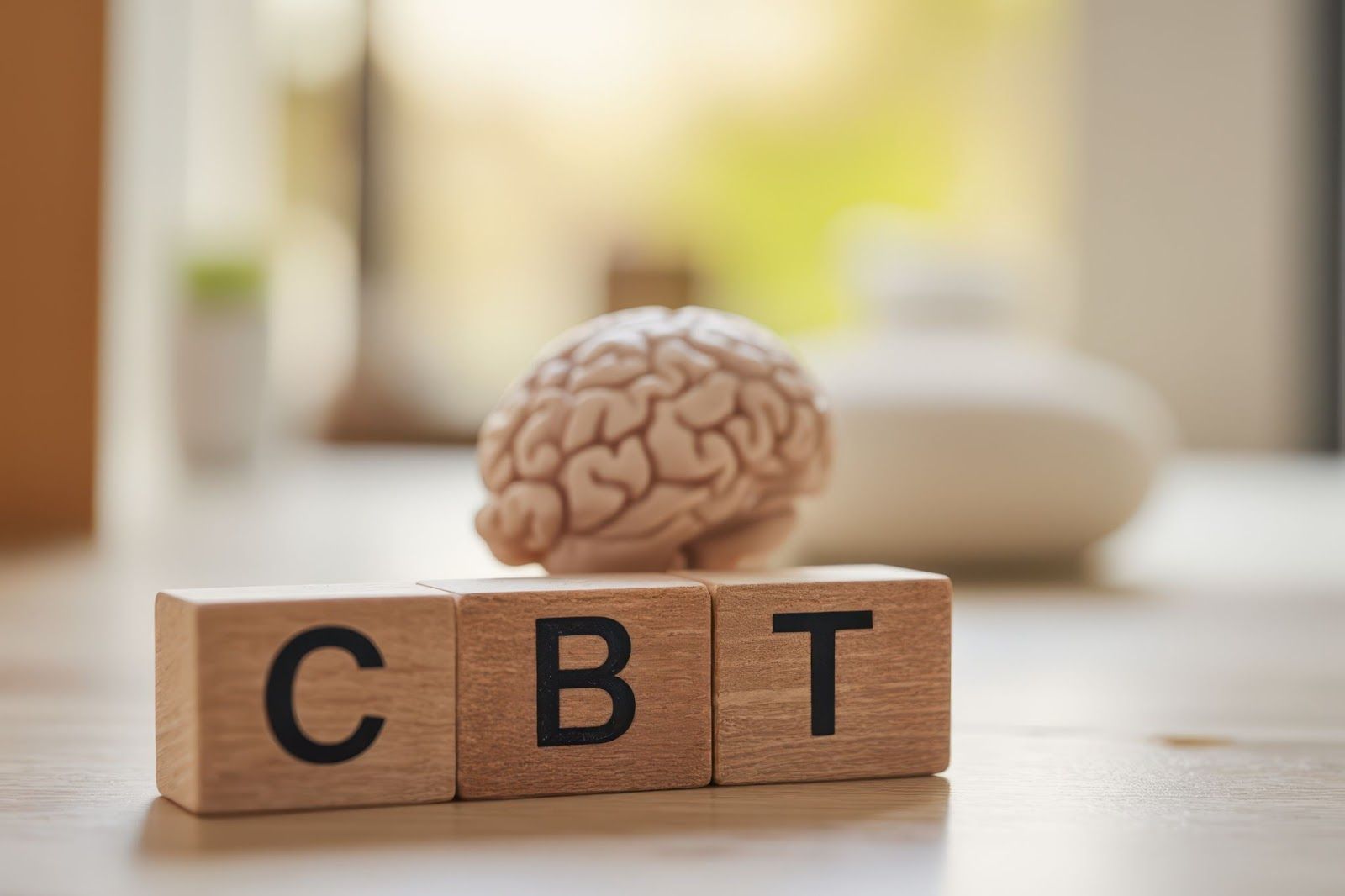
不安障害の治療では、主に『薬物療法』と『認知行動療法』の2つが中心となります。
症状の程度や本人の希望に応じて、どちらか一つまたは両方を併用して治療を行っていきます。
ここではこれら2つの治療方法についてそれぞれ解説しましょう。
薬物療法
不安障害の薬物療法では、主に抗うつ薬や抗不安薬、睡眠薬などが処方されます。
特に『SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)』と呼ばれる抗うつ薬は、不安障害にも効果があります。
SSRIは脳内のセロトニンの働きを調整し、不安や気分の落ち込みを和らげる作用がある薬です。
ただし効果が現れるまでに数週間かかることがあるうえに、服用初期には副作用が出ることもあるため、医師の指示のもとで正しく服用することが大切です。
また即効性のある抗不安薬は不安や緊張をすぐに和らげてくれる一方で、長期使用による依存のリスクが指摘されており、慎重に検討する必要があります。
薬のみに頼るのではなく、認知行動療法などの心理療法と併用することで、より効果的な治療が期待できます。
認知行動療法
認知行動療法は、不安障害において非常に効果が高いとされている心理療法の一つです。
この治療法は、不安を引き起こす「考え方のクセ」や「行動パターン」に焦点を当て、それらを現実的で柔軟なものへと変えていくことを目的としています。
特に不安障害の患者さんは極端なネガティブ思考を持ちやすく、それがさらなる不安を引き起こす原因となることがあります。
認知行動療法はこうした思考のパターンを客観的に捉え直し、状況に応じた対応力を高めていくものです。
また実際に不安を感じる場面にあえて身を置く『曝露療法』も取り入れることで、不安の感情が徐々に和らいでいくことを体験できます。
強い動悸を感じるときは病院の受診も検討しましょう
不安障害による動悸は、自律神経の乱れや強いストレスによって引き起こされますが、適切な対処や治療によって症状の改善が可能です。
動悸などの症状が現れたときは、深呼吸や腹式呼吸など、自分に合った方法を取り入れてみましょう。
症状がつらい場合は一人で抱え込まず、医療機関に相談することも大切です。
かもみーる心のクリニック仙台院では、予約当日の診療にも対応しています。
精神的・身体的症状に悩まされている方は、ぜひ当院までご相談ください。
