更年期に入ると心や体にさまざまな不調が現れ、「これまで通りに仕事ができない」と感じる方が増えてきます。
集中力が続かない、些細なことでイライラする、身体がだるくて出勤がつらいなど、その症状は多岐にわたります。
更年期と、責任ある立場や家庭との両立が求められる年代が重なり、負担はさらに大きくなりがちです。
この記事では、更年期障害で「仕事ができない」と感じる原因や症状について詳しく解説します。
自分でできる対処法もまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
更年期障害とは

更年期障害とは、女性ホルモン(主にエストロゲン)の分泌低下により、心身にさまざまな不調が現れ日常生活に支障をきたす状態のことです。
更年期は閉経をはさむ前後約5年間、計10年間(45〜55歳頃)を指し、この時期は女性のライフステージにおいて大きな変化を迎える時期でもあります。
症状の出方や重さには個人差があり、全く症状が出ない人もいれば、生活が困難になるほど強く出る人もいます。
更年期障害の主な症状は以下の通りです。
血管拡張・放熱症状 | 身体のほてり、のぼせ、発汗など |
身体症状 | めまい、動悸、胸の締め付け、頭痛、肩こり、しびれ、疲れやすさなど |
精神症状 | イライラや落ち込みなどの精神的な不安定さ |
このような症状の発現にはエストロゲンの減少のみでなく、仕事や家庭、介護といった心理的・社会的なストレスも関与しています。
さらに近年、加齢男性性腺機能低下症候群(LOH症候群)として、男性にも更年期障害に類似した症状が認められることが知られているため、男性でも油断は禁物です。
40代以降に男性ホルモン(テストステロン)が低下することで、疲労感やイライラ、性機能の低下などの症状が出ることがあります。
性別に関係なく、年齢とともに現れる体調の変化に気づいたときは、専門の医療機関に相談することが大切です。
更年期障害の「仕事ができない」と感じる主な症状
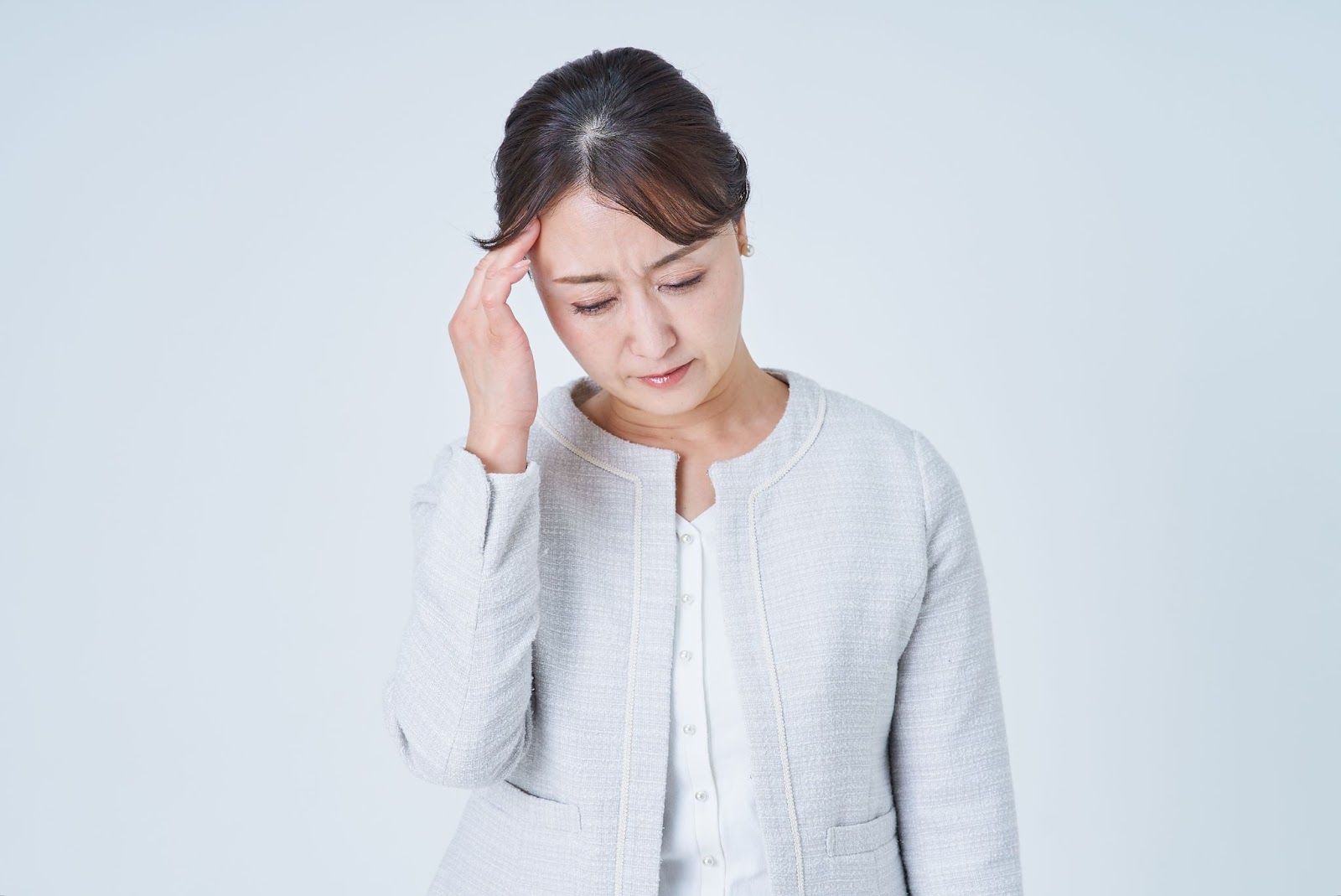
更年期に感じる主な症状として、以下が挙げられます。
- 仕事がつらいと感じる
- やる気が出ない・集中力が続かない
- 疲れやすくなる
- 気分が落ち込む
- 人と会うのが嫌になる
- 自律神経失調症状
- 身体的症状
ここでは上記7つの症状についてそれぞれ解説します。
仕事がつらいと感じる
更年期に入ると、これまで問題なくこなしていた仕事が急につらく感じることがあります。
特にミスが増えたり、作業に時間がかかるようになったりすると、「自分は仕事ができなくなったのでは」と不安になる方も少なくありません。
こうした変化の背景には、ホルモンバランスの乱れによる集中力や判断力の低下、自律神経の乱れによる体調不良などが関係しています。
例えば会議中に発言内容がまとまらなかったり、ミスをしたことに対して過剰に落ち込んだりするなど、精神的にも大きな影響が出ることがあります。
さらに家庭との両立が難しくなることも加わると、日々の業務そのものが負担になってしまうでしょう。
「職場に行くのがつらい」と感じたら、単なる疲れや性格のせいではなく、更年期症状の可能性を考えてみることが大切です。
やる気が出ない・集中力が続かない
更年期には、無気力や集中力の低下といった症状もよく見られます。
これはエストロゲンの減少によって、やる気や快感に関わる神経伝達物質であるドーパミンやセロトニンの分泌が低下することが一因とされています。
そのため仕事中も集中力が続かず、業務が進まなかったり、注意力が散漫になったりしてミスを繰り返してしまうことがあるのです。
以前は楽しめていた趣味や職場での会話にも興味が持てなくなることもあり、自分でも気持ちの変化に戸惑うことがあるでしょう。
こうした精神的な変化は、本人の努力では対処が難しく、周囲の理解や適切なケアが必要です。
疲れやすくなる
更年期には、肉体的にも極端に疲れやすくなることがあります。
洗濯や料理、通勤といった日常的な動作ですらぐったりしてしまうことがあり、仕事では長時間のデスクワークや立ち仕事がつらく感じられることもあります。
特に「休んでも疲れが取れない」「だるくて体が動かない」といった慢性的な疲労感は、更年期女性に非常に多く見られる症状です。
こうした状態では作業効率も下がり、職場での評価に影響するのではという不安にもつながります。
気分が落ち込む
更年期に起こる精神的な症状の中でも、気分の落ち込みはつらいものの一つです。
些細なことでクヨクヨしたり、涙もろくなったりするなど、感情のコントロールが難しくなることがあります。
また自分の発言や行動を過剰に反省してしまったり、「自分は必要とされていないのでは」といった否定的な思考に陥ることも珍しくありません。
さらに将来への漠然とした不安感が強まり、何事にも前向きになれない「更年期うつ」のような状態になる人もいます。
こうした気分の変動は、決して甘えや気の持ちようではなく、ホルモン変化による生理的な反応です。
そのため無理に気分を上げようとせず、まずは症状を理解し、必要に応じて医療機関の受診やカウンセリングの活用を検討してみましょう。
人と会うのが嫌になる
更年期に入ると、これまで普通にできていた人付き合いが急に煩わしく感じられるようになることがあります。
例えば職場でのちょっとした雑談や家族とのやり取りすら負担になり、「誰とも会いたくない」「話すのも面倒」と感じるようになるのです。
こうした心の変化は、ホルモンバランスの乱れが自律神経や感情に影響を及ぼすために生じると考えられています。
特にイライラや不安感が強まる時期には、相手のちょっとした言動にも過敏に反応してしまい、衝突したり気まずくなったりすることもあります。
対人関係のストレスが続くと出勤すら困難に感じてしまうこともあるため、無理せず一人の時間を持ったり、周囲に状況を説明して理解を得たりすることが大切です。
自律神経失調症状
更年期障害では、自律神経のバランスが乱れることにより、さまざまな不調が現れます。
代表的な症状は以下の通りです。
血管運動神経症状 | ホットフラッシュ(ほてり、のぼせ、発汗)、動悸、寒気、冷えなど |
胸部症状 | 胸痛、息苦しさなど |
全身的症状 | 頭痛、肩こり、めまい、疲労感など |
こうした症状は仕事中に現れると非常に厄介で、集中力が途切れたり、作業の中断を余儀なくされたりすることがあります。
さらに頭痛やめまい、極度の疲労感といった全身症状も加わることで、「もう働けない」と感じることも少なくありません。
このような症状は「怠けている」「気の持ちよう」と誤解されがちですが、れっきとした身体の不調であり、早めの対処が必要です。
身体的症状
更年期障害による身体的症状は多岐にわたり、仕事に支障をきたすケースが少なくありません。
代表的な症状として、以下が挙げられます。
運動器症状 | 腰痛、関節・筋肉痛、手のこわばり、むくみ、しびれなど |
消化器症状 | 便秘・下痢、吐き気、食欲不振、腹痛など |
皮膚粘膜症状 | 乾燥感、ドライアイ、湿疹、かゆみ・蟻走感など |
泌尿生殖器症状 | 性交障害、頻尿、排尿障害、月経異常、外陰部違和感など |
これらの症状が複数重なると、肉体的にも精神的にも限界を感じ、「もう仕事を続けられないのでは」と感じてしまうことがあります。
症状が続く場合は一人で抱え込まず、医療機関で相談することが大切です。
更年期障害で「仕事ができない」と感じる原因

更年期障害で「仕事ができない」と感じる原因として、以下の3つが挙げられます。
- ストレスによる影響
- 女性ホルモンの減少による自律神経の乱れ
- 女性ホルモンの減少によるセロトニンの減少
ここでは上記3つの原因についてそれぞれ解説します。
ストレスによる影響
更年期は、家庭でも職場でも多くの責任を担う時期と重なります。
子どもの受験や進学、親の介護問題など家庭内での負担が増える一方で、職場では中堅から管理職などの重要なポジションに就いていることも多く、精神的・身体的ストレスが蓄積しやすくなります。
こうしたストレスが続くと、自律神経の働きが乱れやすくなり、更年期障害の症状が強まる原因となるのです。
またストレスは睡眠にも悪影響を与え、眠れない・眠りが浅いといった状態が続くことで、日中の集中力や判断力が低下し、「仕事が手につかない」「何をしても疲れる」といった状態に陥りがちです。
これらの要因が複雑に絡み合い、本人の努力ではどうにもならない心身の不調を引き起こし、「仕事ができない」と感じるようになります。
女性ホルモンの減少による自律神経の乱れ
更年期に入ると、エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンの分泌が急激に減少します。
これにより、脳の視床下部や下垂体との間で行われていたホルモン分泌のバランス調整がうまくいかなくなり、自律神経の働きにも影響を及ぼします。
自律神経は体温調整・心拍・血圧・呼吸・消化など、生命活動に欠かせない機能を調整しているものです。
この神経が乱れることでホットフラッシュ(顔のほてりや大量の発汗)や動悸、めまい、息切れ、冷えなどさまざまな身体症状が現れ、仕事に集中できない状態になります。
また倦怠感やだるさといった症状が慢性的に続くと、些細な作業であっても大きな負担に感じられ、出勤や日常業務をこなすこと自体が難しくなることもあります。
女性ホルモンの減少によるセロトニンの減少
女性ホルモンの減少は自律神経の乱れのみでなく、脳内の神経伝達物質セロトニンの分泌にも影響を与えるとされています。
セロトニンは感情の安定や不安の抑制、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの材料となるなど、心身のバランスを整える重要な役割を持つものです。
更年期にセロトニンが減少すると、不安感の増大やイライラ、不眠、やる気の低下、集中力の欠如といった精神的な不調が顕著になります。
その結果、「やらなければいけないのに何も手につかない」「ミスが増えて自己嫌悪に陥る」といった状態になりやすく、仕事への意欲が著しく低下します。
「サボっている」「怠けている」と誤解されることもありますが、実際は脳内物質の変動により起こる症状であるため、周囲の理解と適切なサポートが必要です。
更年期障害で「仕事できない」と感じるときの対処法

更年期障害で「仕事ができない」と感じるときに効果的な対処法として、以下の4つが挙げられます。
- 職場の上司や同僚に相談する
- 適度に運動する
- 十分に睡眠をとる
- アロマやハーブティーでリラックスする
ここでは上記4つの対処法についてそれぞれ解説します。
職場の上司や同僚に相談する
更年期障害によって仕事がつらく感じるときは、信頼できる上司や同僚に相談してみましょう。
無理を重ねて我慢していると、心身の状態が悪化し、最終的には休職や退職に追い込まれてしまうこともあります。
症状を伝える際は、「最近集中力が落ちてきた」「体調が不安定である」など、現在の状況を整理して伝えると相手にも理解してもらいやすくなります。
事前にメモを準備するのもよいでしょう。
また勤務時間の調整や業務量の見直しなど、職場の支援を受けることで、仕事と家庭の両立がしやすくなります。
適度に運動する
適度な運動は、更年期症状の緩和に効果的です。
特にウォーキングやヨガ、ストレッチといった軽めの運動は、体への負担が少ないうえに、血流の改善や自律神経の安定、ストレス解消にもつながります。
朝のウォーキングは、日光を浴びることで体内時計が整い、睡眠の質の向上にも効果的です。
また日中の活動量が増えると、心身のだるさや気分の落ち込みも和らぎます。
激しい運動を無理にする必要はなく、自分の体調に合わせたペースで続けることが大切です。
十分に睡眠をとる
更年期に現れる症状を緩和するためには、十分に睡眠をとることが大切です。
まずは寝る前のスマートフォン使用を控えたり、寝室の照明や温度を整えたりするなど、眠りやすい環境づくりを心がけましょう。
リラックスできる音楽や軽い読書、ストレッチなども効果的です。
また日中に軽く体を動かすことで、自然な眠気を誘いやすくなります。
良質な睡眠をとることでホルモンバランスの安定や免疫力の向上にもつながり、身体的にも精神的にも健康的な状態を目指せます。
アロマやハーブティーでリラックスする
アロマやハーブティーなど香りの力を借りて心を落ち着ける方法も、更年期のセルフケアとしておすすめです。
例えばラベンダーやローズ、クラリセージなどのアロマオイルは、自律神経を整え、リラックス効果を高めてくれます。
アロマディフューザーやアロマキャンドルを使えば、自宅や職場でも気軽に香りを楽しめるでしょう。
またローズヒップやカモミール、オレンジフラワーなどのハーブティーには、気分を落ち着かせるだけでなく、身体の緊張を和らげる作用もあります。
眠る前に温かいハーブティーを飲む習慣をつけることで、睡眠の質を高める効果も期待できます。
ただしハーブティーは体質や状況によっては合わない種類もあるため、飲む前に必ず成分表や注意書きを確認しましょう。
更年期障害で仕事ができない場合は周囲のサポートを受けることも大切
更年期障害によって「仕事ができない」と感じるのは、心身のバランスが大きく変化する時期だからこそ起こる自然な反応です。
ホルモンの減少やストレス、睡眠不足など、複数の要因が重なり合って起こるため、無理をせず適切に対処することが大切です。
一人で抱え込まず、必要なサポートを受けながら更年期とうまく付き合っていきましょう。
かもみーる心のクリニック仙台院では、更年期障害に関するお悩み相談を承っています。
一人ひとりの状態にぴったりの医療を提供しているため、症状にお悩みの方はぜひ気軽にご相談ください。
