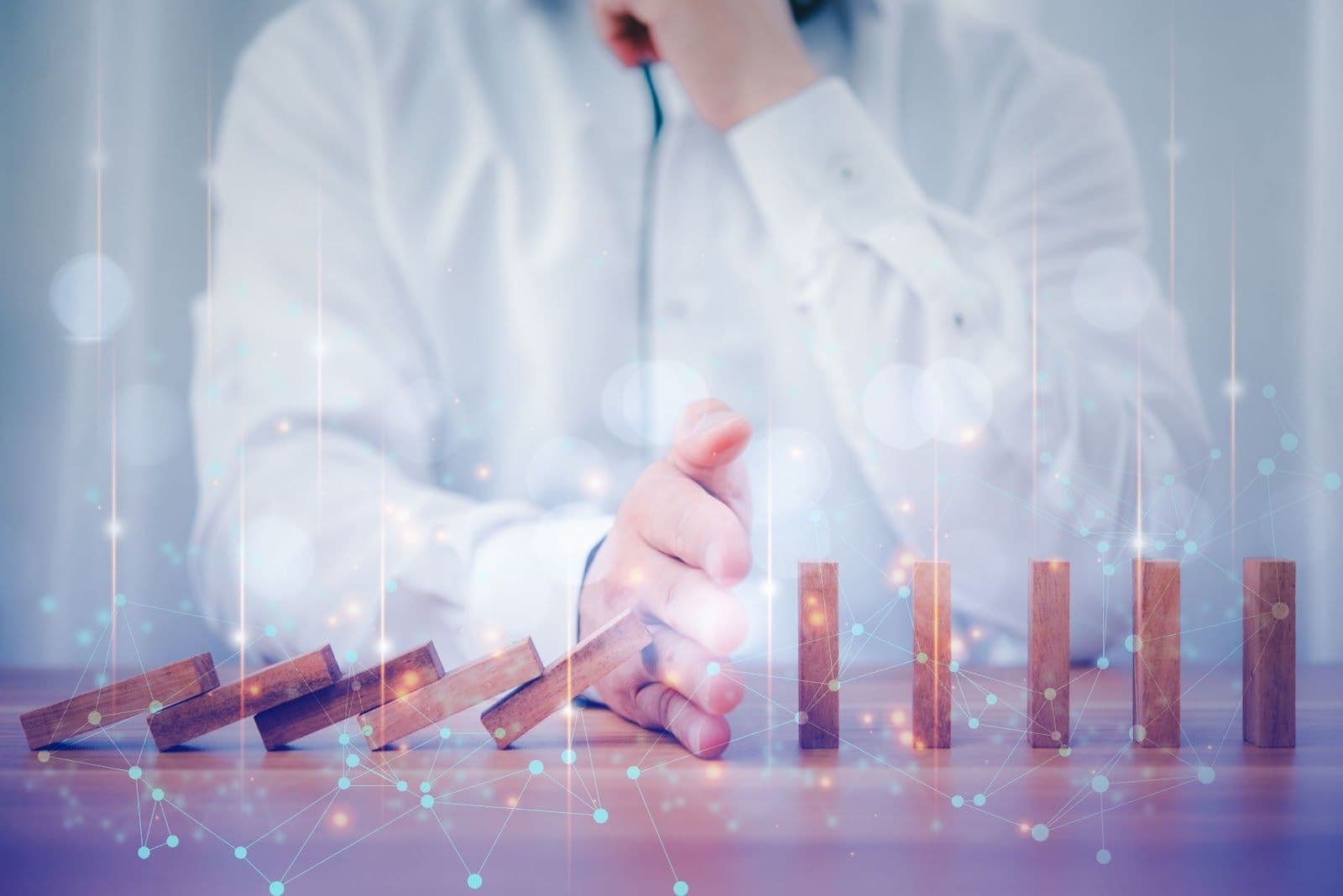うつ病は現代社会で一般的な精神疾患の1つですが、実際には「うつ病かもしれない」と感じても、素直に認められない、認めたくないと考える人が多く存在します。
その背景には社会全体に根強く残る誤解をはじめ、個人のプライドや責任感、症状の自覚の難しさなどが複雑に絡み合っています。
しかし、うつ病は放置するのではなく適切な治療を受けることが望ましい病気です。
治療を始めるためには、うつ病だと考えられる根拠や、実際にうつ病だと感じた時の対応法などを知っておくとよいでしょう。
この記事では、なぜうつ病を認められないのか、その理由や対処法などについて紹介します。
うつ病を認めることに不安のある人は、ぜひ参考にしてください。
なぜうつ病と認めない人、認めたくない人がいるのか

うつ病と認めない、認めたくない人がいる背景には、社会的な誤解や個人の性格、心理的な要因などが絡み合っているケースが考えられます。
ここでは、うつ病を認めにくい理由について代表的な要因を紹介します。
うつ病への誤解や偏見
うつ病を認めたくない人が多い要因として考えられるのは、社会的な誤解や偏見が根強く残っている点が挙げられます。
例えば、以下のようなことを聞いたことはありませんか。
- うつ病は甘え
- 気合いで治る などの誤解
このような考え方は誤解です。うつ病は甘えではなく、気合いで治るものでもありませんが、いまだに一部の人が信じてしまっているケースも見られます。
このような見方が本人や家族だけでなく、職場を含めた身近な環境にも浸透している場合、症状が現れても認めにくくなってしまいます。
また、「病院に行けば『弱い人』というレッテルを貼られるのではないか」と心配してしまい、自ら受診をためらう例も多いです。
プライドや責任感からの否定
うつ病を認めない理由のひとつとして、本人のプライドや責任感も挙げられます。
真面目な性格や完璧主義の方の場合、自分に厳しく振る舞った結果、体調や心の異変を見過ごしやすくなることがあります。
特に、普段から周囲に頼られたり期待されたりしている人ほど、「自分は弱くない」「努力家で忍耐力がある」と思い込むことが多いです。
また、仕事や家庭などで大きな責任を担っている場合、「こんなことで休んだら迷惑だ」と考え、自分の不調を否認してしまうことも少なくありません。
このような心理状態が長引くと、ますます病気を認めにくくなり、適切な治療が遅れてしまいます。
病気であることを認めたくない
うつ病と診断されること自体を心配する人も少なくありません。
例えば、次のような考えが見られます。
- うつ病だと分かったら職場での評価が下がるという不安
- 友人や知人に知られたくない など
キャリアや人間関係への影響を強く心配する人は、うつ病と診断されることを敬遠する傾向があります。
前述したように、うつ病への理解が乏しい環境であるほど、その不安は増すでしょう。
また、治療が長期化するイメージがある人の場合、「うつ病と向き合うのは人生が大きく変わる」と感じるのも特徴のひとつです。
このような不安が重なると、症状があっても「自分は違う」と否定し、必要な支援に繋がりにくくなる恐れがあります。
自覚の難しさ・症状の気づきにくさ
うつ病は症状を自覚しづらい特徴があるため、初期の段階では自分でも気付かず、自覚症状が出た時には悪化していることも多い病気です。
例えば、以下のような症状はうつ病のサインです。
- 気分の落ち込み
- よく眠れない
- 身体が重い
- 食欲がない など
うつ病ではこのような症状が身体的にだけではなく心にも現れやすいですが、「疲れや体調不良だ」と考えて、うつ病の兆候を見逃してしまう人もいます。
しかし、こうした変化はうつ病の代表的な症状であり、気付いたら早めの受診が推奨されています。
また、うつ病の症状は個人差が大きく、本人が「自分はまだ大丈夫」と思い込みやすい点もあります。
そのため、周囲から指摘されてもピンとこない場合や、受診のきっかけをつかめずに時間が経過するケースも多いです。
気付きにくさが、うつ病の自覚や対応の遅れに関わっているといえます。
うつ病を認めない・認めたくないことで起こる問題

うつ病を認めない、認めたくない場合には、さまざまな問題が生まれやすくなります。
ここでは、うつ病を認めなかった場合に生じる問題について詳しく紹介します。
症状の悪化と慢性化
うつ病を認めずに治療を受けない場合、症状が徐々に進行しやすくなります。
治療のスタートが遅れることで、以下のような症状が深刻化・慢性化してしまいかねません。
- 抑うつ状態
- 不眠
- 意欲低下 など
このような症状の深刻化は、日常生活や仕事、学業などへの影響も大きくなります。
慢性的なストレスや精神的な負荷が長期間続けば、うつ病はさらに重度化し、回復までの期間も長くなりやすいため、早期の受診が必要です。
治療しない期間が長くなるほど深刻化のリスクが高まります。
できるだけ早期に受診し、診断を受けて、適切な治療や環境の改善、支援の申請などにつなげましょう。
周囲とのトラブル・誤解
うつ病を隠そうとしたり、認めない態度を取り続けたりすることで、家族や職場との関係悪化につながるケースもあります。
例えば、家族は本人の変化に戸惑い、どう接すればよいか分からなくなり、お互いに不満や不安が蓄積されていくことも多いです。
また、職場では「怠けている」「やる気がない」と誤解され、信頼関係の損失や孤立を招くことがあります。
このような悪循環が続くと、心の負担がさらに大きくなり、症状の悪化にもつながります。
誤った認識が、コミュニケーションの障壁となってしまいかねません。
このような状況は、本人の苦しみが正しく理解されないまま人間関係が悪化しやすくなる恐れがあります。
早期の受診・診断でうつ病を自覚して、必要な説明や環境調整を行うことは、本人だけではなく、家族や周囲の人にとっても大切です。
仕事・生活の困難など社会的な心配
うつ病が進行した場合、仕事のパフォーマンス低下や長期欠勤、離職などの問題が生じる恐れがあります。
日常生活でも家事が手につかなくなったり、社会活動への参加が難しくなったりすることが少なくありません。
収入減少や経済的不安につながり、生活全体が不安定になる原因です。
また、このような社会的な困難が長引くと、本人の自己評価も低下しやすくなり、外出や社会参加をためらって、社会とのつながりが一層薄れてしまいかねません。
うつ病を認めず、生活面での支援や適切な配慮が得られないままだと、さらに孤立感が強まってしまうでしょう。
十分なサポートを受けられず、孤立や自傷・自殺につながることも
うつ病を周囲に理解してもらえないまま過ごすと、必要な支援やサポートから遠ざかってしまうことがあります。
その結果、本人は1人で苦しさを抱え込みやすくなり、孤立や絶望感が増してしまいやすいです。
支援が得られない状況が続くことで、自傷や自殺といった深刻なリスクが高まる恐れも否定できません。
早い段階でうつ病の診断を受け、周囲と協力しながら専門的な支援につなげることが、症状の悪化や深刻な事態の予防に効果的です。
そのためには、本人の積極的な受診のほか、社会全体でうつ病への正しい理解を広めることが大切でしょう。
「うつ病かも」と思ったらしてほしいこと

「うつ病かもしれない」と感じた時には、早い段階で客観的に状態を把握し、適切なサポートや医療につなげることが重要です。
ここでは、セルフチェックや専門家への相談、周囲のサポート、利用できる公的支援などについて紹介します。
セルフチェックで受診のきっかけを
うつ病の兆候に気付いたら、まずはセルフチェックを行い、自分の状態を把握しましょう。
セルフチェックシートは複数の種類がありますが、厚生労働省では簡易抑うつ症状尺度(QIDS-J)を採用しており、使用しているメンタルクリニックも多いです。
QIDS-Jは16項目のセルフチェック式でうつ病の状態を評価し、受診や治療に役立てる方法として注目されています。
睡眠や気分、食欲を始め、多方面からのチェックが可能で、いずれも回答が難しいものではないため気軽に受けてください。
ただし、以下の点には注意しましょう。
- セルフチェックは正確な診断ではない
- 正しい病名や状態は必ず専門医の診断を受ける
セルフチェックはあくまでひとつの目安です。受診のきっかけとして使用しましょう。
専門家に相談する
うつ病が疑われる場合、精神科や心療内科など専門家への相談が望ましいです。
専門医の診断では、医師による丁寧な問診や心理検査が行われ、セルフチェックでは分からなかった症状の背景まで把握できます。
また、受診に対して「診断されたら終わり」と考える必要はありません。
実際には診断がつくことで症状の原因が明確になり、必要な治療や社会的支援につなげやすくなります。
専門家のサポートを受けることにより、薬物療法やカウンセリングなど、自分に合った回復へのステップが見えてきます。
受診に不安を感じる場合もあるかもしれませんが、心配しすぎずに一歩を踏み出しましょう。
周囲の気づきや声かけで意識したいこと
うつ病が疑われる人が身近にいる場合、周囲の適切なサポートが回復につながります。
以下のような普段と違う様子が見えたら、「もしかして」と観察してみましょう。
- 感情の起伏が激しい、または無気力
- 大幅な食欲の増減
- 遅刻や欠席の増加 など
このような状態に気付いても、本人を否定したり「頑張って」と無理に励ましたりする声かけは避けましょう。
大切なのは、「最近どう?」など負担をかけない自然な会話を心がけ、本人の気持ちを否定せずに話を聞く姿勢です。
また、状況に応じて「心配している」「困ったら相談してほしい」と伝えることで、本人が1人で抱え込まずに済みます。
受診は強引に勧めるのではなく、本人のペースや安心感を尊重し、「受診しようかな」と思える環境を整えてあげましょう。
職場の制度や公的なサポートも活用を
うつ病の症状が仕事や生活に影響を与えている場合、職場での配慮や公的な支援を積極的に利用しましょう。
職場では産業医や上司、人事担当者などに相談し、業務の調整や休職制度の活用を検討してください。
また、精神保健福祉センターや地域包括支援センター、電話相談などの公的な支援窓口も活用できます。
相談機関では、医療や生活上のアドバイス、家族や同僚への支援の仕方なども提供されています。
自分1人で抱え込まず、適切なサービスや周囲のサポートを組み合わせることで、生活への負担を軽減しながら回復を目指していきましょう。
うつ病の回復までのステップ

うつ病には『急性期』『回復期』『再発予防期』の3つのステップがあり、各ステップで現れる特徴や必要な対応が異なります。
以下に、それぞれのステップにおける特徴や対応法などをまとめました。
段階 | 主な特徴 | 本人・家族・支援者の対応 |
|---|---|---|
急性期 | 強い抑うつ気分や意欲低下、日常生活が困難になる。 | 無理をせず休養を最優先。安心できる環境で過ごす。主治医の指示に従い、薬物療法やサポートを受ける。 |
回復期 | 症状が徐々に改善し、活動意欲が戻り始める。 | 少しずつ日常生活や社会活動を再開。生活リズムを整え、過労や無理は避ける。主治医や支援者のアドバイスを受けながら、段階的に負担を増やす。 |
再発予防期 | 体調が安定し社会生活を維持できる。 | 規則正しい生活やストレス対策を意識。定期的な通院・カウンセリングを続ける。無理せず体調変化を早めに相談する習慣を持つ。 |
急性期や回復、再発予防期に至るまでの期間には個人差があります。
医師の指導に従い、通院を継続しながら、ゆっくり心身を癒しましょう。
まとめ
うつ病を認めたくない、認めないままでいると、症状や人間関係の悪化、生活全体への深刻な影響が広がりやすくなります。
早い段階で客観的なセルフチェックを行い、必要に応じて専門家の診断や周囲のサポートを活用し、回復を目指しましょう。
うつ病には回復までに3つのステップがあり、それぞれの時期に適した対応が重要です。
自分や身近な人の変化を正しく理解しながら、無理をせず、適切な治療と支援を続けていきましょう。
オンライン診療・オンラインカウンセリングの『かもみーる』では、「自分がうつ病かどうか分からない」「認めることに抵抗がある」という方にもご相談いただけます。
オンラインならではの柔軟性や手軽さ、24時まで診察可能な態勢など、「もしかして」と思った時に受診しやすい環境を整えているため、お気軽にご連絡ください。
対面診療は『かもみーる心のクリニック(東京院)(仙台院)』で受けていただけます。
▶カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶新規会員登録はこちら