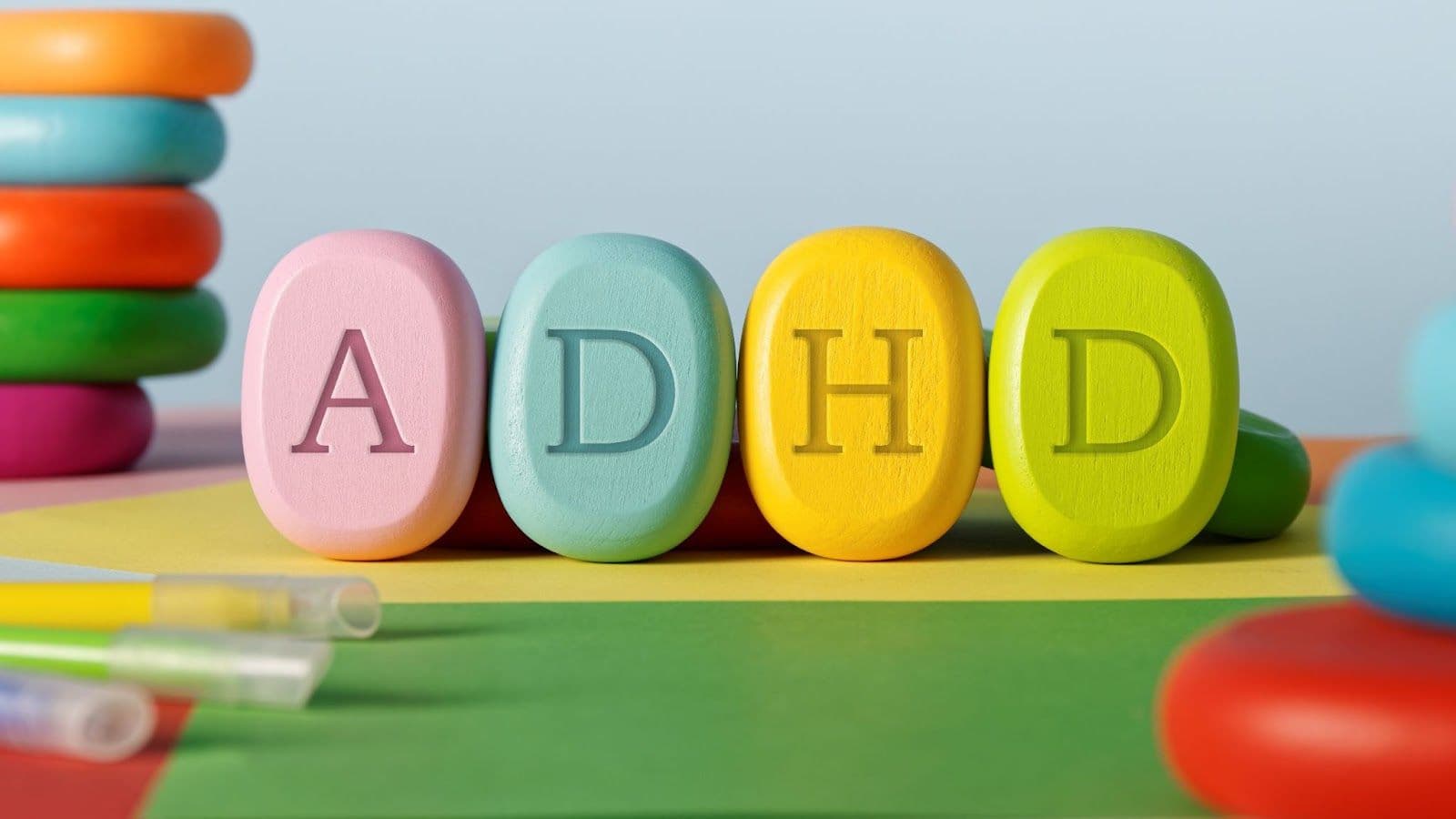ADHD(注意欠如・多動症)は、発達障害に分類される神経発達症の一種であり、「不注意」「多動性」「衝動性」の3つの特性が見られます。
これらの特性は生活や学習、人間関係に幅広い影響を及ぼすことも多く、特に多動性は、過剰な動きや落ち着きのなさとして現れ、家庭や学校での支援が重要になることも少なくありません。
ADHDについての概要や専門的な面について知っておけば、適切な対処に結びつけやすくなるでしょう。
この記事では、ADHDの定義や多動性の特徴をはじめ、具体的な支援方法などを紹介します。
ADHDについて疑問や悩みのある人は、ぜひ参考になさってください。
ADHDとは?
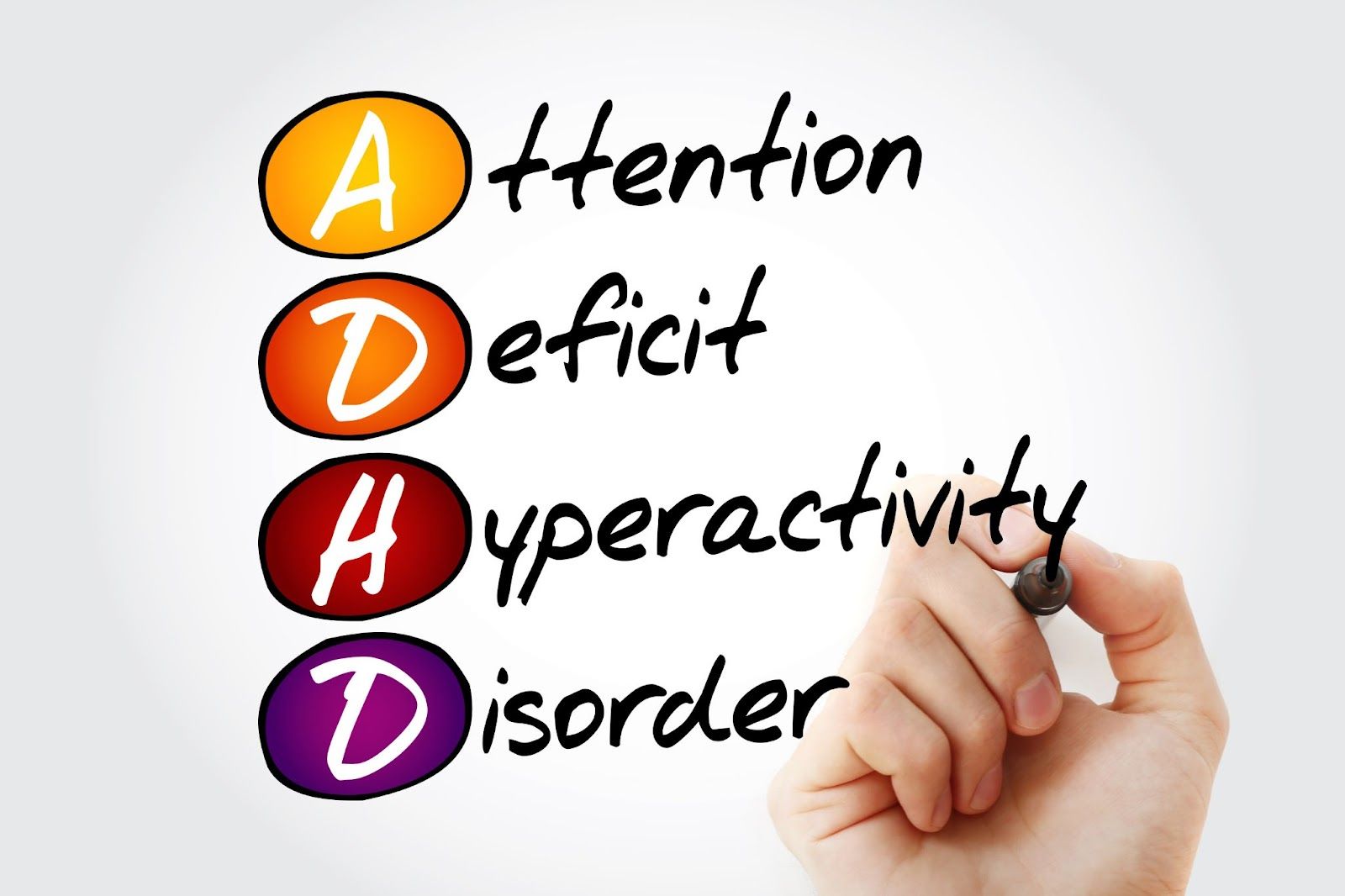
ADHD(注意欠如・多動症)は、子どもから大人まで幅広い年齢層で見られる発達障害のひとつです。
ここでは、ADHDの定義や症状の分類、他の発達障害との関係、発症傾向や成長による変化などについて詳しく紹介します。
ADHDは発達障害の一種
ADHDとは「注意欠如・多動症」を指し、神経発達症群のひとつに分類される障害です。
医学的には先天的な脳機能の特性が関係していると考えられており、乳幼児期から症状が確認できるケースもあります。
成長とともに環境への適応は進んでも、症状が完全に消えるわけではないため、特性を理解し、必要であれば支援を受けながら生活していくことが大切です。
ただし、成長するにつれて症状が弱まることもあるため、ご家族や周囲の観察を通し、一人ひとりの状態に合わせた対応が求められます。
主な特性「不注意」「多動性」「衝動性」
ADHDで知られることの多い特性は「不注意」「多動性」「衝動性」の3つです。それぞれ、以下のような特徴が代表的です。
不注意
- 集中が続かずミスが多い
- 忘れ物や紛失が頻繁に起こる
- 整理整頓が苦手
多動性
- 落ち着いて座っていられない
- 手足を動かし続ける
- 静かに遊ぶことが苦手
衝動性
- 思ったことをすぐ口に出す
- 順番待ちが苦手
- 他人の話に割り込みがち
特性の現れ方には個人差があるため、ADHDと診断されても行動パターンや困りごとの内容はそれぞれ異なります。
ADHDとほかの発達障害の関係
発達障害には複数の種類があり、ADHDのほか、自閉スペクトラム症(ASD)などが含まれます。
ADHDとほかの発達障害は同時に見られることもあり、例えばASDとADHDを併せ持つ人も少なくありません。
こうした併存のケースでは、単独の障害とは異なる支援が必要になる場合があります。
なお、発達障害は生まれつきの脳の働き方に基づくものであり、本人の性格やしつけの問題ではありません。周囲はそのような点を理解し、適切な対応を取ることが大切です。
発症頻度と男女差
ADHDは、学童期の子どものおよそ3〜7%に見られ、一般的に男児の方が女児よりも多い傾向にあります。
これは、男児では多動性や衝動性の症状が目立ちやすく、早期に気づかれることが多いためです。
一方、女児では不注意が主な特徴となるケースが多く、行動が目立ちにくいため見過ごされやすい傾向がある点に注意しなければいけません。
また、成人期には約2.5%の人にADHDがあるとされています。
症状の表れ方は年齢や性別により異なるため、診断や支援には個別の視点が求められます。
成長に伴う症状の変化
ADHDの症状は、成長とともにその表れ方が変化します。
幼児期では「走り回る、騒ぐ、順番が守れない」といった行動が目立ちやすく、小学校に上がると「授業中の集中困難や忘れ物の多さ」などが問題になります。
中高生になると、「勉強への集中が続かない、提出物の管理ができない、人間関係での衝突」といった課題が多いです。
さらに成人になると、「対人関係や仕事での計画性、時間管理の難しさ」として現れることが多くなります。
ADHDにおける多動性とは?特徴や影響について

ADHDにおける多動性は、日常生活や対人関係、学習などの面で、年齢や場面を問わず、広範囲に影響する特徴のひとつです。
ここでは、ADHDにおける多動性について紹介します。
多動性とは?定義と行動パターン
ADHDにおける多動性とは、年齢や場面に不適切なほど活動的になったり、身体を常に動かしていたりする状態を指します。
例えば、授業中や食事の場面でも落ち着いて座っていられない、手足を常に動かす、突然走り出すといった行動です。
また、静かに遊ぶのが難しい、周囲の注意を引くような行動を繰り返すなど、日常生活の中でも目立ちやすい傾向があります。
本人の意思や努力で制御するのが難しいため、療育や治療によるフォローが大切です。
ADHDのタイプと多動性の関係
ADHDは主に「不注意優勢型」「多動・衝動優勢型」「混合型」の3つのタイプに分類されており、それぞれ多動性の現れ方に違いがあります。
不注意優勢型
不注意が目立つ
多動・衝動優勢型
多動性や衝動性が目立つ
混合型
不注意優勢型、多動・衝動優勢型を併せ持つ
「混合型」が多い傾向にありますが、決してすべての人が同じ現れ方をするわけではありません。不注意優勢型のみの人もいれば、多動・衝動優勢型のみの人もいます。
一人ひとり症状が違うため、気になる人は専門家の診断を受けることをおすすめします。
大人のADHDにおける多動性の現れ方
成人のADHDでは、子ども時代のような目立つ身体的な多動性は減少することが多いですが、完全になくなるわけではありません。
代わりに、以下のような形で現れる場合があります。
- 内面的な落ち着きのなさ
- 多弁である
- 同じ動作を繰り返す
- スケジュール管理が苦手 など
社会人になると、こうした多動の傾向は職場での集中力低下や対人関係の摩擦につながりかねません。
ADHDと思われる症状で悩んでいる場合は必要な支援を受けることを検討し、よりよい社会生活の基盤を整えましょう。
ADHDの診断と多動性の評価方法

ADHDの診断では、医師による問診や観察に加えて、家庭・学校・職場などでの困りごとの把握と家族からの情報提供も重要です。
ここでは、ADHDの診断の流れや、多動性の評価方法などについて紹介します。
医療機関での診断の流れ
ADHDの診断は、医療機関での問診を中心に進められます。
まずは保護者や本人への聞き取りが行われ、生活環境や困りごとの背景を把握します。
その後、診察や心理士による行動観察、必要に応じたスクリーニング検査などが実施され、総合的に診断されるという流れです。
一度の診察だけで判断せず、時間をかけて丁寧な評価を行うことが基本です。
医療機関との信頼を築く機会としても有効なため、緊張しすぎず、分からないことは遠慮なく質問するなど、できるだけリラックスしながら臨んでください。
多動性を含む症状評価の方法
ADHDの診断では、DSM-5やICD-10という国際的な診断基準が使用され、多動性・不注意・衝動性の有無や程度が確認されます。
具体的に重点が置かれるのは以下の点です。
- 年齢や発達段階に応じた行動を基準に照合する
- 少なくとも複数の環境(家庭や学校、職場など)で持続的に現れている
チェックリストや質問票を通じて、行動の頻度や社会生活への影響も評価されます。これらの情報をふまえ、医師が家族と相談しながら慎重に診断します。
誤診や見過ごされるケースもある
ADHDはほかの精神的・発達的な問題と症状が似ているため、誤診や見過ごしが起こる可能性があります。例えば、自閉スペクトラム症や不安障害は区別が難しい代表例です。
また、多動性が目立たないタイプでは診断が遅れるケースもあります。
特に女児は不注意型が多く、多動的な行動が目立ちにくいため、周囲に気づかれにくいことも多いです。
診断時に確認される日常生活での困りごと
ADHDの診断では、家庭や学校、職場など日常生活の中でどのような困りごとがあるかを具体的に確認します。例えば以下のような点に注目されることが多いです。
- 約束を守れない
- 片付けが苦手
- 集中困難
- 忘れ物が多い
- スケジュール管理が難しい など
このような情報は本人だけでなく周囲からも集められることがあり、より正確な診断の参考として使用されます。
また、人によって「家庭・職場・学校」など、環境ごとに困難を感じるシーンが異なる場合も多いため、一人ひとりの状況に応じた確認が必要です。
家族の協力と観察の重要性
ADHDの診断には、家族による観察や協力が不可欠です。
本人が自覚しにくい行動の変化や問題点が、周囲の目によって初めて明らかになるケースもあるためです。
特に多動性のような行動面の特徴は、家庭での日常的な様子を知る家族の証言が重要です。
医療機関では、家族や近しい人から具体的なエピソードを聞き取ることで理解を深め、医師による適切な診断へつなげます。
ADHDの多動への対応・支援

ADHDの多動性に対する支援では、日常生活・学校・職場など場面ごとの特性に合わせた工夫や環境調整、医療・心理的サポートを適切に組み合わせることが効果的です。
ここでは、ADHDによる多動に対する対応や支援について紹介します。
日常生活での関わり方の工夫
ADHDのある子どもや大人との関わりでは、日常生活の中で肯定的な声かけや明確なルール設定が有効とされています。
例えば、「静かにしなさい」ではなく「小さい声で話そう」といった具体的な指示が伝わりやすく、安心感にもつながります。
また、成功体験を積み重ねられるようなサポートが重要です。望ましい行動に注目して褒めることにより、モチベーションが維持されやすくなります。
環境調整による支援の重要性
ADHDの多動性に対する支援では、不安や混乱を軽減しやすいよう、環境の工夫が大きな役割を果たします。例えば、以下のような工夫は取り入れやすいでしょう。
- 余計な刺激を減らすために席を壁側にする
- 必要な物だけを机の上に置く
- 1日のスケジュールを視覚的に分かるようにする
刺激を減らしたり、スケジュールの見通しが立ちやすくなったりすることで、不安や混乱を軽減しやすくなります。
集中しやすい環境を整えることは、多動性による逸脱行動の抑制にもつながるでしょう。本人の特性に合わせて、柔軟な環境調整を意識してみてください。
医療・心理面でのサポート
医療的・心理的なアプローチも、ADHDの支援の一つです。主に以下のような方法が代表的です。
医療面
中枢神経刺激薬などによる薬物療法
行動の安定化に効果
心理面
カウンセリングや行動療法
感情のコントロールや適応スキルの向上
また、医師やカウンセラーといった専門家から、本人や家族にアドバイスや情報を提供することにより、安心感を生み出すことも期待できます。
このような支援は一過性のものではなく、発達段階や環境の変化で対応を変える必要があるため、医師と相談しながら調整していきましょう。
大人のADHDへの支援方法
大人のADHDに対しては、職場環境における配慮と就労支援が重要です。例えば、以下のような工夫例があります。
- 業務の優先順位を明確にする
- メモやリマインダーを活用する
- 静かな作業スペースを確保する など
このほか、支援機関による就労支援も活用されており、具体的な課題の整理や対人関係の支援が提供されます。
症状の度合いによっては、一般枠から採用枠への見直しを検討し、働き方を変えるのもよいでしょう。
こうした支援は職場への定着を促進し、本人の能力発揮につながることが期待されます。
ADHDかも?と思ったら早めの相談が大切
ADHDは、本人の特性を尊重しながら、生活環境や対人関係を整える考えが求められます。
肯定的な声かけやルールの明確化、合理的配慮と連携体制など、周囲の理解を得ながら環境を整えていきましょう。
医療面や心理面からのサポートや、職場での工夫、専門機関による支援の活用によって、ADHDの症状による困難を解決しやすくなります。
このような支援を行うためには、医療機関で診断を受け、本人の状況や年齢に応じて柔軟・適切な対応が必要です。
オンライン診療・オンラインカウンセリングの『かもみーる』では、医師や有資格の心理士による治療やアドバイスの提供が可能です。
また、対面診療をご希望の方は、『かもみーる心のクリニック(東京院)(仙台院)』でもご相談いただけます。
ADHDにお悩みの方は、お気軽にご相談ください。