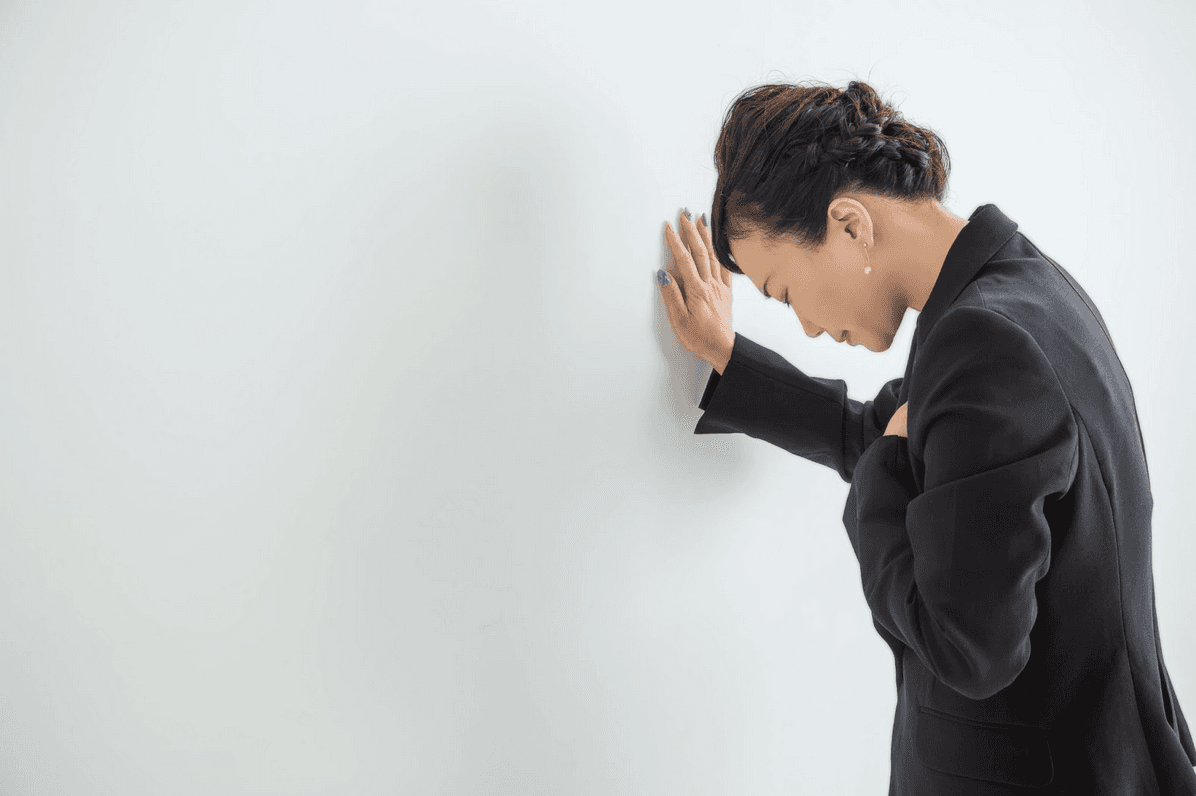「息がうまく吸えない」「胸が締めつけられるように苦しい」といった息苦しさを感じた経験がある人は少なくないでしょう。
このような症状は精神的なストレスのみでなく、精神疾患あるいは身体疾患が原因で引き起こされることもあります。
この記事では、息苦しさの原因について詳しく解説します。
考えられる病気や自宅でできる対処法などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
息苦しい状態とは?

息苦しいとは、空気をうまく吸い込めなかったり、胸やのどに圧迫感を覚えたりする症状を指します。
医学的には『呼吸困難』と呼ばれ、症状の出方や感じ方は人それぞれです。
「胸が締めつけられる」「のどが詰まった感じがする」「息が浅い」「呼吸が追いつかない」など、さまざまな表現がされます。
息苦しさにはいくつかのタイプがあります。
例えば運動後などに起こる息切れ、横になると苦しくなる起座呼吸、動悸に伴う息苦しさ、そして突然呼吸が苦しくなる急性の呼吸困難などです。
これらの症状は単なる疲労のみでなく、肺や心臓の病気、神経や筋肉の異常などが関係していることもあります。
息苦しいと感じたときは、その状況やタイミング、症状の程度をよく観察することが大切です。
安静にしていても改善しない、座った方が楽になる、顔色が悪い、手足に力が入らないなどの症状がある場合は重大な疾患が隠れている可能性があるため、早めに医療機関で相談しましょう。
息苦しいと感じる原因

息苦しいと感じる主な原因は3つ挙げられます。
- 精神的ストレス
- 精神疾患
- 身体疾患
ここでは上記3つの原因についてそれぞれ解説します。
精神的ストレス
息苦しいと感じる大きな要因の一つとして、精神的ストレスが挙げられます。
緊張や不安を感じると呼吸が浅く速くなり、空気をうまく吸い込めない感覚が生じます。
このような状態が長く続くと、呼吸の乱れが繰り返されるようになり、慢性的な息苦しさに悩まされることがあるため注意が必要です。
また怒りや悲しみといったネガティブな感情の変化も呼吸に影響を与えるため、ストレスと息苦しさは密接に関係しています。
精神疾患
不安障害やパニック障害、自律神経失調症なども息苦しさを引き起こす原因となります。
例えばパニック障害では、突然強い不安感に襲われ、動悸や震え、呼吸困難などのパニック発作が起こることがあります。
特に電車やエレベーターなど逃げ場のない場所では息が詰まるような感覚が出やすく、発作を繰り返すことで外出が困難になることも珍しくありません。
また自律神経失調症では、交感神経と副交感神経のバランスが乱れ、息苦しさや動悸、頭痛などのさまざまな症状が現れます。
いずれも、適切な診断と治療により症状の改善が期待できます。
身体疾患
身体的な病気によっても息苦しさは引き起こされます。
代表的なものに呼吸器系や循環器系の疾患があります。
例えば喘息や肺炎、COPD(慢性閉塞性肺疾患)などの呼吸器疾患では、気道が狭くなったり炎症を起こしたりすることで空気の通りが悪くなり、息苦しさを感じることがあるのです。
また心不全や心筋梗塞といった循環器系の病気では、心臓のポンプ機能が低下し、体に酸素が十分に行き渡らなくなることで呼吸が苦しくなることがあります。
顔色の悪化やむくみ、胸の痛みを伴う場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
息苦しいと感じるときに考えられる病気

息苦しいと感じるときに考えられる病気として、以下が挙げられます。
- 喘息
- COPD(慢性閉塞性肺疾患)
- 肺炎
- 肺結核
- 肺がん
- 心不全
- 狭心症
- 貧血
- 睡眠時無呼吸症候群
- 過換気症候群
ここでは上記の病気についてそれぞれ解説します。
喘息
喘息は、気道に慢性的な炎症が起こり、空気の通り道が狭くなる病気です。
喘息の主な症状は咳、痰、息苦しさ、そして「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった呼吸音が鳴る喘鳴です。
これらの症状は夜間や明け方に悪化しやすく、ダニやハウスダストなどのアレルゲン、冷たい空気、タバコの煙、風邪などが発作の引き金になります。
発作が起きると、呼吸がうまくできず胸が圧迫されるような感覚になるため、非常につらい状態になります。
適切な治療により、症状のコントロールが可能です。
COPD(慢性閉塞性肺疾患)
COPD(慢性閉塞性肺疾患)は、主に長年の喫煙によって肺の組織が破壊され、呼吸機能が徐々に低下していく病気です。
慢性的な咳や痰、息苦しさが主な症状です。
初期には症状が軽く、階段の昇降などで少し息切れする程度ですが、病気が進行すると日常の軽い動作でも呼吸が苦しくなっていきます。
肺胞が壊れて酸素交換がうまくいかなくなるため、慢性的な酸素不足を起こしやすくなります。
また、風邪などの感染症をきっかけに症状が急激に悪化する『COPD急性増悪』にも注意が必要です。
肺炎
肺炎は、細菌やウイルス、真菌などによる感染で肺に炎症が起きる病気です。
特に高齢者や免疫力が低下している人では重症化しやすいため、注意が必要です。
初期症状は発熱や咳、痰などですが、進行すると強い息苦しさや胸の痛みが現れることがあります。
新型コロナウイルス感染症も肺炎を引き起こす病原体の一つであり、急激に呼吸機能が悪化することもあります。
悪化すると呼吸困難が顕著になり、入院が必要になることもあるため、早めの診断が重要です。
肺結核
肺結核は、結核菌という細菌が肺に感染して起こる病気です。
初期症状は風邪に似ており、咳や痰、微熱、倦怠感などが見られますが、病気が進行すると呼吸機能が低下し、息苦しさが現れます。
特に咳が2週間以上続く場合や、血痰、体重減少、寝汗などの症状を伴う場合は注意が必要です。
肺結核は空気感染するため、感染者が咳やくしゃみをすると周囲に菌が拡散しやすく、集団生活の場で広がることもあります。
現在では有効な治療薬が複数あり、数か月にわたる内服治療で完治を目指せますが、治療を途中でやめてしまうと薬が効かない耐性菌が発生することがあります。
症状に気づいたら、周囲への感染を防ぐためにも早急に検査・治療を受けることが大切です。
肺がん
肺がんは、肺の細胞にがん細胞が発生して増殖する病気で、初期にはほとんど自覚症状がありません。
しかし、進行するにつれて咳や血痰、胸の痛み、体重減少などが現れ、動いたときに息苦しさを感じるようになります。
特に腫瘍が気管支を圧迫したり、肺に水がたまる『胸水』が生じた場合には、呼吸困難になることがあります。
肺がんは喫煙との関連性が深いため、長年の喫煙歴がある人は注意が必要です。
治療には手術、放射線治療、抗がん剤、免疫療法などがあり、がんの種類や進行度によって方針が決まります。
早期発見できれば治療の選択肢も広がりますが、進行してから見つかることが多いため、定期的な健診が重要です。
心不全
心不全とは、心臓のポンプ機能が低下し、全身に十分な血液を送り出せなくなる状態のことです。
血液の循環が悪くなることで肺に血液が溜まりやすくなり、息苦しさや息切れを感じやすくなります。
横になると息苦しくなったり、夜中に突然息苦しさで目が覚めたりするのも心不全の症状の一つです。
さらに動悸や全身の倦怠感、むくみ、食欲不振なども見られることがあります。
心不全は進行すると日常生活に支障をきたすこともあるため、息苦しさを感じたら早めに循環器内科での診断と治療を受けることが大切です。
狭心症
狭心症は、心臓の筋肉に血液を供給する冠動脈が狭くなり、酸素が不足することで発症する病気です。
心筋が酸素不足に陥ると、胸の締めつけられるような痛みや圧迫感が現れますが、呼吸が浅くなったり動いたときに息切れを感じたりすることもあります。
症状は主に運動中や階段の昇降時など、心臓への負担が増すタイミングで出やすい傾向があります。
発作は数分でおさまることが多いですが、放置すると心筋梗塞へ進行する危険性があるため注意が必要です。
吐き気や冷や汗、めまいなどの症状を伴う場合は、重篤な虚血性心疾患の可能性も考えられます。
貧血
貧血は、血液中の赤血球やヘモグロビンが不足し、体に十分な酸素が行き渡らなくなる状態です。
軽い運動や階段の上り下りでも酸素が足りず、息切れや息苦しさを感じることがあります。
その他にも動悸やめまい、疲れやすさ、顔色の悪さなどが見られます。
鉄分不足による鉄欠乏性貧血やビタミンB12の欠乏、慢性的な出血などが主な原因です。
貧血は血液検査で診断可能で、食事改善やサプリメント、必要に応じて薬物治療が行われます。
慢性的な息苦しさがある場合は、貧血の可能性も念頭に置いて医療機関の受診を検討しましょう。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が何度も止まる病気です。
呼吸が止まることで血中の酸素濃度が低下し、結果として深い眠りが妨げられ、日中の強い眠気や集中力の低下、疲労感を引き起こします。
寝ている間に息苦しさを感じて目が覚める、いびきが大きく途中で止まる、起床時に頭痛がするなどの症状も睡眠時無呼吸症候群により起こるものです。
重度の場合は高血圧や心不全、脳卒中、糖尿病などの合併症リスクも高まります。
肥満や顎の形状、鼻づまりなどが発症要因になることが多く、特に中年男性に多く見られます。
日中の息苦しさや慢性的な倦怠感がある場合は、受診を検討しましょう。
過換気症候群
過換気症候群は、不安や緊張などの心理的要因で呼吸が浅く速くなり、体内の二酸化炭素濃度が低下することによって引き起こされます。
血中の二酸化炭素が急激に減少することで手足のしびれやめまい、動悸、吐き気、胸の締めつけ感などの症状が現れ、強い息苦しさを感じるのが特徴です。
発作時には「息が吸えない」「このまま倒れるのでは」といった強い不安に襲われることもあり、症状が悪循環に陥りやすくなります。
過換気発作が頻繁に起こる場合は、心療内科や精神科の受診を検討することが大切です。
息苦しいと感じたときの対処法

息苦しいと感じたときの対処法として、以下が挙げられます。
- 楽な姿勢をとる
- 口すぼめ呼吸や腹式呼吸を行う
- ストレス管理をする
- 禁煙する
- 病院を受診する
ここでは上記5つの対処法についてそれぞれ解説します。
楽な姿勢をとる
息苦しさを感じたときは、まず自分が呼吸しやすい姿勢をとることが大切です。
代表的なのは前かがみの姿勢です。
椅子に座ってテーブルに肘をつき、少し上体を前に倒すことでお腹の圧迫が軽減し、呼吸がしやすくなります。
壁にもたれて立つ姿勢や、クッションを使って上半身を高くして横になる姿勢も効果的です。
横になって息苦しさが悪化する人は、なるべく上体を起こした姿勢を心がけましょう。
口すぼめ呼吸や腹式呼吸を行う
息苦しさを感じるときは、呼吸法を意識してみましょう。
特に有効なのが『口すぼめ呼吸』です。
鼻から息を吸い、口をすぼめてゆっくりと吐き出すことで、呼吸をコントロールしやすくなり、肺にかかる負担を軽減できます。
ろうそくの火を消すようなイメージで、長く優しく息を吐くのがポイントです。
また同じく呼吸法の一つである『腹式呼吸』も効果的です。
お腹の動きに集中しながら深く呼吸することで、リラックス効果とともに酸素の取り込み効率も高まります。
どちらの方法も練習しておくと、発作時に落ち着いて対応しやすくなるでしょう。
ストレス管理をする
精神的なストレスは、息苦しさの大きな原因になることがあります。
例えば『過換気症候群』や『自律神経失調症』などは、ストレスや不安によって呼吸が浅くなり、息苦しさを引き起こすことがあります。
そのため日頃からストレスをうまく発散し、心と体をリラックスさせる時間を持つことが大切です。
趣味の時間を作る、十分な睡眠をとる、軽い運動を取り入れるなど、無理のない範囲でストレスを軽減する工夫をしましょう。
症状が繰り返されるようであれば、心療内科などでの相談も検討してみてください。
禁煙する
喫煙は肺や気管支にダメージを与え、慢性的な息苦しさを引き起こす大きな原因の一つです。
COPD(慢性閉塞性肺疾患)や肺がんなどの深刻な呼吸器疾患のリスクを高めることが知られており、すでに呼吸が苦しいと感じている人にとっては、症状を悪化させる一因にもなります。
禁煙は息苦しさを軽減するだけでなく、長期的に見て健康全体の改善にもつながります。
ニコチンパッチや禁煙外来の活用も検討しながら、無理のない形で禁煙に取り組んでみましょう。
病院を受診する
息苦しさが繰り返し起こる、あるいは急に激しくなった場合は、迷わず医療機関を受診しましょう。
呼吸器系のみでなく、心臓や血液の病気が隠れていることもあるため、自己判断は禁物です。
特に「安静にしていても息苦しい」「胸痛やめまいを伴う」「顔色が悪くなっている」などの症状があれば、早急に診察を受けるべきです。
医療機関で検査や診断を受けた後、医師のもとで適切な治療を受けることで、症状の改善が期待できます。
息苦しさを感じたら病院の受診を検討しましょう
息苦しさは単なる一時的な体調不良のみでなく、ストレスや不安といった精神的な問題が関係していることも少なくありません。
もし「検査で異常がないのに息苦しい」「ストレスを感じると呼吸がつらくなる」といった状態が続くようであれば、精神科や心療内科の受診も視野に入れて早めに医療機関に相談しましょう。
『かもみーる』では、医師監修のオンラインカウンセリングサービスを提供しています。
息苦しさで悩んでいる方や医療機関の受診をためらっている方などは、ぜひ当院まで気軽にご相談ください。
▶ カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶ 新規会員登録はこちら