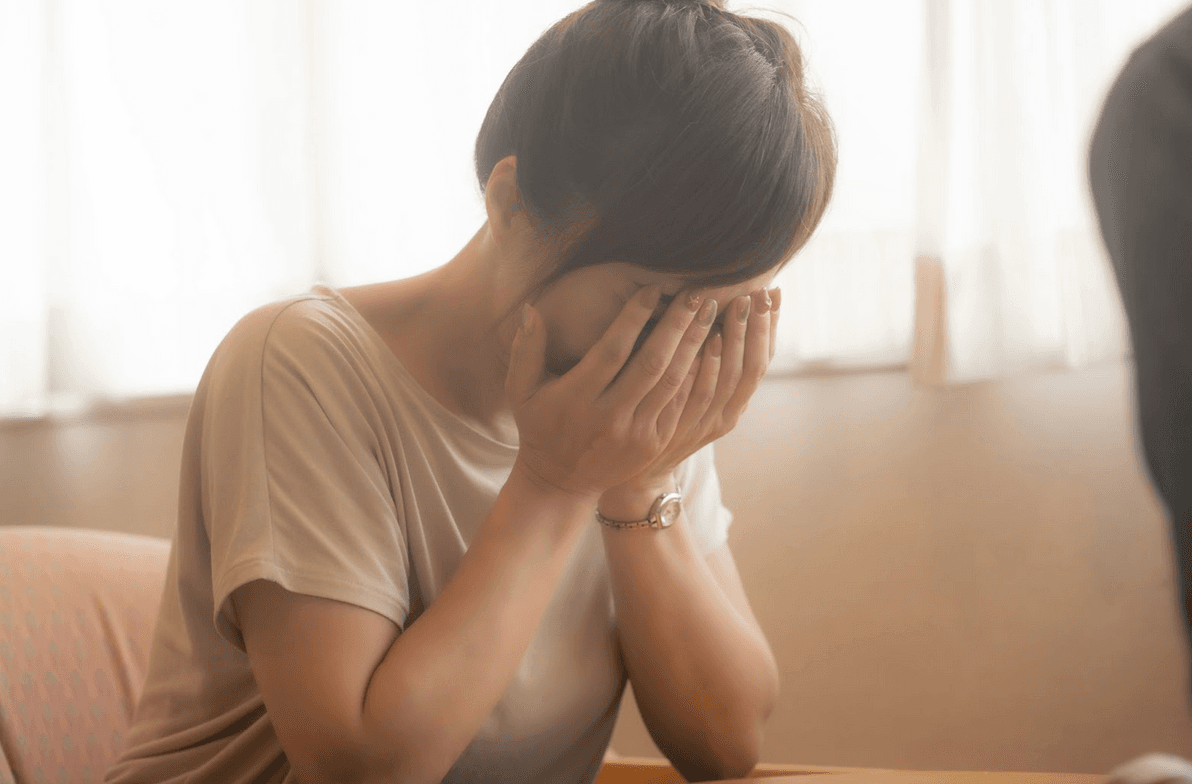「理由もなく涙があふれてしまう」「気づくと泣きそうになっている」そんな無性に泣きたくなる状態は、心や体からのSOSサインかもしれません。
その背景には、ストレスや疲れ、ホルモンバランスが影響しているとされていますが、うつ病や適応障害などの病気が隠れていることもあります。
この記事では、無性に泣きたくなる主な原因と、日常でできる気持ちの落ち着け方、そして受診を検討すべきサインについて詳しく解説します。
無性に泣きたくなる原因は?

無性に泣きたくなる背景には、心理的なストレス、孤独感、身体的な不調や精神的な病気などが関係している場合があります。
ここでは、代表的な原因を3つに分けて詳しく解説します。
心理的な要因
長期間に渡るストレスや孤独感は、心に大きな負担を与える原因です。
仕事や人間関係において緊張状態が続くと、脳の感情をコントロールする機能が乱れ、涙もろくなることがあります。
また、過去の出来事や感情を抑え込んでいる場合、フラッシュバックにより蓄積されていた感情が突然あふれ出すこともあります。
特に夜や休日など、ふと一人になった瞬間に泣いてしまうのは、日中抑えていた感情が解放されるための自然な心の防衛反応です。
しかし、頻度が増える場合は心の疲れが深刻化しているサインかもしれないので、注意が必要です。
身体的な要因
ホルモンバランスの変化は、感情の安定に直結します。
特に女性は、月経周期や妊娠、更年期などにより、エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンの分泌が変動し、涙もろくなる傾向があります。
他にも、睡眠不足や慢性的な疲労、栄養不足や飲酒なども脳の働きを低下させ、ストレス耐性を弱める要因になり、栄養不足や過度な飲酒、過労も感情のコントロールを難しくします。
身体的なコンディションが整っていないと、心のバランスも崩れやすくなるため、生活習慣を改善することが大切です。
精神的な病気が関係している場合
「一人になると泣いてしまう」「何もしなくても涙が出てしまう」という症状が続く場合、うつ病や不安障害といった精神的な病気が関係していることもあります。
うつ病は、脳内の神経伝達物質であるセロトニンやドーパミンのバランスが崩れることで感情のコントロールが難しくなる病気です。
他にも、環境の変化や強いストレスに適応できない適応障害や、理由のない恐怖や緊張感が高まり、涙として表れる不安障害もあります。
これらの病気が原因となっている場合は、専門的な治療やカウンセリングが必要になるため、早めの受診が重要です。
一人になると泣いてしまう理由

一人になると泣いてしまう原因は、我慢や緊張の糸が切れ、感情を抑える必要がなくなるためです。
日中は、仕事や家事、人間関係などで気を張っていても、仕事終わりや夜、休日の静かな時間に心が解放されます。
このとき、秘めていた不安や悲しみが浮かび上がり、涙として表れるのです。
また、孤独感や自己否定感が強い場合、一人の時間がその感情を増幅させることもあります。
このような傾向が続くと、孤独感が深まりやすくなり、泣いてしまうことも増えるため、信頼できる人との交流を意識的に持つことが予防につながります。
ずっと泣きそうな感じが続く背景
理由もないのに常に泣きそうな感覚が続く場合、精神的な疲労や神経が敏感になっている状態が関係していることがあります。
ストレスを感じている時間が長いと自律神経が乱れ、脳が常に緊張モードになりやすく、涙腺の反応も過敏になります。
また、睡眠不足やホルモンの変化によっても状態は悪化します。
ずっと泣きそうな感覚が2週間以上続く場合は、疲労だけでなく、うつ病や不安障害などの可能性もあるため、早期に専門家へ相談することが望ましいです。
意味もなく泣きたくなるときに考えられること
「意味もなく泣きたくなる」「理由もないのに涙が出る」といった場合、心や体からのSOSである可能性があります。
心理的なストレスや身体的な疲労がピークに達すると、脳は涙という形で緊張を緩和しようとします。
また、うつ病や不安障害などの精神的な病気や、ホルモンの変化によっても似たような症状が現れます。
一時的であれば心のリセット作用として前向きに受け止められます。
しかし、頻繁に泣きたくなったり、涙が出たりするような場合は、医療機関での診断を受けるようにしましょう。
泣きたくなる気持ちがあるときの対処法

無性に泣きたくなるときの対処法としては、感情を書き出して整理したり、深呼吸や瞑想で気持ちを整えたり、十分に休息をとったりすることなどが有効です。
「泣かないようにしなければ」と感情を押し込めてしまうと、かえって心の負担が増してしまいます。
無理のない方法で心と体を休めてあげましょう。
ここでは、泣きたくなる気持ちがあるときの対処法を詳しく紹介します。
感情を書き出して整理する
無性に泣きたくなるときは、今の感情や考えていることを紙に書き出すとよいでしょう。
感情を言葉にする作業は、漠然とした不安や悲しみを客観視する効果があり、モヤモヤの正体を明確にします。
例えば、『なぜ泣きたいのか』『今の気分』などを具体的に書くことで、原因が見えやすくなります。
また、実際に手書きすると脳がリラックスし、感情の整理が進みやすいとも言われています。
心の状態を見える化することで、過剰な感情の波に流されにくくなります。
泣きたい気持ちを抑える第一歩として、感情の書き出しを習慣にしましょう。
深呼吸や瞑想で心を落ち着ける
感情の高ぶりを抑えるには、深呼吸や瞑想がよいとされています。
これは、深呼吸をすることにより、自律神経を整えられるためです。
無性に泣きたくなるときは、交感神経が優位になるため、心拍数や呼吸が浅く速くなっている場合があります。
そこで、ゆっくりと鼻から息を吸い、口から長く吐き出す腹式呼吸を行うと、体と心が次第に落ち着きます。
瞑想も同様に、意識を呼吸に集中させることで、過去や未来の不安から解放される効果が期待できます。
呼吸と瞑想を日常に取り入れることで、泣きたい感情のコントロールがしやすくなるでしょう。
信頼できる人に話を聞いてもらう
誰かに話すことで、泣きたくなる気持ちを軽くできる場合があります。
特に、信頼できる人に気持ちを打ち明けることは、心理的圧迫感を和らげる効果が期待できるでしょう。
自分の思いを人に話すことで、感情を整理できるだけでなく、共感やアドバイスを受けることができ、孤独感の払拭にもつながります。
重要なのは、『自分を否定せずに受け止めてくれる相手』を選ぶことです。
相談相手は家族や友人、専門機関や心理カウンセラーでもよいでしょう。
睡眠と生活リズムを整える
十分な睡眠と規則正しい生活は、健康維持はもちろん、感情の安定にも欠かせません。
睡眠不足は、脳の感情コントロール機能を低下させるだけでなく、涙もろくなる原因となります。
特に、夜更かしや昼夜逆転の生活は、自律神経やホルモンバランスを乱してしまい、無性に泣きたくなる状態を悪化させます。
毎日同じ時間に寝起きし、朝日を浴びることで体内時計が整い、心も安定しやすくなります。
寝る前にはカフェインやスマホの使用も控え、落ち着いた状態で心も体も休めましょう。
趣味や軽い運動で気分をリセットする
趣味や運動は、泣きたい気持ちを切り替えたい時に有効な手段です。
好きなことに没頭すると、脳内で『幸福ホルモン』と呼ばれる『セロトニン』や『ドーパミン』が分泌され、気分が上昇傾向になります。
軽い運動やウォーキング、ストレッチ、ヨガなどもストレスホルモンを減らし、感情を安定させる効果があります。
ウォーキングや軽いストレッチ、ヨガなどは運動にもなり、特におすすめです。
また、絵を描いたり、音楽を聴いたり、料理をしたりといった、自分が楽しめる活動なら何でも構いません。
大切なのは『義務ではなく自分から楽しんで行う』ということです。
日常生活の中で、小さな楽しみを積み重ねることで、涙を誘う感情を自然と減らせます。
無性に泣きたくなるときに受診を検討すべきサイン
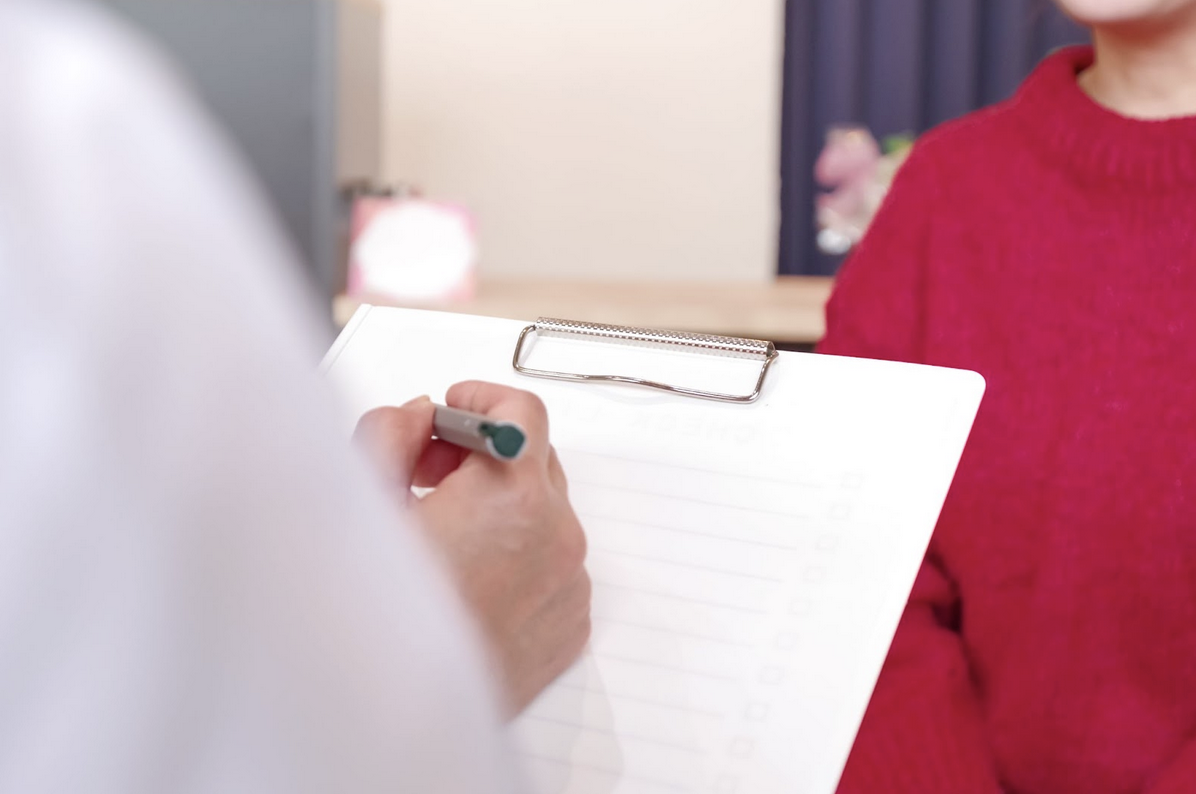
無性に泣きたくなる状態が長く続く場合、心や体が助けを求めている可能性があります。
特に、涙が2週間以上続く、気分の落ち込みがある、寝れないといった日常生活に支障をきたす場合は、専門機関の受診を早めに検討しましょう。
涙が2週間以上続いている
涙が2週間以上続く場合は、単なるストレスではなく、心の病が進行している可能性があります。
うつ病や適応障害などでは、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れ、感情のコントロールが難しくなります。
短期間であれば休養やセルフケアで改善することもありますが、長引く場合は自己判断で放置せず、医療機関を受診することが大切です。
早期に原因を突き止めることで、回復までの期間を短縮できます。
特に、「涙が止まらない日」が続くときは、心の健康状態を知るためにも専門家を受診し、助けを求めましょう。
気分の落ち込み・無気力・不眠がある
泣きたくなる気分のほか、気分の落ち込み、やる気の低下、不眠は、うつ病や不安障害の代表的な症状です。
心のエネルギーが著しく低下しており、我慢してしまうと、日常生活や人間関係に大きな影響を与えます。
特に、不眠は身体や脳の回復を妨げ、感情のコントロールをさらに難しくします。
無気力感は活動量を減らし、孤立感や自己否定感を強める要因となります。
無性に泣きたくなる以外にも、『何もする気にならない』『眠れない』という症状が2週間以上続く場合は、早期に医療機関で相談しましょう。
日常生活に支障が出ている
『涙が出やすい』『感情の起伏が激しい』などが原因で、仕事や家事、学業などの日常生活に影響が出ている場合は、医療機関への相談をおすすめします。
例えば、人前で涙をこらえられない、集中力が続かない、人との交流を避けるようになった場合、心の状態が悪化しているサインです。
こうした変化を放置すると、症状が慢性化して社会生活への復帰が難しくなる可能性もあります。
『以前はできていたことができない』『毎日が苦しい』と感じた時には、我慢をせずに専門家に相談することが重要です。
オンライン診療サービス『かもみーる』では、24時まで受診可能で、初めての方でも安心して相談できます。
経験豊富な医師やカウンセラーが、一人ひとりの状況に寄り添った診療を行い、心の回復をサポートしているため、お気軽にご相談ください。
▶ 『かもみーる』でオンライン診療を予約する
無性に泣きたくなるときに専門機関に相談するメリット

「無性に泣きたくなる」「何もしなくても涙が出る」といった症状に悩んでいるとき、専門機関に相談することには、多くのメリットがあります。
「まだ大丈夫」と我慢しすぎず、限界を迎える前に早めに専門機関に相談しましょう。
ここでは、専門機関に相談するメリットを紹介します。
状態を正確に把握できる
自分では見落としやすい症状や原因も、専門家の診断によって明確にできます。
専門家である医師や心理士は、問診や検査を通じて、精神的・身体的要因を総合的に評価するためです。
例えば、うつ病やホルモンバランスの乱れ、慢性的な疲労など、複数の要因が絡んでいるケースもありますが、正確な把握ができれば、不要な不安を抱えず、必要な治療に集中できます。
特に涙が長引いたり情緒不安定が続く際は、原因特定が改善への近道となるため、早期に相談することが重要です。
適切な治療やカウンセリングが受けられる
一人一人の状態に合わせた治療やカウンセリングを受けられる点も大きなメリットです。
薬物療法や認知行動療法、カウンセリングなど、症状や原因に応じたアプローチを選択できます。
現在では、来院だけでなくオンライン診療や電話カウンセリングなど、自宅から受けられるサービスも増加しました。
専門家と二人三脚で取り組めば、症状の改善に加え、再発予防や生活の質向上にもつながります。
一人で抱え込むより、適切なサポートを受けた方が回復は早まる傾向があります。
孤独感や不安が軽減される
専門家との対話は、感情の整理や安心につながります。
誰かに話を聞いてもらえるだけで、心の負担は大きく軽減されるでしょう。
特に、孤独感や不安感が強いときは、自分だけでは出口を見つけにくい状況です。
専門家は、傾聴と共感を通じて安心できる環境を整えます。
さらに、状況に応じて家族や周囲へのサポート方法も提案し、回復の土台を築きやすくします。
「分かってくれる人がいる」という感覚は、治療と同じくらい重要な支えです。
無性に泣きたくなるときは心のSOS
無性に泣きたくなることは、誰にでも起こり得る自然な反応です。
しかし、それが長期間続いたり、生活に支障をきたす場合は、心や体からの重要なSOSかもしれません。
出来るだけ早く専門家へ相談することで、原因を特定し、自分に合った適切なケアを受けられます。
「どの医療機関に行けばよいのか」「うまく話せるだろうか」といった不安をお持ちなら、ぜひ24時まで診療可能なオンライン診療サービス『かもみーる』にご相談ください。
経験豊富な医師や心理士が、一人ひとりに合わせた診療を行い、心の回復を丁寧にサポートします。
▶︎カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶︎新規会員登録はこちら