発達障害の子どもが反抗期を迎える年齢になると、どう接していいのか分からなくなる保護者の方もいるでしょう。
発達障害で、一般的な反抗期よりも挑発的・攻撃的で周囲の人間に大きな影響を及ぼす症状がみられたら、それは単なる反抗期ではなく反抗挑戦性障害(反抗挑発症)である可能性があります。
発達障害は二次障害を併発しやすいため、適切な対応や予防、早めの診断が必要になります。
この記事では、反抗期と間違いやすい反抗挑戦性障害について、特徴や対処法などを紹介します。
2つの違いや適切な対処法・接し方について理解を深め、早めの受診につなげましょう。
発達障害の反抗期は反抗挑戦性障害(反抗挑発症)かも

思春期の発達障害の子どもにみられる反抗期のような特徴は、二次障害として発生した反抗挑戦性障害(反抗挑発症)が原因である可能性があります。
反抗挑戦性障害とは、主に学童期から思春期にかけての年齢の子どもにみられる行動障害で、過度な怒りや攻撃的な態度、大人に対する反抗的・挑発的な言動などを伴うのが特徴です。
遺伝や脳の構造・機能の偏り、環境を要因とするほか、注意欠如・多動症(ADHD)の二次障害として発症するケースが多く、この2つが併発する場合は両方を考慮した治療計画を検討する必要があります。
反抗挑戦性障害と反抗期は別物であり、反抗期は多くの子どもが通過する成長過程の一部であるのに対して、反抗挑戦性障害は明確な診断基準がある医学的診断名です。
癇癪の強さや頻度、何人の大人に対して問題となる態度をとっているかなどによって診断され、日常生活が困難になるほどの症状を伴うこともあります。
発達障害をもつ子どもの反抗期に対して過剰な問題行動がみられる場合や、度を越えて反抗的な態度をとる場合などは反抗挑戦性障害の可能性を視野に入れる必要があります。
反抗挑戦性障害の特徴

反抗挑戦性障害の子どもには、具体的に以下のような特徴があります。
過剰なイライラや怒りっぽさがある
反抗挑戦性障害では、過剰なイライラを感じることで怒りっぽくなります。
すぐにカッとなるほか、周囲からのストレスに敏感になることで癇癪を起こすケースも多いです。
また、周囲の人間に当たる・他人に対して腹が立つなどの特徴があり、周囲との軋轢を生む原因になります。
挑発的・反抗的な行動がみられる
反抗挑戦性障害は、目上の大人に対して挑発的・反抗的な態度をとるのが特徴です。
激しい自己主張がみられ、大人の指示を無視したり、反発して口論したりしようとする傾向があります。
反抗の対象は、親・先生などの権威のある大人以外に、友達であるケースもあります。
故意に人を困らせる意地悪さや執念深さがある
反抗挑戦性障害の子どもには、故意に人を困らせたいと考える意地悪さや執念があります。
意図的に人をイラつかせたり、傷付けるために悪意のある言動をしたりします。
また、自分のミスや間違った行動を他人のせいにするケースも多いです。
反抗挑戦性障害の診断基準

反抗挑戦性障害は、拒絶的・反抗的・挑戦的な行動様式で以下の問題行動が4つ以上、少なくとも6ヶ月間持続していることで診断されます。
- しばしばかんしゃくを起こす。
- しばしば大人と口論をする。
- しばしば大人の要求、または規則に従うことを積極的に反抗または拒否する。
- しばしば故意に人をいらだたせる。
- しばしば自分の失敗、無作法な振る舞いを他人のせいにする。
- しばしば神経過敏または他人からイライラさせられやすい。
- しばしば怒り、腹をたてる。
- しばしば意地悪で執念深い。
※出典:厚生労働科学研究成果データベース『Ⅲ.反抗挑戦性障害の診断基準(DSM-Ⅳ、参考図書11より引用)』
反抗挑戦性障害は、これらの基準に当てはまっているかや、発達段階、環境などを考慮したうえで慎重に診断されます。
またこれらの症状が、抑うつ障害や双極性障害など他の精神疾患が原因ではないことを確かめる必要もあります。
反抗挑戦性障害の子どもへの対処法

反抗挑戦性障害は、適切な対処をすることで症状の改善・軽減が期待できます。
ここからは、反抗挑戦性障害の子どもへの適切な対処の仕方を紹介します。
ルールや決まり事を設定する
子どもとの間に、一貫したルールや決まり事を設定しましょう。
良い行動や望ましい行動をした場合には褒めることを忘れず、問題行動に対しては明確な決まりを定めることが大切です。
またルールを守らなかった場合に起こる結果を提示することで、予測する環境を整えることも重要です。
ルールを表や箇条書きなどでまとめて、視覚で認識できるようにすることで理解のしやすさにつながります。
ポジティブな関係を築く
反抗挑戦性障害の子どもに対しては、ポジティブな対応や声掛けを意識して、寄り添える存在になることが大切です。
発達障害をもつ反抗挑戦性障害の子どもは間違えることや失敗することに強い嫌悪感を示すケースがあり、例えばテストで100点以外をとったり、競い事で1位になれなかったりした場合に癇癪を起こす可能性があります。
これらの特性がある子は独特な受け取り方をする場合があり、次は出来るよ・間違えることもあるよねなどの根拠のない励まし方をすると否定されたと感じてしまう場合があるため、相手の気持ちに寄り添った声掛けをしましょう。
具体的には、「間違えて悔しいね、頑張ったね」などの共感を示す反応が有効です。
コミュニケーションの方法を工夫する
子どもが反抗挑戦性障害の場合、上手くコミュニケーションを取れるように工夫しましょう。
お願いをするときは短い言葉で明確に指示を出すことで、理解のしやすさや反応の良さにつながります。
子どもと話すときは、大人が感情的にならないように冷静な状態で接すると、相手も落ち着いて発言を受け入れられます。
また望ましい行動がみられた場合には、褒めたりご褒美を与えたりすることで適切な行動を強化する工夫も効果的です。
専門的支援を行う
反抗挑戦性障害の子どもには、専門的な支援を行うことで行動パターンの改善が見込めます。
具体的に行われる支援の方法には、認知行動療法・親子相互作用療法などの行動療法やペアレントトレーニングなどがあります。
お子さんの特性によって支援の方法は異なるため、一度専門の機関や相談窓口などを利用して対処法について相談することをおすすめします。
『かもみーる』では、病院に行かずにオンラインで発達障害のお子さんの診察や認知行動療法が可能です。
反抗挑戦性障害の子どもにしてはいけない対応
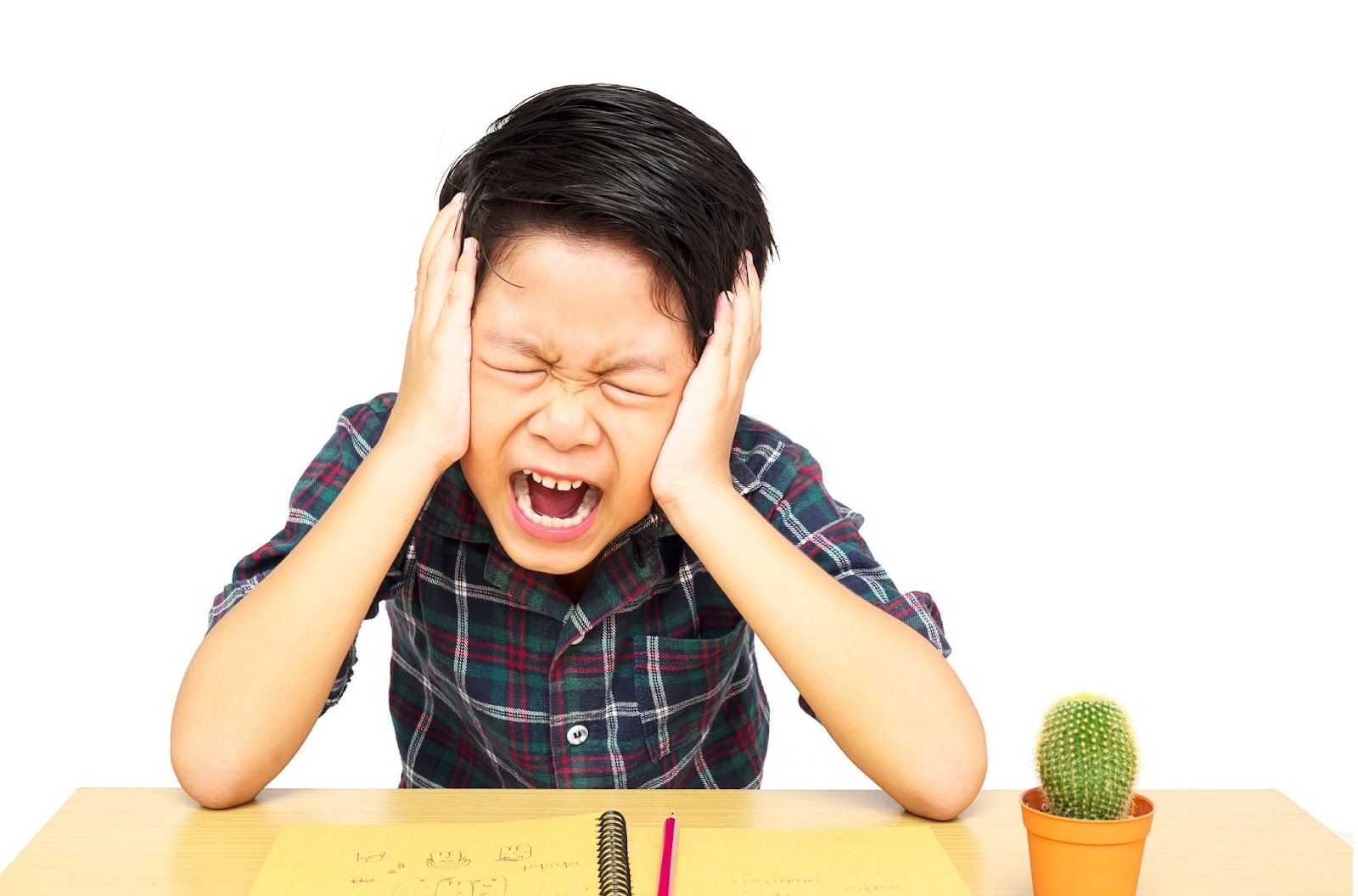
反抗挑戦性障害の子どもには、適切な対処と関わり方が求められるため、以下のような対応はしないように気をつけましょう。
無理に集団行動をさせる
自分のペースで行動したがる反抗挑戦性障害の子どもに対して、集団行動を強要する行為は避けましょう。
反抗挑戦性障害の子どもには、人の指示を無視して周囲を困らせたい特性がみられますが、この場合は集団行動や他人との共同作業が苦手であることが原因の可能性があります。
他の子と行動することを無理強いすると、集団に馴染めずに怒ったりパニックになったりするケースがあるため、本人のペースや興味を尊重することが大切です。
必要に応じて周囲と人間との距離感を調整したり、子どもの表情や態度で気持ちを読み取ったりすることで適切に対処しましょう。
命令のような指示の仕方をする
子どもに何かするように促す場合や言ったことを無視して素直に従わなかったりする場合でも、命令口調は避けましょう。
反抗挑戦性障害の子どもに「〜をしなさい」と命令する言い方で指示を繰り返すと、興奮して口論になったり、暴言が止まらなくなったりする可能性があります。
例えば宿題とお風呂を指示した場合に、無視する・生返事をするなどの態度を見せた場合は、「さっきなんて言ったっけ?」と聞くのではなく、「お風呂に入る?宿題をする?」と質問します。
こうすることで、指示を出す大人と子どもが対峙するのではなく、指示を聞かない自分と対峙するように誘導することが大切です。
歪んだ受け取り方を正そうとする
反抗挑戦性障害の子どもは、善意で伝えた思いや励ましの言葉を歪んで捉えてしまうケースがありますが、この考え方を矯正することはやめましょう。
フォローするつもりでかけた言葉に対して馬鹿にされたと感じたり、大変そうに見えたから手伝った結果、余計なことをされたと感じたりする可能性があります。
お子さんとの関わりで疲弊しているなかで、気持ちが伝わらないとストレスや悲しみを感じる場合もあるでしょう。
しかし、この場合は間違いを正したり頭ごなしに否定したりすることで、子供が自信を喪失する原因になります。
子どもが歪んだ受け取り方をする場合は、それも特性なのだという思考に修正し、まずは子どもが感じた思いに共感してあげることが大切です。
手を上げる・暴力をそのままにする
子どもが言うことを聞かない場合に手を上げたり、子どもの暴力を受け入れたりしないように注意が必要です。
大人の方が子どもに手をあげてしまうと、人を思い通りにしたいときは暴力を振るっていいと認識してしまう可能性があります。
また子どものうちに力で解決することを覚えると、成長するにつれて力が強くなり、事件を引き起こす恐れがあるため危険です。
反対に、子どもが暴力的な場合は放置せずに必ず対処しましょう。
周囲の大人が暴力を受け入れてしまうと、それに慣れた子どもの行動は徐々にエスカレートしていきます。
暴力の背景となる気持ちを理解することは必要ですが、暴力を振るうこと自体は許容せず、専門家による治療や支援を利用して改善を目指しましょう。
発達障害の二次障害を予防するために

発達障害の二次障害を予防するためには、普段から以下の点を意識することが大切です。
健康的な生活習慣を心掛ける
二次障害となる精神疾患は、生活リズムの乱れによって発症リスクが高まるとされているため、健康的な生活習慣を心掛けることが大切です。
規則的な睡眠や栄養バランスの取れた食生活は、心身の健康維持に必要です。
また生活リズムが整っていると精神面が安定しやすいため、発達障害の症状軽減や二次障害の予防に効果が期待できます。
疲労やストレスの蓄積を防ぐ
疲労やストレスの蓄積は二次障害につながる原因になるため、適度な休憩やストレス発散法を取り入れることが大切です。
発達障害の子どもは、人とコミュニケーションを取ることが苦手だったり、感覚過敏があったりすることでストレスを感じやすい特徴があります。
また過集中の特性によって疲労を溜めやすく、これらをそのままにしておくと二次障害のリスクが高まる可能性があります。
蓄積した疲労やストレスを解消することも大切ですが、過集中を防ぐ方法やストレスの原因を取り除く方法を取り入れることで予防することも必要です。
自己肯定感を高める
発達障害の子どもは自己肯定感が低い傾向があるため、自己肯定感を高める工夫をしましょう。
自己肯定感が高まることで、生きるうえでの困難や失敗を乗り越える力が身についたり、広い心を持って他人に関われるようになったりするのに役立ちます。
発達障害は少し周囲と違う特性があることで他人に非難されることがあり、自信を無くしてしまうケースも多いため、二次障害を発症しやすいです。
自己肯定感を高めるためには、子どもの特性を認める、できたことを褒めるなどの対応が効果的です。
ミスや間違いがみられた場合は、それに至るまでに努力したことや失敗に気が付いたことを認めてあげましょう。
成功体験を積ませる
発達障害の子どもには、個人の特性に合わせた成功体験を積み重ねることが大切です。
発達障害やその疑いがある子どものなかには、小さい頃の失敗経験の繰り返しが原因で、周りと違ったり色々なことが上手くできなかったりすることに気が付きやすい子がいます。
過去の失敗から、自分にはできない、やっても無駄だとネガティブな思考になっているケースもあるため、身近な出来事を通して成功体験を積み、自己肯定感を高める工夫が必要です。
例えば、縄跳びや鉄棒などの成功に応じてご褒美シールを集めたり、テストで100点を取れなくても頑張って勉強した過程を褒めたりして、自信につなげてあげましょう。
発達障害で反抗期?と思ったら早めの相談を
反抗挑戦性障害の特徴や対処法について紹介しました。
発達障害の反抗期は反抗挑戦性障害の可能性があり、発達障害と併発しているケースがあります。
お子さんが発達障害なのか、反抗挑戦性障害なのかは専門家による診断が必要なため、早めに精神科・心療内科を受診しましょう。
医師監修のオンライン診療・カウンセリングサービス『かもみーる』では、児童精神科や発達障害などのお悩みに合わせた診察やカウンセリングがオンラインでご利用いただけます。
医師のほか、臨床心理士・公認心理師などの有資格者のみが在籍しているため、些細な悩み相談から発達障害の診断、コーピングや認知行動療法など幅広く承ります。
オンライン診療は24時まで対応しているため、お子さんを寝かしつけた後に自宅からご相談することが可能です。
発達障害のお子さんの反抗期にお悩みの方は、是非お気軽にご相談ください。
▶ 児童精神科のご相談予約はこちら
▶ ASD・ADHDのご相談予約はこちら
▶︎ 新規会員登録はこちら
