「発達障害は何人に一人?」という疑問を抱く方も多いでしょう。
厚生労働省の調査によると、発達障害と診断されている人の割合は約10人に1人とされています。
そして発達障害は子どものみでなく、大人になってから明らかになるケースも少なくありません。
この記事では、発達障害の割合や特性などについて解説します。
生きづらさを軽減するためのポイントもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
発達障害とは

発達障害とは、生まれつきの脳の機能や発達の特性により、社会的な関わりや行動、学習などに困難が見られる状態を指します。
症状は乳幼児期から現れることが多いですが、成長過程や環境によっては、大人になってから気づかれることもあります。
外見上の特徴は少ないため、周囲から理解されにくいことが多く、誤解や偏見の対象となることも少なくありません。
「怠けている」「親のしつけが悪い」と誤解されがちですが、本人の意思や努力とは関係なく、脳の特性として現れるものです。
発達障害には自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如多動症(ADHD)、学習障害(LD)などがあり、それぞれに異なる特徴があります。
ここではこれらの特徴についてそれぞれ解説します。
自閉スペクトラム症(ASD)の特徴
自閉スペクトラム症(ASD)は、対人関係やコミュニケーションに困難が生じ、特定の行動や関心へのこだわりが見られるのが特徴です。
例えば人の気持ちを読み取ることが難しかったり、会話のキャッチボールが上手くできなかったりすることがあります。
また、同じ行動を繰り返す、物の並べ方に強いこだわりがある、感覚過敏や鈍麻などの特徴が見られることもあります。
これらの特性は幼少期から見られることが多いものの、成長過程で表れ方が変化する場合も少なくありません。
特性に応じた支援や環境調整により、本人の生活の質を向上させることが可能です。
注意欠如多動症(ADHD)の特徴
注意欠如多動症(ADHD)は、『不注意』『多動性』『衝動性』の3つを主な特徴とする発達障害です。
不注意の傾向が強い場合は物事に集中するのが難しく、忘れ物が多かったり、作業の抜け漏れが目立ったりします。
多動性が強いと、落ち着きがなく、授業中に席を離れる、絶えず身体を動かすといった行動が見られます。
また衝動性が強い場合は、順番を待てない、思いついたことをすぐに行動に移すなどの問題が生じやすいです。
これらの症状は12歳未満で表れ、就学期に顕著になるケースが多く見られます。
年齢とともに特性の現れ方が変化することもありますが、大人になっても困難が続くこともあります。
周囲の理解が得られないと、「だらしない」「落ち着きがない」と誤解されやすいため、適切なサポートや環境づくりが重要です。
学習障害(LD)の特徴
学習障害(LD)は、知的発達に遅れがないにもかかわらず、『読む』『書く』『計算する』などの特定の学習技能に著しい困難を示す発達障害です。
例えば読字障害のある子どもは文字を読み取るのに時間がかかる、文章の内容が理解できないといった困難があります。
書字障害では文字を書くのに極端に時間がかかる、書き間違いが多いといった特徴があります。
また、算数障害の場合は数字の概念や計算手順を理解することが難しくなるのが特徴です。
これらの困難は学習意欲や知能の問題ではなく、脳の情報処理の仕方に由来します。
小学校の入学以降、授業についていけないことで初めて気づかれるケースが多く、日本では特に板書を中心とした授業形式が多いため、そこで問題が生じやすくなります。
発達障害は何人に1人?
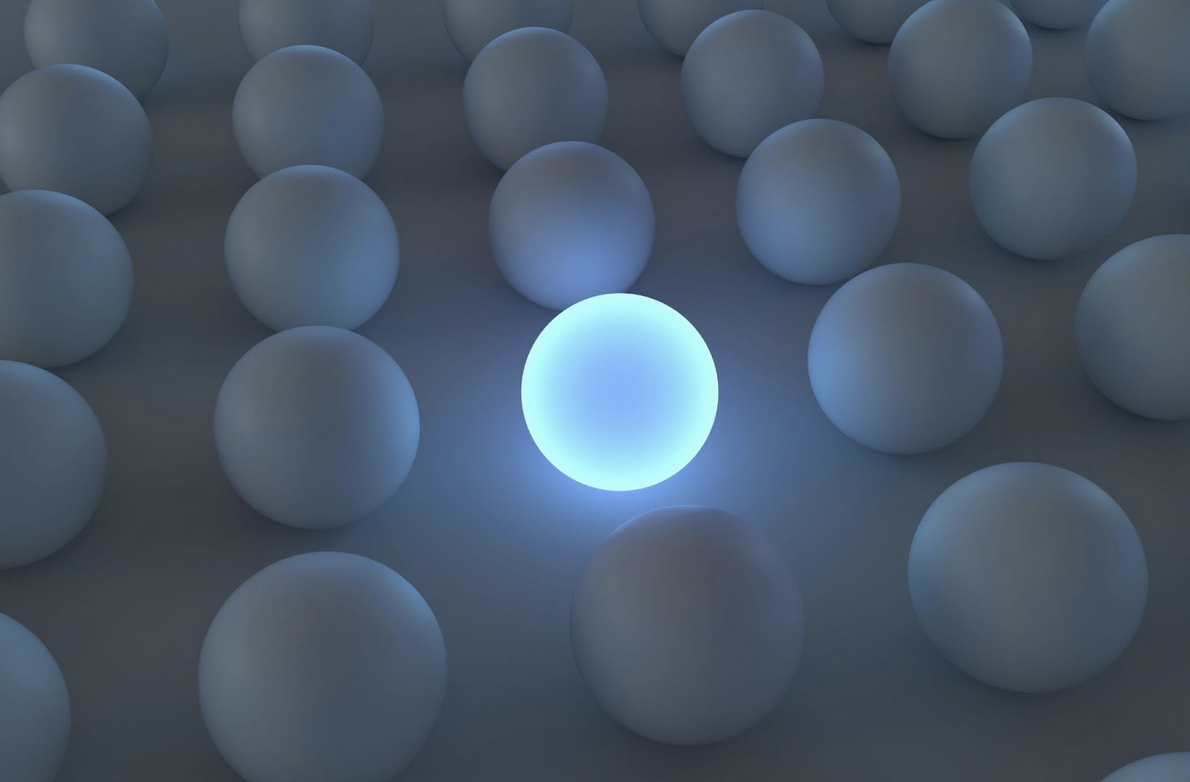
発達障害は、決して珍しいものではありません。
厚生労働省の調査によると、日本国内では約10人に1人が発達障害に該当すると推計されています。
この割合は、近年の診断基準の明確化や社会の理解が進んだことも影響していると考えられます。
発達障害の認知度が高まったことにより、これまで見過ごされていた症状に気づき、診断を受ける人が増えているのです。
子どもの頃に診断されるケースもありますが、大人になってから「生きづらさ」の背景に発達障害があると気づく人も少なくありません。
ここでは発達障害と診断される人の割合について解説します。
発達障害の割合は約10人に1人
発達障害の有病率は約10人に1人とされており、非常に身近な障害の一つです。
厚生労働省が令和4年に実施した調査では、発達障害と診断された人の推定数は約87万人にのぼると報告されています。
参考:令和4年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)結果
この数は子どもから大人までを含めたものであり、今後さらに増加する可能性もあります。
発達障害の診断が広まった背景には、医療の進歩や社会的関心の高まりにより、以前は気づかれなかった症状が見過ごされにくくなっている点が挙げられるでしょう。
また、本人や家族が特性を理解し、適切な支援を求めやすくなってきたことも大きな要因です。
小中学生における発達障害の割合は1クラスに3人
文部科学省の令和4年の調査によると、小中学校の通常学級に在籍する児童生徒のうち、学習面または行動面で顕著な困難があるとされた割合は8.8%にのぼります。
参考:通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果(令和4年)
これは、1クラス35人で換算すると約3人に相当します。
つまり、現在の学校教育の現場では、ほぼすべてのクラスに発達障害の特性をもつ子どもがいると考えられるのです。
特に小学校では、板書や集団行動など一定のルールが求められる場面が多く、特性によって困難を感じやすい傾向があります。
しかし発達障害のある子どもたちは、正しい支援と理解があれば、それぞれの力を発揮することができます。
周囲の大人による特性への理解と適切なサポートが重要です。
発達障害は男性の方が多い
発達障害は、男性に多くみられる傾向があります。
厚生労働省の統計によると、発達障害と診断された人のうち、男性は58.9%、女性は27.6%という結果が出ています。
参考:令和4年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)結果
男女比にすると、女性1人に対して男性が約2人となり、明らかに男性の方が高い割合を示しています。
男性の方が幼少期から特性が目立ちやすく、診断に結びつきやすいという点で、このような割合になっていると考えられるでしょう。
女性はコミュニケーションスキルやソーシャルスキルが保たれている場合もあり、特性が目立ちにくいため、診断されにくい傾向があります。
その結果として、大人になってから初めて自分の生きづらさの原因に気づき、発達障害の診断を受けるケースも少なくありません。
発達障害と診断される人の推移

発達障害と診断される人の数は、年々増加の一途をたどっています。
これは「発達障害が急増している」と捉えられがちですが、実際には診断技術や評価基準が進化し、社会全体での関心が高まったことが背景にあります。
ここでは発達障害と診断される人の推移についてみてみましょう。
発達障害と診断される人は年々増加傾向にある
発達障害と診断される人は、ここ数十年で大きく増加しています。
厚生労働省の平成28年調査では、発達障害のある人の推定数は約48万1千人とされていましたが、近年ではその数が急増し、令和4年の推計では87万人を超えると推定されています。
参考:令和4年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)結果
この増加は子どもに限らず、成人の診断例も増えていることが一因です。
子どもの頃に気づかれなかった特性が、大人になってから「生きづらさ」として表れ、医療機関の受診を通じて発達障害と診断されるケースが増えているのです。
また通級指導を受ける子どもの数も年々増加しており、10〜20年前と比較して、自閉スペクトラム症の子どもは約3倍、注意欠如多動症は約6倍、学習障害では約8倍と大きく変化しています。
これは日本のみでなく、世界的にも共通の傾向とされており、発達障害に対する社会全体の意識や支援体制の変化が、診断数の推移に影響を与えていると考えられます。
社会での認知が高まっているのが一つの要因
発達障害と診断される人が増えている背景には、社会全体での認知の高まりがあります。
以前は「変わった子」「問題のある子」と見られていた子どもも、現在では「もしかしたら発達障害かもしれない」と考えられるようになってきました。
メディアや書籍、インターネットの情報発信により、一般の人々にも発達障害に関する知識が広がりつつあるためです。
また教育や医療の現場でも、発達障害に対する理解が深まり、保育士や教員が早期に気づき、保護者に相談を促す体制が整ってきたことも大きな要因です。
発達障害が増えたというより、社会の理解が進んだ結果といえるでしょう。
発達障害は大人になってから診断される人も多い

発達障害は子どものうちに見つかるものという印象を持たれがちですが、実際には大人になってから診断される人も少なくありません。
これは子どもの頃には周囲のサポートや家庭環境によって困難が表に出にくかったものの、社会人として自立した生活を送る中で問題が表面化することが原因といえます。
例えば時間管理が上手くできない、人との関係を築くのが苦手、仕事のミスが多いといった悩みを通して、自分の特性に気づき、医療機関を受診するケースが多いです。
また、知的障害を伴わない発達障害の場合、学業面では優秀であることも多く、子ども時代には周囲が特性に気づかないこともあります。
発達障害の生きづらさを減らすためのポイント

発達障害の生きづらさを減らすためのポイントとして、以下の4つが挙げられます。
- 得意なことを活かせる環境を選ぶ
- 苦手なことをカバーできる工夫をする
- 困ったら信頼できる人に相談する
- 発達障害に関する相談窓口や支援を活用する
ここでは上記4つのポイントについてそれぞれ解説します。
得意なことを活かせる環境を選ぶ
発達障害の特性は一人ひとり異なり、苦手なことがある一方で、突出した得意分野を持つこともあります。
そのため、自分の強みを理解し、それが活かせる場を選ぶことが重要です。
例えば対人関係が苦手な人でも集中力や記憶力に優れていれば、研究やデザイン、技術職などで力を発揮できる場合があります。
自分に合わない環境に無理に適応しようとすると、ストレスがたまり、自己評価の低下にもつながりかねません。
だからこそ、まずは「自分は何が得意なのか」「どんな状況で心地よく過ごせるのか」を見つけることが大切です。
そのうえで、得意な能力が評価される職場や無理なく過ごせる生活環境を選ぶことで、生きづらさを軽減できるでしょう。
苦手なことをカバーできる工夫をする
発達障害の特性による困難は、ほんの少しの工夫によってカバーできる場合が多いです。
例えば忘れ物が多い場合は、メモやアラーム、ToDoリストを活用して対応できます。
時間管理が難しい場合は、タスクを小分けにして順序を決めるだけでも取り組みやすくなるでしょう。
また口頭での指示が理解しづらい場合は、メールやチャットなど文字で伝えてもらうようにお願いする方法もあります。
大切なのは「苦手を克服しよう」と無理に努力するのではなく、「どうすれば苦手を上手く回避・補えるか」と発想を切り替えることです。
環境や習慣を少しずつ調整していくことで、日常のストレスを大きく減らせます。
困ったら信頼できる人に相談する
発達障害のある人は、困りごとをひとりで抱え込んでしまう傾向があります。
特に周囲に理解されなかった経験がある場合、「どうせ相談しても無駄だ」と感じてしまうこともあるでしょう。
しかし、信頼できる人に話すことで状況が改善することも少なくありません。
上司や同僚、家族、友人などに自分の特性や困っていることを正直に伝えることで、必要な配慮や支援を得られることがあります。
また、相談のハードルが高いと感じる場合は、「週に一度だけ報告する」「事前にメモで伝える」などの方法を使うのがおすすめです。
困りごとは一人で抱え込まず、周囲のサポートを受けましょう。
発達障害に関する相談窓口や支援を活用する
発達障害に関する支援制度や相談窓口は全国に数多く整備されているため、それを活用することで悩みの軽減に大きく役立ちます。
例えば『発達障害者支援センター』では、本人や家族からの相談に応じ、地域の福祉・医療・教育機関と連携した支援を行っています。
また『障害者就業・生活支援センター』では、仕事と日常生活の両面からサポートが受けることが可能です。
発達障害の診断や検査を希望する場合は、精神科や心療内科を受診するとよいでしょう。
各自治体のホームページには、相談可能な医療機関や窓口の一覧が掲載されていることもあるため、お住まいの自治体ホームページをチェックしてみてください。
発達障害は病気ではなく特性であると理解することが大切
発達障害は約10人に1人の割合で診断されており、年齢や性別を問わず多くの人がそれぞれの特性と向き合いながら生活しています。
困難を感じることも多々あるかもしれませんが、病気ではなく特性であると理解することが大切です。
得意なことを活かしたり苦手を補ったりすることで生きやすくなるため、ネガティブにとらえずに、自分でできる工夫を積極的にしていきましょう。
かもみーるでは、医師監修のオンラインカウンセリングを行っています。
「発達障害なのではないか」「病院を受診すべきか迷っている」という方は、ぜひ当院までご相談ください。
▶︎カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶︎新規会員登録はこちら
