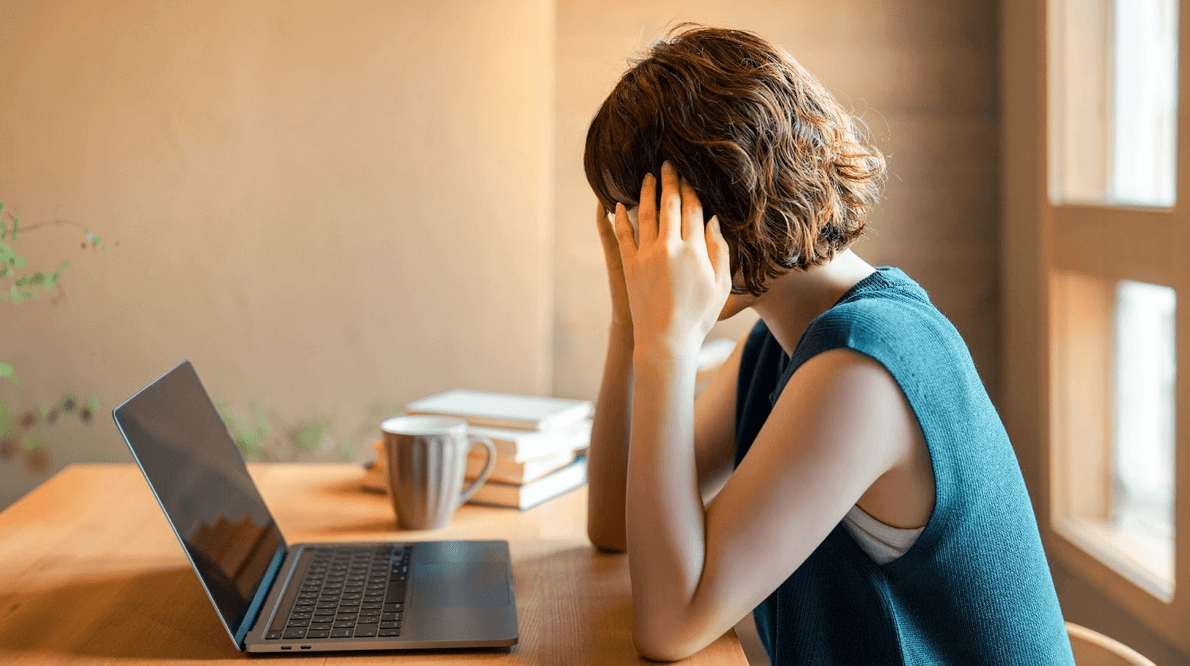考えるのが辛い、何も考えられなくなったなどと感じることが頻繁にある場合、病気が隠れているかもしれません。
また、考えることができない、思考が停止するなどの状態は、仕事や社会生活に支障をきたします。
この記事では、考えや頭がまとまらないときにみられる症状や原因、対処法や疑われる病気、受診の必要性などについて紹介します。
この記事によって、自分の頭で考えられないという不安を少しでも軽減できれば幸いです。
「考えがまとまらない」とはどんな状態?

「考えがまとまらない」とき、具体的には以下のような症状がみられます。
- 頭がぼんやりして集中できない・頭が冴えない・回らない
- 相手の話が頭に入ってこない・言葉が出ないなどスムーズに会話できない
- 考え事をしていても、情報が散らばってしまう
- 覚えたり思い出したりすることがうまくできない
- 頭がうまく働かず、考えるのが遅くなった
- ひとつのことを深く考えられない
- 論理的に考えられない
- 事実ではない妄想や思考の混乱がある
思考するうえで必要となる脳内の作業が、何らかの原因によってうまく働かないことが、考えがまとまらない原因であるといえるでしょう。
考えがまとまらない原因

考えがまとまらない原因は、何かひとつのことではなく、さまざまな要因が絡み合っていることが考えられます。
ここでは、考えがまとまらない状態になる原因について紹介します。
睡眠不足
考えがまとまらない原因の中でも、睡眠不足は特に大きな割合を占めます。
睡眠の目的は、脳や身体の疲労を回復し、日中の活動時間で傷んだ細胞を修復したり免疫細胞を活性化したりすることです。
しかし睡眠不足になると前頭葉の機能が低下し、集中力や注意力、判断力が低下することが分かっています。
情報の処理能力も低下し記憶の定着も妨げられるため、思考力の低下を招き、新しいアイデアが浮かんでこなくなるなど、仕事にも影響が出ます。
また、睡眠不足になるとストレスホルモンの分泌が促進されます。
そうなると、身体全体の調子の悪化を招き、さらに考えがまとまらない事態へ発展するため注意が必要です。
人間関係や疲労によるストレス
仕事や人間関係、または身体的な疲労によるストレスは、頭が回らず考えがまとまらなくなる原因になります。
人間関係のトラブルは、職場では業務を円滑に進めるため、家族や親戚とは長い人生において円満に付き合っていくために、極力避けなければいけません。
しかし、超過勤務や長時間の拘束などは業務上の都合によるもののため、個人で解決できる問題ではありません。
人間関係や過度な疲労によるストレスは、積み重なると自律神経のバランスが崩れ集中力や思考力の低下につながります。
しかし、社会生活を送る上でゼロにすることは不可能です。
ストレスは、積み重なることで心身のバランスを崩してさまざまな不調が現れる原因となるため、考えがまとまらない状態を引き起こします。
身体の疾患
考えがまとまらないというだけでは病気の特定には至りませんが、原因として以下のような身体の疾患が考えられます。
- 脳梗塞……言葉が急に出なくなる、簡単な指示が理解できなくなる
- 脳腫瘍……言葉が出にくい、理解力・記憶力・集中力の低下
- 低血糖・高血糖……集中力の低下・錯乱・意識障害
これらは考えがまとまらない症状が現れる疾患の中でも急性期の可能性があり、自己判断は危険です。
突然の言語障害や麻痺、意識障害の場合は救急搬送を要することが多いため、救急車を呼んで一刻も早く医療機関を受診する必要があります。
精神疾患
心の病気・精神疾患では、考えがまとまらない状態が以下のような症状として現れます。
- 思考が固定化して柔軟な考え方ができなくなる
- 集中力や記憶力が低下する
- 日々の生活においてさまざまな困難が見られる
心の病気や精神疾患は一見しただけでは分かりにくく、認識が周囲からも理解が得られにくいため、本人がつらい状況に立たされることが少なくありません。
適切な治療を受けるためには、専門家による的確な判断と、本人による客観的な状態の把握が必要です。
考えがまとまらないときの対処法

考えがまとまらない状態を改善するためにできることを紹介します。
心身の健康を管理することで改善が期待できるため、まずは自分で対処してみましょう。
十分に休息をとる
心身ともに疲弊した状態では考えがまとまらないのは当然といえるため、まずはしっかりと休息をとりましょう。
特に、十分な睡眠時間の確保を優先する必要があります。
毎日の就寝時間を決め、睡眠に必要な環境を快適に整えて眠りの質を高めることで、思考力も向上します。
日中の短い時間の仮眠も、脳がリフレッシュするためおすすめです。
仕事中は定期的に休憩時間をとるようにしましょう。
睡眠不足の理由に多いのは、残業にみられる超過勤務です。
しかし、個人が会社の現状を変えることは難しいため、休日の過ごし方を工夫してリラックスや疲労回復に努めましょう。
一度に全てを実践するのではなく、できることから少しずつ始めることで持続的な改善が期待できます。
生活リズムを整える
生活習慣が乱れている場合は思考力が低下しやすくなるため、規則正しい生活へと改善しましょう。
朝の明るいうちに日の光を浴び、夜はなるべく決まった時間に寝ることで、体内時計が整います。
体内時計が整うと睡眠の質が向上し、ホルモン分泌や自律神経のバランスも安定します。
さらに、免疫力も高まり健康も促進するなど、メリットは多いです。
もちろん疲労回復にもなるため、思考のまとまりも期待できます。
適度な運動を心がける
適度な運動は、脳の活性化とストレス解消の2つの重要な効果があるとされます。
特に以下のような有酸素運動は、セロトニンやドーパミン・エンドルフィンなどの神経伝達物質の分泌を促すため、気分の改善や集中力向上に効果が期待できます。
- ウォーキング
- ジョギング(軽め)
- ヨガ・ストレッチ
また、運動によって神経伝達物質が分泌されることは、ストレス耐性の向上にもつながりやすいでしょう。
ストレスが解消でき、さらにストレス耐性がつくことで、集中力や思考力の向上が期待できます。
バランスのよい食事
栄養バランスの良い食事を摂ることは、心身の健康維持の他に、脳の働きを正常に保つとされます。
考えがまとまらない、疲労やストレスを感じている場合は、以下の食材から意識的に栄養素を摂取しましょう。
- 良質なタンパク質……肉・魚・卵・大豆製品など
- ビタミンB群……玄米・豆類・魚類など
- オメガ3脂肪酸……青魚・ナッツ類など
栄養のバランスを整えた中でも、以上のような脳に良い栄養素を1日3食意識して摂ることで、疲労回復や思考力の改善が期待できます。
好きなことでリフレッシュする
自分の好きなことに時間を使ってリフレッシュすることで、思考力が戻ってくる可能性があります。
読書、音楽鑑賞・映画鑑賞・ゲーム・絵を描くことなど、自分の好きなことに集中すると日常のストレスから離れられるでしょう。
思考がリセットされるため、まとまらなかった考えに対しても新たな視点を持ちやすくなります。
専門家に相談する
上で紹介したことを実施しても考えがまとまらない、物事を深く考えられない状態が続く場合は、専門家に相談してみましょう。
受診する診療科は精神科や心療内科です。専門家に相談した場合、以下のような視点からアドバイスを受け取れます。
- ストレスの原因を特定
- 治療法の紹介・選択
- 継続的なサポート
- 客観的な視点での評価
- 職場環境の改善についてのアドバイス
一人で抱え込んでも答えを出せるわけではなく、改善が見られない間に重症化する可能性があります。
症状が長引いたり悪化したりする前に、早めに専門家に相談しましょう。
考えがまとまらない時に疑われる病気

考えがまとまらないことが常に続く場合、精神疾患の可能性があります。
誰でもかかる可能性がある疾患も多いため、頭が上手く働かない場合は参考にしてください。
睡眠障害
睡眠障害は日常生活に影響を及ぼす状態で、寝不足になるだけではなく質の悪い睡眠なども症状として現れます。
睡眠の質が悪い場合、ある程度の時間は眠れていても日中の集中力が低下し、考えがまとまらない、思考が停止するなどの症状が見られます。
睡眠障害が長期化すると、心身のどちらに対しても悪影響があり、うつ病や不安障害などの二次疾患のリスクも高まります。
生活習慣の改善や睡眠環境の見直しなどの他、必要に応じた薬物治療でのアプローチなどが有効です。
不安障害
不安障害は、強い不安や恐怖を感じる状態が一時的ではなく長く続き、日常生活に支障が出る疾患です。
小さなことをきっかけにして最悪の事態にまで考えが及ぶため、思考が混乱してまとまらなくなる、集中できず深く物事を考えられなくなるなど、考える力が低下します。
また、不安障害は精神面だけでなく、身体的な症状として冷や汗やめまい、吐き気などが同時にみられる場合もあります。
認知行動療法や薬物療法でのアプローチで症状の軽減が可能です。
適応障害
適応障害とは、新しい環境や出来事など、生活の変化によって発生するストレスに適切に対応できず、不安や抑うつなどの症状が現れる状態です。
本来のような思考ができず、考えがまとまらなかったり深く考えられなかったりするため、生活の質に影響が出る場合があります。
適応障害は一時的な反応であり、原因が明確である場合が多いため、早い段階で適切な心理的支援や環境調整を行う必要があります。
うつ病
うつ病は、気分が落ち込んだり興味が薄れたりする抑うつ状態が長く続く精神疾患です。
遺伝要因や環境的要因、またはストレスで脳の働きに問題が生じなど、原因とされるものは多岐にわたります。
慢性的な疲労感や集中力の低下、思考がまとまらない、深く掘り下げられない、逆に考え事が止まらないなどの症状がみられます。
薬物療法や心理療法が一般的な治療法であり、適切な治療を受けることで改善は期待できますが、専門家による早期診断・ケアが必要です。
統合失調症
統合失調症は、脳の情報処理や現実の認識に障害が生じ、幻覚や妄想、考えがまとまらなくなるといった症状が現れる精神疾患です。
遺伝や環境、脳機能などの要因の複雑な相互作用が原因と考えられています。
治療は長期的な薬物療法や精神療法・作業療法などがあり、心理社会的介入を必要とします。
治療は長期にわたりますが、医師との協力体制により最適な治療を受けることで症状を改善し、社会生活を送ることが可能です。
考えがまとまらないときは受診が必要?

考えがまとまらない状態のときに、改善方法を行ってみても症状が変わらない場合、早めの受診をおすすめします。
呂律が回らなくなる・麻痺・意識障害などが見られる脳梗塞や低血糖など、身体の疾患が原因で考えがまとまらないなどは、救急車を呼ぶ必要がある症状です。
心の病・精神疾患は、自力で対処することは困難であり、専門医にみてもらうことで発見が遅れずに済み、適切な治療法も判明します。
精神疾患の場合は症状が徐々に現れることが多いため、以下のような症状が2週間以上続く場合を目安として、精神科か心療内科の受診をおすすめします。
- 普段はしないような仕事上のミスが突然増え始めた
- これまで苦もなくできていた日常生活が送れなくなってきた
- 会話の際に言葉が出なくなることがある
- 脳に異常が見られない場合
心の病・精神疾患は自分での判断が難しい場合があるため、かかりつけの医師に相談してみるのもいいでしょう。
他の診療科で明らかな身体的疾患が見当たらなかった場合も、精神科や心療内科の受診を検討しましょう。
専門家への相談が強い味方になります
考えがまとまらないことを心の病気や精神疾患につなげるのは大げさな気がしたり、実際診断されてしまうのが怖かったりする人もいるでしょう。
しかし専門家への相談は、放置することで悪化や二次疾患を招くことを避け、早めの診断によって適切な治療を効果的に受けるためのきっかけになります。
『かもみーる』は、医師監修のオンラインカウンセリングサービスを提供しています。
オンライン診療は受診にハードルの高さを感じている人が、相談ならしてみたいという場合に適しています。
医師のほか、臨床心理士や公認心理士を中心とした有資格者がお話を伺います。ぜひお気軽にご相談ください。
▶カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶新規会員登録はこちら