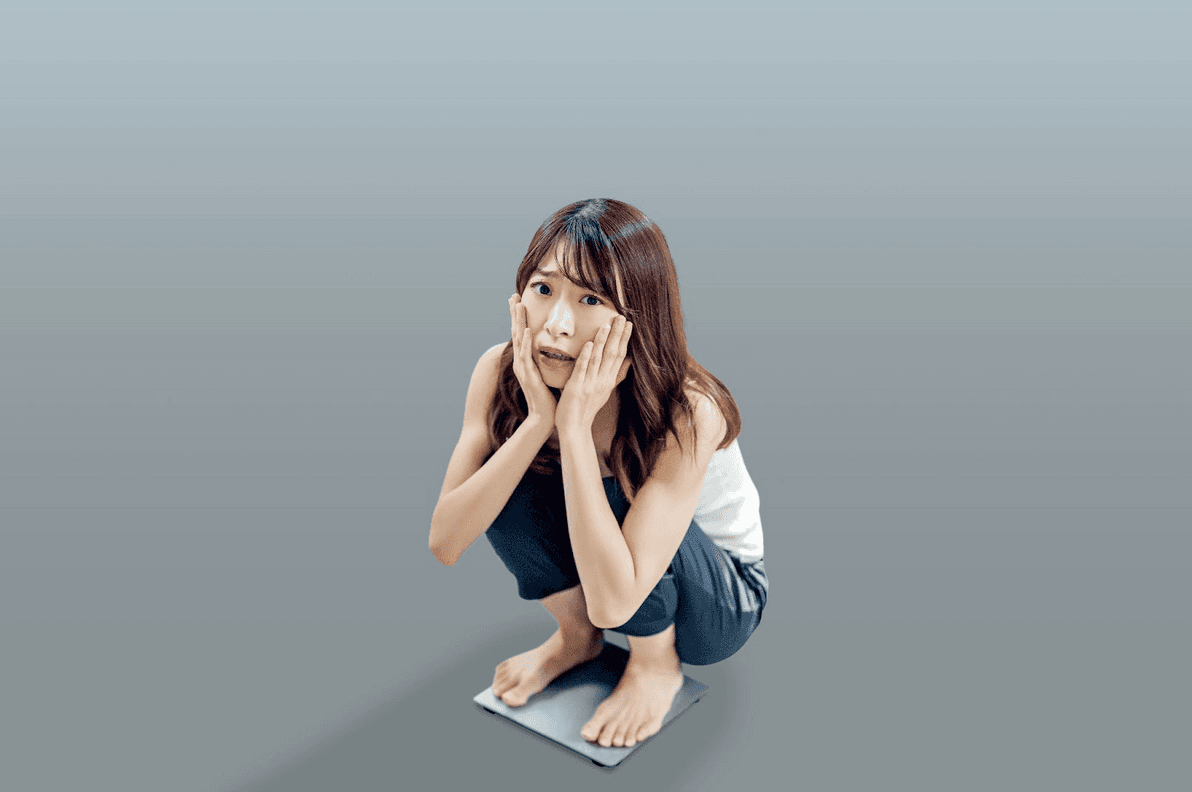忙しさや人間関係などによるストレスが重なると、「お腹が空かない」「ご飯が入らない」と感じる方もいるでしょう。
無理に食べようとしても喉を通らず、つい食事を抜いてしまう……。
そんな状態が続くと、「これは病気なのか、それともストレスのせいなのか」と不安になるものです。
一時的な食欲不振であれば心配いりませんが、体の不調や心の病気が隠れている可能性もあるため注意が必要です。
この記事では、ストレスが原因で食欲がなくなる理由や考えられる病気、日常でできる対処法、そして受診の目安について解説します。
食欲不振でお悩みの方は参考にしてください。
ストレスが原因で食欲不振になるのはなぜ?

強いストレスがあると、「なんだか食べたくない」「お腹空かない」と感じることがしばしばあるものです。
ストレスが原因で食欲を失う場合、その背後には心と体のメカニズムが関係しています。
ここでは、ストレスと食欲不振の関係について詳しくみていきましょう。
自律神経の乱れが原因に
精神的なストレスは、自律神経のバランスを乱す大きな要因となります。
自律神経には、活動時や緊張状態で働く『交感神経』と、リラックス時や睡眠中に優位になる『副交感神経』があり、この2つがバランスを取りながら体の働きを調整しています。
しかし、強いストレスを受けるとこのバランスが崩れ、心身にさまざまな不調があらわれることがあります。
そのひとつが食欲の低下です。
自律神経が乱れると、脳の摂食中枢がうまく働かず、空腹感を感じにくくなります。
さらに、胃の不快感や胃痛、味覚の変化(味がしない、苦く感じるなど)といった症状が出ることもあります。
これが、ストレスによって「食べたくない」「食べられない」と感じる主な理由です。
胃の働きに影響を与える
ストレスが脳の視床下部に作用すると、そこから交感神経を通じて胃の働きにも影響が及びます。
具体的な影響としては、胃の血管が収縮して血流が低下し、胃を守るために必要な胃粘膜液の分泌が減ってしまうのです。
さらに、副交感神経も刺激され、胃のぜん動運動(胃の動き)が過剰になり、胃酸の分泌も増加します。
これらが同時に起こることで、胃の機能が不安定になり、以下のような状態に陥ります。
- 胃が膨らみにくくなり、食べ物が入りにくくなる
- 胃酸過多による胃の不快感や痛み
- 消化不良によるむかつきや吐き気
こうした胃の不調が食欲低下につながり、「ご飯を食べたくない」「少ししか食べられない」という状態が続いてしまうのです。
ストレスで「ご飯食べられない」「お腹空かない」ときに隠れているかもしれない病気

ストレスによる食欲不振が続くときは、何らかの病気が隠れている可能性があります。
特に以下のような症状がある場合は、単なるストレスではなく心身の疾患のサインかもしれません。当てはまる方は、早めに医療機関を受診しましょう。
- 食欲不振が一定期間続いている
- 体重減少が見られる
- 下痢や便秘、腹痛がある
- 気分の落ち込みや不安感が強い
- 倦怠感、めまい、頭痛などがある
ここからは、ストレスによる食欲不振に関係する主な病気について紹介します。
機能性ディスペプシア(FD)
機能性ディスペプシアとは、検査では胃腸に明らかな異常がみられないのに、胃の痛みや不快感などの症状が出る病気です。
ストレスが引き金となり、胃の運動機能や知覚過敏に影響が出るのが原因とされています。
症状はさまざまで、胃の痛み、胃もたれ、すぐに満腹になる、胃が熱く感じる、食欲不振などがあります。
検査では異常が見られないことから、少し前は「気のせい」とされてしまうことも多かった疾患ですが、2013年に健康保険適用疾患と認定されました。
機能性ディスペプシアは、健康診断を受けた人の11〜17%、腹部症状で受診した人の45〜53%に見られると言われており、決して珍しい病気ではありません。
(※参照:日本消化器学会『機能性ディスペプシア(FD)ガイド2023』)
過敏性腸症候群(IBS)
過敏性腸症候群は、ストレスや不安により腸の働きに異常が起きることで、便通のトラブルが繰り返される病気です。
主な症状には以下のようなものがあります。
- 下痢や便秘、腹痛を繰り返す
- 食欲不振
- 腹部の不快感
これらの症状に加えて、頭痛やめまい、疲労、不安感などの胃腸以外の症状を伴うこともあります。
検査では異常がないことが多く、生活の質(QOL)を大きく下げる病気として知られています。
拒食症(神経性やせ症)
拒食症は、食事量を極端に制限してしまう摂食障害の一種で、ストレスや心理的な背景が深く関係しています。
特徴的なのは、太ることへの強い恐怖や歪んだ自己認識を抱いている点です。
体重の増減によって自己評価が大きく左右されるため、生活の中心が体重管理に占められています。
最初は「太るのが怖いから食べられない」と感じますが、やがて空腹そのものを感じなくなることもあります。
10代後半〜20代の若い女性に多く見られ、ダイエットをきっかけに発症するケースも少なくありません。
うつ病
うつ病は気分の落ち込みや意欲の低下といった精神的な症状に加え、食欲不振や睡眠障害、倦怠感などの身体的な不調を伴うことがあります。
日常生活の中でストレスや不安が積み重なると、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れ、うつ病を発症しやすくなるといわれています。
うつ病による不安感や焦燥感は、脳の摂食中枢に影響を与えるため、空腹感がわかりにくくなり、食事をとる意欲が低下してしまうのです。
さらに、うつ病では味覚障害が生じることもあり、「味がしない」「おいしく感じない」といった感覚異常から、食べること自体がつらくなってしまうケースもあります。
▶うつ病はどんな病気?特徴や重さごとの症状、なりやすい人の特性を紹介
胃潰瘍
胃潰瘍は、ストレスなどの影響で胃酸の分泌が増え、胃粘膜が傷ついて炎症を起こす病気です。
主な症状には以下のようなものがあります。
- 胸やけ
- 吐き気
- 胃の痛み
- 食欲不振
- 吐血
- 黒色便(血便)
神経質で真面目な人ほど、ストレス性の胃潰瘍を発症しやすい傾向があります。
逆流性食道炎
逆流性食道炎は、胃の内容物(特に胃酸)が食道に逆流し、食道の粘膜に炎症が起こる病気です。
脂っこい食事や過食、早食い、加齢、肥満などさまざまな要因がありますが、ストレスも発症や悪化に関わる要因のひとつとされています。
胃酸の分泌は自律神経によってコントロールされていますが、ストレスを受けると自律神経のバランスが乱れ、胃酸の分泌量が増えたり、分泌のタイミングが不規則になることがあります。
その結果、胃酸が食道へ逆流しやすくなり、炎症が起きることで逆流性食道炎の症状が現れやすくなるのです。
主な症状には以下のようなものがあります。
- 胸やけ
- 胃もたれ
- げっぷ
- 呑酸(酸っぱいものが上がってくる感じ)
- 食欲不振
こうした症状が続くようであれば、内科や消化器内科を受診し、適切な検査や治療を受けることが大切です。
ストレスによる食欲不振は何科を受診すればいい?

「ストレスでご飯が食べられない」「何日も食欲が戻らない」―そんな状態が続く場合は、早めに医療機関を受診することをおすすめします。
原因がはっきりしないまま我慢を続けていると、体調の悪化や重篤な疾患につながる可能性もあるからです。
消化器症状が強ければ「内科・消化器内科」へ
食欲不振に加えて、
- 胃もたれ
- 胃痛
- 吐き気
- 下痢・便秘
- お腹の張りや不快感
などの消化器系の症状が強く出ている場合は、まずは「内科」または「消化器内科」の受診が適切です。
内視鏡検査や血液検査などを通じて、胃腸の機能に異常がないかを調べてもらえます。
ストレスが強い場合は「心療内科」「精神科」も視野に
ストレスを強く感じていたり、気分の落ち込み、意欲の低下などのメンタル面の不調を自覚している場合は、心療内科や精神科などのメンタルクリニックを受診するのがおすすめです。
これらの診療科では、ストレス性の食欲不振やうつ症状、不安障害などに対する専門的な治療が可能です。
必要に応じて、カウンセリングや薬物療法などを組み合わせたサポートを受けることができ、心と体の回復を図ることができます。
▶仙台市の心療内科・精神科おすすめ7選│当日予約可能な医院&選び方も解説
どこを受診するか迷ったら、「かかりつけ医」に相談を
「内科かメンタルクリニックか、どちらを受診すべきか分からない」
そんなときは、まずかかりつけの医師に相談するのが安心です。
症状や経過をもとに、適切な診療科を紹介してもらえることが多いため、スムーズに専門的な治療へとつなげることができます。
自分でできるストレス・食欲不振対策

医療機関を受診して深刻な疾患はないと診断された場合、日常的なストレスケアを取り入れることで、食欲の回復や再発防止が期待できます。
また、ストレスが溜まるとすぐに食欲が落ちる傾向のある方は、日々の生活の中でストレスを上手にコントロールする習慣づくりが大切です。
ここでは、日常生活で意識したいストレス・食欲不振対策を紹介します。
規則正しい生活を心がける
不規則な生活は自律神経の乱れを引き起こし、食欲不振の原因となることがあります。
まずは、毎日決まった時間に起きて朝日を浴びる習慣をつけましょう。
朝日を浴びると体内時計がリセットされ、睡眠を促すホルモンである『メラトニン』の分泌が止まります。
メラトニンは分泌が止まってから約15時間後に再び分泌される仕組みになっているため、朝にしっかり日光を浴びることが、夜のスムーズな入眠につながるのです。
また、メラトニンの分泌が止まることで、『セロトニン(精神を安定させるホルモン)』や『ドーパミン(やる気や快楽に関係するホルモン)』が活性化され、心身のリズムが整いやすくなります。
こうした生活リズムのメリハリが、ストレスへの耐性を高め、食欲の自然な回復を促すと考えられています。
消化のよいものを少量でも3食しっかり食べる
「お腹空かないから」と食事を抜くと胃腸の動きがさらに悪くなり、悪循環に陥ることもあります。
無理に多く食べる必要はありませんが、消化のよいものを少量ずつでも3食とるよう心がけましょう。
<消化のよい食品の例>
おかゆ、うどん、白身魚、鶏ささみ、卵、豆腐、大根、にんじん、キャベツ、バナナ、りんご、ヨーグルト など
※ただし、吐き気や胃痛がある場合は無理をせず、胃腸に負担をかけない範囲で調整しましょう。
定期的な軽い運動を取り入れる
ウォーキングやストレッチなどの軽い運動には、ストレスの軽減や心身をリラックスさせる作用があるとされています。
運動による適度な疲労感は睡眠の質も高め、ストレス回復の土台になります。
運動習慣がない方は、1日15分程度のウォーキングやヨガ、ストレッチなどから始めてみるとよいでしょう。
寝る3時間前までに食事を終える
夜遅い時間の食事は胃腸に負担をかけ、翌朝の食欲不振につながることもあります。
就寝3時間前までに食事を終えることで、胃腸がしっかりと休まり、翌日の体調リズムが整いやすくなります。
胃の不快感には市販薬の活用も選択肢に
ストレスによる食欲不振では、胃のムカつきや胃もたれ、軽い胃痛などを伴うことがあります。
医療機関で深刻な疾患が否定されている場合は、こうした症状に対して市販の胃腸薬を一時的に使うのもひとつの対処法です。
市販の胃腸薬には、以下のようなタイプがあります。
種類 | 働き |
消化酵素系胃腸薬 | 消化を助け、胃もたれや食後の重さをやわらげる |
胃酸分泌抑制系胃腸薬 | 胃酸の過剰分泌による胃痛、胸やけなどに効果的 |
漢方胃腸薬 | 生薬を中心とし、胃腸の働きを穏やかに整える |
総合胃腸薬 | 制酸・粘膜保護・消化促進など複数の作用を併せ持つ |
胃腸の働きを整える胃腸薬 | 胃の痙攣をやわらげ、リズムを整える |
どの薬を選べばいいか迷った場合は、総合胃腸薬を選ぶとよいでしょう。
ただし、市販薬はあくまで一時的な対処にすぎません。根本的な改善には、生活習慣やストレスへの対応が不可欠です。
また、症状が長引いたり、悪化したりする場合は、我慢せずに再度医療機関を受診しましょう。
小さな楽しみや気分転換を日常に取り入れる
ストレスを感じやすい人、ため込みやすい人は、忙しい日々の中でも、意識的にリラックスできる時間をつくることが大切です。
読書や音楽、アロマ、散歩など、リフレッシュできる行動を意識して取り入れてみましょう。
短い時間でも好きなことをする習慣が、ストレスを溜め込みにくい心の状態をつくります。
一人で抱え込まず、人に頼る
ストレスによる不調を繰り返してしまう方の中には、「誰にも相談できない」「迷惑をかけたくない」と思ってしまう方も少なくありません。
家族や友人、職場の信頼できる人に話してみるだけでも、心が軽くなることがあります。
必要であれば、カウンセラーや精神科・心療内科での相談も選択肢のひとつです。
ストレスで食欲がないときは、早めに専門家に相談を
ストレスが原因で食事が喉を通らなくなったり、食欲がなくなったりすることは、誰にでも起こり得ることです。
とはいえ、食欲不振が何日も続いたり、胃痛や不眠、気分の落ち込みなどの症状をともなう場合は、単なるストレス反応ではなく、心や体の不調のサインかもしれません。
消化器内科や心療内科・精神科などの専門医に相談することで、原因を明らかにし、適切なケアにつなげることができます。
医師と話すだけでも気持ちが軽くなることもありますので、「こんなことで」と遠慮せず、気軽に相談してみましょう。
『かもみーる心のクリニック(仙台院)』では、対面診察や心理カウンセリングを通じて、ストレスによる食欲不振や心の不調に寄り添ったサポートを行っています。
まずはお気軽にご相談ください。
▶︎カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶︎オンラインカウンセリングの新規会員登録はこちら