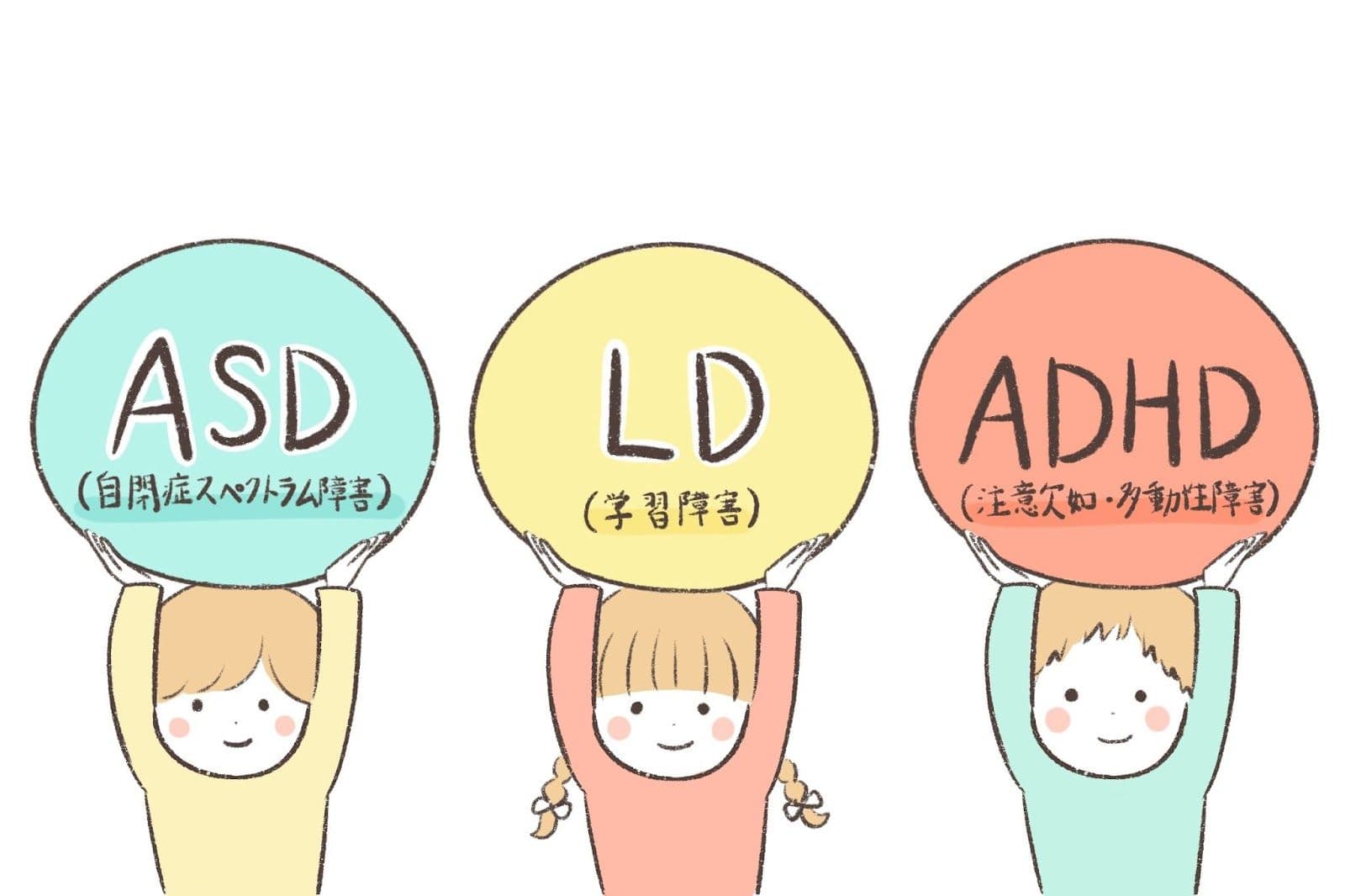ADHDやASD、LDなどの発達障害を患っている方、診断されたお子さんがいる方のなかには、 薬物療法に不安を感じる方も少なくありません。
そんなときに、「TMS治療が発達障害に効果があるようだ」という噂を聞くと、 薬物療法以外の方法に興味をもつのではないでしょうか。
実際のところ、TMS治療が発達障害自体に効果があることはまだ解明されていません。 ただし、ADHDに伴ううつ症状に効果があるとされています。
この記事では、発達障害について、TMS治療が発達障害にどう影響するか、 エビデンスや薬物療法について詳しく紹介します。
ご自身やお子さんの発達障害にお悩みの方、TMS治療に興味がある方は、ぜひご覧ください。
発達障害の種類
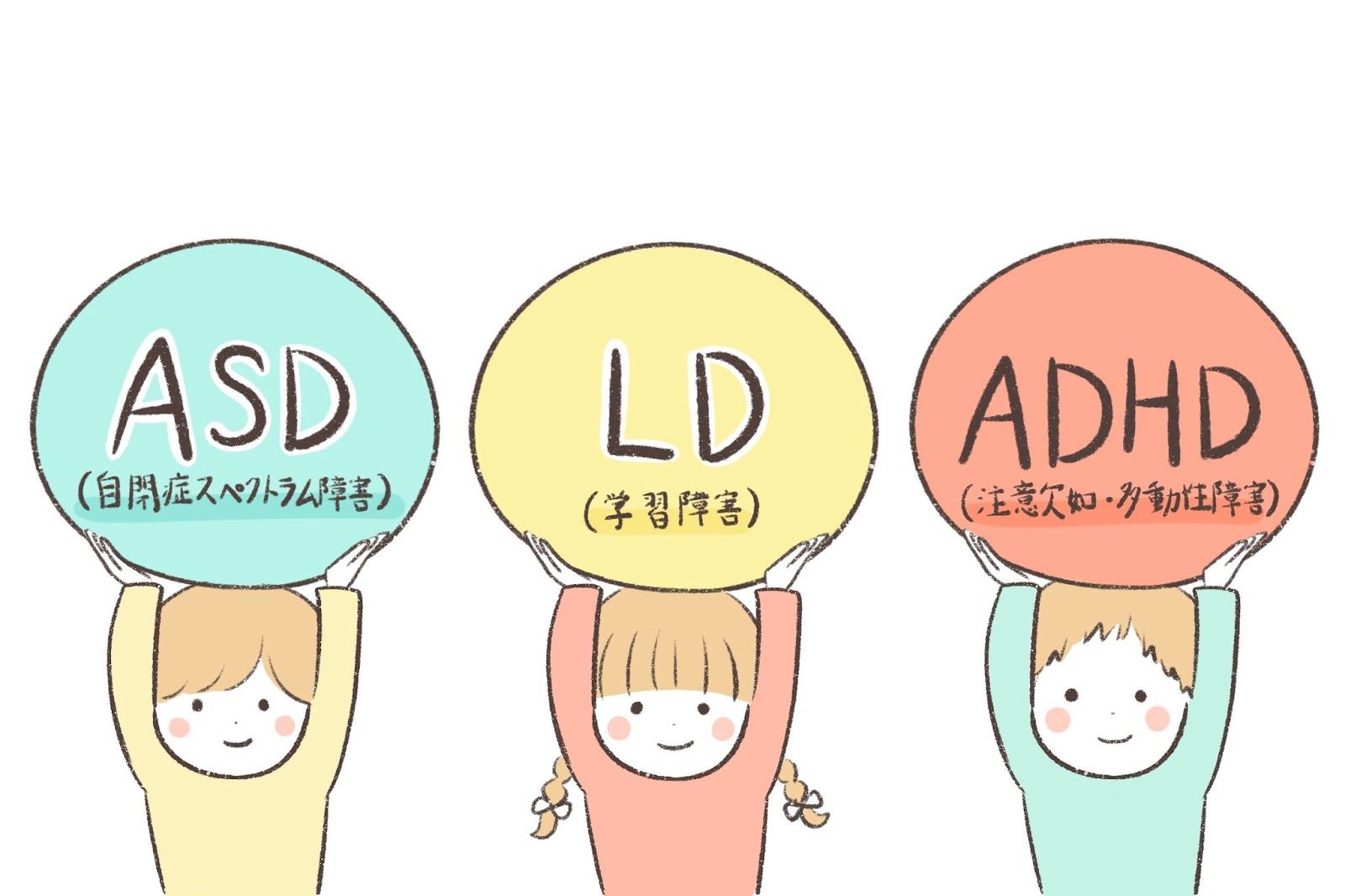
発達障害にはADHD、ASD、LDがあり、それぞれ特性が異なります。 まずは、発達障害の種類を紹介します。
ADHD(注意欠陥多動性障害)
ADHDは、不注意・衝動性・多動性の3つの特性をもつ発達障害です。 3つのうち1つが際立つケースもあれば、混合型と呼ばれ複数が現れる場合もあり、 個人によって症状の特性は異なります。
集中力や注意力が散漫になると、学校では大勢で行う授業への参加が難しくなったり、 職場では次に何をすれば良いかわからなくなったりと、学業や仕事への支障をきたす状態です。
症状として、うつ病、不安症、双極性障害などを併発するケースもあり、 他の発達障害であるASDやLDとの合併症も見られます。
また、多くは12歳以前に出現する症状ですが、幼少期に見られる特性と区別が難しく、 診断が遅れてしまうことも少なくありません。
以下は、文部科学省が定める発達障害の定義です。
ADHDとは、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び/又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。
また、7歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。
出典元:文部科学省
ASD(自閉スペクトラム・アスペルガー症候群)
ASDは、対人コミュニケーションの障害・社会性の障害・強いこだわりの3つが特性として現れるのが特徴です。
3歳頃から診断を受ける方が多く、視線を合わせない、1人遊びをする、 名前を呼んでも振り返らないなどの特徴があります。
一方的に言いたいことだけをしゃべったり、身振り手振りのコミュニケーションが苦手だったりと、 対人関係で特徴が見られます。
また、特定の刺激や活動に強いこだわりが見られる方が多く、 いつもと道順が違う、順番が違うなどとパニックを起こしてしまうことも。
対人関係で思い悩み不登校や行き渋り、抑うつ状態などの二次障害を引き起こすケースもあります。
ASDは、アメリカ精神医学会による「精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM)」に基づいた問診、 心理検査、スクリーニングテストなどを併用して行われます。
以下は、アメリカ精神医学会による診断基準です。
1.複数の状況で社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的欠陥がある
2.行動、興味、または活動の限定された反復的な様式が2つ以上ある (情動的、反復的な身体の運動や会話、固執やこだわり、極めて限定され執着する興味、 感覚刺激に対する過敏さまたは鈍感さなど)
3.発達早期から1と2の症状が存在している
4.発達に応じた対人関係や学業的・職業的な機能が障害されている
5.これらの障害が、知的発達症(知的能力障害)や全般性発達遅延ではうまく説明されない
出典元:大人の発達障害ナビ
LD(学習障害)
LDとは、読書障害(ディスレクシア)・書字障害(ディスグラフィア)・算数障害(ディスカリキュア)と呼ばれる3つの特性がある発達障害です。
読み書きや計算などに学習の遅れが発生するのが特徴で、単体で現れたり、混合して現れたりします。
授業についていけない、宿題ができないなど、小学校に進学してから周りとの差に気づくケースが多いです。
LDと診断されても、文章の構成が得意な方もいれば、算数が得意な方もいて症状の現れ方には個人差があります。
LDは、文部科学省により以下のように定義されています。
学習障害とは、基本的には、全般的な知的発達に遅れはないが、 聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどの特定の能力の習得と使用に 著しい困難を示す、様々な障害を指すものである。
学習障害は、その背景として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、 その障害に起因する学習上の特異な困難は、主として学齢期に顕在化するが、 学齢期を過ぎるまで明らかにならないこともある。
学習障害は、視覚障害、聴覚障害、精神薄弱(注)、情緒障害などの状態や、 家庭、学校、地域社会などの環境的な要因が直接の原因となるものではないが、 そうした状態や要因とともに生じる可能性はある。また、行動の自己調整、 対人関係などにおける問題が学習障害に伴う形で現れることもある。
出典元:文部科学省
発達障害へのTMS治療について

発達障害に対してTMS治療が効果的であるかは、各国で研究が行われていますが限定的な効果しか得られていないのが現状です。 まだ研究は初期段階となるため、参考程度にとどめてください。
ここからは、発達障害へのTMS治療について紹介します。
TMS治療とは
TMS治療は、主にうつ病患者に用いられます。脳の特定部位に磁気刺激を与えて活性化させ、脳血流を増加させることで低下した機能を回復させます。
副作用が少なく、これまでの向精神薬での治療に比べて早く効果が現れることや、 服薬で効果が感じられなかった方もTMS治療を受けて改善した例があります。
ADHDへのTMS治療のエビデンス
ADHDは、前頭前野の機能障害が関連していると考えられるため、 その部分をTMS治療で刺激することで、注意力や行動制御の改善が期待できる結果が得られています。
参考:
1.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22551775/
2.https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10970838/
ASDへのTMS治療のエビデンス
TMS治療で脳領域を刺激すると、社会的認知機能を向上させる可能性があります。ASDの繰り返し行動や、 強迫観念、認知の機能に効果があるとされています。
参考:
1.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26536383/
2.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28346865/
発達障害へのTMS治療の注意点

TMS治療が発達障害に効果があると報告されている論文もありますが、 日本ではまだ研究発表も少なく、臨床事例も少ないことからクリニックや医師によって見解が異なるのが現状です。
ここからは、発達障害へのTMS治療の注意点を紹介します。
大人の場合
大人の方で発達障害と診断され、TMS治療を検討している方も少なくありませんが、 日本国内でのTMS治療は重度のうつ病の場合に保険適用となり、それ以外は自由診療です。
臨床効果の事例が少ないことから、回復が期待できない可能性も考えなければいけません。
ただし、ADHDにおけるうつ症状を発症している場合は、TMS治療が有効である可能性が高く、 副次的な症状が落ち着くことでご本人が楽になるケースは十分に考えられます。
発達障害へのTMS治療は、医師とよく相談のうえで判断する必要があります。
子どもの場合
TMS治療は、そもそも成人に適応される治療となるため、子どもへの治療はリスクが高いと考えられています。
脳が未発達な子どもにTMS治療を行う場合は、安全性が確保されていないため、 脳機能だけではなく他の機能にも悪影響を及ぼすリスクがあると考えておきましょう。
発達障害に使用される代表的な薬と副作用

発達障害への治療は、症状に合わせた薬物療法が行われる場合もあります。 ただし、注意点もあるためリスクも把握しておきましょう。
コンサータ
コンサータは、ADHDの治療に用いられる中枢神経刺激薬です。
主成分はメチルフェニデートで、脳内のドパミンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害し、濃度を上げて不注意や頭のモヤモヤなどに効果を発揮します。
1日1回の服用で12時間効果が持続する長時間作用型の薬で、朝に服用すれば日中の症状をカバーできるのが特徴です。 効果が現れるまでには1週間程度かかります。
コンサータは認められた医療機関でしか処方できず、医師や医療機関の登録が必要なことも特徴として挙げられます。
主な副作用として、食欲減退、不眠症、体重減少、頭痛、腹痛、悪心などがあります。 特に食欲減退と不眠は高頻度で報告されているため注意が必要です。
さらに、依存のリスクがあるため適切な休薬期間を設けることが推奨されています。 成長期の小児の場合、体重減少や成長遅延が懸念されるため、定期的な成長観察が必要です。
ストラテラ
ストラテラは、ADHDの治療に用いられる非中枢神経刺激薬です。
主成分はアトモキセチンで、ノルアドレナリン再取り込み阻害作用をもち、前頭前野でのノルアドレナリンとドパミンの濃度を上げて過集中への視野を広げる効果が期待できます。
依存性がなく、24時間効果が持続しますが効果の発現が緩やかで、1〜2週間程度で実感でき、 6〜8週間で安定するのが特徴です。
主な副作用として、悪心、食欲減退、傾眠、頭痛、口渇などが挙げられます。 特に悪心は高頻度で報告されているため注意が必要です。
コンサータと異なる点として、依存性や乱用のリスクが低く、不眠や食欲低下などの副作用が少ない傾向にあります。
1日1回または2回に分けて服用します。効果の発現が緩やかですが、途中でやめずに継続的に服用することが重要です。
インチュニブ
インチュニブは、ADHDの治療に用いられる非中枢神経刺激薬です。 主成分のグアンファシンは、α2Aアドレナリン受容体作動薬であり、前頭前野の神経伝達を改善することで効果を発揮します。
インチュニブの特徴として、依存性がなく、24時間効果が持続することが挙げられます。 効果の発現は比較的早く、1〜2週間程度で効果が現れ始めます。
主な副作用には、傾眠、血圧低下、頭痛、口渇、めまいなどがあります。特に傾眠は高頻度で報告されています。血圧低下や徐脈も注意が必要な副作用です。
インチュニブは1日1回の服用で、通常は朝に服用します。急な中断は血圧上昇や頻脈につながる可能性があるため、 減量は徐々に行う必要があります。
インチュニブは中枢神経刺激薬と比べて、不眠や食欲低下などの副作用が少ない傾向にあります。 また、依存性や乱用のリスクが低いため、長期的な使用が可能です。
リスパダール
リスパダールは、小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性の治療に用いられる非定型抗精神病薬です。
主成分のリスペリドンは、ドパミンD2受容体とセロトニン5-HT2A受容体を遮断することで効果を発揮します。
リスパダールの特徴として、陽性症状(幻覚、妄想など)だけでなく、陰性症状(意欲低下、感情鈍麻など)にも 効果があることが挙げられます。効果の発現は比較的早く、1〜2週間程度で効果が現れ始めます。
主な副作用には、錐体外路症状(アカシジア、パーキンソン症状など)、高プロラクチン血症、体重増加、眠気などがあります。特にアカシジアや不眠症は高頻度で報告されています。
リスパダールは1日1回または2回に分けて服用します。 錐体外路症状や高プロラクチン血症などの副作用に注意が必要ですが、 第一世代抗精神病薬と比べてこれらの副作用は少ない傾向にあります。
リスパダールは統合失調症の再発予防にも効果があり、長期的な使用が可能です。 ただし、長期使用による体重増加や代謝異常には注意が必要です。
TMS治療はADHDのうつ症状に効果的
発達障害へのTMS治療は、服薬に比べてリスクが少ないと考えられる場合もありますが、 現在はまだ研究途中であるためはっきりと効果があるとは言い切れません。
特に、小児へのTMS治療は脳に悪影響を与える可能性が否定できないため、 現状は服薬での治療が一番と言えるでしょう。
ただし、ADHDによるうつ症状には効果があると考えられているため、二次障害が改善することで 日常生活を過ごしやすくなる可能性はあります。
オンライン診療・オンラインカウンセリングの『かもみーる』では、発達障害に関するご相談も承っております。
医師・公認心理士・臨床心理士・精神保健福祉士の資格をもったカウンセラーが、 患者様の不安を取り除きます。
不安を抱えている方は、まずはオンラインカウンセリングでゆっくりとお話しください。 専門家がしっかりとお聞きします。
▶ カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶ 新規会員登録はこちら