「職場復帰したいが適応障害の再発が怖い」
「再発しないためににはどうしたらいい?」
「適応障害がぶり返しそうな感じがする」
適応障害を経験した方の中には、再発について不安に感じている方も多いでしょう。
適応障害は一度回復したとしても、再び同じストレス環境に戻ることで症状がぶり返すことがあります。
しかし、適応障害について正しく知り、適切な対策を取れば再発リスクを軽減することが可能です。
この記事では、適応障害の再発率や原因、そして再発を防ぐための方法、職場復帰をサポートする支援制度や支援機関などについて解説します。
適応障害とは

適応障害とは、特定のストレスによって気分の落ち込みや不安、意欲低下、不眠などさまざまな精神症状・身体症状が起こる病気です。
個人差もありますが、症状が強く、仕事や学業、家事育児に支障が出てしまうケースも少なくありません。
適応障害は働き盛りの年代で多く見られ、『職場におけるメンタルヘルス不調者の事例性に着目した支援方策に関する研究(厚生労働省)』の調査結果では、適応障害はうつ病に次いで診断書に記されることが多い病気であることがわかっています。
適応障害については、以下の記事でも詳しく解説しています。
適応障害の再発率
適応障害やうつ病といった病気は、再発率の高い病気です。
『主治医と産業医の連携に関する有効な手法の提案に関する研究(厚生労働省)』の調査によれば、適応障害やうつ病などメンタルヘルスの不調で復職した人のうち、1年以内に57.4%、2年以内に76.5%の人が再病休していました。
この結果から復職後の2年間は特に再発に注意が必要と考えられており、再発防止のためには職場環境(業務量・業務内容・勤務時間・配属先の調整など)について会社としっかり相談することが大切です。
なぜ?適応障害が再発を繰り返す理由や原因

ではなぜ、適応障害は再発・再燃を繰り返しやすいのでしょうか。ここからはその理由について解説します。
ストレスの原因が残っている・再度ストレス環境に陥ってしまった
適応障害の主な原因はストレスです。一度回復しても以下のような状況に陥ってしまうと、再発のリスクが高まります。
- 職場環境の変化がない……休職前と同じ環境に戻ることで、同様のストレスに直面する
- 業務量の調整不足……段階的な復帰ではなく、一気に元の業務量に戻ってしまった
- 人間関係の改善がない……職場の人間関係が原因だった場合、配置換えがされていない
また、これまでのストレスは無くなったものの、新しいストレスが現れるケースもあるでしょう。
適応障害は、悪いことだけがストレスになるわけではありません。昇進や進学、結婚、出産など喜ばしいことや本人が望んでいたことであっても、適応障害を発症することがあります。
適応障害の再発を防ぐためには、無理をしないことが大切です。
発達障害など先天的な特性が原因になっている
発達障害と適応障害には、深い関連があります。発達障害とは、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如多動症(ADHD)など複数の障害の総称です。
発達障害では「一つのことに集中できない」「じっとしていられない」「コミュニケーションが苦手」「強いこだわりがある」といった特性があるものの、日常生活を送ることには問題がなく 本人が気づいていないケースも多いです。
発達障害のある方はこれらの特性によりストレスを感じやすく、適応障害につながることがあります。
適応障害の再発を何度も繰り返す場合、発達障害が隠れている可能性も考えて医師やカウンセラーに相談しましょう。
適応障害の再発のサイン・兆候
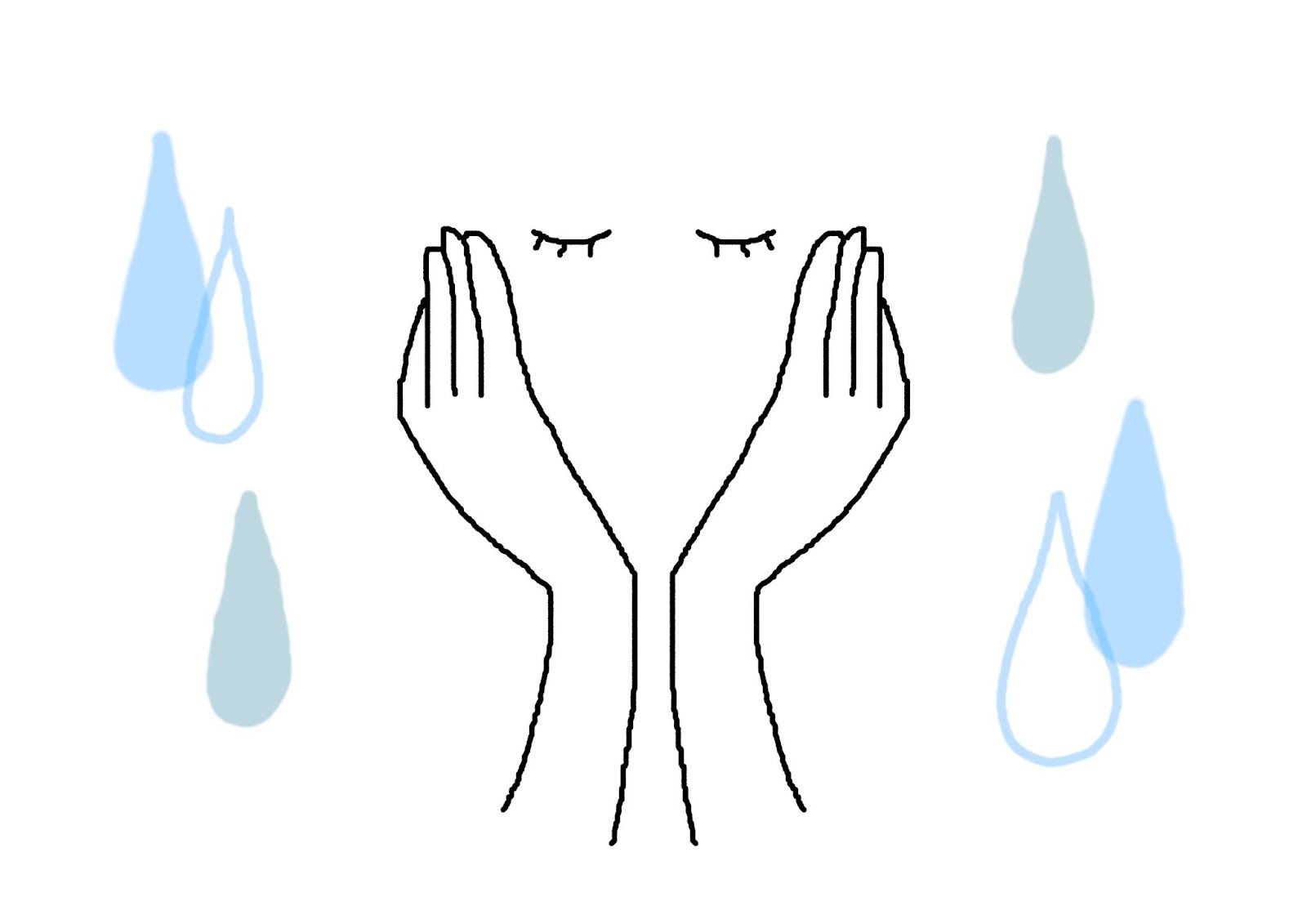
適応障害の再発のサインや兆候としては、不安感、抑うつ気分、頭痛や食欲不振、睡眠障害、認知機能低下などがあります。
また、仕事で何かがあったときに自暴自棄になったり強い怒りを感じる場合も、ストレスに対処する処理能力が低下しているかもしれません。
このような兆候があった場合は十分休息を取り、早期に対処するためにも早めに医師やカウンセラーに相談しましょう。
【日常生活】適応障害の再発を防ぐための対策・注意点

適応障害の再発を防ぐためには、日常生活でさまざまな対策を取ることが大切です。
- 体調・生活リズムを整える
- しっかり治療を継続する
- 周囲に頼ったり相談することを心がける
- 無理せずストレスを溜め込まないようにする
- ストレスとの付き合い方を学ぶ
ここからは、日常生活での対策についてそれぞれ詳しく解説します。
体調・生活リズムを整える
規則正しい生活リズムを維持することは、心と身体の健康を保つうえで非常に重要です。
十分な睡眠時間を確保するだけでなく、起きる時間と寝る時間をなるべく一定にし、規則正しい生活を送りましょう。
また、栄養バランスの良い食事をしっかり食べ、自分に合った適度な運動を定期的に行うことも大切です。
しっかり治療を継続する
適応障害の治療は、症状が改善した後も継続しましょう。自分では完治したと思っても、環境が変化したときや大きなストレスがかかったときに症状がぶり返してしまうことがあります。
自己判断で治療を中断してしまうと再発や悪化につながるリスクがあるため、前もって医師やカウンセラーと十分相談することが大切です。
周囲に頼ったり相談することを心がける
適応障害の再発を防ぐためには、一人で抱え込まず周囲にサポートを求めることも有効です。
適応障害になりやすい人の特徴の一つに「人に頼るのが苦手で、一人で抱え込んでしまう」が挙げられます。
家族や友人、同僚や上司など身近な人に悩みを打ち明けるのが難しい場合は、医師やカウンセラーに相談してみるといいでしょう。
無理せずストレスを溜め込まないようにする
適応障害の再発を防ぐために大切なことは、無理をせずストレスを溜め込まないことです。
仕事や日常生活でのストレスをゼロにすることはできませんが、こまめにストレス解消をしたり、ストレスとの向き合い方を工夫することで対応できます。
また、回復したからといって、いきなり以前と同じ量の仕事や家事をこなそうとするのは避けましょう。時間をかけて徐々に業務量を増やしていくことが大切です。
ストレスとの付き合い方を学ぶ
ストレスを完全になくすことは難しいため、上手に付き合うスキルを身につけることも有効な対策です。
適応障害にかかってしまう方の中には、何事も極端に考えてしまう「0か100か思考(全か無か思考)」や、「〜べき思考」など、考え方に癖があることが多くあります。
このような癖はそれ自体がストレスにつながってしまうため、自分の考え方の癖について知り、柔軟に対処するための方法を学ぶことが大切です。
ストレスと向き合う方法にはさまざまなものがありますが、適応障害の再発防止や回復を早めるのに有効なのが、心理カウンセリングです。
心理カウンセリングでは専門の資格を持った心理士が認知行動療法などさまざまなアプローチを行い、ストレスに対処する能力を身につけていくことができます。
【復職時】適応障害の再発を防ぐための対策・注意点

職場への復帰を考える際は、以下の点に注意しましょう。
- ストレスから離れられる環境を整える
- 環境が変化するタイミングに注意する
- サポート制度を活用する
- 職場復帰を焦らない
それぞれ詳しく解説します。
ストレスから離れられる環境を整える
ストレスの原因から離れる、ストレスの原因と接触する時間や頻度を減らすなど、職場の環境を整えることで適応障害の再発を予防しましょう。例えば、以下のような点です。
- 業務内容(業務量の軽減、責任の分散、優先順位付けで無理のないスケジュールを組む)
- 勤務形態・勤務時間(短時間勤務、部分的な在宅勤務など)
- 人間関係・コミュニケーション(配置転換)
会社の理解や協力が欠かせないため、復帰前に上司や人事担当者としっかり話し合いましょう。
環境が変化するタイミングに注意する
適応障害の再発を防ぐためには、環境の変化に注意を払うことも大切です。特に職場復帰の際は大きな環境の変化が生じるため、慎重に対応する必要があります。
また、復職後に業務に慣れてからも「新しいプロジェクトの立ち上げ」「昇進・出世」「担当・部署変更」など、ストレスがかかりやすいタイミングには注意しましょう。
サポート制度を活用する
適応障害からの復職時には、職場や専門機関のサポート制度を積極的に活用することが再発防止に効果的です。
例えば、「リワークプログラム(復職支援プログラム)」ではグループワークや心理教育、リハビリテーション、作業療法など専門家のサポートを受けながら、職場復帰を目指すことができます。
職場復帰を焦らない
適応障害からの回復や職場復帰までにかかる期間には個人差があるため、焦らず自分のペースで進めることが大切です。
復職のタイミングは、医師や会社と相談しながら慎重に決定しましょう。一気に同じ業務量・勤務時間に戻ると調子を崩す可能性があります。
適応障害で復職が難しい場合は?

適応障害から回復しても、元の職場環境では働き続けることが難しい場合があります。その際には異動や転職・退職という選択肢も検討してみましょう。
異動を検討する
今の業務や人間関係がストレスの原因となっている場合、異動することで環境を変えることができます。
自分に合った業務内容への変更、部署の移動、勤務地の変更などを行えば、同じ会社で働き続けることが可能です。
異動を希望する場合は、上司や人事部としっかり話し合ったうえで検討しましょう。前もって医師やカウンセラーに相談し、アドバイスをもらっておくと安心です。
転職や退職を検討する
職場環境の改善が期待できない場合や、今の会社で働き続けるのが非常につらい場合は、転職や退職によって大きく環境を変えるという選択もあります。
業務内容や働き方など、自分の希望や価値観と改めて向き合って考えてみましょう。
ただし、転職や退職は大きな決断のため、焦って決断を急がないようにしてください。一旦休職し、家族や医師、カウンセラーとじっくり相談しながら慎重に考えていくことをおすすめします。
適応障害の方をサポートする支援制度・支援機関

適応障害で悩む方々が利用できる多くの支援制度や支援機関があります。これらの制度を使うことで、負担を軽減しつつ、社会生活への復帰を進めることが可能です。
支援制度
適応障害で悩んでいる方が利用できる支援制度には、以下のようなものがあります。
個人の状況によって対象になるかは異なるため、会社やお住まいの自治体の窓口に相談してみましょう。
- リワークプログラム
- リハビリ出勤(休職している従業員の復職を支援する制度)
- 手当や制度(傷病手当金、失業保険、障害年金、自立支援医療制度、労災保険、障害者手帳、生活保護)
リハビリ出勤は法定制度ではなく企業に導入義務はありませんが、中には制度を導入しているところもあるため、会社に確認してみましょう。
支援機関
精神保健福祉センター・就労移行支援事業所・ハローワークなどでも、就活支援や生活支援、社会復帰相談といった就労のサポートを受けることができます。
就労移行支援事業所でかかる費用は世帯収入によって変わりますが、ほとんどの場合無料で利用可能です。精神保健福祉センターとハローワークは無料で利用できます。
適応障害の再発を防ぐためにも、焦らず自分のペースで
適応障害は再発しやすい病気ですが、適切な準備を行い、家族や職場、医師やカウンセラーなど周囲のサポートを受けることで、再発リスクを下げることができます。
また、心理士による心理カウンセリングも有効です。物事の捉え方や評価、行動に働きかけることでストレスに対処する能力を高めることができます。
『かもみーる』では、オンライン診療・オンラインカウンセリングを行っています。悩みや希望に合わせてカウンセラーを選ぶことも可能です。
「仕事に復帰したいが適応障害の再発が怖い」「もっとストレスにうまく対処できるようになりたい」などお悩みの方はお気軽にご相談ください。
▶ カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶ 新規会員登録はこちら
