「抗うつ薬が必要といわれたけど、副作用が心配」 「抗うつ薬は飲まない方がいいと聞いたことがあるけど、本当?」 「副作用がつらくて治療継続が難しい」
など、抗うつ薬について不安や疑問をお持ちの方は多いでしょう。 うつ病の治療において薬物療法は重要な選択肢の一つですが、抗うつ薬には副作用があるため、抵抗感をお持ちの方も少なくありません。
この記事では、抗うつ薬の種類や副作用、副作用への対処法、薬物治療以外の治療法などについて詳しく解説します。
副作用がつらい場合は、抗うつ薬を使わない他の治療法を選択することも可能です。また、抗うつ薬はすべてのケースで服用しなければならないわけではありません。
記事を読めば、抗うつ薬の効果や副作用がわかり、自分に合った治療選びにつなげられるはずです。ぜひ最後までチェックしてみてください。
抗うつ薬(抗うつ剤)とは

抗うつ薬(抗うつ剤)は、うつ病の治療に用いられる薬剤です。 うつ病の原因ははっきりとはわかっていないものの、脳内の神経伝達物質が減ってしまう病気であると考えられています。抗うつ薬は、脳内の神経伝達物質のバランスを調整することで、うつ症状の改善を図ります。
うつ病と診断されたすべての人が使うわけではない
うつ病と診断されたからといって、必ずしも全ての人が抗うつ薬を服用するわけではありません。
軽度のうつ病の場合、カウンセリングや認知行動療法などの精神療法が主な治療法となることも多いです。一方、中等度から重度のうつ病では、薬物療法が効果的とされています。
また、うつ病はただ抗うつ薬を飲めば治る病気ではありません。薬物療法に加えて、休養や環境調整、精神療法なども回復のために欠かせないものです。
抗うつ薬を使った方がいいのか、薬物療法以外で治療した方がいいのかは、医師と十分に相談したうえで決める必要があります。
抗うつ薬の副作用について
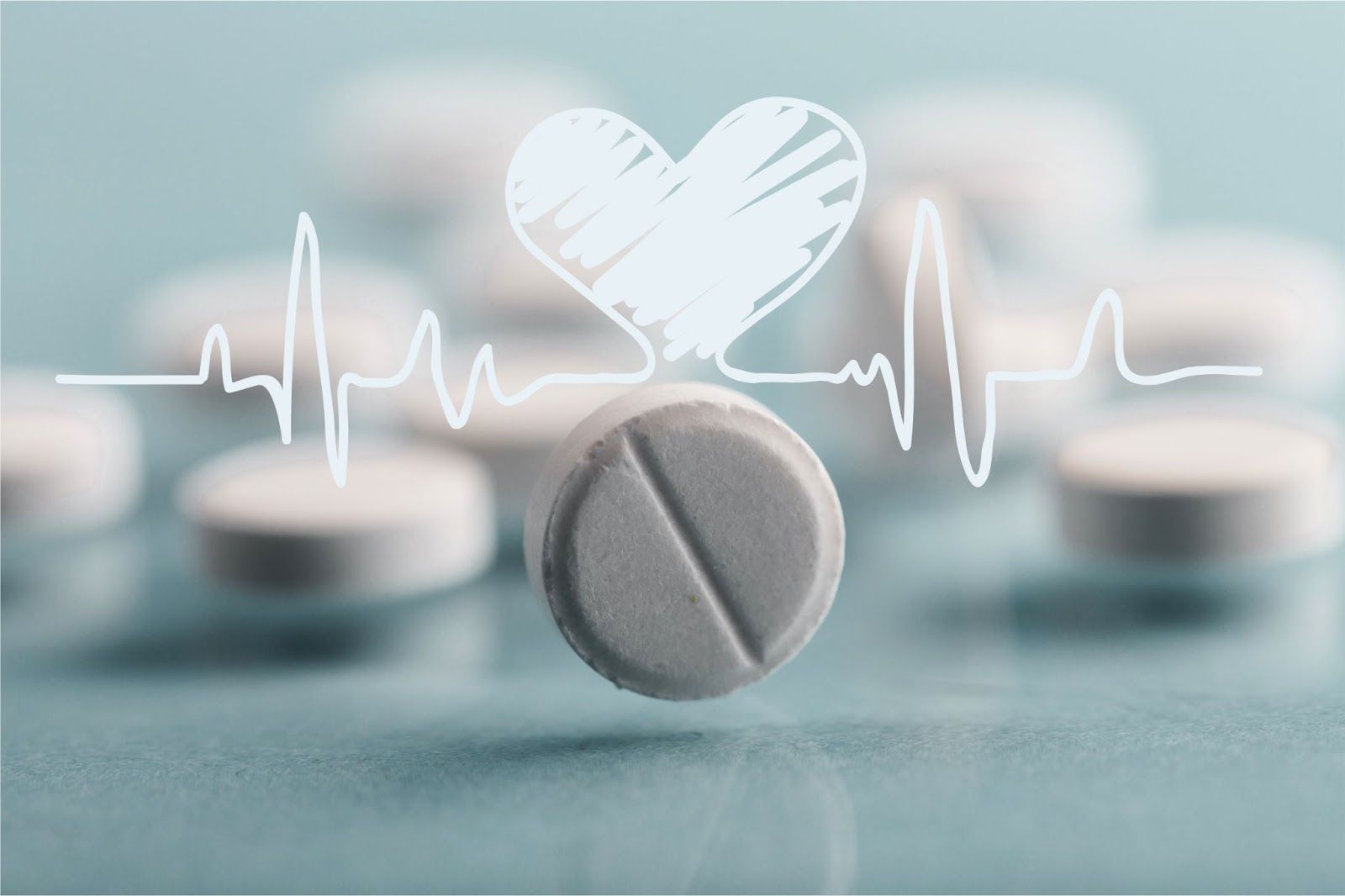
ここでは、抗うつ薬の副作用が起こる仕組みや薬の種類による違いなどについて詳しく見てみましょう。
副作用が起こる仕組み
抗うつ薬には、モノアミン(セロトニン・ノルアドレナリン・ドーパミンなどの神経伝達物質の総称)を増やすことで脳内のバランスを整える作用があります。
しかし、これらの物質は脳だけでなく体全体にも影響を与えるため、それが副作用として現れることがあります。
薬の種類によって副作用は異なる
抗うつ薬にはさまざまな種類があり、起こる副作用には違いがあります。例えば、SSRIは消化器系の副作用が比較的多く、NaSSAは眠気や体重増加が特徴的です。
個人によって合う・合わないもあるため、効果や副作用を確かめながら「同じ薬を継続する」「他の薬に変える」など治療方針を決定します。
副作用は軽減されてきている
抗うつ薬の開発は進歩を続けており、新しい世代の薬剤ほど副作用が軽減される傾向にあります。
初期の三環系抗うつ薬に比べると、現在日本で主流のSSRI・SNRI・NaSSAは、副作用のリスクが低くなっています。
しかし、完全に副作用がないわけではありません。個人差もあるため、医師と相談しながら、自分に合った薬剤を見つけていくことが大切です。
抗うつ薬で起こることがある副作用
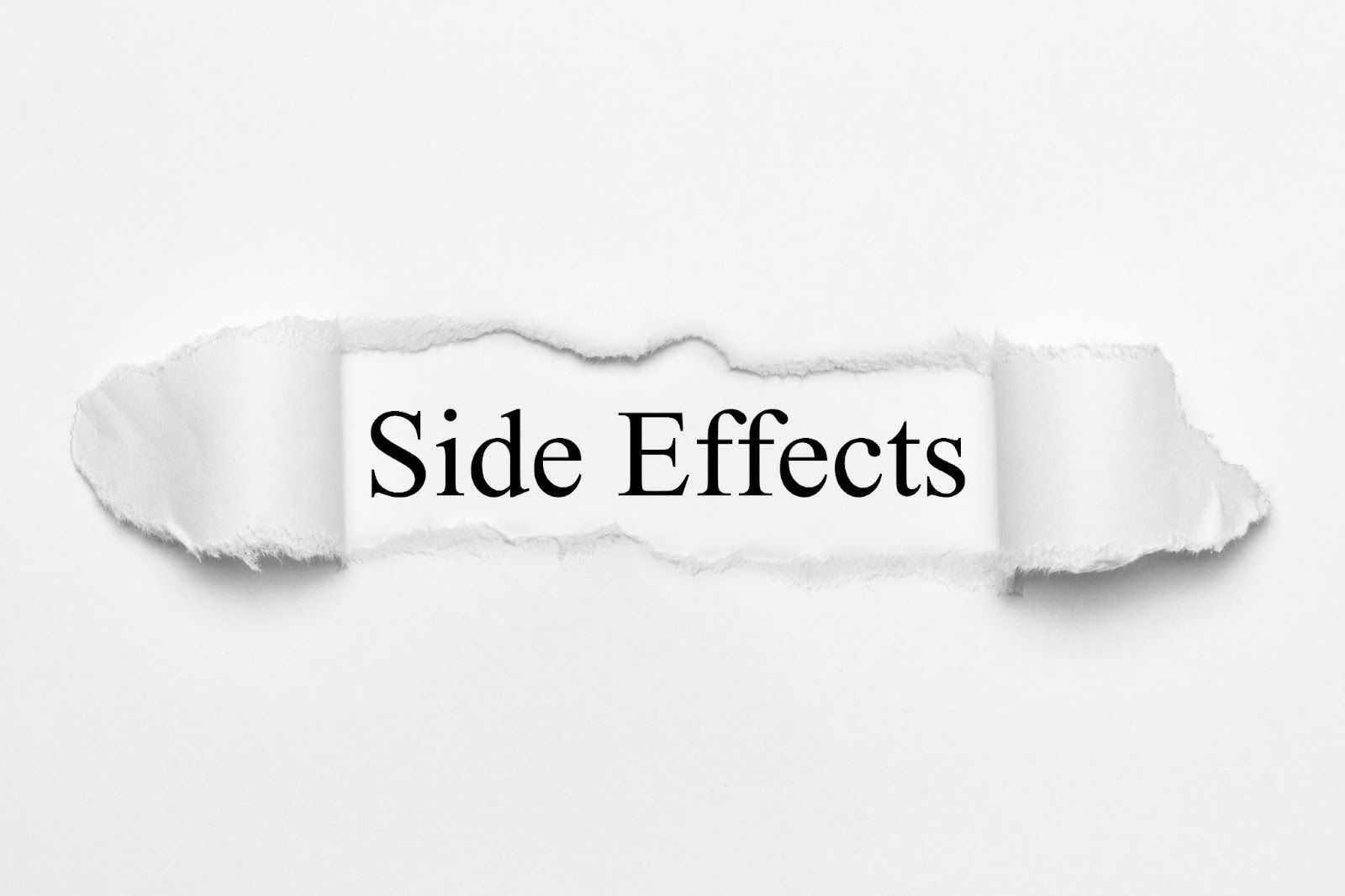
抗うつ薬で起こる可能性のある主な副作用は以下のとおりです。
【起こりやすい副作用】
- 消化器系症状(吐き気、下痢、便秘など)
- 眠気、不眠、だるさ
- 体重増加
- 口渇(唾液の分泌が減少し、口の中が乾燥する)
- めまい、ふらつき
- セロトニン症候群(発汗、発熱、震えなど)
- 感情鈍麻
- 性機能障害(PSSD)
【注意が必要な副作用】
- アクティベーションシンドローム(賦活症候群。不安、焦燥、イライラ)
- 不整脈、心停止
まれではあるものの、アクティベーションシンドローム(賦活症候群)や不整脈、心停止といった副作用のリスクもあるため、抗うつ薬の服用中に異変を感じた場合はすぐに医師に相談しましょう。
【種類別】抗うつ薬の特徴と副作用

抗うつ薬は、効果の仕組みによって以下のような系統に分けられています。
- 三環系抗うつ薬(TCA)
- 四環系抗うつ薬(TeCA)
- SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)
- SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取込み阻害薬)
- NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)
- S-RIM(セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節薬)
以下の1〜6の順番で開発されており、現在日本で主流なのはSSRI・SNRI・NaSSAの「新規抗うつ薬」3種類です。
以前使われていた三環系抗うつ薬・四環系抗うつ薬は副作用が強く出ることがあり、現在は新規抗うつ薬では効かない場合などで用いられています。
三環系抗うつ薬(TCA)
三環系抗うつ薬は、古くから使用されてきた抗うつ薬です。強い抗うつ効果がある一方で副作用が多く、現在では他の選択肢がない場合や、他の薬剤が効果不十分な場合に使用されることが多くなっています。
【主な副作用】
- 口渇
- 便秘
- 排尿困難
- 眠気
- めまい
- 体重増加
四環系抗うつ薬(TeCA)
四環系抗うつ薬は、三環系抗うつ薬の改良型として開発されました。三環系抗うつ薬に比べて副作用が軽減されていますが、抗うつ効果もそれほど強くありません。
【主な副作用】
- 眠気
- めまい
- ふらつき
- 口渇
- 便秘
SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)
SSRIは現在、広く使用されている抗うつ薬の一つで、セロトニンだけを増やす作用に優れています。
従来の抗うつ薬に比べて副作用が少なく、第一選択薬として多くの患者に処方されています。ただし、飲み忘れや急に服用を中止すると離脱症状が起こりやすい点に注意が必要です。
【主な副作用】
- 吐き気
- 胃痛
- 下痢
- 眠気、不眠
- 性機能障害
SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取込み阻害薬)
SNRIは、セロトニンとノルアドレナリンの両方に作用する抗うつ薬です。SSRIと同様に副作用が比較的少なく、幅広い症状に効果があるとされています。
痛みを軽減する作用もあり、うつ病だけでなく慢性疼痛や線維筋痛症などにも使用されることがあります。
【主な副作用】
- 吐き気
- 下痢
- 不眠
- 口渇
- 便秘
- 発汗
- 性機能障害
NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)
NaSSAは四環系抗うつ薬を改良して作られた薬で、セロトニンとノルアドレナリンの両方に作用しますが、SSRIやSNRIとは異なるメカニズムを持ちます。
新しいタイプの抗うつ薬の中でも効果が強く、SSRIで起こりやすい消化器症状が出にくい一方、体重増加や眠気などが生じやすいです。
【主な副作用】
- 強い眠気
- 体重増加
- めまい
S-RIM(セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節薬)
S-RIMは日本では2019年から発売された新しい抗うつ薬で、セロトニンの再取り込みを阻害すると同時に、セロトニン受容体を調節する作用があります。
副作用がマイルドで性機能障害が出にくく、離脱症状が少ないことが特徴です。
【主な副作用】
- 吐き気
- 下痢
- 便秘
- 頭痛
- 不眠
抗うつ薬の副作用の現れ方・起こるタイミング

抗うつ薬の副作用は、特に服用開始時に見られる傾向にあります。また、急な断薬・減薬を行うと離脱症状が起こることがあるため注意が必要です。
服用開始時(効果よりも副作用が先に現れやすい)
抗うつ薬の副作用は多くの場合、服用開始後すぐに現れます。
一方で、抗うつ効果が十分に現れるまでには通常2〜4週間程度かかり、このタイムラグが患者さんを悩ませる原因の一つとなっています。
ただし、副作用の多くは一時的なものであり、1〜2週間ほど経って身体が慣れると落ち着いてくることが多いです。
離脱症状(中断症候群)
抗うつ薬を突然中止したり、急激に減薬したりすると、離脱症状(中断症候群)が現れることがあります。
これは、身体が薬に慣れていた状態から急になくなることで起こる症状で、SSRIやSNRIは離脱症状が起こりやすいといわれています。
抗うつ薬に限ったことではありませんが、薬は正しい用法用量で使用することが大切です。 症状がよくなったからといって自己判断での断薬・減薬は行わず、必ず事前に医師に相談しましょう。
【主な離脱症状】
- めまい
- 吐き気
- 頭痛
- だるさ
- 耳鳴り
- しびれ
- 不眠
- 不安、イライラ
病院での抗うつ薬の副作用への対策
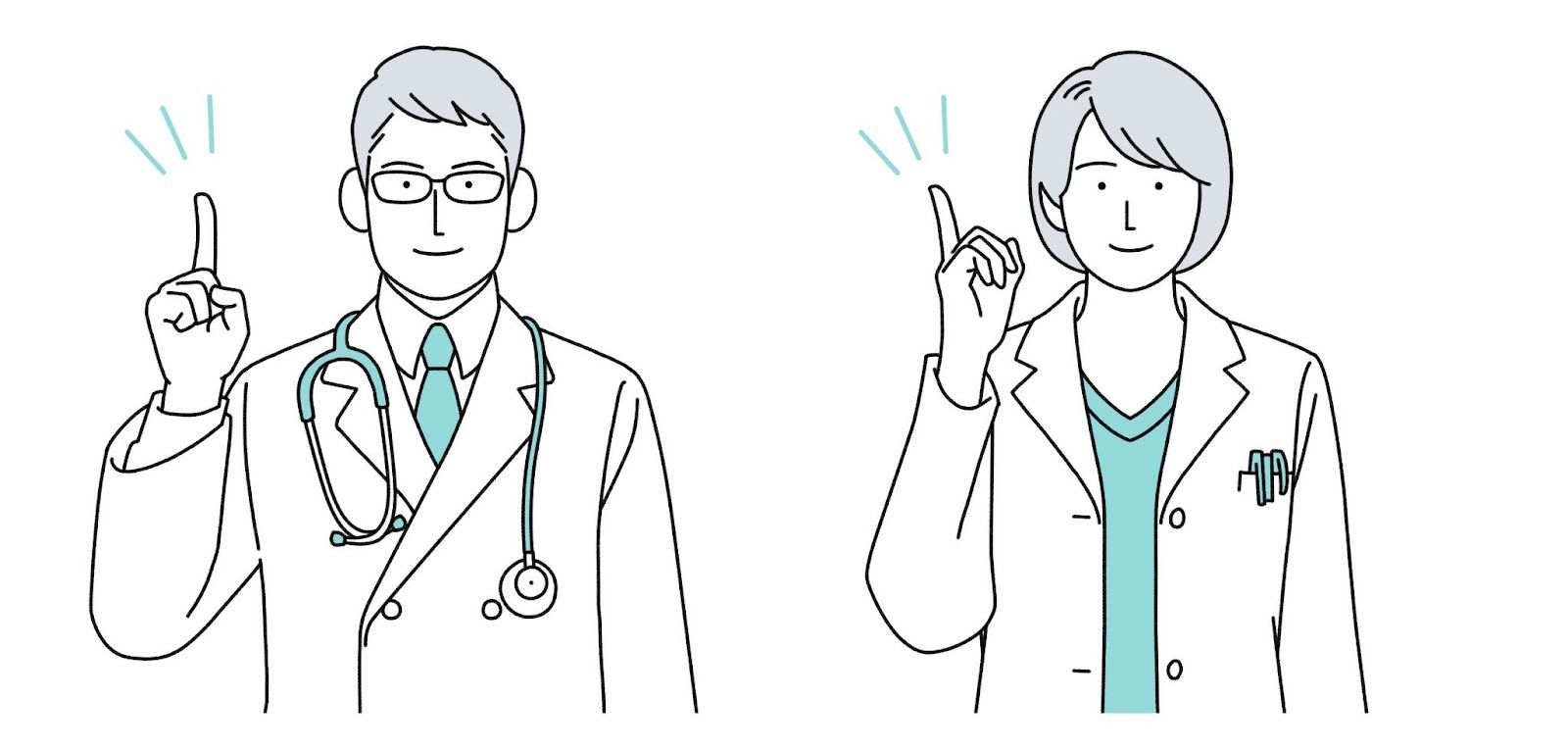
抗うつ薬で副作用がある場合、病院では以下のような対策を取ります。
- 副作用をやわらげる薬を使用する
- 薬を減らす
- 他の抗うつ薬に変更する
副作用を軽減する薬を使用する
飲み始めでまだ抗うつ薬の効果がわからないときや、薬を継続するメリットの方が大きいと考えられる場合は、副作用の症状を抑える薬を使用します。
例えば胃薬や下剤、整腸剤、睡眠薬などです。
薬を減らす
副作用が強い場合や効果が十分に出ている場合、医師の判断のもと薬を減らすこともあります。
また、患者さんがかかっている他の身体疾患(肝臓や腎臓の病気など)がある場合、薬を減らした方がいいケースもあります。
他の抗うつ薬に変更する
十分な効果が得られない場合や、副作用が強く出る場合は、他の抗うつ薬に変更することがあります。
また、複数の薬剤を組み合わせて治療するケースもあります。
自分でできる抗うつ薬の副作用対策

抗うつ薬の副作用は1〜2週間ほどで軽減していくことが多いです。それまでは、自分でできる抗うつ薬の副作用対策を実践してみましょう。
- 吐き気や胃痛……食事の量を減らす、胃に優しい食べ物や飲み物を選ぶ
- 便秘……水溶性食物繊維などを積極的に摂取する、水分を十分摂る、運動する
- 眠気……十分な睡眠を取る、生活リズムを整える
- 体重増加……食事の量を管理する、運動する
- 口渇……唾液腺マッサージ
- 不眠……運動する、生活リズムを整える
ただし、副作用がつらいときは無理に我慢し続けず、早めに主治医に相談しましょう。
抗うつ薬の副作用が気になる場合は非薬物療法の選択肢もある
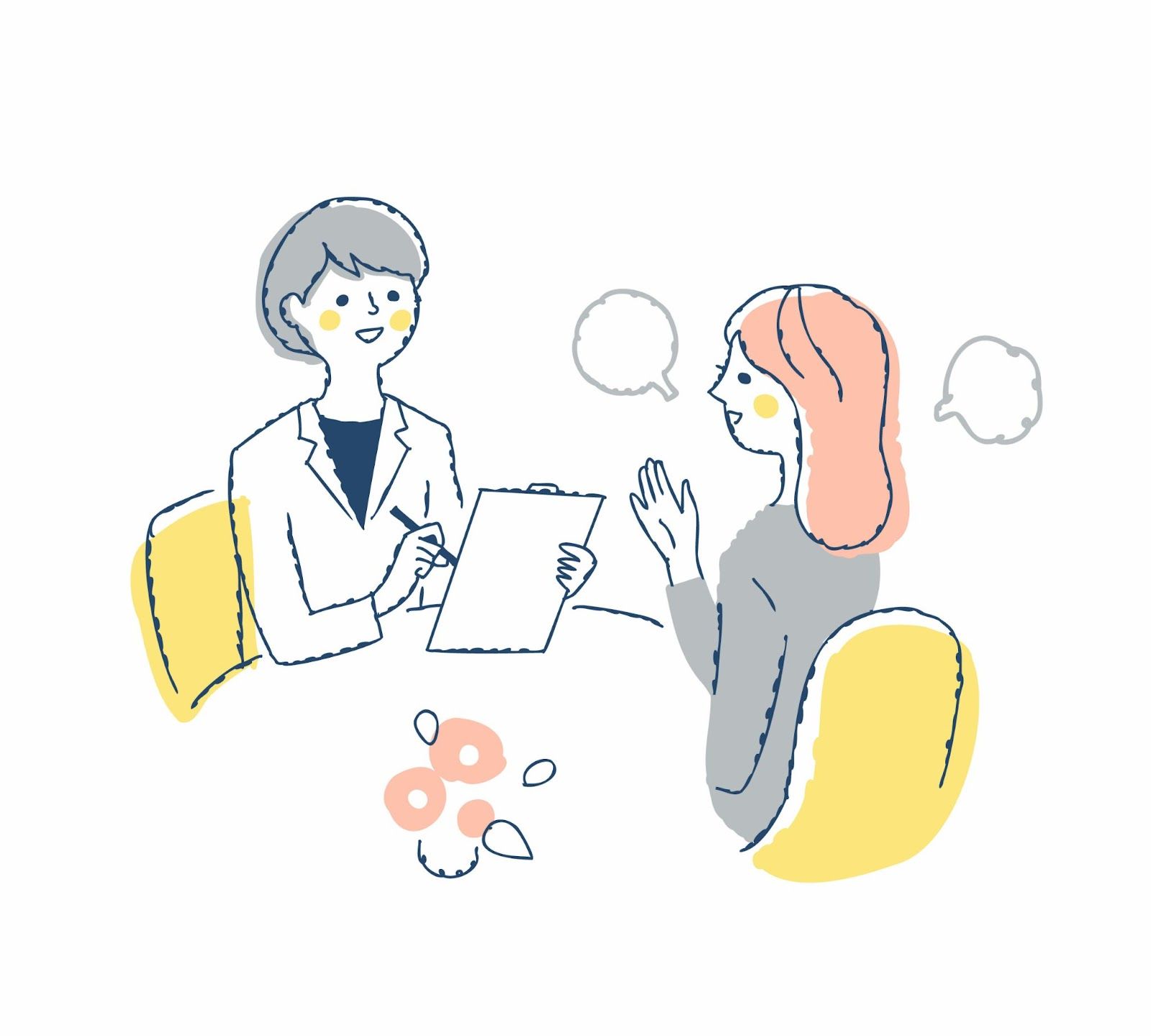
うつ病の治療法は、抗うつ薬だけではありません。薬を使わない以下のような治療法もあります。
- 休養・環境調整
- 精神療法(心理療法)
- TMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)
特に、休養や環境調整はうつ病治療の基本です。抗うつ薬を使用するかしないかに関係なく、十分な休養を取り、ストレスを減らすことが回復には欠かせません。
そのほかにも、認知行動療法、対人関係療法といった「精神療法(心理療法)」や、磁気を使って脳を刺激する「TMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)」のような副作用の心配がない治療法もあります。
薬との相性が悪いケースや副作用がつらく服薬を続けるのが難しいケースもあるため、無理せず医師に相談してみましょう。
▶うつ病を自力で治す方法はある?病院での治療法・長引く原因・自宅での過ごし方を解説
抗うつ薬についてのよくある質問

ここでは、抗うつ薬についてのよくある質問を紹介します。
Q:抗うつ薬は飲まない方がいい?
抗うつ薬を飲んだ方がいいか、飲まない方がいいかは一概には言えず、一人ひとりの患者さんの状況や症状の程度によって判断が必要です。
「薬に頼らないうつ病治療」と聞くと、とても良いもののように感じるかもしれません。 もちろん、軽度の場合は中には薬を飲まなくてもよくなるケースもありますが、反対に薬に頼らなければ改善が難しいケースもあります。
抗うつ薬を使用するにしても、非薬物療法で治療するにしても、信頼できる医師を見つけて十分に話し合い、納得したうえで治療を受けることが大切です。
Q:抗うつ薬の副作用はいつまで続く?
抗うつ薬の副作用の多くの症状は1〜2週間ほどで改善されていくことが多いです。
ただし個人差もあるため、副作用が気になる場合は自己判断で服用を中止せず、まずは医師に相談してみましょう。
Q:抗うつ薬の副作用で太ることはある?
抗うつ薬が代謝に影響することは少ないものの、一部の抗うつ薬には食欲を増進させる作用があり、体重増加につながることがあります。
体重増加が気になる場合は、バランスの取れた食事と適度な運動を心がけましょう。医師に相談して薬の種類や用量の調整を検討するのも一つの方法です。
Q:抗うつ薬を飲むと感情がなくなる?
SSRI・SNRIなどの一部の抗うつ薬では、感情鈍麻(喜怒哀楽の感情に乏しくなる、無気力や無関心になる)の副作用が起こることがあります。
このような副作用が現れた場合、薬を減らしたり中止したりすることがあります。
抗うつ薬の副作用が気になる場合は医師に相談を
抗うつ薬による薬物療法は、うつ病治療において重要な役割を果たすものです。副作用のリスクはありますが、適切に使用すれば多くの患者さんの症状改善に貢献してくれます。
ただし、うつ病と診断されたすべての患者さんに抗うつ薬が適しているとは限りません。
初診時から安易に抗うつ薬を使うのは避けた方がいいとされているため、信頼できる医師と十分相談したうえで使用を検討することが大切です。
「できれば抗うつ薬を使わない治療を受けたい」「現在抗うつ薬を使った治療をしているが、このまま継続すべきか迷っている」などのお悩みがある方は、ぜひ一度『かもみーる』のオンライン診療でご相談ください。
うつ病に詳しい医師が、あなたに合った治療法を提案いたします。 また、『かもみーる心のクリニック』では、副作用がほとんどないTMS治療も行っています。ぜひお気軽にお問い合わせください。
▶ カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶ 新規会員登録はこちら
