うつ病は、適切な治療を受けることで良くなる病気です。
しかし、うつ病は良くなったり悪くなったりを繰り返しながら回復するため「本当に良くなるのかな…」「どのくらいで回復するんだろう」など、不安になってしまうときもあります。
この記事では、うつ病の正しい治療法や回復の過程、自宅での過ごし方などについて詳しく解説します。
うつ病になったら、焦らずゆっくり休みながら治療を続けることが大切です。不安を感じている方はぜひこの記事を読んで、うつ病からの回復への道筋を見つけてみてください。
うつ病を自力で治すことはできる?

うつ病の治療で、薬を飲むことに抵抗感を持つ方もいらっしゃいます。
症状が重くない場合は、十分な休養によって薬を飲まずに良くなるケースもありますが、反対に、薬に頼らなければ治療が難しいケースもあります。
大切なのは「薬に頼らないこと」ではなく、「心と身体の状態を回復すること」だということを忘れないようにしましょう。
薬を飲まずに自力で治すことに固執してしまうと、思うように良くならず、停滞や悪化につながってしまうケースも少なくありません。自分でなんとかしようと「頑張る」ことで、かえって追い詰められてしまうこともあります。
うつ病には、脳内の神経伝達物質のアンバランスさが大きく影響しています。そのため、薬によってこの神経伝達物質を調整することが、うつ病治療に有効です。
薬はずっと飲み続けなければいけないわけではなく、症状の改善に合わせて減らす、または服用をやめることができます。(必ず医師の指示のもとで行います。患者さんの判断で勝手に薬をやめないようにしましょう)
また、薬を使う方法以外にも「認知行動療法」「対人関係療法」などストレスに対処する方法や、TMS療法といった治療法があります。
自力で治すことにこだわりすぎて再発を繰り返したり、悪化させてしまうことのないよう、まずは治療方針も含めて一度クリニックで相談してみるのがおすすめです。
うつ病の治療法
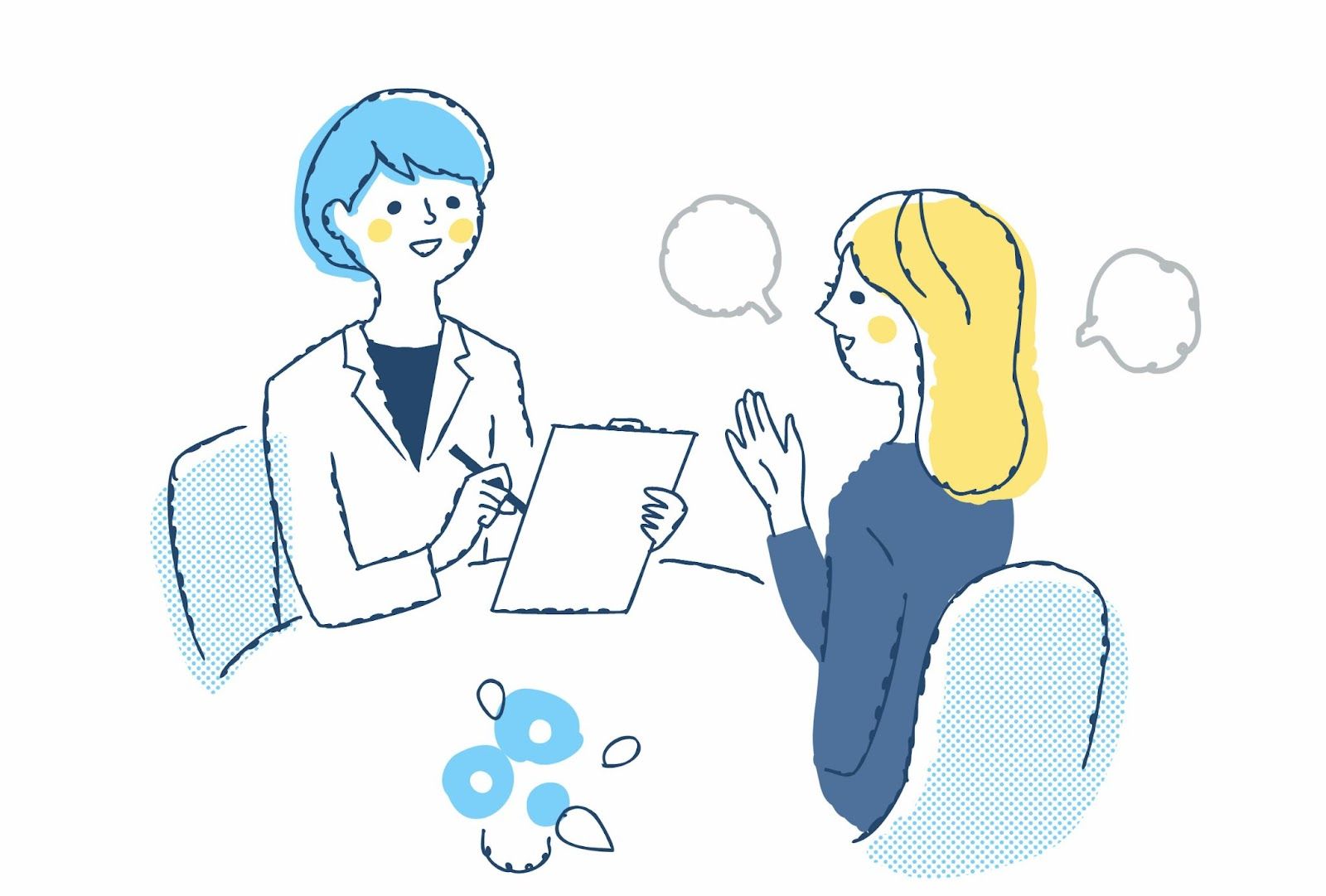
うつ病治療は「休養・環境調整」「薬物療法」「カウンセリング・精神療法」の三本柱で行います。
また近年、うつ病の新たな治療法として「TMS治療(磁気刺激療法)」も登場しています。
うつ病は脳の病気であり、早期治療が早期回復につながります。
悪化すると治るのに時間がかかったり、その後の生活に影響してしまったりする可能性があるため、無理や我慢をせず早めに治療をスタートしましょう。
休養・環境調整
十分な休養は、うつ病治療の基本です。うつ病は脳のエネルギー不足状態であるため、休養によってしっかり脳を休ませてあげましょう。
休むことに罪悪感を感じてしまう方もいますが、「回復のために必要なこと」と割り切って、ゆっくり心と身体を休めましょう。
また、十分な休養のために環境の調整や改善(仕事量の調整、家事の分担、人間関係の見直しなど)も合わせて行います。自分一人では難しいことも多いので、周囲の協力を得ながら整えていきましょう。
薬物療法
うつ病では、心や身体にさまざまな症状が起こります。症状がつらく、ゆっくり休むことが難しい場合は、主に抗うつ剤を使った薬物療法を行います。
抗うつ剤は、もともと自分が持っている「セロトニン」「ノルアドレナリン」「ドーパミン」といった神経伝達物質に作用し、バランスが整うようサポートする薬です。
飲んですぐに効果が現れるわけではなく、2週間ほどかけて効いてくるのが一般的です。現在はSSRI、SNRI、NaSSaなどの種類が主流です。
カウンセリング・精神療法
カウンセリングや精神療法も大切な治療の一つです。
代表的な治療法としては「認知行動療法」があり、物事の捉え方や考え方のクセを改善することで症状改善や再発防止を図ります。
休養や薬物療法だけでは、ストレスを溜め込みやすい性格や考え方を変えることは難しいため、カウンセリングや精神療法によって、ストレスへの対処法を学ぶ必要があります。
TMS治療(磁気刺激方法)
TMS治療(磁気刺激方法/経頭蓋磁気刺激法)は、お薬を使わないうつ病の新しい治療法です。
うつ病を発症している方の脳は、血流や代謝の低下が見られます。TMS治療では専用機器で磁場を発生させ、脳の特定の部位を刺激することで脳血流を増加させ、低下した脳機能を改善させます。
副作用が少なく安全性が高いのが特徴で、薬物療法だけでは十分な効果が得られなかった方にも有効です。
うつ病の治療期間と回復の経過

焦らずしっかり治していくためにも、うつ病の治療期間や回復の経過について知っておきましょう。
うつ病は、良くなったり悪くなったりを繰り返しながら、徐々に改善していく病気です。「また悪くなってしまった」と思っても、焦る必要のないことがほとんどです。
経過 | 特徴 | 期間の目安 |
|---|---|---|
急性期 | 症状が最もつらく感じる時期。休養と適切な治療が大切 | 診断から1〜3ヶ月ごろ |
回復期 | 回復傾向にある時期。調子には波があるため無理は禁物 | 診断から4〜6ヶ月ごろ |
再発予防期 | 症状が安定し、社会復帰を考える時期。再発予防が大切 | 診断から1年以降〜 |
これらはあくまで目安であり、個人差も大きいです。他の方のケースや周囲と比較して焦る必要はありません。
うつ病から立ち直るきっかけは?

うつ病の治療は、ケガの治療と同じようにある程度の期間が必要ですが、立ち直るきっかけの一つとして「自信(自己効力感)の回復」があるといわれています。
うつ病の症状による自己否定や悲観的な考え方が強くなると、心身のコントロールが難しくなり、「自分はダメだ」「誰の役にも立てない」といった悪い思い込みに陥りがちです。
ゆっくり休み、症状が落ち着いてきたら、ほんの小さなことでいいので小さな成功体験を積み重ねていくといいでしょう。
根拠なく物事を悪い方に捉えてしまう「マイナス思考」になりがちな場合は、認知行動療法が有効です。
うつ病が長引く原因

うつ病は適切な治療により改善を目指せる病気ですが、中には長期化してしまうケースもあります。ここからは、うつ病が長引いてしまう原因を見ていきましょう。
自己判断で薬を飲むのをやめてしまう
うつ病の治療で最も注意したい点の一つは、自己判断で薬を中断しないことです。症状が改善してきたからといって自己判断で薬をやめると、再発や長引く原因になってしまいます。
薬を減らす、やめる場合は必ず医師に相談しましょう。
クリニックや医師・カウンセラーが合っていない
うつ病の治療では、患者さんと医師の信頼関係がとても大切です。しかし、相性が合わないと感じることや、治療方針に疑問を感じる場合もあるでしょう。
合わないと感じる場合は、他のクリニックで相談してみるのがおすすめです。安心して治療を続けられる相性の合う医師やカウンセラーを見つけましょう。
うつ病ではなく他の病気の可能性がある
うつ病と間違えられやすい病気として、双極性障害や適応障害、不安障害、統合失調症などがあります。
これらの病気は、うつ病と似た症状が起こることがあり、治療法が異なるため、あまりにも改善が見られない場合は他の病気の可能性も考えて、他のクリニックで相談することも検討しましょう。
うつ病を治すための考え方

うつ病からの回復には、適切な治療と共に「自分自身の考え方」も重要な役割を果たします。
まず大切なのは、焦らないことです。うつ病の回復には時間がかかります。良くなったと思ったらまた症状が悪化することもありますが、それは回復過程の一部だと理解しましょう。
また、完璧を求めすぎないことも大切です。うつ病になる方は真面目で責任感が強い傾向があるため、焦りや無理は再発リスクを高めることになります。「できることからゆっくりやればいい」という姿勢を持ちましょう。
うつ病を治すための自宅での過ごし方

うつ病になると「何をしたらいいのだろう」と悩んでしまう方も多いですが、自宅での過ごし方で大切なポイントを紹介します。
なお、ここで紹介するのはあくまで一例です。症状がつらいときは無理をせず、医師と相談しながら治療を続けていきましょう。
焦らずゆっくり休む
まずは、しっかり休むことが大切です。自宅では焦らず、無理をせずに自分のペースで過ごしましょう。
十分に休めていないとうつ病が長引いてしまうこともあるため、1日3食を規則正しく食べ、安心して休める環境を整えてゆっくり過ごしましょう。
日光を浴びるようにして、生活リズムを整える
不規則な生活はうつ病の症状悪化を招くため、規則正しい生活を送ることが大切です。
日光を浴びると体内時計がリセットされ、セロトニンの分泌が促進されます。外出が難しければ、窓際で日光を浴びるだけでも効果があるため試してみましょう。
運動をする
適度な運動は、うつ病の症状改善や再発防止に効果的といわれています。
まずはウォーキングや散歩など軽い運動から始め、体力が回復してきたらジョギングや水泳など好きな運動を取り入れましょう。
ただし、無理は禁物。調子の悪い日にあえて行う必要はありません。できるタイミングを見計らって、少しずつ取り入れましょう。
趣味や好きなこと、楽しめることをする
うつ病の症状が和らいできたら、趣味や楽しめることを少しずつ取り入れていくとよいでしょう。
音楽を聴く、映画を観る、絵を描くなど、自分が楽しめる物事に取り組むことで気分転換や自己肯定感を高める効果が期待できます。
もちろん、やりたくなければ無理をする必要はありません。やってみたいと思ったタイミングで少しずつ始めてみましょう。
うつ病についてのよくある疑問

ここでは、うつ病についてのよくある疑問を紹介します。
Q:笑えないのはうつ病の可能性がある?
よく笑っていた人が急に笑わなくなったり、口数が減った場合は、うつ病の可能性が考えられます。その他にも「楽しめていたことを楽しめなくなった」「必要以上に自分を責めてしまう」「憂鬱な気分が続く」などもうつ病でよく見られる症状です。
▶ うつ病の初期症状?12のサイン丨受診目安・対処法・顔つきの変化も解説
▶ うつ病の人への接し方│やってはいけないこと&避けるべき言葉や心構えを解説
Q:人前で明るい場合はうつ病ではない?
人前で笑えたり、明るく見えるからといってうつ病でないとは限りません。
微笑みうつ病(正式な病名ではなく俗称)と呼ばれる、表面上は元気そうに見えて実は落ち込んでいるタイプもうつ病の一つです。理解されにくく、悪化しやすい傾向があるといわれています。
「もしかしたらうつ病かもしれない」「自分は治療が必要なのか」と不安に思ったら、下記の記事で紹介している自己診断チェックを試してみましょう。
うつ病を悪化させないためにも早めにクリニックに相談しよう
うつ病は適切な治療を受けることで良くなる病気ですが、間違った治療法や無理を続けると長期化や悪化につながる場合があります。
「気分の落ち込みが続く」「普段できていたことができなくなってきた」と感じるときは、早めにクリニックを受診するのがおすすめです。
薬物療法への抵抗感から受診を躊躇している方もいますが、薬以外にもさまざまな治療法があるため、まずは医師に相談してみましょう。
医師監修のオンラインカウンセリング『かもみーる』では、オンラインで気軽に経験豊富な医師やカウンセラーに悩みを相談できます。
うつ病は日本では約15人に1人がかかるといわれ、決して珍しい病気ではありません。
「もしかしたらうつ病かもしれない」「うつ病をしっかり治療したい」「誰かに話を聞いてほしい」とお悩みでしたら、ぜひ『かもみーる』にご相談ください。
▶ カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶ 新規会員登録はこちら
