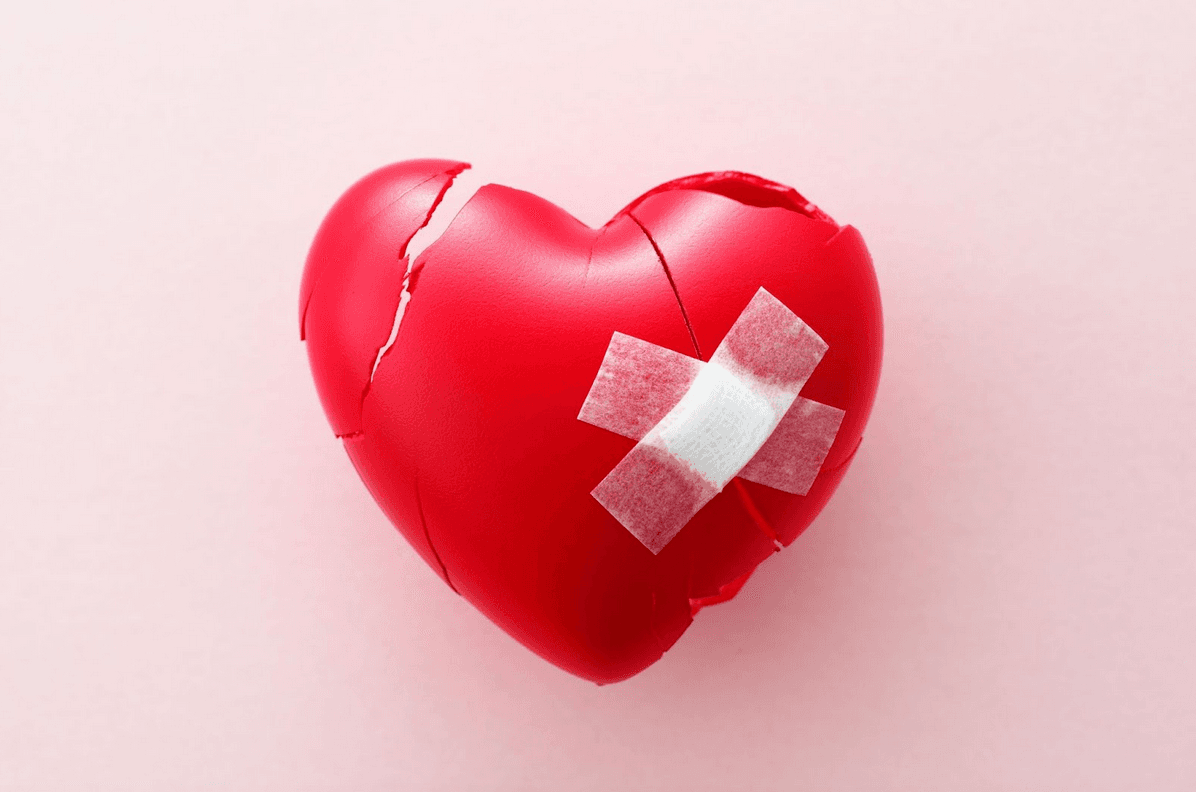双極性障害は、気分が極端に高まる躁状態と、深く落ち込むうつ状態を繰り返す精神疾患です。
「双極性障害は一生治らないのではないか」と考える方もいるかもしれませんが、実際には治療の継続により完治に近い状態まで症状が改善できます。
双極性障害では、症状が落ち着き安定した生活を維持できる『寛解』を目指すのが治療の基本方針です。
この記事では、双極性障害の特徴や治療方法について詳しく解説します。
寛解までの期間の目安や再発を防ぐセルフケア方法、向き合い方のポイントなどもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
双極性障害は治る?

双極性障害は、『完治』というよりも『寛解』を目指す病気です。
寛解とは、症状が安定し、日常生活に大きな支障がない状態を指します。
完全寛解は症状がまったくない状態が一定期間続くこと、不完全寛解は軽い症状が残っていても生活が安定している状態をいいます。
適切な薬物療法や心理療法、生活習慣の調整を続けることで、以前とほぼ変わらない生活を送れる方も少なくありません。
一方で、双極性障害は再発しやすい特徴があります。
治療を自己判断で中止したり、強いストレスにさらされたりすると、再び躁状態やうつ状態が現れることがあるため注意が必要です。
糖尿病や高血圧などの慢性疾患と同じように、治療と自己管理を継続すれば、安定した生活を維持することは可能です。
寛解までの期間の目安
双極性障害が寛解に至るまでの期間は、人によって大きく異なります。
症状の重さ、発症から治療開始までの時間、治療内容、生活環境、ストレス要因の有無など、さまざまな要素が関わるため、「〇か月で寛解」といった明確な基準はありません。
大切なのは、自分の症状が悪化するきっかけを把握し、事前に回避や軽減の対策を取ることです。
例えば仕事や家庭での大きなイベント、睡眠不足、季節の変わり目などが引き金になる人もいます。
そのため、症状が落ち着いた後も定期的な通院と治療を続けることが重要です。
双極性障害とは

双極性障害は、かつて『躁うつ病』と呼ばれていた精神疾患で、気分が極端に高ぶる『躁状態(または軽躁状態)』と、著しく落ち込む『うつ状態』を繰り返す特徴があります。
うつ病と同じく『気分障害』に分類されますが、うつ病が気分の落ち込みだけを示すのに対し、双極性障害は正反対の気分の波が起こる点が大きな違いです。
症状が出ていない期間は比較的安定して過ごせますが、再発を繰り返すことが多く、治療と予防が重要な病気です。
WHOの国際疾病分類ICD-11では、『障害』という言葉の誤解を避けるため『双極症』という日本語訳が採用される予定となっています。
ここでは双極性障害の主な症状と分類についてみてみましょう。
躁状態とうつ状態を繰り返す病気
双極性障害は、活動性や気分が異常に高まる躁状態と、意欲や興味が低下するうつ状態を周期的に繰り返す病気です。
躁状態 |
|
軽躁状態 |
|
うつ状態 |
など |
躁状態では、睡眠がほとんど不要になったり、次々とアイデアが浮かんで止まらなくなったり、浪費や無謀な行動に走ったりすることもあります。
軽躁状態でも同様の傾向が見られますが、社会的な問題は比較的少ない場合が多いです。
一方、うつ状態では、何をしても楽しく感じられない、極端な疲労感、自分には価値がないという思い込み、食欲や睡眠の異常などが出ます。
多くの場合、うつ状態の期間の方が長く、躁状態の自覚が乏しいため、初診時にはうつ病と誤診されるケースもあります。
双極Ⅰ型障害と双極Ⅱ型障害がある
双極性障害は、躁状態の程度により2つのタイプに分かれます。
双極Ⅰ型障害は、生活や仕事に重大な支障をきたすほど強い躁状態が出現し、時に入院が必要な場合もあるタイプです。
多くはうつ状態も伴い、躁状態が一度でもあればⅠ型と診断されます。
双極Ⅱ型障害は、躁状態より軽い軽躁状態とうつ状態を繰り返すタイプです。
軽躁状態は一見調子が良く見えるため、本人や周囲が病気と気づかないことも多いですが、Ⅱ型はうつ状態の再発率が高く、長期的には生活への影響が大きいとされています。
どちらの型も早期治療と再発予防が欠かせず、薬物療法と生活管理を組み合わせた継続的なケアが必要です。
双極性障害とうつ病の違い
双極性障害とうつ病の大きな違いは、躁状態(または軽躁状態)の有無です。
うつ病は、長期的な気分の落ち込みや意欲の低下、不眠などのうつ症状のみが現れますが、双極性障害ではうつ症状に加えて躁または軽躁状態が周期的に起こります。
治療法にも違いがあり、うつ病では抗うつ薬が主に使われるのに対し、双極性障害では気分安定薬や抗精神病薬が中心です。
抗うつ薬単独では躁転(うつ状態から急に躁状態になること)の危険があるため注意が必要です。
誤診や不適切な治療を防ぐためには、診断の際に、現在だけでなく過去の気分変化や行動パターンも含めて医師に詳しく伝えることが重要になります。
▶うつ病と双極性障害(躁うつ病)の違いは?症状・原因・治療法とセルフチェックリスト
双極性障害の治療方法

双極性障害の主な治療方法は以下の3つです。
- 薬物療法
- 心理療法
- 電気けいれん療法(ECT)
ここでは上記3つの治療方法についてそれぞれ解説します。
薬物療法
薬物療法は躁状態・うつ状態の両方をコントロールし、再発を防ぐ役割があります。
主に使用されるのは『気分安定薬』と『抗精神病薬』です。
気分安定薬にはリチウム、ラモトリギン、バルプロ酸、カルバマゼピンなどがあり、症状改善だけでなく予防効果も期待できます。
抗精神病薬はオランザピン、クエチアピン、アリピプラゾールなどが代表的で、躁症状や急性期の治療に効果を発揮します。
服薬は自己判断で中断せず、医師と相談しながら副作用と効果のバランスを取りつつ継続することが重要です。
心理療法
心理療法は薬物療法を補完し、再発予防や生活の質向上を目指す治療方法です。
中でも代表的なのは『心理教育』で、病気の特徴や薬の必要性、副作用、再発の初期サインについて患者さんと家族が理解を深めます。
再発の兆候を早期に察知できれば、重症化を防ぐことが可能です。
そのほかにも、以下のような治療方法があります。
認知行動療法 | 否定的な思考パターンを修正し、現実的で前向きな考え方を身につける |
家族療法 | 家族が病気を理解し、適切なサポートを行えるよう支援する |
対人関係療法 | 対人関係の問題を解決し、良好な人間関係を回復して症状の再発を防ぐ |
社会リズム療法 | 自分の生活リズムを記録し、社会リズムが不規則になりやすい場面を客観的に理解・修正できるようにする |
また、睡眠不足や徹夜は躁状態の引き金になるため、規則正しい睡眠・食事・運動習慣を整えることを目的とした生活習慣指導が行われることもあります。
電気けいれん療法(ECT)
電気けいれん療法(ECT)は、薬物療法や心理療法で十分な効果が得られない場合や、重度のうつ状態・強い自殺念慮がある場合に選択される治療方法です。
全身麻酔下で脳に電流を流し、神経伝達物質の働きを改善します。
近年は、より安全性が高く身体への負担も少ない『修正型ECT(mECT)』が普及しています。
即効性があり、薬が効きにくい症例でも改善が見込まれる一方、一時的な記憶障害や頭痛、血圧上昇などの副作用が出る可能性がある点には注意が必要です。
効果とリスクについて医師と十分に話し合い、慎重に判断することが大切です。
双極性障害の再発を防ぐセルフケア方法

双極性障害は完治が難しい病気で再発リスクもあるため、長期的な自己管理が重要です。
再発を防ぐための具体的なセルフケア方法は以下の通りです。
- 再発のサインを知っておく
- うつ状態のときは休養に専念する
- 医師の指示通りに薬を飲む
- ストレス管理を行う
- 規則正しい生活を心がける
ここでは上記5つのセルフケア方法についてそれぞれ解説します。
再発のサインを知っておく
双極性障害の再発を防ぐためには、再発のサインを知っておくことが大切です。
躁状態では睡眠時間が短くなっても元気に活動できる、おしゃべりが増える、イライラしやすくなるといった変化が見られます。
うつ状態の兆候としては、疲れやすくなる、集中力が低下する、睡眠リズムが乱れるなどがあります。
自分の再発パターンを把握するために、日々の気分や体調を日記やアプリで記録しておくと便利です。
また、家族や信頼できる友人にサインを共有しておくと、自分では気づきにくい変化を指摘してもらえる可能性が高まります。
うつ状態のときは休養に専念する
うつ状態で無理な活動をすると、かえって症状が悪化してしまいます。
気力や集中力が低下し、普段できることが困難になるため、「頑張らなければ」と自分を追い込むのは避けましょう。
代わりに、静かに過ごせる環境を整え、睡眠と休養を優先することが大切です。
日中に短時間の散歩や軽いストレッチを取り入れると気分転換になりますが、疲れを感じたらすぐ休むようにしましょう。
焦らずに回復を待つ姿勢を心がけることで、心身への負担を抑えられます。
医師の指示通りに薬を飲む
双極性障害の再発を防ぐためには、医師の指示通りに薬を飲むことが大切です。
症状が安定していても、自己判断で中断すると、高い確率で再発してしまいます。
副作用や服薬に不安を感じる場合は、必ず医師に相談し、必要に応じて薬の種類や量を調整してもらいましょう。
双極性障害の薬は効果が出るまでに時間がかかることがあり、途中でやめてしまうと治療の効果が失われます。
薬は毎日同じ時間に服用するなど、習慣化して忘れにくくする工夫を取り入れるのもおすすめです。
ストレス管理を行う
ストレスは症状悪化の引き金になるため、ストレス管理を徹底することが重要です。
深呼吸や瞑想、ヨガなどのリラクゼーション法を取り入れるほか、趣味やリフレッシュできる時間を持つのも効果的です。
自分の限界を知り、過剰な予定や負担を抱え込まないようにしましょう。
また、職場や家庭などでストレスの原因が明確な場合は、業務の調整や環境改善も検討してみてください。
規則正しい生活を心がける
生活リズムの乱れは、躁状態やうつ状態を招く大きな要因となります。
毎日同じ時間に起床・就寝すること、朝に日光を浴びて体内時計を整えること、適度な運動やバランスの取れた食事を続けることが大切です。
特に睡眠不足は躁転のきっかけとなるため、徹夜や極端な夜更かしは避けましょう。
カフェインやアルコールの過剰摂取も睡眠の質を下げるため、なるべく控えるのが望ましいです。
双極性障害と向き合うときの心構え

双極性障害と診断されると、最初は驚きや不安、戸惑いといった感情が湧くのは自然なことです。
しかし、病気を否定し続けると治療の開始や継続が遅れ、再発リスクが高まります。
まずは自分が双極性障害であることを受け入れ、治療に前向きに取り組む姿勢を持つことが大切です。
症状の波を上手に管理すれば、充実した生活を送ることは十分に可能です。
そのために自己理解を深め、家族や周囲の協力を得ながら、安定した生活リズムと治療継続を意識して過ごしましょう。
また、家族やパートナーには症状の特徴や行動の変化について事前に説明し、理解を得ておくことも大切です。
そうすることで、いざというときに適切なサポートを受けやすくなります。
特に躁状態は本人が自覚できない場合が多いため、周囲が早めに変化に気づくことが重要です。
双極性障害は適切な治療で寛解を目指せる病気
双極性障害は、発症後も適切な治療と自己管理を継続することで、症状を安定させて日常生活を送れるようになる病気です。
大切なのは、病気を受け入れ、医師の指示に従って服薬を続け、生活リズムを整えることです。
加えて、再発の兆候を把握し、家族や周囲と情報を共有することで、症状悪化を未然に防ぐ可能性が高まります。
完全に症状がなくなることをゴールとするのではなく、症状をコントロールしながら自分らしい生活を送ることを目指しましょう。
『かもみーる』では、いつでもどこでも悩みを相談できるオンライン診療・オンラインカウンセリングサービスを提供しています。
心療内科の受診を迷っているという相談にも対応しているため、悩んでいることがある方はお気軽に当院までご相談ください。
▶ カウンセラー(医師・心理士)一覧 はこちら
▶ 新規会員登録 はこちら