「体に力が入らず何もする気になれない」といった状態にお悩みの方は少なくないでしょう。
こうした身体や心が極度に疲弊した状態は虚脱感と呼ばれるもので、日常生活に支障をきたすこともあります。
ストレスや睡眠不足による一時的なものもありますが、症状が長引く場合には、身体的・精神的な疾患が隠れている可能性も否定できません。
この記事では、虚脱感・脱力感が起こる原因について解説します。
考えられる精神疾患・身体疾患などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
虚脱感・脱力感とは

虚脱感・脱力感とは、身体に力が入らず、エネルギーが枯渇したような状態を指します。
どちらも日常生活に支障をきたすことがあり、心身の不調を示すサインとして注意が必要です。
具体的な症状としては、次のようなものが挙げられます。
- 寝起きに身体が重くて起き上がれない
- 手や腕に力が入らず物を落としやすくなる
- 足元がふらついて歩きにくくなる
- 片方の手や足だけ力が入らなくなる
- 何もしたくない、やる気が出ない
このような虚脱感や脱力感は、過労や睡眠不足、ストレスが原因になることもあれば、うつ病や自律神経失調症、神経系の疾患など病気が関係していることもあります。
日常的にこうした症状が続く場合は、単なる疲れでは済まされない可能性もあるため、早めに医療機関を受診することが大切です。
虚脱感・脱力感が起こる原因
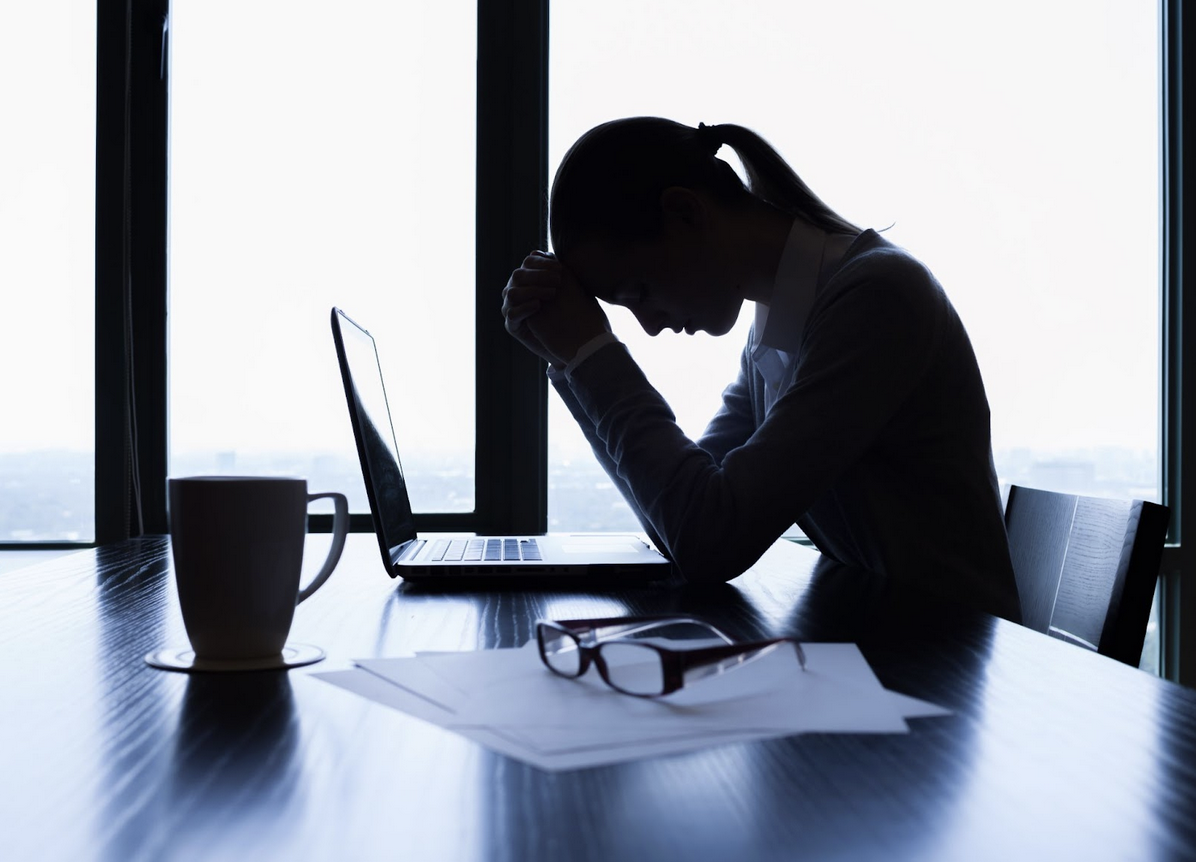
虚脱感・脱力感が起こる原因として、以下の4つが挙げられます。
- ストレスによる自律神経の乱れ
- 血流の低下
- 脳神経伝達の異常
- 栄養不足
ここでは上記4つの原因についてそれぞれ解説します。
ストレスによる自律神経の乱れ
ストレスは脱力感や虚脱感の大きな原因の一つです。
自律神経は心拍や呼吸、消化、血流などを無意識に調整する働きがありますが、強いストレスや不安が続くと、この自律神経のバランスが乱れてしまいます。
特に交感神経が優位な状態が続くと、筋肉や脳への血流が低下し、体に力が入りにくくなったり、慢性的な疲労感を引き起こしたりするのです。
また精神的な症状として無気力や集中力の低下なども生じるため、心身ともに不調を感じやすくなります。
自律神経の乱れを整えるためには、生活リズムを整えることが大切です。
質の良い睡眠、適度な運動、ストレス発散方法を見つけることで、神経のバランスを保ちやすくなります。
自律神経の不調は見えにくいため、体の変化を見逃さず早めに対策を講じることが大切です。
血流の低下
血流が悪くなると、体の隅々に十分な酸素や栄養が行き届かなくなり、結果として脱力感や虚脱感を招くことがあります。
血流の低下は、長時間同じ姿勢で過ごす、睡眠不足、過労、運動不足、冷えなどが原因で起こります。
筋肉に十分な血液が行き渡らないと、筋収縮がうまくできず、力が入らない、体が重く感じるといった症状が出やすくなるのです。
十分な休息や睡眠をとる、適度な有酸素運動やストレッチを日常に取り入れる、湯船に浸かって体を温めるといった対策が効果的です。
血流を促進させることで、筋肉の働きも回復し、脱力感の軽減につながります。
脳神経伝達の異常
虚脱感・脱力感が起こる原因の一つとして、脳神経伝達の異常が挙げられます。
人の体は、脳からの信号が神経を通じて筋肉へ伝えられることによって動きます。
この脳神経伝達に異常があると、筋肉に正しく信号が届かず、力が抜ける、動きが鈍くなるといった脱力感が生じる場合があるのです。
特に片側の手足にだけ力が入らなくなる、物を持てなくなる、歩行が困難になるといった症状が現れる場合は、脳の病気が疑われます。
脳梗塞や脳卒中、てんかんなどが関連している可能性もあり、放置すると症状が悪化する恐れがあります。
一時的な症状であっても、何度も繰り返したり、しびれを伴ったりする場合は注意が必要です。
早めに脳神経外科や神経内科を受診し、適切な検査や治療を受けることが大切です。
栄養不足
栄養が不足していると、体を動かすエネルギー源や筋肉を構成する成分が足りなくなり、結果的に脱力感や虚脱感を引き起こす原因となります。
特にビタミンB群や鉄分、マグネシウム、カリウムなどが不足すると、筋肉の動きや神経伝達に支障が出やすくなります。
例えばカリウムは神経と筋肉の正常な働きに欠かせないミネラルであり、不足すると脱力感の症状が現れやすくなるため注意が必要です。
偏食や過度なダイエット、コンビニ食・インスタント食品中心の生活では、必要な栄養が不足しがちです。
脱力感が続く場合は、まずは栄養バランスの見直しを行い、必要な栄養素をしっかりと摂取するように心がけましょう。
虚脱感・脱力感を引き起こす精神疾患

虚脱感・脱力感を引き起こす精神疾患・状態として、以下の2つが挙げられます。
- 自律神経失調症
- うつ病
ここでは上記2つについてそれぞれ解説します。
自律神経失調症
自律神経失調症は、ストレスや生活習慣の乱れによって自律神経のバランスが崩れ、心身にさまざまな症状があらわれる状態です。
ストレスにより自律神経のバランスが乱れると、身体を活発にさせる交感神経が過剰に働いたり、逆に副交感神経が抑制されることで、心身の不調につながるのです。
症状には脱力感のほか、倦怠感、慢性的な疲労感、頭痛、不安感、焦り、意欲の低下などがあります。
これらは他の精神疾患の症状と似ているため、明確な診断が難しいこともあります。
一般的には、検査をしても原因となる明確な病気が見つからず、かつ症状が続く場合に『自律神経失調症』と診断されることが多いです。
うつ病
うつ病は、強い気分の落ち込みや何もやる気が出ない状態が長期間続き、日常生活に支障をきたす精神疾患です。
症状は自律神経失調症と似ており、初期段階では区別が難しいこともあります。
気分の落ち込み、意欲の低下、不眠、食欲不振、疲れやすさなどがほぼ毎日現れ、これらが2週間以上続く場合はうつ病の可能性が考えられるでしょう。
アメリカ精神医学会が定めた『DSM-5』では、うつ病の正式名称を『大うつ病性障害』としており、抑うつ状態が長く続く場合に診断されます。
一時的な気分の落ち込みや軽度の抑うつとは異なり、興味や喜びの喪失、食欲や体重の変化、自責感、不眠、極度の疲労、自殺念慮などの症状が複数見られることが特徴です。
原因は明確には解明されていませんが、脳の機能的変化が関係していると考えられています。
長期間にわたり抑うつ状態が続く場合は、心療内科や精神科の受診が必要です。
突然現れる虚脱感・脱力感は身体疾患の可能性も

突然現れる虚脱感・脱力感は、以下のような身体疾患が原因となっている場合もあります。
- 慢性疲労症候群
- 脳卒中
- 周期性四肢麻痺
- ギランバレー症候群
- 重症筋無力症
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
ここでは上記6つの身体疾患についてそれぞれ解説します。
慢性疲労症候群
慢性疲労症候群は、ただの疲労とは異なる神経・免疫系の難病です。
健康に生活していた人がある日突然強い倦怠感に襲われ、以降、微熱や頭痛、筋肉痛、脱力感、思考力の低下、不安や抑うつなど、さまざまな症状が長期間続きます。
この病気は世界保健機関(WHO)の国際疾病分類においても『神経系疾患』として登録されており、身体的な問題として明確に位置づけられています。
この病気の特徴は、6か月以上にわたり日常生活に支障が出るほどの疲労や虚脱感が続く点です。
しかしその症状の性質から、周囲に理解されず「怠けている」などと誤解を受けるケースも少なくありません。
脳卒中
突然の脱力感や手足のしびれ、ろれつが回らないといった症状が現れた場合、脳卒中の可能性があります。
脳卒中には『脳梗塞』『脳内出血』『脳腫瘍』などがあり、いずれも早急な対応が求められる重大な疾患です。
脳梗塞は脳の血管が詰まることで発症し、4.5時間以内であれば血栓を溶かすt-PA治療が有効です。
脳内出血は血管が破れて出血する病気で、意識障害や重篤な後遺症を残す可能性もあるため、降圧薬や手術で対応します。
脳腫瘍は良性と悪性がありますが、どちらも慢性的な頭痛や嘔吐、視力低下などを引き起こします。
脳卒中は片側の手足の動きが悪くなる、言葉が出にくいなどの症状が出ることが多く、早期発見・治療により後遺症を軽減することが可能です。
周期性四肢麻痺
周期性四肢麻痺とは、体を動かす際の神経伝達に異常が起こり、手足に力が入らなくなる『麻痺』を引き起こす病気です。
この疾患では、筋肉に存在する『あるタンパク質』が電気信号に正しく反応できず、結果として筋肉が力を出せなくなるというものです。
周期性四肢麻痺は大きく分けて『遺伝性(一次性)』と『二次性』の2種類があります。
特に遺伝性周期性四肢麻痺では、麻痺発作の際に血中のカリウム濃度が変化することが知られており、『高カリウム性周期性四肢麻痺』と『低カリウム性周期性四肢麻痺』に分類されます。
いずれも突然四肢に力が入らなくなり、発作的に虚脱感や脱力感が起こるのが特徴です。
ギランバレー症候群
ギランバレー症候群は、急性かつ急速に進行する炎症性の多発神経障害です。
この病気は発症の1〜3週間前に風邪や下痢などの感染症にかかっていたというケースが多く、その中でも『カンピロバクター』と呼ばれる細菌感染が主な原因とされています。
ギランバレー症候群では、筋力低下や軽度の感覚障害が生じます。
症状は急速に進行し、多くの場合は4週間ほどでピークを迎え、その後改善に向かう傾向がありますが、重症化すると回復に時間がかかってしまうケースも少なくありません。
突然の脱力感が下肢に現れた際には、この病気の可能性も考えられるでしょう。
重症筋無力症
重症筋無力症は、末梢神経と筋肉の接合部に異常が起こる自己免疫疾患です。
神経から筋肉に伝わる信号を受け取る『受容体』が自己抗体によって破壊されることで、筋肉がうまく収縮できず、全身の筋力が低下します。
特に眼の筋肉に影響が出やすく、眼瞼下垂(まぶたが下がる)や複視(物が二重に見える)などが初期症状として現れるケースが多いです。
眼の症状に限定される場合は『眼筋型』、全身に広がる場合は『全身型』と呼ばれます。
さらに進行すると嚥下障害が出たり、重症化すると呼吸筋の麻痺により呼吸困難を引き起こすこともあるため注意が必要です。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、運動に関わる神経細胞が障害を受けることで、手足・のど・舌・呼吸筋などの筋肉が徐々に痩せて力が入らなくなる進行性の病気です。
筋肉自体の病気ではなく、それを動かすための神経である『運動ニューロン』が機能を失うことにより、脳からの指令が筋肉に届かなくなる点が特徴です。
結果として筋力が落ち、日常生活に支障をきたすようになります。
一方で、感覚・視力・聴力・内臓機能などは正常に保たれるのがALSの特徴です。
精神的な疾患による虚脱感・脱力感の治療方法

精神的な疾患による虚脱感・脱力感の治療方法は主に3つあります。
- 認知行動療法
- 対人関係療法
- マインドフルネス
ここでは上記3つの治療方法についてそれぞれ解説します。
認知行動療法
認知行動療法は、物事の受け取り方や思考パターンに生じる認知の歪みを修正することで、心の状態を整える治療方法です。
うつ状態や虚脱感、脱力感のあるときは、何事にも悲観的にとらえ、自分を責めたり落ち込んだりしがちです。
認知行動療法を行い、柔軟な考え方を身につけたり問題解決力を高めたりすることで、少しずつ現実的で前向きな思考ができるようになります。
自分の考えや行動が変わることで、日常の中で起きる困りごとにも冷静に対処できるようになり、「自分にはできる」という自己効力感も育まれます。
対人関係療法
対人関係療法は、自分にとって重要な人との関係に焦点を当て、その中にある問題点を明らかにして改善を目指す治療方法です。
人間関係に悩みがあると、それがストレスとなり、心身の不調として虚脱感や脱力感となってあらわれることがあります。
対人関係療法では、人間関係にまつわる4つのテーマのうち、どの領域に課題があるのかを明確にして具体的な感情や行動を分析します。
そして、どうすれば関係が良くなるかを考え、実際の生活の中で対策を実践していくという治療方法です。
対人関係の悩みは本人にとって非常にデリケートなものですが、適切な方法で向き合うことで精神的な負担が軽減され、症状の改善にもつながります。
人とのつながりに不安や葛藤を抱える方に有効な治療方法です。
マインドフルネス
マインドフルネスは、今この瞬間の感覚に意識を向けることで、心の安定をはかる方法です。
過去の後悔や未来への不安にとらわれがちな人は、常に頭の中が緊張や焦りでいっぱいになり、やがて虚脱感や脱力感といった症状につながることがあります。
マインドフルネスでは、良い・悪いといった評価をせず、ただ「今、自分が何を感じているか」に意識を向けます。
自分の今の感覚に向き合うことで、ストレスと上手く付き合う力を養う治療方法です。
虚脱感が長く続く場合は医療機関を受診しましょう
虚脱感や脱力感は心身の疲労から一時的に現れることもあれば、慢性疲労症候群や脳疾患、神経系の病気などが関係している場合もあります。
精神面では、うつ病や自律神経の乱れなどが背景にあるケースも少なくありません。
いずれにしても、症状が長く続く場合は、自己判断せず医療機関で適切な診断と治療を受けることが大切です。
かもみーるでは、オンライン上で受けられるカウンセリングサービスを提供しています。
「人間関係で疲弊している」「病院を受診すべきか悩んでいる」といった相談にも対応しているため、お悩みの方は気軽に当院までご相談ください。
▶︎カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶︎新規会員登録はこちら
