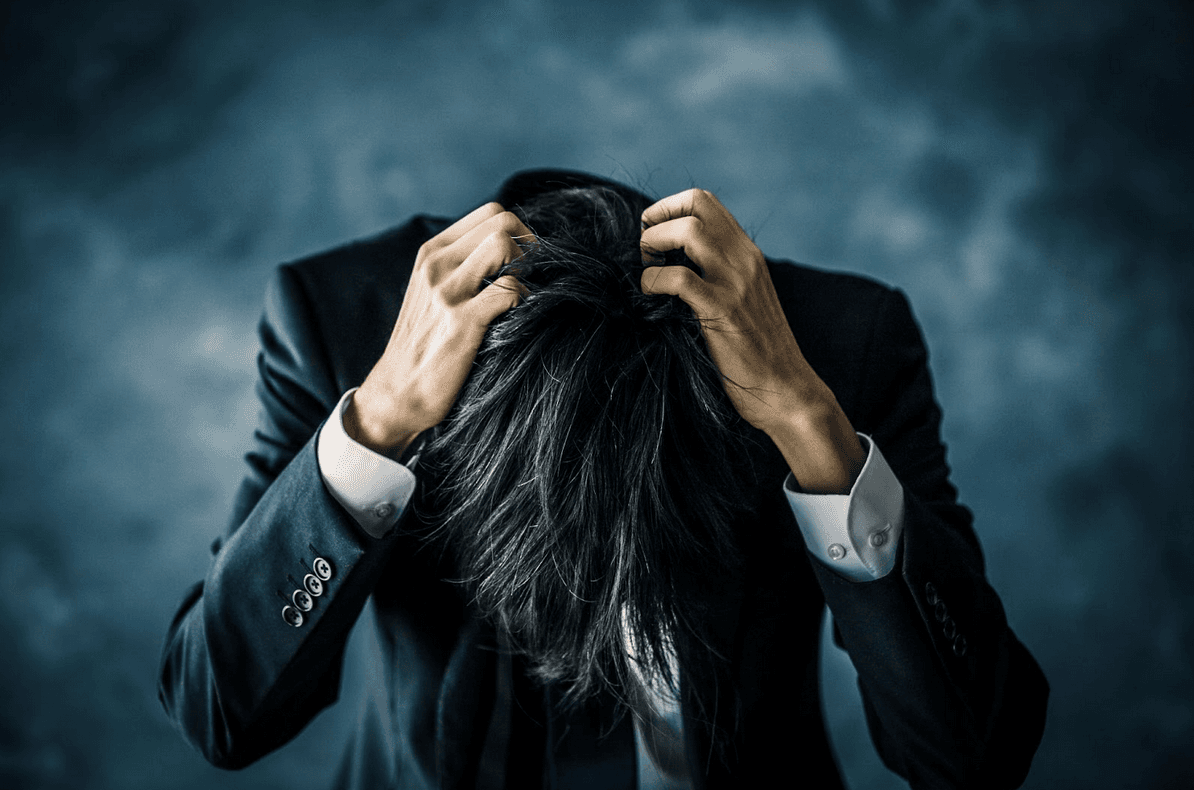「なんだかイライラしやすい」「理由もなく気持ちが不安定になる」そんなことはありませんか?
イライラする背景には、心理的ストレスや身体の不調、ホルモンバランスの乱れ、睡眠不足など、複数の要因が関係しています。
その要因を放置したままだと、メンタル不調や生活習慣病のリスクにもつながる可能性があるため、早めの対処が大切です。
この記事では、イライラを引き起こす原因を分かりやすく整理し、すぐに取り入れられるセルフケアや受診の目安まで詳しく解説します。
なぜすぐイライラするのか?

すぐイライラしてしまうのは、性格の問題だけではなく、心や身体の不調に加え生活習慣が大きく関係しています。
人は誰でも、ストレスや不安などを抱えると、感情をコントロールする力が低下します。
その結果、普段なら気にならない些細な出来事にも敏感に反応し、ちょっとしたことでイライラが募りやすくなります。
さらに、ホルモンバランスの乱れや栄養不足、自律神経の不調などは『イライラしやすい体質』をつくる要因となるため、注意が必要です。
例えば、仕事や家庭などでストレスが続くと、心の余裕がなくなり、家族や同僚のちょっとした一言にも腹が立ってしまうことがあります。
『すぐイライラする』のは必ずしも性格のせいではありません。原因を理解し正しいケアを行うことが、イライラ解消への第一歩です。
心理的要因(ストレス、不安、完璧主義など)
心理的な要因としてあげられる、ストレスや不安、完璧主義という性格は、イライラの大きな引き金となります。
ストレス | 仕事が多忙である、人間関係に悩んでいる、家庭内の負担が大きいといったことで心に圧力がかかると、余裕を失いやすくなる |
不安 | 来への不安や過去の失敗の反動により、心が緊張してしまい、ちょっとした刺激に過敏になる |
完璧主義 | 理想通りにいかないと苛立ちやすく、自分や他人に厳しい視点が怒りを増幅させる |
心理的要因は、無意識に積み重なることも多く、思い込みによってストレスが蓄積されてしまうこともあります。
ストレスの内容を可視化し、思考のクセに気づくだけでもイライラの頻度は減少します。
身体的要因(ホルモンバランス、疲労、睡眠不足、栄養不足)
ホルモンバランスの乱れや疲労、睡眠不足や栄養不足も、感情コントロールに直結し、イライラを加速させる原因になります。
ホルモンバランス | ホルモンバランスの乱れ、特に女性は月経周期や更年期によるホルモンの揺らぎが影響する |
疲労や睡眠不足 | 脳の前頭前野が働きにくくなり、怒りを抑えにくくなる |
栄養不足 | 鉄分やビタミンB群、マグネシウムは神経伝達物質の合成に不可欠であるため、不足すると感情が不安定になる |
十分な休養や睡眠、バランスの取れた食事は、イライラを予防するためにも重要です。
急にイライラするのはなぜ?

突然意味もなくイライラしてしまうという経験は多くの人にあります。
これは単なる性格の問題ではなく、身体の一時的な変化や生活習慣、ストレスの影響による自然な反応で起こる場合が多くあります。
ホルモンバランスの変動
ホルモンバランスの変動は、イライラする原因の一つです。
特に女性は、月経前症候群(PMS)や更年期によるホルモン変動の影響を受けやすいため、年齢の変化とともにイライラも変化していきます。
例えば、エストロゲンやプロゲステロンといった女性の体内で重要な役割を果たす2種類の女性ホルモンのバランスが変化すると、脳内の神経伝達物質にも作用し、気分が不安定になりやすくなります。
これは自然な身体の反応であり、生活習慣の見直しやサプリメント、医療的なサポートで改善が期待できる場合もあるので、気になる場合は医療機関を受診しましょう。
血糖値の急激な変動
血糖値の急激な変化も、イライラする原因の一つです。
食事の間隔が空きすぎたり、糖質を一度に大量に摂取すると血糖値が急激に変動します。
例えば、血糖値が下がると、『エネルギー不足で危機』と脳が判断し、イライラや焦燥感を強めるのです。
血糖値を安定させるためには、バランスの取れた食事やナッツやヨーグルトなどの間食を活用すると効果的です。
慢性的な疲労やストレスの蓄積
日々の生活の中で「ちょっと疲れた」「少しイライラした」という小さな負担をそのまま放置していると、気づかないうちに心と身体に蓄積されます。
その結果、限界に達したときに一気に感情としてあふれ出し、急にイライラしたり、些細なことで怒りっぽくなってしまうのです。
例えば、睡眠不足が続いている、人間関係に気を遣って気持ちを抑え込んでいる、休日もやることに追われてリラックスできないといった状態が続くと、心身ともに緊張モードになり、脳や神経が休まらなくなるのです。
『慢性的な疲労やストレスの蓄積』は、自律神経の乱れを引き起こしやすく、集中力の低下、頭痛や肩こり、胃腸の不調など体の症状にもつながります。
イライラが続くとどうなる?

イライラが一時的なものであれば自然に収まることも多いですが、長期間続く『慢性的なイライラ』には要注意です。
放置すると、心にも体にも大きな悪影響を及ぼし、生活の質を大きく低下させる原因となります。
メンタル面への影響
イライラが続くと、心のエネルギーが消耗し、不安や抑うつ、意欲低下を引き起こします。
人はストレスが強くかかると、『幸せホルモン』と呼ばれる脳内のセロトニンやドーパミンの分泌が減少します。
その結果、気分の落ち込みや不安感が増し、感情のコントロールが難しくなってしまうのです。
「以前は楽しめていたことに興味がわかない」「仕事に集中できない」といった状態は、慢性的なイライラがメンタルに影響しているサインです。
単なる「気分の問題」ではなく、心の不調の前触れととらえて、早めに対策することが大切です。
身体面への影響(自律神経の乱れ、胃痛や頭痛など)
慢性的なイライラは、心身双方に負担をかけます。怒りや緊張を抱えたままでいると交感神経が優位になり、自律神経のバランスが乱れやすい状況に陥ります。
その影響で血流や消化機能が滞り、体の不調として現れてしまうのです。
胃痛や胸やけ、頭痛や動悸などの症状が出る場合には、慢性的なストレスが原因である可能性があります。
『体の不調があるからイライラする』『イライラがあるから体調が悪い』という悪循環に陥る前に、生活習慣の見直しや専門家への相談が必要です。
▶ストレスで胃が痛い…原因・対処法・受診すべき病院(何科)をわかりやすく解説
イライラする時の対処法

イライラを感じたとき、すぐに取り入れられる方法があります。
深呼吸をしたり、感じたことを日記にしたりすることで、気持ちを落ち着ける助けになるでしょう。
イライラする感情を無理に抑え込むのではなく、自分に合った方法で切り替えることが大切です。
深呼吸やマインドフルネスで気持ちを切り替える
ゆっくりと深呼吸するだけでも自律神経が整い、自然と気持ちが落ち着いていきます。
呼吸によって副交感神経が働きやすくなり、自律神経のバランスが回復しやすくなるのです。
さらに、マインドフルネスは「今ここ」に意識を向けるため、怒りや不安に振り回されにくくなります。
瞑想を習慣にすると、感情の動きに気づき、冷静に受け止める力が身についていきます。
(参考:マインドフルネス瞑想)
ストレス日記で感情を言語化する
感情をため込むと、イライラが強まったり気持ちが爆発したりする原因になります。
そこで有効なのが「ストレス日記」です。
日記やメモに「なぜイライラしたのか」「そのときどう感じたのか」を書き出すことで、自分の感情を客観的にとらえやすくなります。
また、実際に文字にすることで頭の中が整理され、気持ちの切り替えにも役立つでしょう。
続けて記録していくことで、自分の思考や行動のパターンに気づけるようになり、イライラを減らすための具体的な対策を考えやすくなります。
軽い運動やストレッチで体をリセット
イライラがたまったときは、体を動かすことが効果的です。
運動をすることで血流が促され、脳に酸素が行き渡ることで、ストレスホルモンであるコルチゾールが減少します。その結果、気持ちの高ぶりが落ち着きやすくなるのです。
激しい運動をする必要はありません。ウォーキングやストレッチ、ヨガなど軽めの運動で十分です。
特に、デスクワークが多い人は、数分でも体をほぐす習慣を取り入れると、自律神経のバランスが整い、イライラしにくい心や身体をつくれます。
香りや音楽を活用したリラックス法
香りや音楽は、手軽に取り入れられるストレス対処法の一つです。
例えば、ラベンダーやベルガモットなどのアロマは、副交感神経を優位にし、心を落ち着ける働きがあります。
また、リラックスできる音楽を聴くことで、緊張が和らぎ、感情の高ぶりが自然と鎮まりやすくなります。お気に入りの香りや音楽を『気持ちのリセットアイテム』として用意しておくと、イライラを感じたときにすぐ切り替えられます。
五感を通じたリラックス法は、日常に取り入れやすく、継続しやすい点も大きなメリットです。
イライラをためない生活習慣

イライラを感じにくい心身をつくるためには、日常生活の基盤を整えることが欠かせません。
ストレスの原因を完全になくすことは難しいですが、工夫次第でイライラしにくい体質に近づけます。
規則正しい睡眠、栄養バランスの取れた食事、適度な運動などは、自律神経やホルモンの安定に直結するため、怒りや不安をため込みにくい健やかな毎日につながるのです。
栄養バランスのよい食事を心がける
イライラしやすい人は、食事内容を見直すことが大切です。
なぜなら、血糖値の急変動や栄養不足が、脳や神経の働きを不安定にしてしまうからです。
例えば、糖質だけを摂取すると血糖値が急上昇し、気分の浮き沈みを招きやすくなります。
一方、タンパク質や食物繊維を組み合わせると、血糖値は安定しやすくなります。
また、鉄分やビタミンB群、マグネシウムといった栄養素は神経の働きを支え、感情の安定に役立つため、栄養バランスの取れた食事を心がけましょう。
適度な運動をする
イライラした時だけでなく、日常的に適度な運動を取り入れることも大切です。
運動をすると脳内でセロトニンが分泌され、ストレスホルモンであるコルチゾールが減少するからです。
例えば、ウォーキングやヨガ、軽い筋トレなどを週に数回行うだけでも、心身のリフレッシュにつながります。
日常生活の中で無理なく続けられる範囲で運動を取り入れ、心の安定につなげましょう。
睡眠の質を改善する
質の高い睡眠は、翌日のイライラ防止に直結するため、自分に合ったナイトルーティンを取り入れることが有効です。
その理由は、寝る前の行動が自律神経を整え、入眠をスムーズにするからです。
具体的には、就寝前にぬるめのお風呂に入ったり、ストレッチや読書をしたりすることで、副交感神経が優位になり、心身がリラックスしやすくなります。
逆に、スマホやPCの強い光やブルーライトは睡眠ホルモンの分泌を妨げるため、就寝前の使用には注意が必要です。
医療受診を検討すべきタイミング

イライラは一時的なストレス反応で収まることもありますが、長引く場合は注意が必要です。
セルフケアを続けても改善が見られない、日常生活に影響が出ているというときは、専門医への相談を検討しましょう。
イライラが2週間以上続く
イライラが一時的であれば自然に収まることが多いですが、2週間以上続く場合は心身の不調が背景にある可能性があります。
慢性的なストレスやホルモンバランスの乱れ、うつ病や不安障害などの精神的な病気が隠れているケースも少なくありません。
我慢していると、症状が悪化して日常生活に大きな支障をきたす恐れがあります。
早めに専門家へ相談することで、適切な治療やアドバイスを受けられ、安心感にもつながります。
感情のコントロールが難しく生活に支障が出ている
イライラが強すぎて感情をコントロールできず、生活に悪影響が出ている場合は医療機関への受診を検討すべきです。
例えば、人間関係でぶつかることが多くなる、仕事の集中力が落ちるなどの影響が考えられます。
こうした状態を放置すると、さらにストレスが積み重なり、心身に深刻な不調を招く恐れがあるため、医療機関に相談しましょう。
医療機関では、薬物療法やカウンセリングなど、自分に合った専門的なサポートを受けられる可能性があります。
強い落ち込みや不安を伴う
イライラしながらも、落ち込みや不安感が続く場合、心の病気が関与している可能性があります。
特に『気分が晴れない』『常に不安を感じる』といった症状が強いと、うつ病や不安障害などのサインであることもあります。
こうした状態を我慢して放置すると、症状が慢性化し回復までに時間がかかってしまいます。
医療機関を受診することで、原因に応じた治療やカウンセリングを受けられるため、回復の糸口を見つけやすくなります。
慢性的なイライラは医療機関へ相談しよう
イライラは誰にでも起こる自然な感情です。
しかし、慢性的に続くと心身に不調をもたらし、生活の質を大きく下げてしまいます。
心理的要因や身体的要因を理解し、深呼吸や運動、生活習慣の改善などでセルフケアを行うことが大切です。
また、セルフケアを行っても改善されない場合や、生活に支障が出ている場合は、無理に我慢せず早めに専門家へ相談することが回復への近道です。
「どんな医療機関に相談に行けばいいのか」と迷われている方には、オンライン診療サービス『かもみーる』がおすすめです。
診療時間が24時までのため、忙しい方でも時間を気にせず診断を受けられます。
『かもみーる』では、経験豊富な医師や心理士が、一人ひとりに合わせたカウンセリングを行い、心の回復を丁寧にサポートします。
▶︎カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶︎新規会員登録はこちら