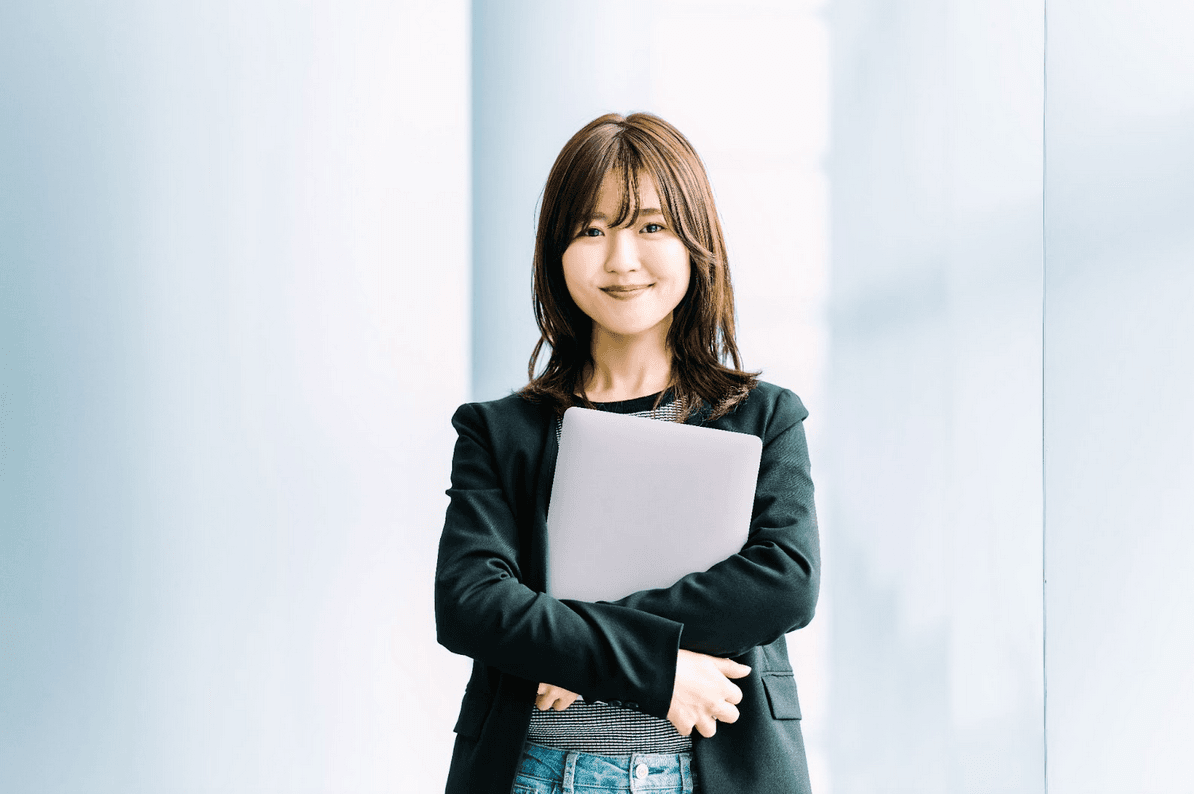仕事をするうえで「人前で話すのがつらい」「電話が怖い」「通勤電車に乗るのが苦痛」といった悩みを抱えている人は少なくありません。
そのような悩みは不安障害が関係している場合があり、日常生活や仕事に影響を与えることがあります。
しかし、不安障害を抱えていても、適切な治療や職場環境・生活習慣の工夫によって無理なく働くことが可能です。
この記事では、不安障害が及ぼす仕事への影響、向いている仕事の特徴、転職の際に気を付けたいポイントなど幅広く解説します。
不安を抱えながらも自分らしく働きたいと思う方は、ぜひ参考にしてください。
不安障害と仕事の関係

大勢の人の前で話をしたり、発表をする場合に緊張することは誰にでもあります。
しかし、そのような状況下で過度に不安を感じ手足が震える、冷や汗や動悸・吐き気を感じるなど苦痛を伴う場合は、不安障害かもしれません。
不安障害は、仕事にも影響を与えることがあります。
ここでは、不安障害の種類と症状が仕事に与える影響について紹介します。
不安障害とは
人前で何かする時や特定の状況下で、心配や不安が過度になり、日常生活に影響が出る病気を不安障害と呼びます。
精神的な不安から、心と身体にさまざまな不快な変化が起こり、学校や会社に行けなくなることもあります。
不安障害にはいくつかの種類があり、代表的なものは以下のとおりです。
種 類 | 特徴・症状 | 具体例・行動パターン |
パニック障害 | 突然の激しい不安・恐怖と身体症状(動悸・息切れ・めまいなど) →パニック発作 | 電車に乗れない・人混みを避ける・一人での外出を避ける(予期不安) |
社会不安障害 | 人前で話す、人と接する場面に強い不安や恐怖を感じる | 会話が怖い・人混みや公共交通機関に苦痛・外出を避ける |
強迫性障害 | 自分でも不合理とわかっていても繰り返し確認・行動をしないと不安 | 手洗いをやめられない・戸締りを何度も確認など |
全般性不安障害 | 日常のさまざまなことに過剰に不安・心配を感じる状態が6か月以上続く | 学校や家庭、将来などについて常に心配している。イライラ・不眠・集中力の低下が併発することもある |
不安障害の中の社会不安障害は、他者との関わりに強い不安を感じるため、仕事にも影響を与えます。
不安障害の詳しい内容はこちらも参考にしてください。
→【精神科医監修】不安障害とは?種類ごとの特徴や症状、治療法について詳しく解説
不安障害の症状が仕事に与える影響
不安障害の症状が仕事に与える影響は以下のようなものが挙げられます。
- 人の視線が気になる
- 人前で話せない
- 電話でうまく話せない
- 会議や宴会など人が集まる場所に参加できない
- 電車やバスなどに乗れない
会議や電話、宴会など人と話す場面が多い仕事は、不安障害の方にとって苦痛を伴ってしまうかもしれません。
しかし、不安障害を抱えながら働くことは可能です。
業種や職場環境を調べ、治療を続けながら自分に合った仕事をしている不安障害の方も少なくありません。
「不安障害だから仕事ができない」と考えずに、まずは自分に向いている仕事を考えることから始めてみましょう。
不安障害のある人に向いている仕事

不安障害で業務を遂行することが難しい場合には、転職や部署移動を願い出るという選択肢があります。
ここでは、不安障害の方がどのような仕事が向いているのかを紹介します。
業務にムラのない定型的な仕事
忙しかったり、暇だったりする差が大きい業務の場合、急に忙しくなることで不安や緊張が増すことがあります。
事務職や工場勤務、図書館司書などの、日によって業務内容や業務量に差がなく、決まった手順で進められる業務であれば、不安や緊張が強くなることを避けられるでしょう。
マイペースにできる仕事
不安障害では、周囲の視線や発言が気になってしまう症状が起こるため、自分のペースを守りながらできる仕事も向いています。
研究職、エンジニア、清掃員などの仕事は必要以上に他人と直接接触する機会が少ないため、心を守ることにつながるかもしれません。
在宅勤務が可能な仕事
自宅で仕事ができる在宅勤務やテレワークが多い仕事は、マイペースにリラックスして作業を進めることができます。
具体的には、WebデザイナーやWebライター、動画編集、イラストレーター、個人事業主・フリーランス、一般事務アシスタントなどの仕事が挙げられます。
不安障害の人が働きやすくなる工夫

不安障害の症状があっても、できるだけストレスを受けずに長く働き続けるために、以下のような工夫をおすすめします。
- 専門家のもとで治療を続ける
- 合理的配慮を申し出て周囲の理解を得る
- 生活習慣・食生活の改善
- リラックス方法を身につける
- 無理せず休む
これらの工夫について、以下で詳しく紹介します。
専門医のもとで治療を続ける
不安障害は、専門医による治療を継続的に行うことで軽減する可能性が高まります。
医師やカウンセラーとの関わりにも不安を感じるかもしれませんが、医師らの専門的な知識によって不安や緊張を和らげることができます。
仕事と治療の両立をする場合、治療による勤務時間の変更・作業内容の変更など職場に理解を得なくてはなりませんが、医師に相談すれば職場への伝え方も教えてもらえるでしょう。
カウンセリングによって、コミュニケーションに慣れる効果もあるため、仕事に対する姿勢にもよい影響を与える可能性があります。
合理的配慮を申し出て周囲の理解を得る
024年4月1日から改正障害者差別解消法により、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。
合理的配慮の提供には、障害のある方や家族から勤務先に配慮を求める意思表明を行う必要があるため、事前に医師・家族と相談し、申請しましょう。
合理的配慮により、周囲の理解とサポートを得られるため、仕事に対する不安や緊張が軽減され、働きやすさにつながります。
産業医や社内の相談窓口などから、職場への伝え方を相談できます。
生活習慣・食生活の改善
ストレスや疲労をためこまない生活習慣や食生活は、不安障害を改善するのに効果的です。
- 毎日寝る時間を決め、睡眠時間を確保する
- 散歩やラジオ体操など適度に身体を動かす
- 暴飲暴食を避け、栄養バランスを考えた食事をする
上記のような習慣を身に着けることで、心身の状態が安定する場合があります。
リラックス方法を身につける
不安障害の主な症状に、心身の緊張があります。
緊張状態が続くことでストレスや疲労につながり、症状が悪化する可能性も考えられるでしょう。
例えば、湯舟にゆっくりつかる、アロマを焚く、好きな音楽を聞く、ストレッチをするなど、自分なりにリラックスできる方法を身につけ、緊張を和らげましょう。
無理せず休む
体調がすぐれない時は、無理をせず休むことも大切です。
症状が悪化している時に無理に仕事を続けてしまうと、さらに悪化するリスクが高まります。
業務の継続が難しくなったと感じたら、まずは職場へ業務量や内容を調整してもらえるか相談してみましょう。
一時的な休暇や休職をする場合は、職場によって規定を事前に確認し、利用できる制度があるか調べることも大切です。
不安障害を理由に休職・転職を考えたら

不安障害の症状が原因で、休職や転職を考える際に利用できる公的制度があります。
ストレスや不安を抱えない休職・転職期間を送るためにも、ぜひ参考にしてください。
不安障害の人が利用できる公的制度
不安障害の方が休職や転職を考える際には、以下のような公的制度を利用できます。
制度 | 内容・目的 | 利用条件 | 支援内容 |
傷病手当金 | 病気やケガで働けない時の生活補填 | ・業務外の病気やケガで休業 ・仕事ができない状態 ・連続3日を含む4日以上の休業 ・給与が出ていない | ・最長1年6か月支給 ・平均給与の約3分の2(加入保険により異なる) |
失業保険 | 失業中の生活支援と再就職支援 | ・雇用保険の加入期間が一定以上 ・働く意思・能力がある ・ハローワークに求職申し込みをしている | ・給付金額は収入や年齢による ・離職届の提出が必要 |
自立支援医療制度 | 精神科通院医療費の自己負担軽減 | ・不安障害などで継続的な通院が必要 ・医師の診断書がある | ・医療費の自己負担が3割から1割に軽減 |
傷病手当金は加入している健康保険組合、失業手当(雇用保険の基本手当)はハローワーク、自立支援医療制度は市区町村の福祉・保健担当窓口に申請することで利用できます。
障害者雇用という選択肢
不安障害がある方は、障害者雇用枠での就職を選択肢に入れることができます。これは「障害者雇用促進法」に基づき、企業が障がいのある方のために設けている雇用制度です。
障害者雇用枠での就職には、原則として精神障害者保健福祉手帳などの障害者手帳の取得が必要です。申請には医師の診断書が必要になるため、主治医や自治体に相談しましょう。
障害者雇用には以下のようなメリットがあります。
- 業務内容や勤務時間の合理的配慮が受けやすい
- 病気を開示して働くため、職場の理解が得られやすい
- 通院や治療との両立がしやすく、長く働きやすい
開示することで周囲の理解や配慮が得られやすくなり、不安や緊張を感じることが減る可能性があります。
一方で、障害者雇用には以下のようなデメリットもあることを知っておきましょう。
- 給与や昇進面で制限がある場合がある
- 求人の数が限られている
- 企業によっては配慮やサポートが不十分なこともある
限られた求人件数の場合が多いため、障害者雇用と一般雇用の両方を視野に入れて柔軟に応募するのをおすすめします。
自分に合った働き方を見つけるには

不安障害があっても、自分に合った環境で働くことは可能です。そのためには就労をサポートしてくれる公的機関や支援制度を活用することが大切です。
ここでは、代表的な支援先を紹介します。
ハローワーク
ハローワークでは、一般的な求人のほか、症状に配慮した職場の紹介や職場適応訓練、トライアル雇用の案内などが受けられます。
障害者手帳がなくても相談が可能で、不安や悩みに合わせたアドバイスももらうことができます。
地域によっては障害者専門窓口もあるため、転職を考える際には足を運んでみましょう。
障害者就業・生活支援センター
就職活動の支援だけでなく、金銭管理や生活リズムの相談など、生活面の支援も含めたサポートが受けられるのが障害者就業・生活支援センターです。
ハローワークや医療・福祉機関と連携しているため、地域での暮らしと就労の両立を手助けします。全国に設置されており、誰でも相談が可能です。
地域障害者職業センター
不安障害などの症状に応じた専門的な職業リハビリテーションを提供する機関です。
職業評価、訓練、指導などを通じて、自分に適した職業の発見や職場定着を支援します。
就職後も希望に応じて仕事の進め方・職場での人間関係などについてアドバイスを受けることができます。
就労移行支援事務所
一般企業への就職を目指す障害のある方に向けて、就職活動や職場定着をサポートする福祉サービスです。
体調管理の方法、コミュニケーションの練習、ビジネススキルの習得などが行われ、履歴書の書き方から面接対策まで幅広く支援します。
事務所によって雰囲気や支援内容が異なるため、見学や相談を事前に行い、自分に合った事務所を選びましょう。
医師やカウンセラーとの相談
不安障害の症状があるなかで働くには、主治医やカウンセラーへの相談が大切です。
症状は人によってさまざまで、主治医やカウンセラーは一人ひとりの症状に合わせて就労に向けた無理のない選択肢を見つけてくれるでしょう。
必要であれば、診断書の作成や支援機関との連携のサポートも行います。
不安障害の方は治療を受けつつ自分に合った仕事をしよう
不安障害の症状があると、働くことに不安を感じてしまいますが、適切な治療や環境の工夫で無理のない形で働き続けることは可能です。
自分の症状や特性に合った働き方をみつけるには、専門医の治療やカウンセリングを受けながら、公的制度や支援機関を活用することが大切です。
『かもみーる』では、医師監修のオンライン診療・オンラインカウンセリングサービスを提供しています。
症状に合わせて経験豊富な医師、臨床心理士や公認心理師を中心とした有資格者が、一人ひとりに合わせたカウンセリングを行います。
不安障害の症状で業務の進め方に悩んでいる方は、一人で悩まずにぜひご相談ください。
▶︎カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶︎新規会員登録はこちら