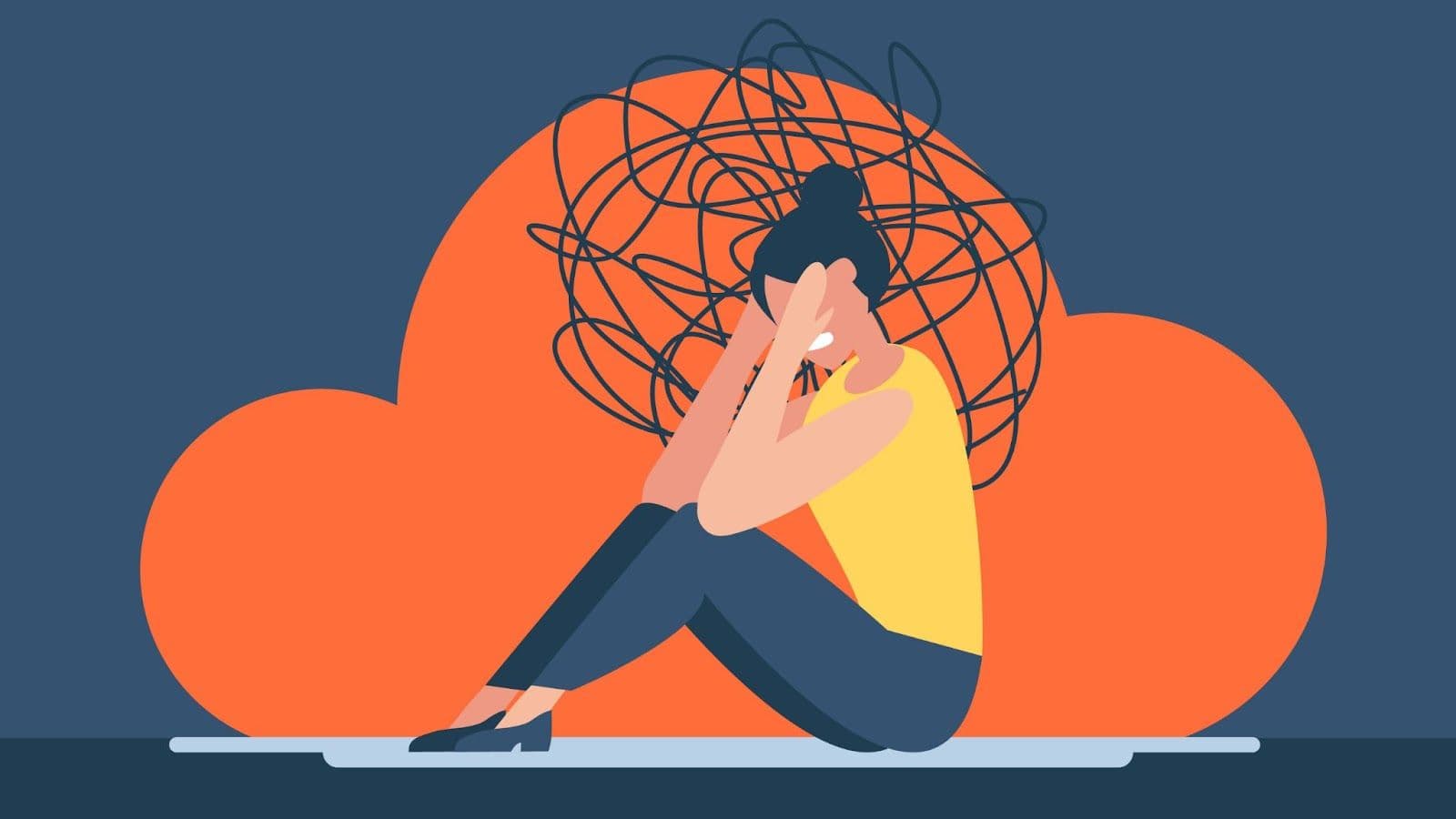適応障害はストレスが原因で起こる病気です。日常生活の中で誰もが感じるストレスですが、負担に感じる出来事やその受け止め方、対処法は人それぞれ異なります。
ストレスに対応できなくなってしまうと、心や身体、行動にさまざまな症状が現れるのです。
この記事では、適応障害の原因となるストレスや家庭環境の影響、治療法などについて詳しく解説します。
適応障害と診断された場合、病気を引き起こす原因となっているストレスから距離を取ることが大切です。適応障害の理解を深め、予防や早期発見に役立てていただければ幸いです。
適応障害とは?原因は「ストレス」
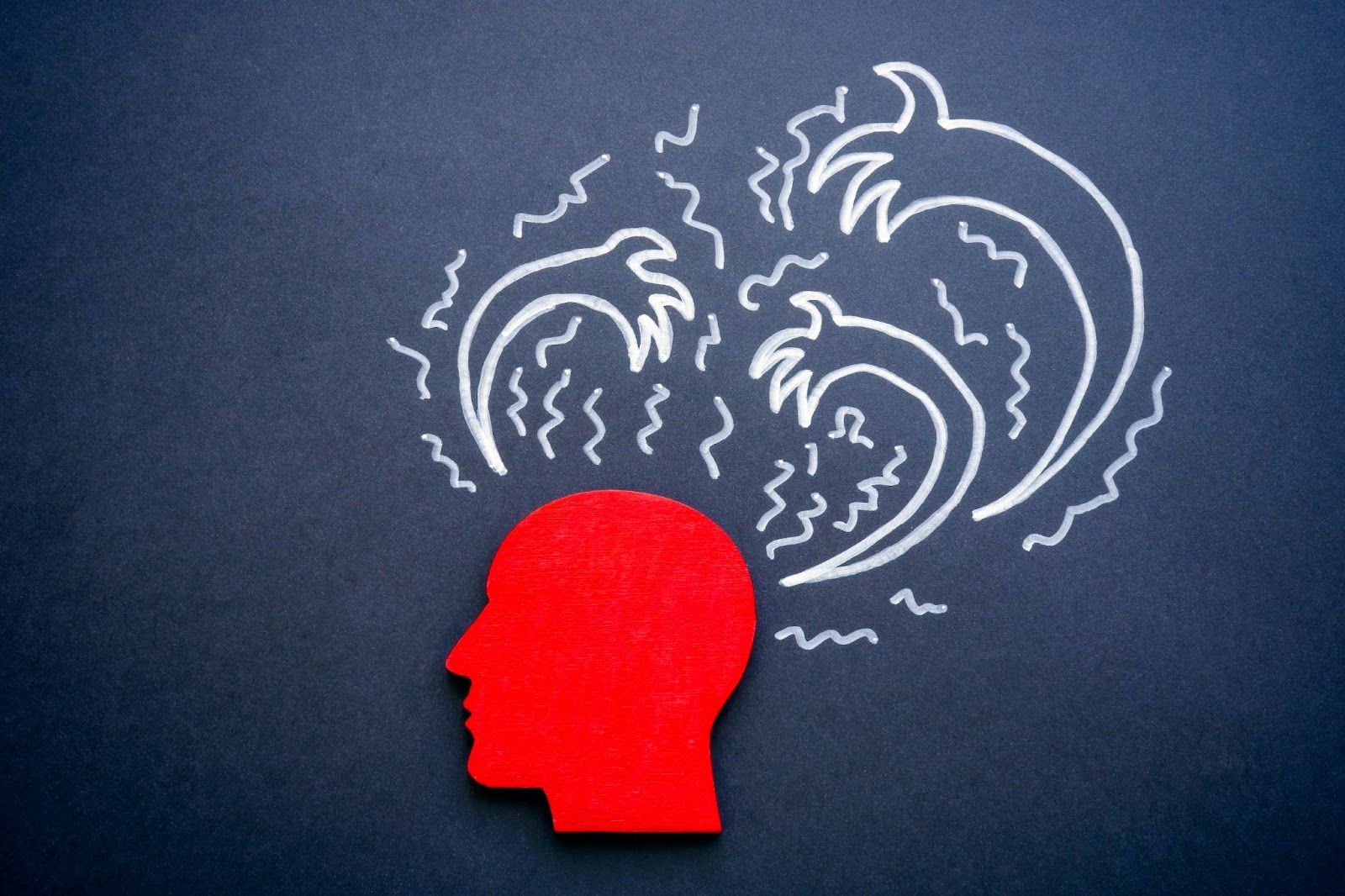
適応障害はストレス性障害の一つで、特定のストレスが原因となって発症する病気です。
適応障害では、通常の範囲を超えたストレスにさらされることで、心身に多彩な症状が現れます。
症状の現れ方には個人差がありますが、気分の落ち込みや意欲低下、不安、焦燥感、不眠、イライラ、吐き気、頭痛、無謀な運転、無断欠勤・遅刻などさまざまです。
適応障害の症状の中にはうつ病と似た症状もあるものの、適応障害とうつ病は異なります。
うつ病は発症のきっかけがないことが多いですが、適応障害は発症のきっかけとなった原因や時期がはっきりしていることが特徴です。
適応障害の治療はストレスの原因を突き止めることから
適応障害は、原因となったストレスから離れると症状が軽くなる傾向にあります。そのため、治療ではストレスの原因を特定することが非常に重要になります。
原因を突き止め、ストレスから距離を取れるようにすることが効果的な治療の一つです。
とはいえ、ストレスの原因を突き止め、距離を置くことは患者さん一人では難しいケースも少なくありません。職場や家族、医師やカウンセラーなどが必要に応じてサポートを行いながら、治療を進めていきます。
アメリカの診断基準(DSM-5)では、適応障害は原因となったストレスが取り除かれると通常は6ヶ月以内に症状が改善するとされていますが、だからといって治療をやめて大丈夫というわけではありません。
適応障害は再発しやすい病気でもあるため、改善してからもしっかり治療を継続し、再発を防止することが大切になってきます。
適応障害の原因となる主なストレス

適応障害の原因となるストレスは、患者さん個人の生活に関連することから事件や災害など多種多様です。
- 仕事のストレス(長時間労働・業務量の多さ・人間関係)
- 家庭でのストレス(結婚・出産・介護)
- 環境変化によるストレス(引っ越し・転職・転校)
- その他のストレス(病気・ケガ・事件・災害)
中でも最も多く見られるのが、仕事や家庭、学校や恋愛など「本人の生活」にまつわるストレスです。働き盛りの世代や学生はストレスが多く、適応障害が起こりやすいといわれています。
ストレスの感じ方には個人差があり、周囲の人からすると些細なことでも、本人にとっては重大なストレスとなることもあります。
また、つらい出来事や悲しい出来事によるストレスだけでなく、嬉しい出来事でのストレスでも発症することも適応障害の特徴です。
ここからは、適応障害の原因となる主なストレスについて詳しく見ていきましょう。
仕事のストレス(長時間労働・業務量の多さ・人間関係)
職場環境のストレスは適応障害の主な原因の一つです。
例えば長時間労働や多すぎる業務量、責任の重さ、上司や同僚との人間関係のトラブル、いじめ、嫌がらせ、パワハラやセクハラなどは大きなストレスです。
また、業務量が適正でも、業務内容が自分の性格や能力に合っていないと、ストレスとなることがあります。配置転換や組織の再編といった環境変化も、適応障害を引き起こすきっかけです。
家庭やプライベートのストレス(結婚・出産・介護)
家庭やプライベートのストレスや変化も、適応障害を引き起こす原因になります。
結婚や出産は喜ばしい出来事ですが、同時に大きな環境の変化をもたらします。新しい役割や責任への適応が求められるため、ストレスを感じやすい状況です。
介護では身体的・精神的な負担に加え、仕事との両立や経済的な問題など、複合的なストレスにさらされることがあり、適応障害や介護うつを引き起こしてしまうことがあります。
その他、失恋や離婚、パートナーや家族との不仲、育児や教育の悩み、就職活動や受験の失敗なども影響します。
環境変化によるストレス(引っ越し・転職・転校)
引っ越しや転職、転校など、新しい環境への適応を強いられる出来事も、適応障害のきっかけとなります。
慣れ親しんだ環境から離れて新たな人間関係を構築する必要があるため、強いストレスを感じやすくなるのです。
環境変化が起こるタイミングは適応障害を発症しやすくなるため、無理をせず、ある程度の余裕を持つようにしましょう。
その他のストレス(病気・ケガ・事故・災害)
自身や家族の病気やケガ、交通事故などの予期せぬ出来事も適応障害の原因となることがあります。
事件や自然災害などの大規模な出来事も、強いストレスをもたらす原因です。
適応障害のなりやすさに影響する要素
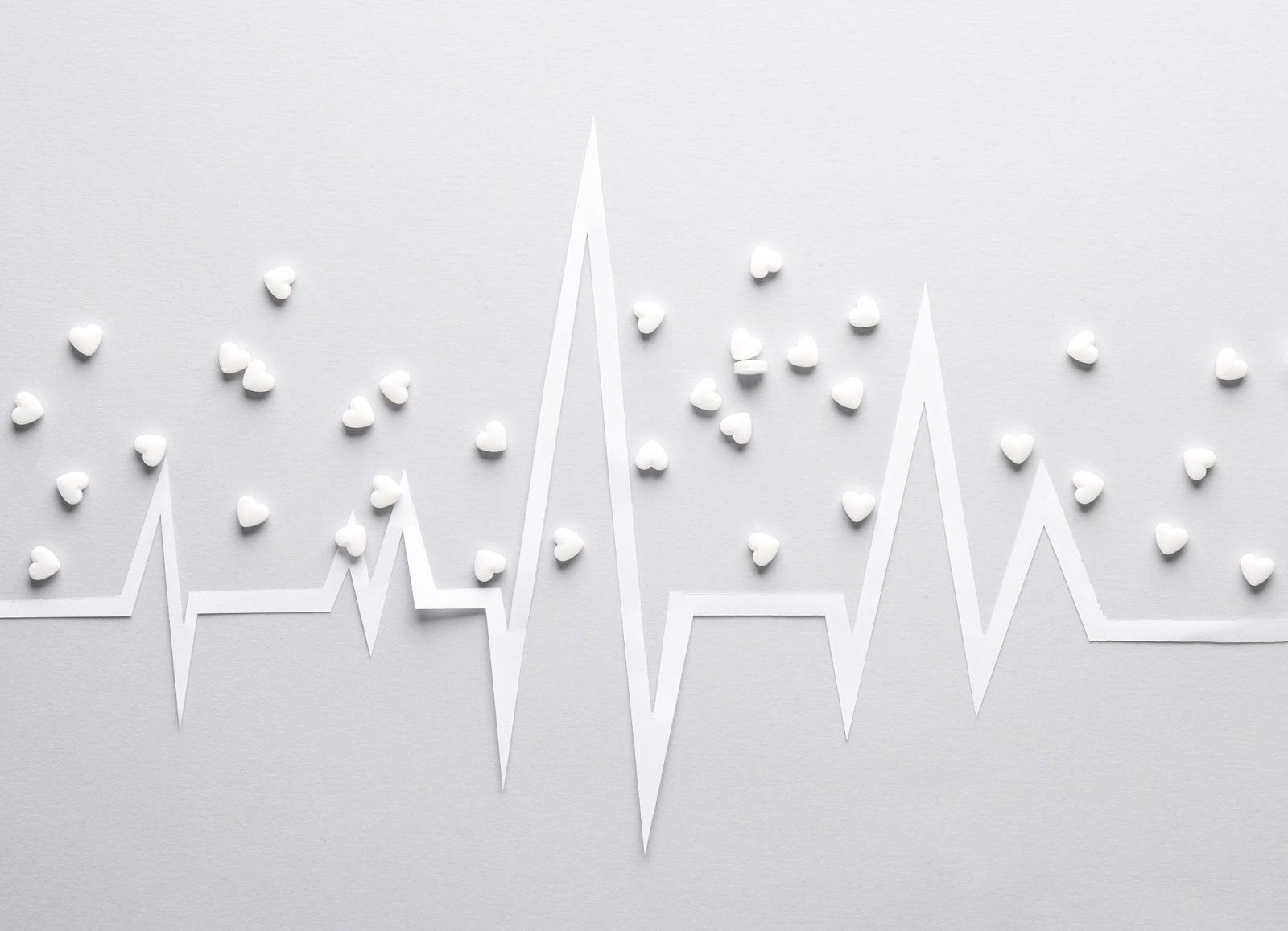
同じストレスを受けても、適応障害を発症する人と発症しない人がいます。それは、以下のような適応障害のなりやすさに影響する要素に個人差があるためです。
- 本人の性格・性質
- 置かれている状況
- ストレス耐性・ストレス対処能力
本人の性格・性質
適応障害のなりやすさは、個人の性格や性質によっても左右されます。
完璧主義や神経質、自己肯定感が低い、ネガティブ思考が強い性格はストレスに対して敏感であったり、ストレス耐性が低かったりする傾向があり、適応障害のリスクが高くなります。
また人に相談することが苦手な人や、人の頼みが断れない人も、負担を抱え込みやすいため注意しましょう。
この他、ADHD(注意欠如・多動症)とASD(自閉スペクトラム症)、LD(学習障害)といった「発達障害」の傾向がある場合も、適応障害のリスクが高くなります。
適応障害になりやすい人の性格や特徴については以下の記事で詳しく解説しています。
▶ 適応障害になりやすい人の特徴│性格や環境、顔つきなどを解説!予防法&治療法も
置かれている環境
個人を取り巻く環境も、適応障害の発症に大きく関わります。
サポート体制の有無は特に重要で、家族や友人、同僚など信頼できる人々からの支援が得られない孤立した環境では適応障害になりやすいといわれています。
また、経済的な不安、不安定な生活環境、多忙な環境、ストレスの多い環境も適応障害のリスクを高めます。
ストレス耐性・ストレス対処能力
単に「ストレス」といっても受け止め方や程度には個人差があり、同じような状況下で非常に大きなストレスを感じる人もいれば、全く負担に感じない人もいます。
このような違いはストレスに対する「認知(受け止め方)」が影響しています。
例えば、上司からミスを叱られたとして、ひどく落ち込んでしまう人もいれば、全く気にしない人、「絶対に見返してやる」と思う人など、同じ出来事でも受け止め方は人それぞれです。
ストレスに対する耐性が低い場合や、ストレスを過度に深刻に受け止めてしまう傾向がある場合、適応障害のリスクが高まるため、専門家のカウンセリングを受けるのもおすすめです。
適応障害は母親や家族が原因になる?注意が必要な家庭の特徴

個人の性格や性質は生まれ持ったものだけでなく、環境に影響を受ける部分も多くあります。そのため、問題のある家庭環境は、適応障害のリスクになります。
幼少期のみならず、青年期や若年成人期になってからも両親の不仲や両親からの情緒的拒否、母親からの過度な期待や母親が強迫的で過干渉といった、心理的打撃や重圧を受ける環境下にある親子関係では、温かく支えられた経験が乏しくなり、外の世界に適応していく場面では自信を持つことができなくなる。重症な場合は適応障害や情緒障害、うつ病といった精神疾患を引き起こす可能性が高くなる。
引用:『親子の愛着関係と青年期における気分状態・心身状態との関連性』(J-STAGE)
例えば以下のような特徴があると、適応障害のリスクが高まる可能性があります。
- 過干渉・過度な期待
- 高圧的な態度・厳しすぎるしつけや制限
- 本人と兄弟で対応に差がある
- 家事や育児、介護の負担が一人に集中している
- 家族からの暴力や暴言
家庭環境が問題となっている場合、本人だけでは状況の改善が難しいケースも少なくありません。一人で思い悩まず、医師やカウンセラーなど専門家に相談するのがおすすめです。
過干渉・過度な期待
親の過干渉は、子どもの自立心や自己決定能力の発達を妨げる可能性があります。また、過度な期待は大きなプレッシャーとなり、ストレスの原因となることがあります。
高圧的な態度・厳しすぎるしつけや制限
怒鳴り付ける、高圧的な態度で接する、行動を厳しく制限する家庭環境は、自尊心を低下させ、ストレス耐性を低下させてしまう可能性があります。
また、自分の意見を言えなくなり、ストレスを溜め込みがちになってしまうかもしれません。
本人と兄弟で対応に差がある
兄弟間での不公平な扱いも、適応障害のリスクを高める原因になり得ます。
親の愛情や関心、期待が兄弟間で偏っていると感じると、自尊心の低下や不安感の増大が起こり、ストレスを感じやすくなってしまうのです。
また、常に兄弟と比較され完璧を求められていた場合も、心が疲れ切ってしまいやすいです。
家事や育児、介護の負担が一人に集中している
本来であれば家庭は、疲れたときに心を休められる場所のはずです。
しかし、家事や育児、介護などの負担が一人に偏っていると、十分に休むことができず心身の疲労が蓄積されやすくなります。
適応障害で見られる症状

適応障害では「精神症状」と「身体症状」そして、「問題行動」が見られることがあります。
精神症状 | 身体症状 | 問題行動 |
|---|---|---|
・気分の落ち込み、憂鬱感 | ・不眠 | ・勤務への影響(無断欠勤や遅刻、仕事への支障) |
適応障害の症状の現れ方は人によって異なり、区別なくさまざまな症状が出ることもあれば、以下の4パターンに当てはまるケースもあります。
- 「うつ症状」が中心のタイプ(気分の落ち込みや憂鬱感など)
- 「不安症状」が中心のタイプ(不安や焦り、神経過敏など)
- 「身体症状」が中心のタイプ(頭痛やめまい、腹痛など)
- 「問題行動」が中心のタイプ(無謀運転、ギャンブル、遅刻や欠勤など)
また、適応障害ではうつ病に似た症状が起こりますが、効果的な治療法は異なります。悪化を防ぎ、適切な治療を受けるためにも早めに専門家に相談しましょう。
適応障害の治し方

適応障害の治療法には以下のようにさまざまな方法があります。中心となるのは「環境調整」と「心理カウンセリング」です。
- 環境調整(原因であるストレスの軽減・除去)
- 心理カウンセリング(認知行動療法や問題解決療法など)
- 薬物療法
- TMS治療(磁気刺激療法)(症状が慢性化した場合に効果が見られることがある)
環境調整では原因となるストレスの軽減や除去を行います。例えば職場でのストレスが原因の場合、上司や人事部と相談し、業務内容や勤務時間を調整するなどです。
心理カウセリングでは、適応障害の人が持っていることが多い考え方の癖にアプローチしてストレスにうまく対処できるようにする「認知行動療法」や、今ある問題と症状にフォーカスして解決方法を探る「問題解決療法」などを行います。
薬物療法は適応障害の治療では基本的には行わず、使用する場合も補助的な治療となるケースが多いです。
また近年では、「TMS治療(磁気刺激療法)」という薬を使わない新しい治療法も登場しています。TMS治療は磁気で脳の特定部位を刺激し、血流を増加させて低下した脳の機能を回復させる治療です。
適応障害はストレスの原因を知って対処することが大切
適応障害は、特定のストレスが原因で発症する病気です。仕事、家庭、環境の変化など、さまざまなストレス要因が引き金となり、個人の性格や環境、ストレス耐性なども発症に影響しています。
そのため適応障害の治療では、ストレス原因の特定とストレスの軽減・除去が大切になってきますが、職場環境や家庭環境が大きく影響していることもあり、患者さん一人では対処が難しいケースも少なくありません。
そんなときは、医師やカウンセラーなど専門家に相談するのがおすすめです。
クリニックではお悩みを聞くだけでなく、診断書を発行することで今のつらい人間関係を断ち切ったり、離れたいパートナーから距離を置いたりなど、ストレスから距離を取るサポートを行っています。
『かもみーる』ではオンライン診療・オンラインカウンセリングを行っており、最短当日中に診断可能です。
適応障害は決して珍しい病気ではありません。誰もが経験する可能性のある心の不調です。一人で悩まず、まずはご相談ください。
▶ カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶ 新規会員登録はこちら