適応障害とは、強いストレスをきっかけに心や体に不調が現れ、日常生活に支障をきたす状態を指します。
ストレスの原因がはっきりしている点が特徴で、職場の人間関係や家庭のトラブル、転勤などが発症の引き金になることが多く見られます。
適切な治療を受ければ改善が期待できますが、対応が遅れると、うつ病などに進行するリスクもあるため注意が必要です。
この記事では、適応障害の治療方法について詳しく解説します。
クリニックでの治療方法のみでなく、自分でできる対処法もまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
適応障害とは
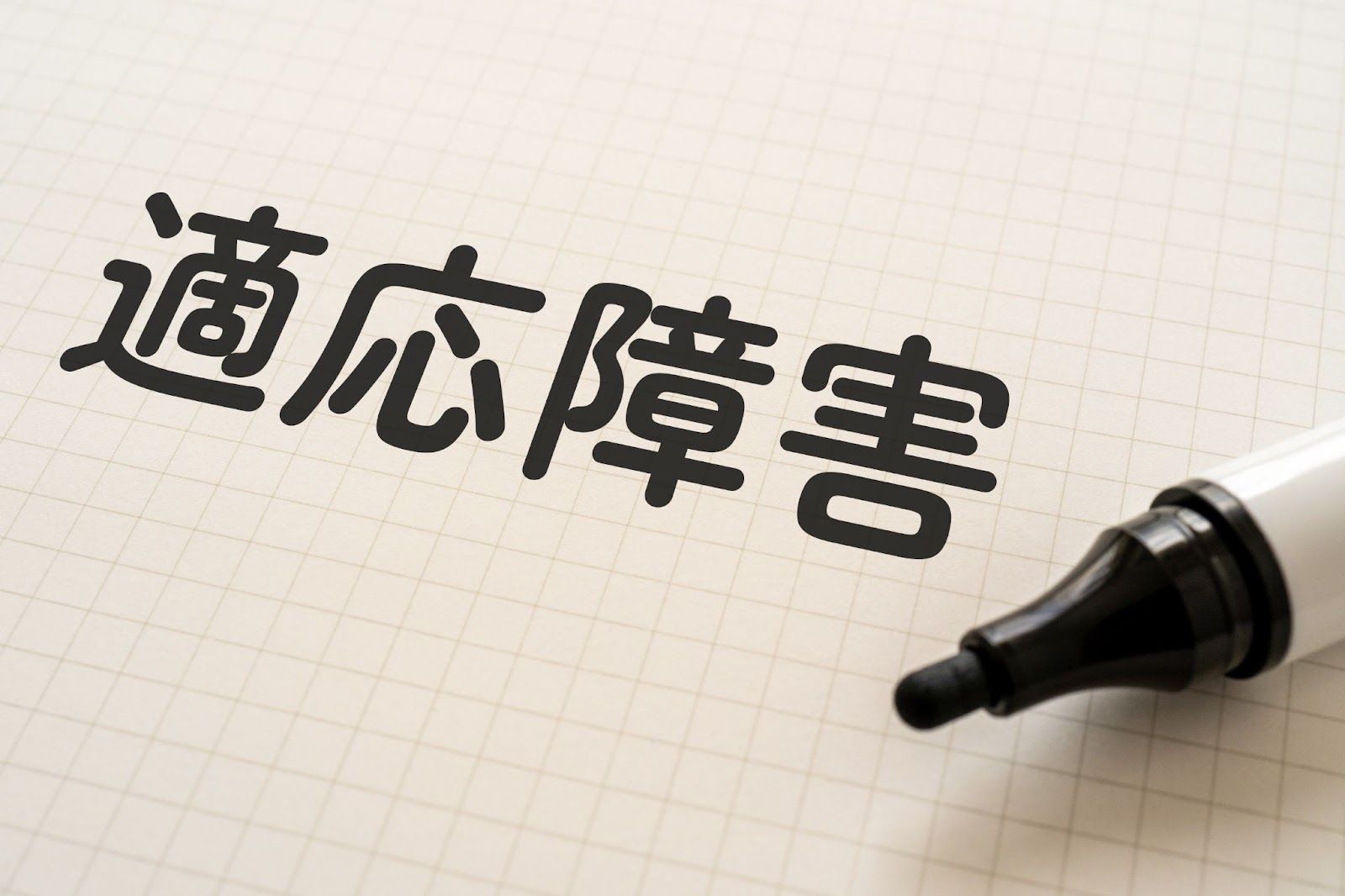
適応障害とは、特定のストレスに心や体が上手く対応できなくなり、日常生活や社会生活に支障が生じる精神疾患の一つです。
ストレスの原因がはっきりしている点が特徴で、例えば職場の人間関係、家庭内トラブル、転勤、進学、失恋などがきっかけとなることがあります。
ストレスを受けてから比較的早い段階、通常は3か月以内に症状が現れます。
適応障害は一時的なものであることが多いものの、放置すると症状が長期化し、うつ病や不安障害などへ発展する可能性もあるため注意が必要です。
ここでは適応障害の主な症状やなりやすい気質・環境について解説します。
適応障害の主な症状
適応障害の症状は『身体的症状』『精神的症状』『行動面の変化』の3つに分類されます。
それぞれの具体的な症状は以下の通りです。
身体的症状 | • 頭痛やめまい |
精神的症状 | • 憂うつな気分 |
行動面の変化 | • 無断欠勤や遅刻 |
これらの症状はストレスのある場面で強く出やすく、逆にストレスから離れると軽くなることもあります。
また本人が自覚していないまま行動や体調に変化が出ているケースもあるため、家族や周囲の人が気づいてあげることが大切です。
適応障害になりやすい気質・環境
適応障害になりやすい人には、いくつかの共通した気質があります。
例えば繊細で感受性が強い人、真面目で几帳面な人、完璧主義な傾向がある人などはストレスを受けやすく、反応も強く出やすい傾向があります。
自己肯定感が低く、自信を持ちにくい人も、ちょっとした変化に過剰に反応してしまうことがあるでしょう。
また環境要因も大きく関係しており、身近に相談できる人がいない、職場でパワハラを受けている、孤立している、家庭内に緊張感があるといった状況に置かれている人は注意が必要です。
こうした環境にいる人はストレスを抱え込みやすいため、適応障害を発症しやすくなります。
▶適応障害になりやすい人の特徴│性格や環境、顔つきなどを解説!予防法&治療法も
適応障害の治療法|クリニックでの治療法

クリニックでの適応障害の治療方法は以下の通りです。
- 休養・環境調整
- 薬物療法
- 精神療法
- TMS治療
ここでは上記4つの治療方法についてそれぞれ解説します。
▶適応障害とは?再発率や兆候・繰り返さないための対策・復職時の注意点を解説
休養・環境調整
適応障害の治療において重要なのが、ストレスの原因から距離を置く『休養』と『環境調整』です。
例えば職場が原因であれば、医師の診断書をもとに休職を検討し、必要に応じて部署異動や転職を行うことも選択肢に入ります。
学校生活や家庭環境が原因であれば、休学や家族との関わり方の見直し、一時的な別居なども効果的です。
重要なのは、ストレス源を明確にし、それに対して適切な対応をとることです。
薬物療法
薬物療法は、適応障害で生じる不安や不眠、抑うつなどの症状に対して行われることがある治療方法です。
主に使用される薬には、以下のような種類があります。
症状 | 薬の種類 | 薬の作用 |
|---|---|---|
不安 | ベンゾジアゼピン系抗不安薬、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)など | 過度な不安を改善する |
不眠 | ベンゾジアゼピン系睡眠薬、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬など | 不眠症状を改善する |
抑うつ | SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)、SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)など | 落ち込んだ気分を改善する |
適応障害の場合、必ず薬物療法が必要というわけでなく、基本的には薬なしで治療できます。
薬に抵抗がある場合は、遠慮なく医師に相談してみましょう。
精神療法
精神療法では、主に認知行動療法や問題解決療法といった方法が用いられます。
それぞれの特徴は以下の通りです。
認知行動療法 | 自分がストレスにどう反応しているのかを客観的に把握し、否定的な考え方を柔軟に変えていく力を養う治療法 |
問題解決療法 | 現在抱えている課題に対して、具体的な対処法を心理士や医師と一緒に考えていく治療方法 |
精神療法を通じて自分自身のストレス耐性を高め、今後似たような状況に直面した際に、過剰に反応しない力を身につけていくのが治療の目標となります。
TMS治療
TMS治療(反復経頭蓋磁気刺激療法)は、薬を使わずに脳の神経活動を整える治療法です。
磁気を用いて脳の特定部位を刺激することで、気分を安定させる効果が期待されます。
主にうつ病に対して行われる治療ですが、適応障害によるうつ症状に対する治療としても用いられています。
1回あたり15〜30分程度の治療を週に数回、数週間〜数か月続けることで、改善を目指します。
薬に抵抗がある方や、薬物療法で十分な効果が得られない場合の選択肢として注目されています。
現在、TMS治療は日本ではうつ病で一定の条件を満たす場合にのみ保険適用となり、適応障害の場合は自由診療となります。
適応障害の対処法|セルフケア方法

適応障害に対する自分でできる対処法として、以下の5つが挙げられます。
- ストレスの原因から距離を置く
- 信頼できる人に相談する
- 自分に合ったストレス解消法を身につける
- 焦らずゆっくり治す意識を持つ
- 薬に頼りすぎないようにする
ここでは上記5つのセルフケア方法についてそれぞれ解説します。
ストレスの原因から距離を置く
適応障害の根本的な原因は、特定のストレスに対する過剰な反応のため、まずはそのストレス源から距離を置くことが大切です。
例えば職場の人間関係が原因であれば、休職や部署異動、在宅勤務への切り替えなどを検討しましょう。
家庭内の問題であれば、一時的に距離をとる、関係性を見直すなどの方法もあります。
物理的に離れるだけでなく、SNSを見ない、連絡を絶つなど精神的に距離を置くのも有効です。
ストレス源から離れて過ごすことで、無意識に感じてしまう精神的負担を軽減できます。
信頼できる人に相談する
精神的につらいときは一人で抱え込まず、誰かに話すだけでも気持ちが軽くなることがあります。
信頼できる家族や友人に気持ちを打ち明けることで、自分の状態を客観的に見つめ直すきっかけにもなります。
身近に相談できる人がいない場合は、精神科や心療内科でのカウンセリングを活用しましょう。
医師や臨床心理士は専門的な視点で悩みを整理し、適切なアドバイスをしてくれます。
自分に合ったストレス解消法を身につける
適応障害を乗り越えるためには、ストレスと上手く付き合うスキルを身につけることが大切です。
例えばウォーキングや軽いストレッチ、ヨガなどの運動は、心を落ち着かせる効果があります。
また音楽を聴く、映画を観る、読書を楽しむといった趣味も、気分転換に役立ちます。
無理に「何かしなければ」と思わず、「やってみたい」と思えることを少しずつ試すことが大切です。
自分に合ったストレス解消法を見つけてみてください。
焦らずゆっくり治す意識を持つ
適応障害の回復には、時間がかかることもあります。
症状の波に一喜一憂せず、「今日は少し気分が良かったな」といった小さな変化を大切にしましょう。
「早く元に戻らなければ」と焦ると、かえって心に負担をかけてしまいます。
たとえ仕事や学校に復帰したとしても、最初は思うように動けないことがあるのが普通です。
完璧を目指さず、「今できることを少しずつ」という気持ちで、自分を責めずに過ごすことが大切です。
生活リズムを整え、体調と相談しながら無理のないペースで回復を目指しましょう。
薬に頼りすぎないようにする
適応障害の治療で処方されることのある薬には、不安や不眠などの症状を一時的に和らげる効果があります。
しかし薬だけに依存していると根本的な問題解決にはつながりません。
薬はあくまで補助的な手段であるため、並行して環境調整や認知行動療法などに取り組むことが大切です。
また、服薬中は自己判断で中断したり量を変えたりせず、必ず医師の指示に従いましょう。
適応障害の治療に関するよくある質問

適応障害の治療に関するよくある質問をまとめました。
- ストレスの原因から離れても治らない場合は?
- 適応障害は再発リスクがある?
- 適応障害は労災認定される?
ここでは上記3つの質問についてそれぞれ解説します。
ストレスの原因から離れても治らない場合は?
適応障害は特定のストレス源が原因で心身に不調が生じるため、ストレスから距離を取ることで多くの場合は改善します。
しかしストレス要因を取り除いても「気分の落ち込みが続く」「食欲がわかない」「楽しみを感じられない」「夜に眠れない」などの症状が2週間以上続く場合は、うつ病などの他の精神疾患に進行している可能性があります。
このような場合には自己判断せず、精神科や心療内科を受診し、専門家の診断を受けることが大切です。
適応障害とうつ病には以下のような違いがあります。
適応障害 | うつ病 | |
|---|---|---|
発症のきっかけ | 明確なストレスによるもの | 必ずしも明確な原因があるとは限らない |
発症までの期間 | ストレスにさらされてから3か月以内に発症する | 慢性的なストレスにさらされた後に発症する |
症状が現れる場面 | ストレス場面でのみ症状が出やすい(波がある) | 日常のあらゆる場面で症状が持続する |
主な症状 | 気分の落ち込み、不安感、イライラ、頭痛、腹痛、食欲不振、不眠など | 憂うつな気分、イライラ、興味の喪失、意欲の低下、集中力の低下、食欲不振、不眠など |
主な治療方法 | 休養・環境調整(ストレスの原因から離れる)、精神療法が中心。その他、薬物療法やTMS治療など | 薬物療法が中心、その他カウンセリングや精神療法など |
適応障害とうつ病は症状が似ていても治療方針が異なるため、正確な診断を受けることが今後の回復過程に影響します。
症状に違和感を覚えたら、遠慮せず医療機関を受診しましょう。
適応障害は再発リスクがある?
適応障害は一度回復しても、再び強いストレスに直面した際に再発する可能性があります。
特に過去と似た状況や人間関係、精神的負荷の大きな出来事が起きたときには注意が必要です。
再発を防ぐためには、まず自分がどんな状況に弱いのかを把握し、ストレスの予兆に気づけるようになることが大切です。
無理をしない・頑張りすぎないという意識を持ち、日常生活の中で定期的にリラックスする時間を持つことも予防に役立ちます。
また再発リスクの高い方は、リワークプログラムや心理教育、グループカウンセリングなどを受けて、自分自身の考え方やストレス対処法を見直すのも効果的です。
ストレスと上手に付き合っていく習慣を身につけることで、再発リスクを抑えられます。
適応障害は労災認定される?
適応障害は、発症の原因が業務による強い心理的負担と認められる場合には、労災として認定される可能性があります。
具体的には以下の要件を満たすと労災認定となります。
- 発症前の6か月以内に業務による著しい心理的負担があったこと
- その精神障害が仕事以外の原因では説明できないこと
例えば長時間労働やパワーハラスメントなどが該当することがあります。
労災申請には、診断書の提出や業務内容の詳細な説明が必要です。
適応障害で労災申請を考える場合は、まず医師や職場の産業医に相談し、必要があれば労働基準監督署や専門家のサポートを受けながら手続きを進めましょう。
申請が認められると、療養補償給付や休業補償給付などを受けられる可能性があります。
適応障害の治療ではストレスの原因から離れることが何よりも重要
適応障害は、強いストレスがきっかけとなって発症する精神疾患です。
早期に原因を特定し、休養や環境調整を行うことで改善が見込めます。
また必要に応じて薬物療法や精神療法を取り入れることで、より症状が改善しやすくなるでしょう。
再発を防ぐためには、日々のセルフケアやストレスへの対処法を身につけることが大切です。
かもみーる心のクリニック仙台院では、適応障害の診断に対応しています。
休職・復職のための診断書作成も可能なため、強いストレスや精神的・身体的症状にお悩みの方は、ぜひ当院までご相談ください。
