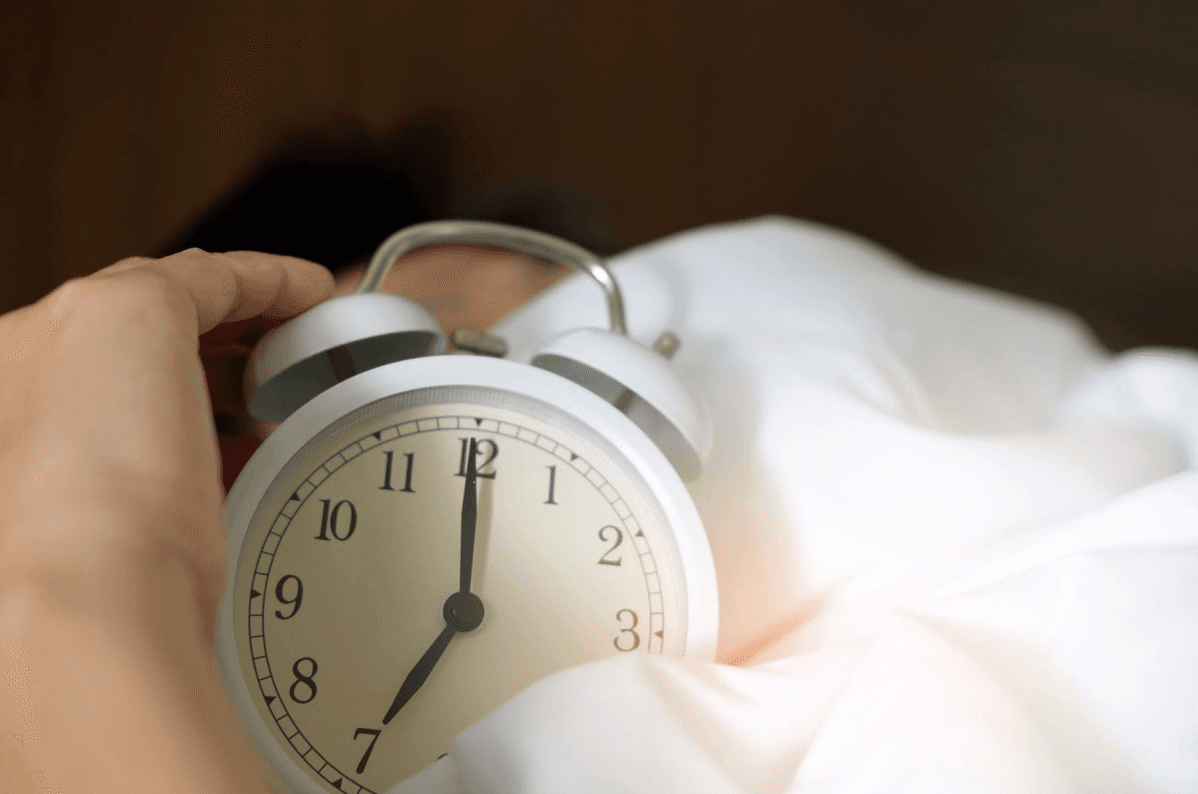「朝、目覚ましが鳴ってもなかなか起きられない」という経験をしたことのある人は少なくないと思いますが、それが毎日のように続くと生活や仕事に大きな影響を及ぼします。
単なる夜更かしや疲労のみでなく、睡眠障害やうつ病、自律神経の乱れ、ホルモンバランスの異常など、体や心の不調が原因となっていることも少なくありません。
特に「十分な睡眠を取っているのに日中強い眠気がある」「朝の倦怠感やめまいが続く」「気分の落ち込みや無気力感がある」といった症状は、早めの対策や受診が必要なサインです。
この記事では、朝起きられない原因とその対処法について詳しく解説します。
考えられる病気や受診の目安などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
朝起きられないのは甘え?主な原因

朝起きられないのは甘えではありません。
朝起きられない主な原因として、以下が挙げられます。
- ホルモンバランスの乱れ
- 睡眠不足・睡眠の質の低下
- 体内時計の乱れ
- 自律神経の乱れ
- 起立性調節障害
- 低血圧
- その他の病気
ここでは上記7つの原因についてそれぞれ解説します。
ホルモンバランスの乱れ
人間の睡眠と覚醒のリズムは、ホルモンの分泌によって大きく左右されます。
特に重要なのが『メラトニン』と『セロトニン』です。
メラトニンは体内時計を調節するホルモンで、セロトニンは感情や気分を安定させる効果がある神経伝達物質です。
この二つは連動しており、日中に十分なセロトニンが作られないと、夜のメラトニン分泌が乱れ、眠りの質が低下します。
ホルモンバランスが崩れる原因には、不規則な生活やストレス、うつ病などがあります。
特に朝日を浴びない生活や夜型の生活を続けると、体内時計のリセットがうまくいかず、朝なかなか起きられないという状態に陥りやすいです。
睡眠不足・睡眠の質の低下
必要な睡眠時間は人によって異なりますが、成人ではおおむね7〜8時間が目安です。
これを下回る状態が続くと脳や体は十分に休めず、日中の集中力低下や判断力の鈍化、気分の落ち込みなどが現れます。
これが蓄積された状態を『睡眠負債』と呼び、朝の目覚めが困難になります。
また、時間は確保できても睡眠の質が低下している場合も問題です。
質を下げる要因として、寝る直前のスマホやパソコンの使用、寝室の照明や騒音、カフェインやアルコールの摂取、ストレスなどが挙げられます。
浅い眠りや夜間の中途覚醒が続くと、起床時に強いだるさを感じやすくなります。
体内時計の乱れ
人間の体は約24時間周期の『体内時計』によって、睡眠と覚醒のリズムを保っています。
この体内時計は朝日を浴びることでリセットされますが、夜型生活や不規則なスケジュール、夜遅くまでのスマホ使用などで簡単に乱れます。
その結果、夜になっても眠れず、朝起きられない状態が慢性化してしまうのです。
その代表的な例が『睡眠相後退症候群』で、これは通常より数時間遅れて眠くなるため、社会生活に必要な時間に起きるのが難しくなる状態です。
この状態は本人の意思や努力では改善しにくく、休日に遅くまで眠ってしまう傾向が強まります。
思春期に多い睡眠障害ですが、大人でも発症する場合があります。
自律神経の乱れ
自律神経は血圧や心拍、体温などを調整する重要なシステムです。
健康な状態では、朝になると交感神経が優位になり活動モードへ切り替わります。
しかし不規則な生活やストレス、過労などで自律神経が乱れると、この切り替えがうまくいかなくなります。
その結果、朝起きたときにめまいや立ちくらみ、だるさ、吐き気などが生じてしまうことがあるのです。
これによって、朝の目覚めが困難になります。
起立性調節障害
起立性調節障害は、自律神経の働きがうまく機能せず、立ち上がったときに血圧が急低下したり心拍数が急上昇したりする状態です。
これによりめまいや立ちくらみ、倦怠感、頭痛、吐き気などが生じます。
症状は特に朝に強く出やすく、布団から出ること自体が困難になることも少なくありません。
思春期に多く見られる症状ですが、大人にも発症例があります。
午前中は活動できず、午後から徐々に動けるようになる日内変動が見られる場合は、起立性調節障害の可能性が高いです。
低血圧
低血圧は慢性的に血圧が低い状態のことで、特に起床時や立ち上がり時に症状が現れやすくなります。
血圧が低いと体を起こしたときに下半身に血液が溜まりやすく、脳への血流が一時的に不足します。
その結果、立ちくらみやめまい、頭のぼんやり感、強い倦怠感などが起こり、朝の覚醒が難しくなるのです。
低血圧には特定の原因がない『本態性低血圧』と、病気や薬の副作用で起こる『二次性低血圧』があり、後者は特に若い女性に多い傾向があります。
症状が続く場合は、他の疾患が隠れていないか医療機関での検査が必要です。
その他の病気
朝起きられない原因として、睡眠障害や精神疾患、身体疾患などが隠れていることもあります。
具体的には睡眠時無呼吸症候群や睡眠障害、甲状腺機能低下症、うつ病、自律神経失調症などです。
これらは本人の努力だけでは改善できないため、症状が長引く場合は医療機関での検査が必要不可欠です。
なるべく早めに原因を特定し、適切な治療を行うことで、朝の目覚めや生活の質の改善が期待できます。
朝起きられないときに考えられる病気

朝起きられないときに考えられる病気として、以下が挙げられます。
- 睡眠時無呼吸症候群
- 睡眠障害
- 甲状腺機能低下症
- うつ病
- 自律神経失調症
ここでは上記5つの病気についてそれぞれ解説します。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に10秒以上呼吸が止まる『無呼吸』を繰り返す病気で、7時間の睡眠中に30回以上、または1時間あたり5回以上の無呼吸がみられる場合に診断されます。
原因の多くは、上気道が周囲の組織によって圧迫され、空気の通り道が塞がることです。
大きないびきや呼吸が途切れる際の苦しそうなあえぎ声が大きな特徴で、これらは本人が気づかないことが多く、家族の指摘で発覚する場合もあります。
睡眠が断続的に中断されるため、熟睡感が得られず、朝の強い倦怠感や頭痛、日中の過剰な眠気、集中力低下を引き起こします。
放置すると高血圧や心筋梗塞、脳卒中などのリスクが高まるため、疑わしい場合はなるべく早めに検査を受け、必要に応じてCPAP療法や生活習慣改善などの治療を行うことが大切です。
睡眠障害
睡眠障害は、睡眠に関連するさまざまな問題を総称したもので、不眠症、過眠症、睡眠時随伴症などがあります。
不眠症 | 寝つきが悪い(入眠困難)、途中で目が覚める(中途覚醒)、早朝に起きてしまう(早朝覚醒)などが続き、日中の活動に支障をきたす。 |
過眠症 | 夜間の睡眠が十分でも日中に強い眠気が現れ、覚醒を保てない状態。ナルコレプシーや概日リズムの乱れが原因になることもある。 |
睡眠時随伴症 | 夢遊病やレム睡眠行動障害などがあり、夜間に頻繁に覚醒したり深い眠りが妨げられたりする。 |
これらはいずれも朝の倦怠感や集中力低下、気分の落ち込みを引き起こし、慢性化すると生活の質を大きく下げます。
症状が続く場合は、睡眠外来での診断・治療を検討しましょう。
▶うつ病でずっと眠い・強い眠気の原因は?過眠との関係や対処法も解説
甲状腺機能低下症
甲状腺機能低下症は、代謝を調節する甲状腺ホルモンの分泌が不足することで、全身の代謝が低下し、朝の強い倦怠感や意欲低下、無気力感などが生じる病気です。
主な症状としては、体重増加やむくみ、皮膚の乾燥、便秘などがあります。
睡眠時間を十分に取っても疲労が取れず、目覚めが悪い状態が続くのが特徴です。
逆に甲状腺ホルモンが過剰に分泌される甲状腺機能亢進症では、代謝が過剰に活発になり、寝つきが悪くなったり昼夜逆転になったりして朝の起床が困難になることもあります。
原因を放置すると症状が進行し、生活の質が大きく低下するため、早期の診断と治療が重要です。
うつ病
うつ病は、気分の落ち込みや興味・喜びの喪失が2週間以上続き、日常生活に支障をきたす精神疾患です。
脳内の神経伝達物質(セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンなど)のバランス異常や強いストレス、遺伝的要因、ホルモンの乱れなどが発症に関与します。
睡眠障害を伴うことが多く、不眠だけでなく過眠として現れることもあります。
うつ病特有の症状として『日内変動』があり、朝に症状が最も強く、午後から徐々に改善するケースが多いです。
そのため、朝の起床が極めて困難になり、布団から出られない状態が続くこともあります。
適応障害など類似した疾患との鑑別が必要で、治療には休養や心理療法、薬物療法が行われます。
自律神経失調症
自律神経失調症は、交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかず、心身の機能が正常に働かない状態です。
本来、起床時には交感神経が優位になり、体温上昇や心拍数増加、血圧上昇などによって活動モードに切り替わります。
しかし、この切り替えができないと、朝起きても頭がぼんやりし、強い倦怠感やめまい、立ちくらみなどが生じます。
ストレスや過労、生活リズムの乱れ、ホルモンバランスの変化などが主な原因です。
特に長時間の緊張状態や夜型生活が続くと、自律神経のバランスが崩れやすくなります。
慢性化すると生活に大きな支障をきたすため、なるべく早めに医療機関の受診を検討しましょう。
朝起きられないときの対処法

朝起きられないときの対処法として、以下が挙げられます。
- 睡眠環境を見直す
- 寝る前の生活習慣を見直す
- 規則正しい生活を心がける
- 朝起きたら太陽の光を浴びる
- 日中は適度に運動する
- ストレスをため込まない
ここでは上記6つの対処法についてそれぞれ解説します。
睡眠環境を見直す
朝起きられないときは、睡眠環境を見直すことが大切です。
理想的な室温は18〜22℃、湿度は50〜60%とされているため、季節に応じてエアコンや加湿器・除湿機で調整しましょう。
光は眠りを妨げるため、遮光カーテンで外光を遮り、真っ暗に近い状態で寝るのが望ましいです。
また寝室は静かな環境が望ましいため、外の騒音が気になる場合は耳栓やホワイトノイズの利用も有効です。
さらに寝具も重要で、枕やマットレスが体に合っていないと寝返りが減り、体の緊張が抜けにくくなります。
自分の体に合ったマットレスやまくらを選び、体の負担を減らすことで、リラックスして眠りやすくなるでしょう。
寝る前の生活習慣を見直す
就寝前の過ごし方は、眠りの質に直結します。
寝る直前のスマートフォンやパソコンの使用はブルーライトの影響で脳を覚醒させ、入眠を妨げるため、就寝1〜2時間前からは使用を控えるのが理想です。
また、カフェインやアルコールの摂取も眠りを浅くするため、なるべく控えましょう。
寝る前はぬるめのお風呂で入浴して深部体温を上げ、その後下がる過程で自然な眠気を誘うのがおすすめです。
軽いストレッチやアロマの香り、読書や静かな音楽もリラックス効果を高めます。
これらの習慣を寝る前のルーティンとすることで、眠りにつきやすくなるでしょう。
規則正しい生活を心がける
体内時計を整えるには、毎日同じ時間に起きることが重要です。
休日も平日と大きく変えず、起床時間の差は1〜2時間以内に留めましょう。
朝食をとることで体内時計のリセットが促され、代謝と覚醒がスムーズになります。
また、日中は自然光を浴びたり適度な運動を行ったりして、活動量を確保することが大切です。
生活リズムの乱れは睡眠の質の低下と朝のだるさを招くため、食事・睡眠・運動の時間をなるべく固定し、心身が覚醒と休息のサイクルを自然に繰り返せるようにしましょう。
朝起きたら太陽の光を浴びる
体内時計をリセットし覚醒を促すために効果的な方法として、朝日を浴びることが挙げられます。
起床後すぐにカーテンを開け、太陽の光を浴びましょう。
可能であれば15分ほど屋外を散歩すると、セロトニンが分泌されて気分も前向きになります。
毎日のルーティンとして取り入れることで、起床直後のぼんやり感を減らし、スムーズに活動を始められるようになります。
日中は適度に運動する
日中の適度な運動は、睡眠の質の向上と朝の目覚め改善に有効です。
有酸素運動や軽い筋トレは、体温や血流を上げて代謝を活発にし、夜に自然な眠気を誘います。
特に朝や昼の運動は交感神経を活性化させ、日中の活動量を増やす効果があります。
ただし、就寝直前の激しい運動は脳と体を覚醒させて眠りを妨げる可能性があるため、避けましょう。
1日20〜30分程度のウォーキングやストレッチでも効果が期待できるため、無理のない範囲で運動する習慣をつけることをおすすめします。
ストレスをため込まない
慢性的なストレスは自律神経を乱し、眠りの質を下げて朝の覚醒を妨げるため、日常的にストレス解消の時間を確保して心身をリラックスさせることが大切です。
深呼吸や瞑想、ヨガなどのリラクゼーション法は、副交感神経を優位にして緊張を和らげます。
また、趣味や好きなことに没頭する時間を持つのも効果的です。
悩みや不安は紙に書き出す、信頼できる人に話すなどして抱え込まないようにしましょう。
完璧を求めすぎず「ほどほど」を意識することも、ストレス軽減につながります。
朝起きられないときの受診の目安

朝起きられない状態が一時的であれば生活習慣の見直しで改善する場合もありますが、症状が2週間以上続く場合や、日常生活に大きな支障が出ている場合は医療機関の受診を検討すべきです。
例えば、十分な睡眠をとっても日中に強い眠気があり仕事や勉強に集中できない、遅刻や欠勤を繰り返す、強い倦怠感や気分の落ち込みが慢性的に続くといった症状は要注意です。
原因は睡眠時無呼吸症候群、うつ病、自律神経失調症、起立性調節障害、甲状腺機能低下症など多岐にわたります。
そのため、まずはかかりつけ医や内科で相談し、必要に応じて睡眠外来・精神科・耳鼻咽喉科など専門医を紹介してもらうと安心です。
受診時に症状の経過や生活習慣を具体的に伝えることで、診断や治療がスムーズになります。
ただの怠けと自己判断せず必要に応じて受診も検討しましょう
朝起きられない背景には、生活習慣や環境の乱れだけでなく、睡眠障害や精神疾患、身体疾患など多くの要因が潜んでいます。
自分では「疲れているだけ」と思っていても、症状が長引く場合や日常生活に支障が出ている場合は専門医の診断が必要です。
まずは睡眠環境や生活習慣を整え、それでも改善しないときは早めに医療機関に相談しましょう。
『かもみーる』では、医師監修のオンラインカウンセリングサービスを提供しています。
「心療内科の受診を迷っている」「職場での人間関係に疲弊している」など、さまざまなお悩みに対応しているため、気軽に当院までご相談ください。
▶ カウンセラー(医師・心理士)一覧 はこちら
▶ 新規会員登録 はこちら