日々の生活のなかでストレスを感じ、イライラしてしまうことは誰にでもあるものです。
しかし、「些細なことで怒りっぽくなる」「イライラが止まらない」といった状態が続く場合、うつ病など心の病気が隠れていることもあります。
うつ病といえば、「気分が落ち込む」「やる気が出ない」といった症状を思い浮かべる方が多いかもしれません。
そのため、イライラがうつ病のサインのひとつとは意外に感じる方も少なくないでしょう。
実際には、うつ病にはさまざまな症状があり、感情のコントロールが難しくなるケースも珍しくありません。
この記事では、うつ病とイライラの関係について解説し、気持ちを落ち着けるための対処法も紹介します。
原因のわからないイライラに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
そもそも『うつ病』とはどんな病気?―気分の落ち込みだけじゃない心の不調

うつ病とは、気分が落ち込み、やる気が出ない状態が長く続く心の病気です。
人によっては、身体のだるさや不眠、食欲の変化など、体調にも不調があらわれることがあります。
一時的な気分の落ち込みや疲れによる無気力は、誰にでも起こり得るものですが、うつ病の場合はこうした症状が2週間以上続き、日常生活に支障をきたすのが特徴です。
原因のひとつとされているのが、脳内の神経伝達物質(セロトニンやノルアドレナリン)の働きの低下です。
この影響で気分を安定させる機能がうまく働かなくなり、憂うつな状態が続いてしまうと考えられています。
また、うつ病の症状は気分の落ち込みだけではありません。
人によっては怒りっぽくなったり、焦りを強く感じたりすることもあります。こうしたイライラや感情の変化も、うつ病の症状のひとつであり、性格の問題ではない場合もあります。
「怠けているだけ」「気の持ちよう」などと誤解されがちですが、うつ病は意思や根性でどうにかなるものではありません。
適切な治療とサポートを受けることで、回復を目指すことができます。
なお、うつ病は日本人の約15人に1人が一生のうちにかかるといわれており、決して特別な人だけがなる病気ではありません。
(※参照:厚生労働省『こころの病気について知る うつ病』)
うつ病について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
うつ病とイライラの関係

うつ病というと、「気分の落ち込み」や「やる気の低下」などが主な症状として知られています。
しかし実際には、「イライラしやすくなる」「怒りっぽくなる」といった感情の変化が現れることも少なくありません。
このようなイライラは、単なる性格の問題ではなく、うつ病にともなう脳の働きの変化や環境要因が関係していると考えられています。
脳内の神経伝達物質の乱れ
うつ病では、脳内の神経伝達物質であるセロトニンやノルアドレナリン、ドーパミンの分泌が低下することで、感情のコントロールが難しくなるといわれています。
特にセロトニンの不足は、怒りっぽさやイライラといった症状と深く関係していると考えられています。
ストレスの蓄積
仕事や人間関係など、強いストレスを長期間抱えていることが、うつ病のきっかけになることもあります。
日々のストレスが蓄積すると心に余裕がなくなり、小さなことでも怒りや苛立ちを感じやすくなってしまいます。
このように、ストレスによる心身への負荷が、イライラの背景にある場合も多いのです。
睡眠不足や疲労
うつ病の症状として、眠れない、眠りが浅いといった睡眠障害がしばしばみられます。
十分な休息が取れない状態が続くと、心身の疲労が回復せず、感情のコントロールも難しくなっていきます。
その結果、普段なら気にならないようなことにも過敏に反応し、イライラを感じやすくなってしまうのです。
自己否定的な思考
うつ病になると、「何をやってもうまくいかない」「自分はダメだ」といった自己否定的な考えが強くなりがちです。
このような考えに支配されていると、周囲の些細な言動でも自分を責められているように感じてしまうことがあります。
結果的に、その不安や不満がイライラという形で表れるケースもあるのです。
うつ病でイライラしやすい自分を責めないで|性格の問題ではありません

うつ病によるイライラは、性格のせいではなく、脳内の働きや心身の状態の変化によって引き起こされるものです。
「こんなにイライラしてしまうなんて、自分は人間として未熟なのでは……」と落ち込む必要はありません。
うつ病になると、感情をうまくコントロールする脳の働きが低下したり、些細な刺激にも過敏に反応しやすくなったりします。
これは誰にでも起こり得ることで、意志や努力だけで乗り越えられるものではありません。
「イライラしてしまう自分はダメだ」と責めるのではなく、「これは心のSOSなんだ」と受け止めて、まずは自分をいたわることが大切です。
イライラが止まらないときの対処法

うつ病によるイライラは自分の意志でコントロールしにくいものの、日常生活の中で少し工夫をするだけでも気持ちを落ち着ける助けになります。
以下に紹介するのは、うつ病でイライラが止まらないときに役立つ対処法です。
深呼吸をする
イライラを感じたときは、まず深呼吸をしてみましょう。
ゆっくりと息を吸って吐くだけでも、自律神経が整い、自然と気持ちが落ち着いてきます。
「またイライラしてきたな」と感じたタイミングで、意識的に深呼吸を取り入れてみてください。
イライラの原因から距離をとる
特定の状況や人がイライラの原因になっている場合は、無理に我慢せず、できるだけその場から離れることが大切です。
「この人といるとどうしてもイライラする」「この作業がどうしてもストレスになる」など原因がはっきりしている場合は、物理的・心理的な距離をとることも対処のひとつです。
規則正しい生活を意識する
うつ病になると、夜型の生活になったり、気分によって食事のタイミングがバラバラになることがあります。
こうした生活の乱れは、自律神経を乱し、イライラしやすくなる要因になります。
「朝起きられない」「食欲がわかない」といった日があっても、なるべく同じ時間に起き、食事をとるよう意識してみましょう。
睡眠をしっかりとる
睡眠不足は、脳内の神経伝達物質のバランスを崩し、イライラや不安を強める要因になります。
うつ病でイライラが止まらないと感じるときは、まず睡眠を確保することを心がけましょう。
それでも「眠れない」「寝ても疲れが取れない」という日が続く場合は、早めに医療機関に相談することをおすすめします。
人に話す・紙に書き出す
悩みを一人で抱え込むと、ますますイライラしやすくなってしまうものです。
そんなときは信頼できる人に話すだけでも、気持ちが軽くなることがあります。
「うまく言葉にできない」「誰にも言えない」というときは、紙に思いのまま書き出してみるのもおすすめです。
頭の中を整理でき、感情の整理にもつながります。
我慢せず、断る勇気をもつ
うつ病になりやすい人は、真面目で責任感が強く、人からの頼みを断れない傾向があります。
しかし、無理を重ねてしまうと、心の負担が大きくなり、症状が悪化することも少なくありません。
「今の自分には無理」と思ったときは、勇気をもって断ることも大切です。
自分の心と体を守ることを最優先にしましょう。
うつ病の初期症状とは?|イライラの裏に隠れたサインに注意

ここまで読んできた方の中には、「イライラが止まらないのは事実だけど、本当にうつ病なのだろうか?」と疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。
うつ病には、イライラ以外にもさまざまなサインがあります。
イライラだけを見て判断するのは難しいため、ほかの症状にも目を向けてみましょう。
以下は、うつ病の初期にみられることが多い代表的な症状です。
- 朝起きられない
- 夜寝つきが悪く、眠れない
- 十分に寝ても疲れがとれない
- 食欲がない、または過食してしまう
- 焦りやイライラが続く
- 好きだったことを楽しめなくなる
- 集中力や思考力が落ち、仕事に支障が出る
- 「死にたい」「消えてしまいたい」と感じる
- 気分が沈み、憂うつになることが多い
これらの症状はあくまで目安ではありますが、該当する項目が複数ある場合は、うつ病の可能性も否定できません。
「気のせいかも」「まだ大丈夫」と思わず、早めに医療機関で相談してみることをおすすめします。
うつ病かも?と思ったら|受診のすすめと治療の流れ
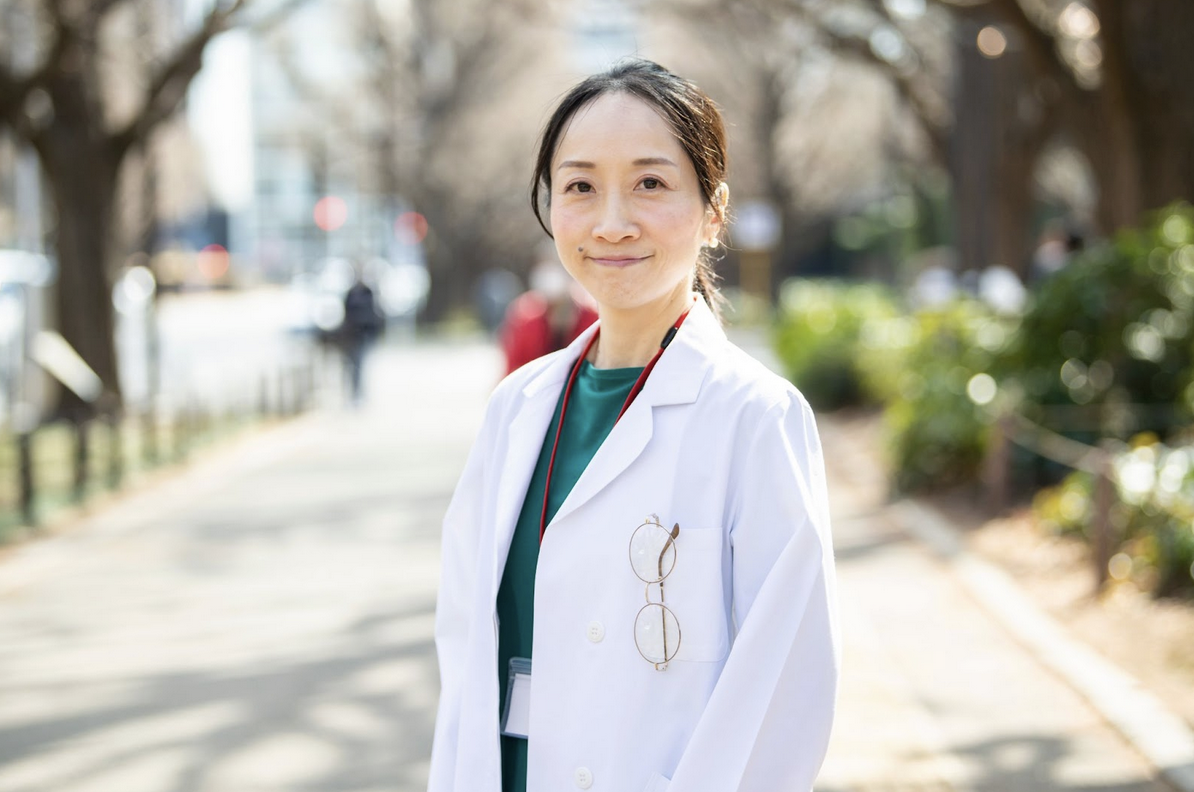
イライラが止まらないなどの症状が長く続く場合、うつ病の可能性も考えられます。
「ただの疲れかも」と思っていても、放っておくと悪化することもあるため、できるだけ早めに医療機関を受診することが大切です。
「うつ病と診断されたらどうしよう……」と不安に感じる方もいるかもしれませんが、うつ病は治療によって改善が見込める病気です。
一人で抱え込まず、まずは専門家に相談してみましょう。
何科を受診すればいいの?
うつ病が疑われる場合は、『心療内科』や『精神科』の受診が一般的です。
心療内科は、ストレスが原因の体調不良や気分の落ち込みなど、心と体の両面からサポートしてくれる診療機関です。
うつ病の初期段階で「気軽に相談してみたい」という場合にも適しています。
一方で、より専門的な治療や診断が必要なケースでは、精神科が選ばれることもあります。
どこを受診するか迷うときや、「いきなり専門科に行くのは抵抗がある」という場合は、まずはかかりつけ医(内科など)に相談するのもひとつの方法です。
必要に応じて、専門機関を紹介してもらえます。
診察から治療の流れ
うつ病が疑われて心療内科や精神科を受診した場合、一般的には以下の流れで診察、治療が進められます。
1.問診・診察
初診時には、受付で問診票に症状や生活状況などを記入します。
その内容をもとに、医師がより詳しく質問し、現在の状態や困りごとを丁寧に確認していきます。
2.検査
必要に応じて、うつ病以外の疾患が隠れていないかを調べるための検査が行われます。
血液検査や尿検査、血圧測定のほか、医療機関によっては心理検査や光トポグラフィー検査、画像検査(CT・MRI)などが行われることもあります。
3.診断の確定と治療方針の決定
問診や検査の結果をもとに、医師が診断を行います。
うつ病と診断された場合は、症状の程度やライフスタイルに合わせて、以下のような治療が組み合わされます:
- 薬物療法(抗うつ薬・抗不安薬など)
- 精神療法(カウンセリングや認知行動療法など)
- 生活改善のアドバイス(睡眠や食事、ストレス管理など)
治療期間は個人差がありますが、早期に治療を始めた場合は数ヶ月〜半年ほどで回復するケースもあります。
焦らず、自分のペースで回復を目指すことが大切です。
再発を防ぐためには、治療を自己判断でやめず、医師と相談しながら少しずつ日常生活を整えていくことがポイントです。
うつ病が疑われる場合の病院の選び方は以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
▶うつ病かも……何科を受診すればいいの?初めての病院選びと治療の流れをわかりやすく解説
早めの受診が回復への近道
うつ病は「気の持ちよう」や「性格の問題」ではなく、脳や神経の働きに関係する病気です。
我慢を続けてしまうと、心身の負担が増して症状が悪化する可能性もあります。
「イライラが続く」「今まで楽しめていたことが楽しめない」など、少しでも不調を感じるなら、早めに専門家に相談してみましょう。
受診することで、自分の状態を正しく理解し、必要なサポートを受ける第一歩になります。
うつ病のイライラは専門機関に相談を
気分が沈んだり、突然イライラしたりするなど、うつ病は感情のコントロールが難しくなる病気です。
こうした自分の変化に戸惑い、「どうしてこんなことで怒ってしまうのだろう」と自分を責めてしまう方も少なくありません。
しかし、自分を責めることでさらに症状が悪化したり、周囲との関係がうまくいかなくなったりすることもあります。
大切なのは、一人で抱え込まず、専門家の力を借りることです。
とはいえ、「本当にうつ病なのか分からない」「病院に行くのはハードルが高い」と感じる方もいるでしょう。
そんなときは、医師監修のオンラインカウンセリング『かもみーる』の利用を検討してみてください。
自宅にいながら医師や心理士にオンラインで相談ができるため、初めての方でも安心して利用できます。
専門家による丁寧なヒアリングとアドバイスを通じて、心の整理がしやすくなり、必要に応じて医療機関への橋渡しも可能です。
気分の落ち込みやイライラが続くなら、あなたの今の気持ちを、誰かに話すことから始めてみませんか?
『かもみーる』が、あなたの心に寄り添う第一歩になります。
▶カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶新規会員登録はこちら
