「通勤電車が怖い」「突然の発作が心配で外に出るのがつらい」など、パニック障害を抱えながら働くことへの不安を感じている方は少なくありません。
パニック障害は珍しい病気ではなく、適切な理解とサポートがあれば、働きながら回復を目指すことも可能です。
この記事では、パニック障害の基本的な症状から、仕事への影響、向いている仕事の特徴を詳しく解説します。
また、「会社に伝えるべきなのか」「休職や退職はどうする?」という悩みにも具体的なアドバイスを紹介します。
パニック障害を抱えながら働きたいと思う方は、自分に合った働き方を見つける参考にしてください。
パニック障害とは?

パニック障害は、特別な病気や身体的異常がないにもかかわらず、突然、動悸・息切れ・めまい・発汗などの強い身体症状を伴うパニック発作を繰り返す精神疾患です。
発作は突然起こり、本人にとっては死を予感させるほどに強烈で非常に強い苦痛を伴います。
症状そのものは、数分でピークを迎え、数十分で自然におさまるのが一般的です。
しかし、発作を経験したことで「また発作が起こったらどうしよう」という強い不安(予期不安)が生まれ、日常生活や行動が大きく制限される場合があります。
発症年齢は20~30代が多く、女性にやや多い傾向があります。
パニック障害の主な症状と発作の特徴
パニック障害の症状は、パニック発作・予期不安・広場恐怖の3つに大きく分けられます。
症状名 | 概要 | 具体的な特徴・症状 |
パニック発作 | 予兆なく突然現れる強い身体症状と恐怖感 | ・動悸・息苦しさ・吐き気・発汗・震え・息苦しさなどが数分~数十分続く ・検査では異常が見つからないことが多い |
予期不安 | 発作が起こるかもと日常的に強い不安を抱く状態 | ・発作がない時にも不安が続く ・行動範囲が狭まり、外出や人との接触を避けるようになる |
広場恐怖 | 発作が起こった場所・逃げづらい環境に対して不安を感じる状態 | ・電車、エレベーター、会議中、高速道路などを避けるようになる ・外出や通勤が困難になりやすい |
パニック障害の症状や原因については、こちらの記事も参考にしてください。
▶パニック障害とは?主な症状や原因、診断方法・治療法などを紹介
▶パニック障害の原因は?ストレスとの関係や発症・発作のきっかけついて解説
パニック障害の仕事への影響
パニック障害は、仕事にもさまざまな形で影響を及ぼします。
大きな課題は通勤の困難さです。
パニック障害を発症すると、電車やバス、エレベーターなどの「逃げづらい空間」に不安を感じやすく、通勤自体が大きなストレス要因となります。
体調に問題がなくても、通勤ができず出社できない状態に陥ることもあります。
また、業務内容によるストレスも影響を与える要因です。
会議での発言、プレゼンテーション、電話応対といった人前での対応や突発的な対応が求められる場面では、緊張が高まり発作の引き金となることがあります。
さらに、長時間労働や夜勤などで心身の疲労が蓄積されると、発作の頻度や不安感が増すこともあるでしょう。
その結果、「自分はこの業務には向いていないのでは」と自信を失い、仕事の範囲を制限してしまう傾向もみられます。
発作や不安を回避しようとするあまり、できる仕事が限られてしまい、キャリアへの影響が出ることもあるのです。
パニック障害を会社に言うべき?

パニック障害があることを職場に伝えるべきかどうか悩んでいる方もいるかもしれません。
この記事では、パニック障害を会社に伝えるメリットと注意点、伝えない場合に考えられるリスクや判断の基準について解説します。
会社に伝えるメリット
パニック障害を抱えながら働いている方にとって、会社に伝えるかどうかは悩ましい問題です。
結論から言うと、業務に支障が出る場合は会社に伝えることをおすすめします。
例えば、以下のような状況に心当たりがある場合は、会社に相談することで働きやすい環境が整う可能性があります。
- 発作や体調不良によって欠勤や遅刻が増えている
- 出張やプレゼン、会議などが強いストレスや発作の引き金になっている
- 通院のために勤務時間の調整が必要
- 通勤ラッシュで発作のリスクがある
- 隠していることで不安が強まり、業務に集中できない
上記のようなケースでは、上司や人事担当者に相談することで、具体的な配慮を受けられる可能性があります。
具体的なサポート案としては、以下のようなものがあります。
- 通勤ラッシュを避ける時差出勤や在宅勤務
- 出張や緊張を伴う業務の免除や調整
- 通院のための早退・遅刻の配慮
- 発作時に近くの同僚にサポートを頼める体制
また、会社には安全配慮義務や合理的配慮の提供義務があります。
これは、労働者が安心して働ける環境を整備するための企業側の法的責任ですが、配慮を受けるためには本人からの申し出が必要です。
伝える際には、どんな配慮があれば働きやすいかを整理し、正確に伝えることが重要です。
会社に伝えるデメリット
パニック障害であることを会社に伝えるメリットがある一方で、伝えた際に考え方などの違いから理解が得られない場合、次のようなデメリットが考えられます。
- 偏見や誤解を受ける
- 評価や昇進に影響する
- 過剰に業務を外される
パニック障害を伝えたあとに周囲との温度差に苦しむケースもあるため、伝える場合は、信頼できる上司や人事など、相手を慎重に選ぶことも大切です。
言わないとどうなる?
法令上、パニック障害を会社に申告する義務はありません。ただし、就業規則等で健康状態の申告が定められている場合は、その規則に従う必要があります。
業務に支障がなければ無理に公表する必要はないため、病名を伏せて働く方もいます。
しかし、パニック障害を伏せて働くことで以下のようなリスクもあります。
- 発作時に周囲が状況を把握できず、トラブルや誤解が起こる
- 欠勤や早退が増えた場合に、やる気がないと誤解され、信用を失う
- 病状が悪化してからでは、対応が後手に回ってしまう
- 就業規則で健康状態の申告が推奨されている場合、虚偽とみなされる場合がある
特に、症状が強く出ているにもかかわらず無理をして働き続けると、体調を悪化させるだけでなく、職場との関係性に悪影響が出るおそれもあります。
一方で、症状が安定しており、業務に影響がない場合は、伝えない選択も現実的です。
プライバシーの尊重や周囲の偏見・誤解を避けたいという理由から、自分でコントロールできる間は非開示にする方も多くいます。
ただし、以下のような点に注意が必要です。
- 隠して働く場合、通院や服薬などは自己管理が必要
- 緊急時の対応を周囲に頼めない
- 無理をしすぎることで、状態が急変する可能性がある
職場に伝えるかどうかは、業務への影響と今後の働き方を基準に判断するのが賢明です。
パニック障害で働けないと感じた時の選択肢と支援制度
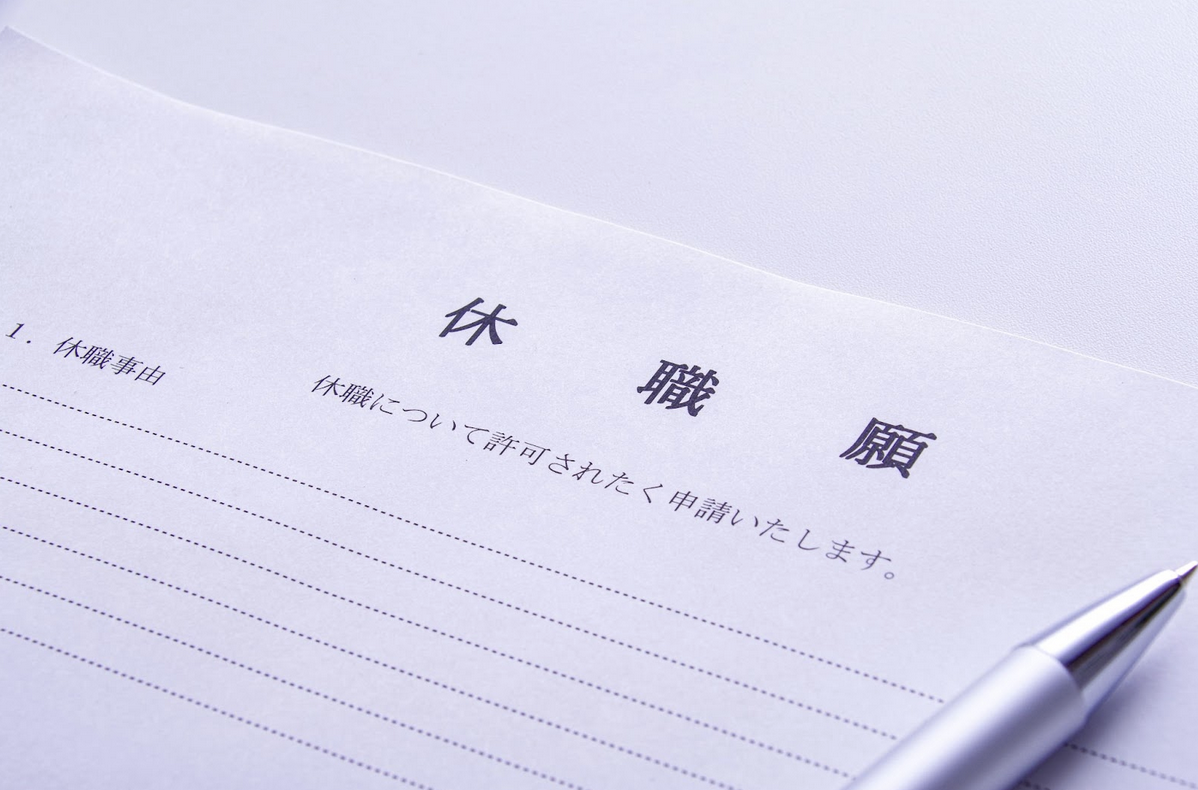
「職場に行くだけで息苦しい」「通勤途中に発作が出そうで不安」など、パニック障害を抱えながら働くことがつらく感じる場面は少なくありません。
無理を重ねることで症状が悪化する可能性もあるため、つらいと感じたときは、自分の状態を見つめ直し、環境を整えることが大切です。
ここでは、仕事が難しいと感じた時の選択肢と、利用できる支援制度について紹介します。
休職・退職という選択肢
パニック障害は、我慢すれば乗り切れるという方法では解決できない病気です。
症状を抱えながら無理をして働き続けると、うつ病を併発する可能性もあり、症状が強い時は早めに対処することが重要です。
パニック障害で働けないと感じた時には、休職する、退職して治療に専念するといった選択肢が考えられます。
休職する
仕事と治療の両立が難しい場合は、一時的に休職して治療に専念するのも有効です。
多くの企業では就業規則に基づき、一定期間の休職が認められています。
休職を申請する場合には、診断書の提出が必要になる場合があるため、主治医と会社の担当者に相談しましょう。
休職中の金銭的支援として傷病手当金を受けられる場合があります。
傷病手当金は標準報酬日額の約3分の2が最長1年6か月まで支給される制度で、金銭に不安を感じることなく治療に取り組めます。
退職して治療に専念する
休職しても症状が改善せず、今の職場が合わないと感じた時は、退職することも選択肢のひとつです。
退職後も一定期間は傷病手当金を受け取れる場合があります。
また、障害者手帳や障害基礎年金、自立支援医療制度などの公的支援を利用することで、経済的な負担を減らすこともできます。
公的支援については、自治体や福祉窓口で相談できます。
就労支援サービス・相談先
今は働けないけれど、将来的にもう一度働きたいと感じている方に向けて、再就職や復職を支えるさまざまな支援サービスが用意されています。
代表的なものは就労移行支援事務所、ハローワーク、障害者就業・生活支援センターが挙げられ、それぞれ以下のようなサポートが受けられます。
支援機関名 | 対象 | 主なサポート内容 |
就労移行支援事業所 | 65歳未満の障害や精神疾患のある方 | ・生活リズムの安定支援 ・ビジネスマナーやPCスキル訓練 ・模擬面接 ・職場実習 ・面接同行 ・定着支援 |
ハローワーク | 精神疾患・障害を抱える求職者 | ・専門スタッフによるカウンセリング ・履歴書や職務経歴書の添削 ・就職セミナーや職業紹介 |
障害者就業・生活支援センター | 原則は障害者手帳を持つ方(手帳がなくても相談可能な場合も) | ・就職に必要なスキル支援 ・職場体験の場の紹介 ・就職後の訪問支援や相談 |
治療を受けながら、これらの支援を受けることで、もう一度働けるようになる可能性が高まります。
復職したい場合は?
復職を目指すときは、主治医と相談しながら職場での働き方の見直しを検討しましょう。
具体的には以下のような検討が必要です。
- 通勤ラッシュを避けるための時差出勤
- 一部の業務の制限(接客・電話対応など)
- 在宅勤務の導入
職場に理解を得ることで、安心して働ける環境づくりにつながります。
また、リワークプログラムを活用する、障害者雇用で就職を検討するなども選択肢として挙げられます。
リワークプログラムは、医療機関や支援事業所が提供している、復職を目指す方向けのトレーニングプログラムです。
グループワークや認知行動療法、ストレスマネジメントなどを通じて、自分の状態を理解しながら働く力を身に着けるという内容です。
職場に近い環境で活動し、生活リズムを取り戻しつつ、復職を目指してプログラムに取り組むことが復職への近道になる可能性があります。
再就職を考える場合には、障害者雇用枠での就職を検討するのもひとつの方法です。
障害についての理解がある企業であれば、無理なく働ける環境が整っている場合が多く、発作時の対応や勤務形態の相談もしやすくなるでしょう。
しかし、障害者雇用枠は限りがある可能性が高く、早めの再就職を目指すのであれば、一般雇用と併せて就職活動を行うことをおすすめします。
パニック障害に向いている仕事の特徴

パニック障害がある方が働きやすい仕事には、いくつかの共通した特徴があります。
発作の引き金になりやすい、ストレス・疲労・予測できない業務・対人プレッシャーなどを避けられる環境が大切です。
ここでは、パニック障害に向いてる仕事の特徴を紹介します。
自分のペースで取り組める定型業務
パニック障害の方には、業務内容が毎日変化するような職種よりもルーティンワークに近い業務が向いています。
一般事務・データ入力・工場での検品・営業事務やアシスタント業務などが例として挙げられます。
対人ストレスが少ない仕事
人との対応で強い緊張を感じやすい方にとって、接客や電話対応が中心の業務はプレッシャーになります。
コミュニケーション量が比較的少ない職種を選ぶことで精神的な負担が軽減できます。
エンジニア職(開発・運用)・CADオペレーター・倉庫内作業・社内SEなどがおすすめです。
在宅でできる仕事
パニック障害の方は通勤や外出に不安を感じやすい方には、在宅勤務が可能な職種がおすすめです。
自宅であれば自分の体調に合わせて作業でき、精神的な安心感も高まります。
在宅経理・会計補助・オンラインデータ入力・事務作業やライティング・オンライン秘書など自宅でもできる仕事の種類は多くあります。
これらの職種に加え、短時間勤務・時差出勤・休職制度など、柔軟な働き方をサポートしてくれる職場であれば、体調に合わせて働くことができます。
パニック障害の方は治療を受けながら自分に合った形で働こう
パニック障害があっても、環境や働き方を工夫すれば、自分に合った形で働き続けることは十分に可能です。
無理をせず、自分のペースでできる仕事を選び、必要に応じて会社や支援制度を活用することが大切です。
また、発作や不安を放置せず、医療機関で適切な治療を受けることが症状の改善や働きやすさにつながります。
我慢せずに早めに心療内科や精神科を受診し、治療を受けながら働き方を考えていきましょう。
医師監修の『かもみーる』は、電車や外出に不安や恐怖を感じるパニック障害の方でも相談しやすいオンラインカウンセリングサービスです。
職場での悩みや休職の相談なども行うことができるため、パニック障害を抱えながら働く方もぜひご相談ください。
▶︎カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶︎新規会員登録はこちら
