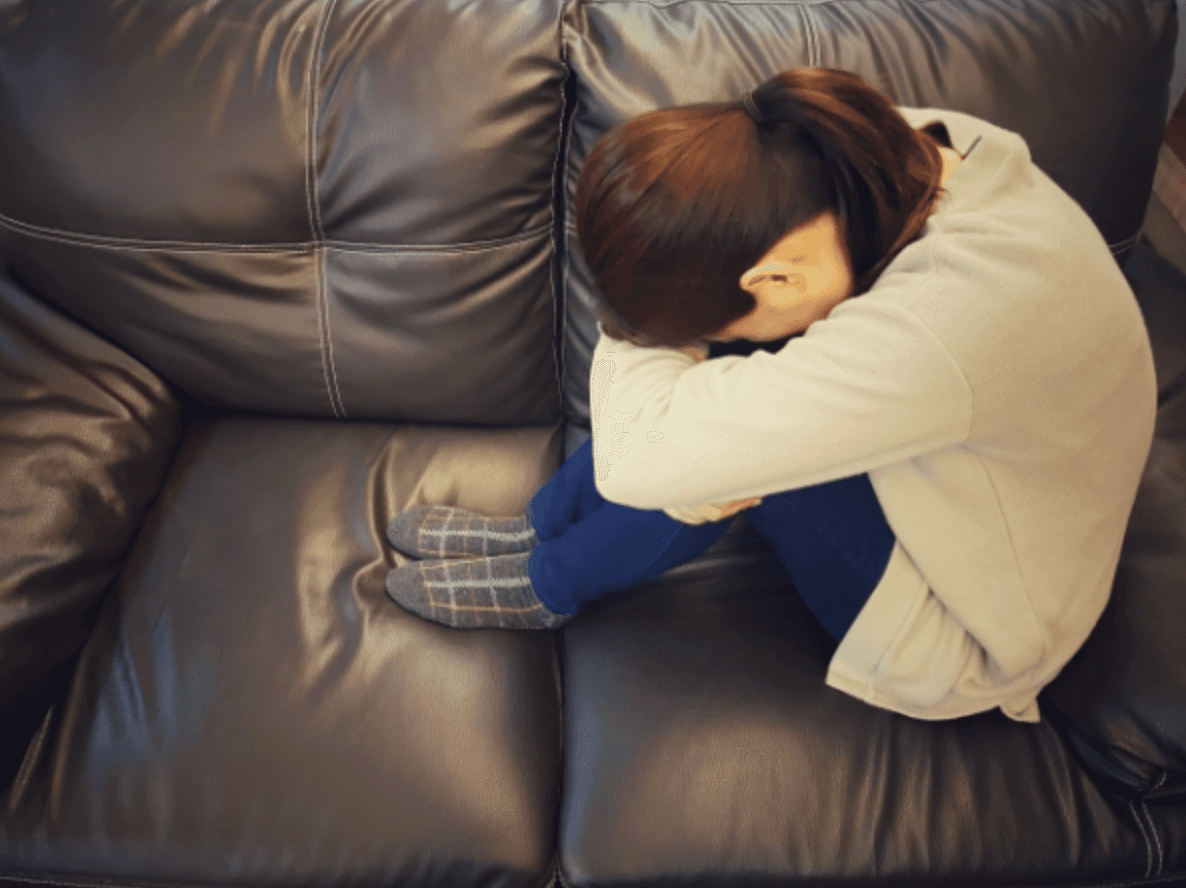やる気が起きなくて寝てばかりの日が続くと、「自分はダメなんじゃないか」と不安になりますよね。
何もできない自分に落ち込んだり、怠けているのではと責めてしまう方も多いでしょう。
しかし、その状態は心や身体からのSOSサインかもしれません。
この記事では、やる気が起きない理由を解説しながら、今日からできる7つの対処法や受診が必要なケースなどをご紹介します。
つらい毎日を少しでも軽くしたい方は、ぜひ参考にしてください。
やる気が起きない・寝てばかりになる身体的な原因

やる気が出ない、寝てばかりの状態には、身体の不調が隠れていることがあります。
ここでは、睡眠・栄養・自律神経の乱れなど、身体的な原因について詳しくみていきましょう。
過眠・睡眠リズムの乱れ
やる気が出ない、寝てばかりという状態が続く背景には、過眠や睡眠リズムの乱れが大きく関係していることがあります。
例えば、夜遅くまで起きていて昼に起きる生活や、長時間の昼寝を習慣にしていると、体内時計が乱れ、脳の覚醒リズムもうまく働かなくなります。
その結果、日中もぼんやりとした感覚が抜けず、だるさや無気力感が続いてしまうのです。
また、長く眠っているように感じても、睡眠の質が悪ければ疲労回復につながりません。
途中で何度も目が覚める、寝つきが悪いといった状態が続いている場合は、睡眠障害の可能性もあります。
栄養不足・ホルモンバランスの乱れ
やる気が起きない、寝てばかりといった状態は、栄養不足やホルモンバランスの乱れが原因となっていることがあります。
特に、鉄分・ビタミンB群・たんぱく質などの栄養素が不足すると、脳の働きが低下し、気分の落ち込みや集中力の低下、無気力感につながります。
また、女性はPMS(月経前症候群)や更年期によるホルモンの変動の影響を受けやすく、感情の起伏ややる気の低下を感じやすくなる時期があるため、注意が必要です。
こうした身体の変化に気づかずにいると、「ただ怠けているだけ」と自己否定につながることもあります。
バランスの良い食事を心がけ、必要に応じてサプリメントを活用するなど、自分の身体に合った栄養を意識しましょう。
自律神経の乱れ
自律神経は、身体のリズムや内臓の働きをコントロールする大切な神経で、交感神経(活動モード)と副交感神経(休息モード)のバランスによって心身の状態が整えられています。
しかし、この切り替えがうまくいかなくなると、日中もぼんやりと眠く、やる気が出ない、夜は眠れないといった不調が現れることがあります。
特に生活習慣が乱れている人や、気温・気圧の変化が激しい季節の変わり目は、自律神経のバランスが崩れやすい時期です。
ストレスや不規則な生活、過度な疲労が続くことも、自律神経に大きな負担をかけます。
この状態が続くと寝ても疲れが取れず、心も身体もだるく感じる悪循環に陥るでしょう。
やる気が起きない・寝てばかりになる心理的・環境的な原因

やる気が起きない、寝てばかりの状態は心の疲れや環境からの影響によって引き起こされることもあります。
ここでは、ストレスや目標の喪失といった心理的・環境的な原因を解説します。
ストレス過多・精神的疲労
日常的に強いストレスを感じ続けていると、心や脳が過度に疲弊し、いわば「活動停止モード」に入ってしまうことがあります。
仕事のプレッシャーや人間関係のトラブル、育児の負担などが積み重なると、心が処理しきれず、自分を守るために「何もしたくない」と感じる状態になります。
頭がぼんやりして集中できない、気づくと何時間も寝てしまうといった状態は、脳が強制的に休息を取ろうとしているサインです。
このような心の疲労は、見た目では分かりにくいため、自分でも気づきにくいのが特徴です。
頑張らなきゃと無理に動こうとするよりも、「今は回復が必要な時期」と認識し、まずは心を休ませることが大切です。
希望や目標の喪失
やる気が出ない、寝てばかりという状態は、希望や目標を見失ったときにも起こりやすくなります。
日々の生活の中で、「これをやりたい」と思えることがなくなると、生きる意味や目的を見出せず、無気力感に支配されてしまいます。
特に転職、退職、子育ての一区切り、喪失体験など、人生の転機に直面したときにこのような状態に陥ることがあるようです。
また、周囲との関わりが減り、孤独を感じやすくなると、自分の存在価値がわからなくなり、どんどん気力を失っていくこともあります。
このような状態は、本人の努力不足ではなく、心が疲れて希望を見失っているサインです。
やる気が起きない・寝てばかりのときに考えられる病気

やる気が起きない、寝てばかりという状態が長く続く場合、以下の4つの病気が隠れていることもあります。
- うつ病
- 適応障害
- 睡眠障害
- 自律神経失調症
詳しく解説していきます。
うつ病
うつ病は、やる気が出ない、気分が落ち込む、眠ってばかりいるといった症状が続く代表的な心の病気です。
特に「朝起きられない」「何をしても楽しく感じない」といった状態が2週間以上続く場合、うつ病の可能性があります。
脳内の神経伝達物質のバランスが崩れることが主な原因とされ、環境的なストレスや体調不良が引き金になることもあります。
うつ病になると、意欲の低下に加えて、食欲や睡眠の変化、集中力の低下、自己否定感なども見られることが多いです。
また、気分の落ち込みが日によって変動する「日内変動」や「死にたい」といった希死念慮が現れることもあります。
症状が軽いうちに専門の医療機関に相談することで、早期回復が期待できます。放置せず、まずは一歩踏み出すことが大切です。
適応障害
適応障害は、特定の環境や出来事による強いストレスに対して心や身体がうまく適応できず、さまざまな不調が現れる心の病気です。
転職、人間関係のトラブル、引っ越し、離婚など、生活環境の変化が引き金になることが多く、ストレスの原因が明確であるのが特徴です。
症状としては、気分の落ち込み、やる気の低下、強い不安感、過眠または不眠、無気力などが見られ、「何もする気が起きない」と感じることもあります。
また、頭痛や吐き気、腹痛といった身体症状を伴うこともあり、仕事や日常生活に支障をきたす場合もあります。
ストレスの原因がなくなると徐々に回復していく傾向がありますが、放置するとうつ病などに進行する可能性もあるため、早めの相談や治療が大切です。
▶適応障害とは?再発率や兆候・繰り返さないための対策・復職時の注意点を解説
睡眠障害
睡眠障害にはさまざまな種類があり、中には日中の強い眠気や過眠を主な症状とするものもあります。
- ナルコレプシー:突然強い眠気に襲われ、感情の高まりに伴う脱力(情動性脱力発作)や入眠時幻覚などを伴う難治性の病気
- 特発性過眠症:夜間に十分な睡眠を取っていても日中に強い眠気が続く病気で、仮眠を取っても改善しにくいのが特徴
- 睡眠時無呼吸症候群:睡眠中に繰り返し呼吸が止まり、眠りが浅くなるため、朝起きても疲れが取れず、集中力の低下や気力の減退を招くこともある
これらの症状が続く場合、単なる寝不足とは異なり、専門的な検査と治療が必要になります。
自律神経失調症
自律神経失調症は、交感神経と副交感神経のバランスが崩れることで、心身にさまざまな不調が現れる状態です。
睡眠や消化、呼吸、体温調節などをコントロールする自律神経が乱れると、日中に強い眠気を感じたり、やる気が出ずに寝てばかりになることがあります。
ストレスの蓄積や生活習慣の乱れ、過労、不規則な睡眠などが主な原因とされ、女性に多く見られます。
頭痛、めまい、倦怠感、動悸などの身体症状に加えて、気分の落ち込みや不安感などの精神的症状も伴うことがあります。
特に季節の変わり目や気圧の変化にも影響を受けやすく、日によって体調が大きく変わるのも特徴です。心と身体の両方にアプローチするケアが重要です。
やる気が起きない・寝てばかりのときにできる5つの改善策

やる気が起きなくて寝てばかりの状態を改善するには、以下5つの方法から始めていきましょう。
- 起床・就寝時間を固定する
- 朝の光を浴びる
- 食事の質を見直す
- 簡単なタスクから始める
- 人と話す・相談できる相手を見つける
それぞれ詳しくご紹介していきます。
1. 起床・就寝時間を固定する
やる気が出ない、寝てばかりという状態を改善するためには、起床・就寝時間を固定して生活リズムを整えることがとても大切です。
生活リズムが乱れると、体内時計が狂い、脳の覚醒スイッチがうまく機能しなくなります。その結果、朝起きても頭がボーっとしたままになり、日中も気力が湧かず、再び寝てしまうという悪循環に陥りやすくなります。
毎日同じ時間に起き、夜も同じ時間に眠る習慣をつけることで、少しずつ身体が規則正しいリズムを取り戻し、自然とやる気も戻りやすくなります。
また、就寝前はカフェインやアルコールを避け、部屋を暗く静かに保つことで、より質の高い睡眠につながります。
スマートフォンやパソコンの使用も控え、心と身体がリラックスできる環境を意識しましょう。
2. 朝の光を浴びる
朝の光を浴びることは、心と身体のリズムを整えるうえでとても効果的です。
太陽の光には、脳内のセロトニン分泌を促す働きがあり、このセロトニンはやる気や気分の安定に深く関わっています。
朝起きたらまずカーテンを開け、部屋に自然光を取り入れるだけでもOKです。可能であれば10〜15分ほど外に出て、軽く散歩をするとより効果的です。
日光を浴びることで体内時計がリセットされ、夜の眠りも深まりやすくなります。
また、朝の時間帯に光を感じることで、1日のスタートにスイッチが入り、気持ちも前向きになりやすくなります。
無理に遠出する必要はなく、ベランダや玄関先で深呼吸するだけでも十分なので、ぜひ毎朝の習慣に取り入れてみましょう。
3. 食事の質を見直す
食事の内容を見直すことも大切です。
甘いものやジャンクフード、炭水化物に偏った食事ばかりでは、血糖値の急激な変動によって気分が不安定になりやすく、エネルギーも持続しません。
脳と体の働きを支えるためには、鉄分やビタミンB群、たんぱく質などの栄養素をしっかりと摂ることが重要です。
特に鉄分不足は女性に多く、貧血や集中力低下、疲労感の原因にもなります。
ビタミンB群は神経や代謝に関わり、たんぱく質は脳内の神経伝達物質の材料になります。
栄養バランスの良い食事を心がけることで、体調だけでなく気分の面でも安定しやすくなり、やる気の回復にもつながるでしょう。
無理に完璧を目指さず、少しずつ整えていくことがポイントです。
4. 簡単なタスクから始める
やる気が出ないときは、「何もしない自分」に落ち込んでしまいがちですが、そんなときこそ簡単なタスクから始めることが効果的です。
まずは、1分だけ机を拭く、今日やることをメモに書き出す、顔を洗う、歯を磨くなど、ほんの小さな行動で構いません。
こうした「できた」という実感が少しずつ自信になり、次の行動への原動力になります。
脳は成功体験を積み重ねることで前向きなモードに切り替わっていくため、ハードルをできるだけ低く設定し、小さな達成を繰り返すことがポイントです。
たとえわずかな一歩でも、「動けた自分」を肯定することで、やる気は自然と戻ってきます。
5. 人と話す・相談できる相手を見つける
やる気が出ない、寝てばかりという状態が続いているときは、ひとりで抱え込まずに誰かに話すことがとても大切です。
気持ちを言葉にして外に出すだけで、心が少し軽くなり、自分の状態を客観的に見つめ直すきっかけにもなります。
話す相手は、家族や友人でも、同じような悩みを持つ人でも構いません。
もし身近に頼れる人がいなければ、SNSやオンラインカウンセリング、自治体の相談窓口などを活用するのも1つの方法です。
大切なのは、「頼ってもいい」と自分に許可を出すことです。
無理にうまく話そうとせず、気持ちを吐き出すだけでも十分価値があります。
心と身体にやさしい一歩を踏み出すために
やる気が起きない、寝てばかりの状態には、心や身体からのサインが隠れていることがあります。
無理に頑張ろうとせず、まずは自分を責めずに休むことが大切です。身体や心の疲れが蓄積されているときは、休息が何よりの回復薬です。
小さなことでも「できた」と思える行動を少しずつ積み重ね、自分自身を労わる意識を持ちましょう。
日々の小さな変化が、やる気の回復につながっていきます。
セルフケアで改善しないと感じたら、医療機関を活用するのも1つの選択肢です。
オンライン診療・オンラインカウンセリングの『かもみーる』では、いつでもどこでも悩みを相談いただけます。
『かもみーる心のクリニック(東京院・仙台院)』では対面診療も対応しているため、ご都合に合わせて利用していただくことが可能です。
焦らず、自分を大切にしながら少しずつ前に進んでいきましょう。
▶︎カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶︎新規会員登録はこちら