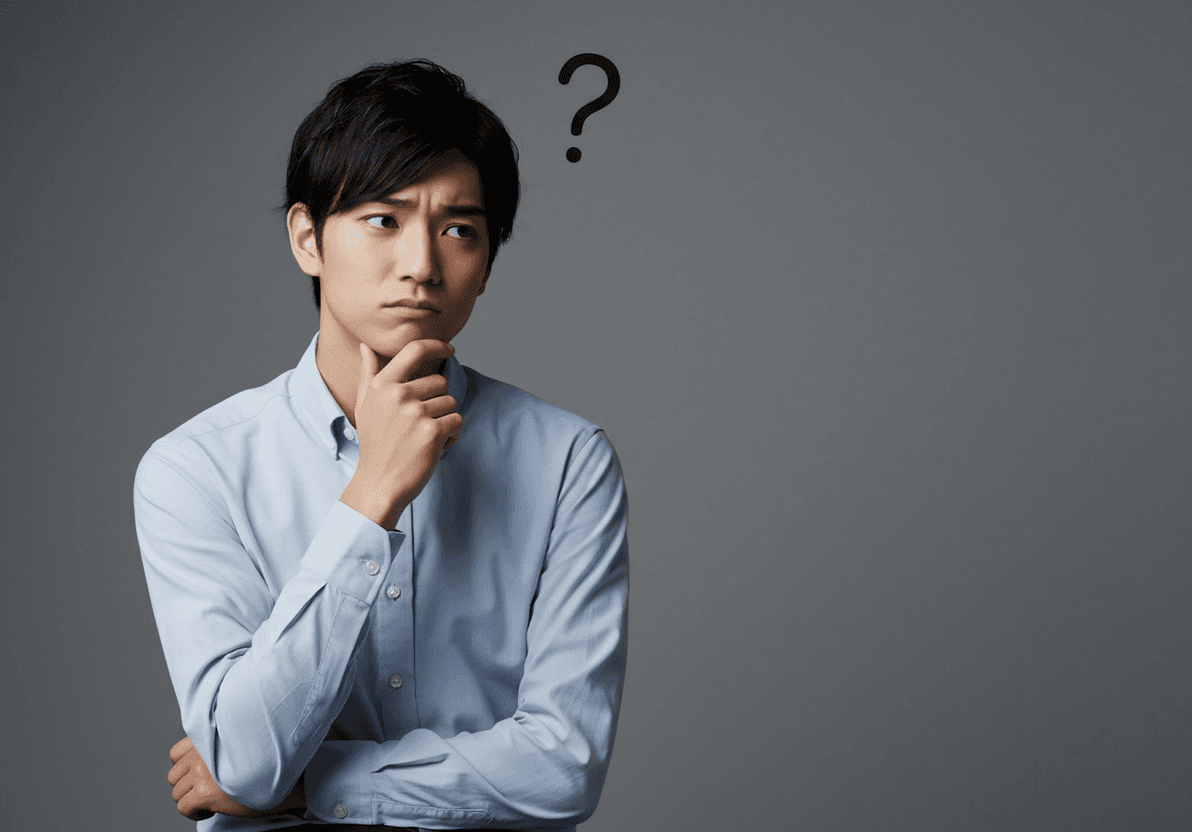人の話が頭に入らなくなった、スムーズに会話ができないなどの問題は、仕事の進行やコミュニケーションに影響を与えるため、放置できません。
会話が頭に入らない原因の一つに、病気や発達特性が関係している場合があります。
この記事では、人の話が入ってこない原因や疑われる病気とその治療法、対処法などを紹介します。
よくある症状だからと放置していると、早期治療を逃す可能性があるため、この記事をきっかけに積極的に改善していきましょう。
人の話が頭に入らないのはブレインフォグ?

人の話が頭に入らない状態は一般的に『ブレインフォグ』という言葉で表現されることがあります。
頭の中にモヤがかかったようにぼーっとする、内容が頭に入ってこないなどの症状が見られます。
その他に、マルチタスクができない、物事を開始できない、行動までに時間がかかる、集中できないなどで、仕事や日常生活に支障があるのもブレインフォグの症状です。
しかしブレインフォグは医学用語としての正式な定義はなく、医療機関を受診しても疾患として診断が下されるわけではありません。
ブレインフォグの一般的な原因として詳しいことははっきりとしていませんが、身体が正常に機能していない、さまざまな要因が関係している症状と考えられています。
人の話が頭に入らない原因
ブレインフォグのように、人の話が頭に入らない状態を招く原因について紹介します。
ストレス
ストレスを受けると副腎皮質から分泌される『コルチゾール』の影響により、人の話が理解できないような状態になることがあります。
コルチゾールはストレスから身を守るために分泌されるホルモンです。
しかし長期的なストレスにさらされると、副腎皮質が疲労するためバランスよく働けなくなり、以下のような問題が起こります。
- コルチゾールの過剰分泌が長期にわたると脳の海馬を萎縮させる
- ストレス時や炎症時の免疫抑制作用、脂肪の代謝、糖新生のための分泌ができなくなる
このように、過度なストレスは人の話を理解しづらくする一因となります。
脳疲労
脳疲労は、過剰な情報処理や長時間にわたる集中などで、処理能力が低下した状態のことです。
脳疲労を引き起こしているのは具体的に以下のような原因です。
- 情報が多すぎる
- 過度なストレス
- インターネット・スマートフォンへの依存
脳疲労を起こすと記憶力や注意力、集中力などが落ちるため、会話中の相手の話が頭に入らなくなることがあります。
脳の疲れは身体の疲れと違って自覚が難しく、深刻な状態になってから気付くことが多いため、人の話が頭に入らない症状が続く場合は脳疲労を疑いましょう。
睡眠不足
睡眠不足、または睡眠リズムの乱れは、脳の機能の低下につながります。
睡眠をとっている間、脳は以下のようなことを行っています。
- 日中に蓄積した不要な情報を整理
- 日中に得た大切な情報を記憶として固定する
- 情報処理による代謝物の除去
- 脳細胞の修復
睡眠が十分でない、または睡眠の質が悪い場合、睡眠中に行われる必要なプロセスを欠くため頭が働かず、結果として人の話が頭に入らない状態を引き起こします。
生活習慣
上に紹介した睡眠不足の他に、栄養不足や運動不足などにみられる生活習慣の乱れも、脳が十分休まらない原因です。
脳機能を維持するためにはビタミンB群や鉄分、タンパク質など特定の栄養素が必要であり、不足すると気力の低下や倦怠感につながります。
また、運動不足になると血行が悪化するため、脳への酸素供給が低下します。
適度な運動は気分転換が可能ですが、運動不足はネガティブな思考に傾きがちです。
よく眠り、バランスよく食べ、よく動くという、日常生活の範囲内で行えることが、人の話を聞ける健康な脳を保つことにつながります。
更年期
更年期になると、特に女性はホルモンが減少することで自立神経が乱れ、疲労や頭痛を引き起こします。
物忘れや注意力の低下が見られるため、年齢的に認知症を疑われることも多く、更年期障害の症状に悩んで心身にストレスがかかることでさらに記憶力の低下を招きます。
更年期で人の話が頭に入らないという場合は、ここで紹介する通りに生活を整えたり更年期障害の治療を受けたりすることで改善する可能性があるため試してみましょう。
抗うつ薬の副作用
うつ病の治療を受けている人は、抗うつ剤の副作用として人の話が頭に入らなくなる可能性があります。
抗うつ剤には脳の神経伝達物質であるセロトニンやノルアドレナリン、ドーパミンなどの量を増やし働きを高める作用があります。
その一方、リスクとして可能性があるのは、眠気や不眠、吐き気などの副作用です。
眠気や体調不良は、集中力や注意力の低下につながる場合もあるため、会話をしていても頭に入ってこない様子がみられることもあるでしょう。
ウイルス感染
他の症状と共に、人の話が頭に入らない・理解できないなどの症状が後遺症として取り上げられるようになったのは、新型コロナウイルス感染症です。
他にも「集中力が低下した」「倦怠感がある」などの症状が長引き、日常生活に影響がある人も多く見受けられました。
ウイルスやワクチン接種を原因とした感染症は、脳を含む身体全体が免疫反応によって炎症を起こすことがあるため、人の話が頭に入らない症状につながると考えられています。
疾患
人の話が頭に入らない症状がある場合、治療が必要な病気や特性が隠れているかもしれません。
後述する対処法の中から実践できることを試してみて、改善できないようであれば原因である疾患を明確にすることが必要です。
人の話が頭に入らない場合の対処法

人の話が頭に入らない場合の対処法を紹介します。挑戦しやすい方法から、少しずつでも試してみましょう。
聞く環境を整える
雑音を減らしてなるべく気の散らない静かな場所を選ぶと、落ち着いて話を聞くことができます。
話し相手の顔が見える位置に座ることで、言葉以外の目や表情などから情報が得られやすくなります。
周りの環境を整えて聞くことで人の話が頭に入ることが分かれば、会話するときに感じていた不安を軽減できるため、より効果的かもしれません。
前もって相手に伝えておく
人の話が頭に入らないことが不安であり、迷惑をかけてしまうかもしれないことを、事前に相手に伝えておくと、理解してもらえた上で話ができるでしょう。
なるべく分かりやすく説明してもらえたり、話を短めに済ませてもらえたりすると、協力してくれる人がいるという安心感もあり、負担が軽くなります。
協力し合うことで、話の行き違いや理解不足などで起こるトラブルも回避できるでしょう。
メモを取りながら聞く
記憶力の低下を自覚しているのであれば、重要な言葉をメモしながら聞くと、後で思い出しやすくなります。
すべてをメモできなくても、そのメモを見ながら後で分からないことを質問できます。
また、話が終わった後にメモを見直しながら整理すれば、記憶の整理ができて理解も深まります。
話を聞いた後、要点を確認する
一方的に聞くのではなく「○○ということですね」というふうに自分の言葉でまとめ、要点を確認すると確実な理解が期待できます。
また、長い話を一度に聞くのではなく、区切りのよいところで切って小分けにしてもらうと、聞く際の負担が軽減できます。
疲れを感じたら無理をしない
心にゆとりがある状態で話を聞かないと、会話に集中できず、頭に入りにくいものです。
疲れを感じたら、または、疲れている時は無理をしないで休憩をはさんでもらったり、一旦区切ったりしてもらいましょう。
分からないときは聞き返す
話が理解できなかったり、一生懸命聞いていても頭に入らないときなど、分からないことがあったら聞き返しましょう。
例えば仕事の話において分からないことをうやむやにすると、トラブルの元になる可能性があります。
人の話が頭に入らないとき、その自覚があるときなど、迷惑をかけることが不安になりますが、「聞き返すことが怖いのは自然なこと」ということを受け止めましょう。
また、理解しようと努力している自分のことを自覚することをおすすめします。
ストレスを解消する
ストレスを解消することで、会話する際の集中力や理解力の低下が改善されるでしょう。
例えば軽い運動は血行や代謝を促進するため、脳に十分な栄養が供給されるようになります。
好きな趣味に没頭することは日常のストレスから解放され、リラックスする効果があります。
ストレスから離れる方法は人それぞれのため、自分のストレス解消法を見つけておくとよいでしょう。
医療機関を受診する
以上のような対処法を実践してみても、やはり会話中に頭が回らない、他にも気になる症状があるという場合は、専門家に相談することも考えてみましょう。
人の話が頭に入らない症状が2週間以上続く場合や不安がある場合、精神科や心療内科を受診するのが一般的です。
かかりつけ医しか知らない場合は、かかりつけ医から必要に応じて専門家を紹介してもらうことも選択肢のひとつです。
人の話が頭に入らない場合に疑われる病気

人の話が頭に入らない場合に疑われる病気は少なくありません。
以下のような病気を発症している場合、人の話が頭に入らないことがあります。
うつ病
うつ病は、無気力感や気分の落ち込み、不安などが日常生活に支障をきたすほどの程度で現れる疾患です。
脳内の神経物質のバランスが乱れるため、思考力や記憶力・集中力の低下がみられ、言葉が出にくくなるなど、人との会話が難しくなる場合があります。
▶うつ病で連絡が途絶える理由と適切な対処法|周囲ができるサポート
適応障害
適応障害は、転勤や新しい人間関係など、特定の状況や出来事が引き起こす耐えがたいストレス要因によって引き起こされます。
抑うつ気分や不安などの精神症状や動悸やめまいなどの身体症状が見られることがある疾患で、脳が疲弊するため人の話が頭に入らない場合があります。
原因が明確であるため、ストレス要因から離れると症状が改善することが多いです。
▶適応障害の人への対応方法は?付き合い方やしてはいけない声掛けなども解説
発達障害
発達障害は以下のような生まれつきの脳の持つ特性があります。
- 長く集中ができない
- 環境の刺激に敏感すぎる
- 記憶の整理がしづらい
- 曖昧な表現が理解しづらい
発達障害の原因は遺伝要因が指摘されていますが、まだ明確には認められていません。
躾けや性格・生活環境が原因でもなく特性のために、人の話が頭に入らない症状が現れます。
聴覚情報処理障害
聴覚情報処理障害(APD)は、聴覚に問題はないものの、脳が音や言葉をうまく処理できない障害です。
聞こえているのに言葉が聞き取りづらく、字幕がないとテレビの言葉が分からない、会話中に何度も聞き返すというような症状が見られます。
聴力検査では異常がなく、耳鼻科でも十分に認知されていないことが多く、診断が難しい障害です。
不安障害
不安障害とは、強い不安に襲われ、仕事や学業、日常生活において支障をきたす疾患です。
集中力や記憶力の低下により、人との話が頭に入らないなどの症状が見られますが、原因は不安によって脳疲労が蓄積するためです。
特に理由もなく怯えるような精神的な症状と、発汗や動悸がみられる身体症状があります。
心身が受けるストレスの他に、環境的なストレスや遺伝要因などが複雑に絡み合って発症すると考えられています。
▶不安障害は治るのか?自力での対処法と病院での治療方法について解説
統合失調症
統合失調症は、遺伝的要因や環境的要因(幼い頃のトラウマ・母体のウイルス感染症・出生時の合併症など)、脳の機能不全などが重なり合って発症すると考えられています。
症状としては、幻覚や妄想・感情の平坦化や意欲の欠如の他に、思考の混乱・記憶力や情報処理能力・集中力の低下が見られます。
会話が飛躍的になったり、理論的に一貫性のない内容になったりと、支離滅裂になることが多く、もちろん会話も難しくなります。
人の話が頭に入らない場合の治療方法

人の話が頭に入らない場合、診断した疾患や症状に合わせて治療が行われます。
治療法の一例は以下の通りです。
- 生活習慣の改善……睡眠・食事・運動などについて指導・アドバイスを行う
- 薬物療法……うつ病や不安障害など精神疾患の場合に選択される
- 精神療法……認知行動療法や思考の整理などのカウンセリングやトレーニング
- TMS(経頭蓋磁気刺激療法)……脳疲労や不安・ストレスが原因の場合はTMSが有効
以上のような治療法を適切に組み合わせて行うことで、人との会話で困りごとが生じている症状が軽減、または改善する可能性があります。
まずは原因をはっきりさせましょう
人の話が頭に入らない場合の、原因や対処法、疑われる病気や治療法について紹介しました。
自分でできる対処法を紹介しましたが、まず専門家の診断を受けて、必要に応じて早期発見・早期治療を行うことがおすすめです。
『かもみーる』は、医師監修のオンラインカウンセリングサービスを提供しています。
精神科や心療内科を初めて受診する場合の戸惑いや不安がある場合は、オンライン診療が便利です。
医師のほか、臨床心理士や公認心理士を中心とした有資格者がお話を伺います。
一人で悩まずに、まずは気軽にご相談ください。
▶カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶新規会員登録はこちら