「すぐ横になりたくなる」「疲れが取れず、座っているのもつらい」というお悩みを抱える方は少なくありません。
こうした状態は一時的なものであれば心配ありませんが、休んでも改善しない、日常生活に支障をきたしている場合には注意が必要です。
この記事では、すぐ横になりたくなる原因について詳しく解説します。
このような状態に考えられる病気や具体的な対処法などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
すぐ横になりたくなる主な原因

すぐ横になりたくなる主な原因として、以下の5つが挙げられます。
- 身体的疲労
- 睡眠不足
- ストレスや精神的疲労
- 生活習慣の乱れ
- 環境要因
ここでは上記5つの原因についてそれぞれ解説します。
身体的疲労
身体的疲労は、「すぐ横になりたい」と感じる原因の一つです。
日常生活や仕事、育児、介護などで身体を酷使すると、筋肉や神経がエネルギーを消費し、身体全体に倦怠感が広がります。
これは単なるだるさではなく、筋肉や神経のパフォーマンスが著しく低下しているサインです。
また慢性的な運動不足によって筋力が低下していると、わずかな動作でも疲労を感じやすくなります。
筋力が衰えることで姿勢保持が難しくなり、すぐ横になりたくなることがあります。
睡眠不足
十分な睡眠をとっていないと、身体や脳の回復が妨げられ、日中に強い眠気や倦怠感を感じやすくなります。
睡眠は身体のエネルギーを回復させ、脳の機能を整えるために欠かせないものです。
しかし、睡眠時間が短かったり、夜中に何度も目が覚めたりするような質の低い睡眠が続くと、翌日のパフォーマンスに大きな影響が出ます。
特に睡眠不足は、自律神経のバランスを乱す原因にもなります。
自律神経のバランスが乱れ、身体が常に緊張状態に陥って疲労が取れにくくなるのです。
その結果、「ずっと眠い」「動きたくない」「横になりたい」といった感覚が強まります。
ストレスや精神的疲労
精神的なストレスや心の疲労も、身体を動かすエネルギーを奪います。
仕事や人間関係、将来への不安などによる慢性的なストレスは、自律神経を乱し、全身に影響を及ぼします。
特に交感神経が常に優位になると、身体は常に緊張状態となり、やがて限界を迎えて強い疲労感となって表れるのです。
また精神的な疲れは、意欲や気力低下も招きます。
その結果、「考えるのがしんどい」「やる気が出ない」といった症状に加え、何もせずにただ横になっていたいという欲求が強まります。
精神的な疲労は目に見えにくいため軽視されがちですが、放置するとうつ病や不安障害に進行する恐れもあるため注意が必要です。
生活習慣
不規則な生活習慣も、すぐ横になりたくなる感覚を引き起こす大きな要因です。
例えば朝食を抜いていたり、ジャンクフードや糖質の多い食品ばかりを摂取していたりすると、血糖値の急激な変動によってエネルギー切れを感じやすくなります。
これが日中の眠気やだるさの原因になります。
また、栄養不足も疲労感や倦怠感を招く原因の一つです。
特に鉄分、ビタミンB群、マグネシウムといった栄養素が不足すると、エネルギー代謝が上手くいかず、慢性的な疲労感につながります。
さらにカフェインやアルコールの過剰摂取も注意が必要です。
これらは一時的に元気になったように感じても、効果が切れた後に強い疲労感が襲ってくることがあります。
日頃から規則正しい食事と睡眠、適度な運動を心がけることが大切です。
環境要因
周囲の環境が原因で「横になりたい」と感じることもあります。
例えば空気がこもって酸素濃度が低い部屋や、湿度・温度が極端な環境に長時間いると、体温調整機能や自律神経に負荷がかかり、強い倦怠感を招きます。
また、部屋が散らかっている、照明が暗すぎる、逆にまぶしすぎるといった物理的な環境も脳にストレスを与える要因になるため注意が必要です。
騒音や振動なども、知らず知らずのうちに精神的な疲労を蓄積させる原因となります。
すぐ横になりたくなる場合には、生活環境を見直すことも大切です。
すぐ横になりたくなるときに考えられる病気
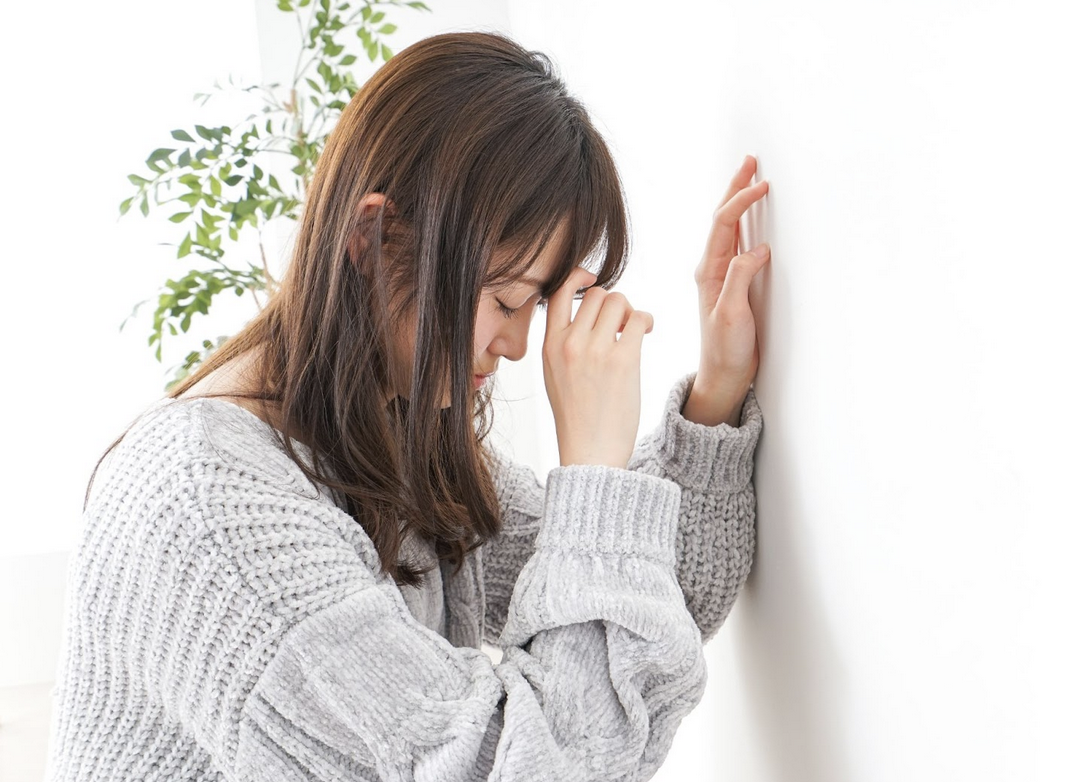
すぐ横になりたくなるときに考えられる病気として、以下の8つが挙げられます。
- 貧血
- 起立性調節障害
- 甲状腺機能低下症
- うつ病
- 自律神経失調症
- 睡眠障害
- 適応障害
- 統合失調症
ここでは上記8つの病気についてそれぞれ解説します。
貧血
貧血は、血液中の赤血球やヘモグロビンの不足により、酸素を十分に体内に届けられなくなる状態です。
酸素は身体や脳のエネルギー産生に欠かせないため、不足すると疲労感や倦怠感が強く表れます。
特に立ち上がったときや運動後に「座っているのもしんどい」「すぐ横になりたい」と感じるのは、酸素不足が関係している可能性があります。
貧血は性別関係なく起こるものですが、特に女性に多く見られ、月経や無理なダイエットが原因で発症しやすいです。
主な症状にはめまいや動悸、息切れ、顔色不良、集中力の低下などがあり、症状が進むと日常生活に支障をきたします。
血液検査で診断でき、鉄剤の服用や食生活の見直しによって改善が期待できます。
起立性調節障害
起立性調節障害は、自律神経の不調により血圧や心拍数の調節がうまくいかず、めまいや立ちくらみ、倦怠感が生じる病気です。
特に思春期の子どもや若年層に多く見られますが、大人にも起こることがあります。
朝に起き上がれない、立っていると気分が悪くなる、疲れやすくすぐ横になりたくなるといった症状が特徴です。
この病気は起立時に脳への血流が不十分になるため、横になっているときが楽に感じます。
水分・塩分の摂取、適度な運動、生活リズムの改善などで軽減が期待できますが、重症化している場合は内服治療が必要になることもあります。
甲状腺機能低下症
甲状腺機能低下症とは、甲状腺ホルモンの分泌量が低下し全身の代謝が落ちることで、慢性的なだるさや眠気、無気力を感じる病気です。
甲状腺ホルモンは身体の代謝を維持するために不可欠な存在で、『元気の源』とも言える役割を担っています。
このホルモンの分泌量が不足すると、エネルギー産生が滞り、横になっていたくなるほどの疲労感が表れるようになるのです。
その他の症状としては、体重増加、寒がり、むくみ、皮膚の乾燥、便秘、動作緩慢などがあり、日常生活にも影響を及ぼします。
ホルモン補充療法により症状の改善が見込めるため、気になる症状が続く場合は早めの受診を検討しましょう。
うつ病
うつ病は精神的な病気とされていますが、身体的な症状が表れる場合も多いです。
代表的な症状には気分の落ち込み、意欲の低下、不眠、食欲不振などがあり、何をするにも億劫で、「横になっていたい」という気持ちが強くなります。
これは単なる怠けではなく、脳内の神経伝達物質(セロトニンやノルアドレナリンなど)のバランス異常が関与していると考えられています。
また心の疲れが身体の疲れとして表れるケースも少なくありません。実際には身体をほとんど動かしていなくても、全身が重く感じられることがあります。
治療方法には抗うつ薬や認知行動療法、生活リズムの改善などがあります。
気分の落ち込みに加え、強い倦怠感や疲労感がある場合は、早めに心療内科や精神科を受診することが大切です。
自律神経失調症
自律神経失調症は、交感神経と副交感神経のバランスが乱れることで、全身にさまざまな不調が表れる状態です。
代表的な症状には、めまい、動悸、頭痛、冷え、消化不良、不安感、そして倦怠感などがあります。
特に朝起きるのがつらく、日中も強い疲労感やだるさから「すぐ横になりたくなる」という症状が出やすくなるのが特徴です。
原因としては、慢性的なストレスや不規則な生活、睡眠不足、ホルモンバランスの変化などが挙げられます。
症状が続く場合は医療機関の受診を検討しましょう。
睡眠障害
「夜はしっかり寝ているのに日中に強い眠気がある」「我慢できずに横になってしまう」といった症状が続く場合、睡眠障害が原因の可能性があります。
中でも過眠症や睡眠時無呼吸症候群などは、日中の活動に大きな支障をきたす病気です。
過眠症は、夜間に十分な睡眠をとっても日中に耐え難い眠気に襲われ、集中力の低下や居眠りを繰り返すようになります。
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が何度も止まり、眠りが浅くなってしまう病気で、いびきや日中の強い眠気、倦怠感が特徴です。
これらの睡眠障害は生活の質を大きく低下させるため、慢性的な眠気がある場合は、早めに医療機関を受診するのが望ましいでしょう。
▶TMS治療は睡眠障害にも効果がある?原因別のアプローチ法や効果を紹介
適応障害
適応障害は、環境の変化や強いストレスにより心身のバランスを崩してしまう病気です。
職場の異動、人間関係のトラブル、進学や引っ越しなど、明確なストレス要因が引き金となって発症しやすく、ストレスを受けてから3か月以内に症状が出るのが特徴です。
主な症状には、気分の落ち込み、不安感、集中力の低下、イライラ、そして全身の疲労感や倦怠感などがあります。
こうした症状は心と身体の両面に表れるため、活動するのが億劫に感じ、「何もせずに横になっていたい」という状態に陥りやすくなるのです。
ストレス要因を特定し、距離を置くことが治療の基本となります。
▶適応障害とは?再発率や兆候・繰り返さないための対策・復職時の注意点を解説
統合失調症
統合失調症は幻覚や妄想、感情の平板化など、精神と行動にさまざまな異常が表れる精神疾患です。
症状が急激に表れるケースと、時間をかけて表れるケースがあり、症状のタイプは以下の3つに分類されます。
- 妄想型:妄想や幻覚の症状が表れるタイプ
- 破瓜型:支離滅裂な言動と感情の平板化が表れるタイプ
- 緊張型:激しい興奮と昏迷状態が共存するタイプ
「すぐ横になりたくなる」という状態が続き、他にも違和感を覚える症状がある場合は、早めに専門医に相談することが大切です。
すぐ横になりたくなるときの対処法

すぐ横になりたくなるときの対処法として、以下が挙げられます。
- 十分な休息をとる
- バランスの良い食事を心がける
- 適度に運動する
- 規則正しい生活習慣を身につける
- ストレスをため込まない
- 医療機関の受診やカウンセリングを検討する
ここでは上記6つの対処法についてそれぞれ解説します。
十分な休息をとる
すぐ横になりたくなるときは、まずは十分な休息をとりましょう。
特に質の良い睡眠は、脳や筋肉の回復に必要不可欠です。
就寝前はスマホやパソコンの使用を控え、静かな環境でリラックスできる時間を過ごしましょう。
短時間の昼寝も効果的ですが、長すぎると夜の睡眠に悪影響を及ぼすため、20〜30分程度に抑えるのが理想です。
バランスの良い食事を心がける
すぐ横になりたくなるときは普段の食事を見直し、バランスの良い食事を心がけるようにしましょう。
偏った食事は身体のエネルギー不足や栄養の偏りを招き、慢性的な倦怠感の原因となります。
炭水化物・たんぱく質・脂質に加えて、ビタミンB群や鉄分、ミネラルを意識して摂取することが大切です。
糖質中心の食事や過度な加工食品の摂取は血糖値の乱高下を招き、逆に疲れやすくなるため注意が必要です。
栄養バランスの整った食生活を心がけましょう。
適度に運動する
適度に運動することで、血流が促進され、身体全体のエネルギー循環を整えられます。
ウォーキングや軽いストレッチ、ヨガなど、無理のない範囲で身体を動かすことで、倦怠感や気分の落ち込みを軽減できるでしょう。
また、運動は睡眠の質を高める効果もあるため、疲れにくい身体づくりにもつながります。
無理のない頻度で継続することが大切です。
規則正しい生活習慣を身につける
生活リズムの乱れは体内時計を狂わせ、日中の眠気や疲労感を引き起こす原因になります。
毎日決まった時間に起きて、同じ時間に就寝することを意識しましょう。
規則正しい生活習慣を身につけることで体内時計が整い、自然な眠気を誘いやすくなります。
ストレスをため込まない
ストレスは心身の疲労感や倦怠感を引き起こす大きな原因となります。
深呼吸や瞑想、趣味の時間、リラクゼーションなど、自分なりのストレス解消法を見つけることが大切です。
また、誰かに話を聞いてもらうだけでも気持ちが軽くなることがあります。
家族や友人、同僚などの信頼できる人に悩みを相談してみるのも良いでしょう。
医療機関の受診やカウンセリングを検討する
セルフケアを続けても改善が見られない場合は、病気の可能性も視野に入れて医療機関での相談を検討しましょう。
慢性的な疲労感や強い眠気がある場合、内科、心療内科、睡眠外来などの専門医の診察が必要になることがあります。
また、ストレスや心理的要因が関係していると考えられる場合は、臨床心理士やカウンセラーによるカウンセリングも効果的です。
自分一人で抱え込まず、早めに専門家の力を借りることが大切です。
すぐ横になりたくなるときの医療機関の受診目安

すぐ横になりたくなる状態が2週間以上続く場合は、単なる疲労ではなく、何らかの病気が隠れている可能性があります。
特に以下のような症状を伴う場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
- 発熱
- 体重減少
- 強いめまい
- 動悸
- 息切れ
- 気分の落ち込み
- 強い不安
上記に当てはまるものでなくても、日常生活に支障が出ている症状がある場合は、医療機関での適切な診断・治療が必要です。
まずは内科を受診し、必要に応じて循環器内科や精神科、心療内科などの専門家への紹介を受けるのが望ましいでしょう。
もし医療機関を受診するのが億劫という場合には、オンラインカウンセリングで症状を相談してみるのもおすすめです。
すぐ横になりたくなる倦怠感がつらいときは医療機関の受診を検討しましょう
すぐ横になりたくなるような強い倦怠感は、身体や心が限界を知らせているサインかもしれません。
まずは十分な休息や食事、運動などの生活習慣を見直すことが大切ですが、症状が長引いたり日常生活に支障をきたしていたりする場合には早めに医療機関を受診しましょう。
かもみーるでは、医師監修のオンラインカウンセリングサービスを提供しています。
「医療機関を受診すべきか迷っている」という方の相談にも対応しているため、お悩みの方はぜひ当院までご相談ください。
▶︎カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶︎新規会員登録はこちら
