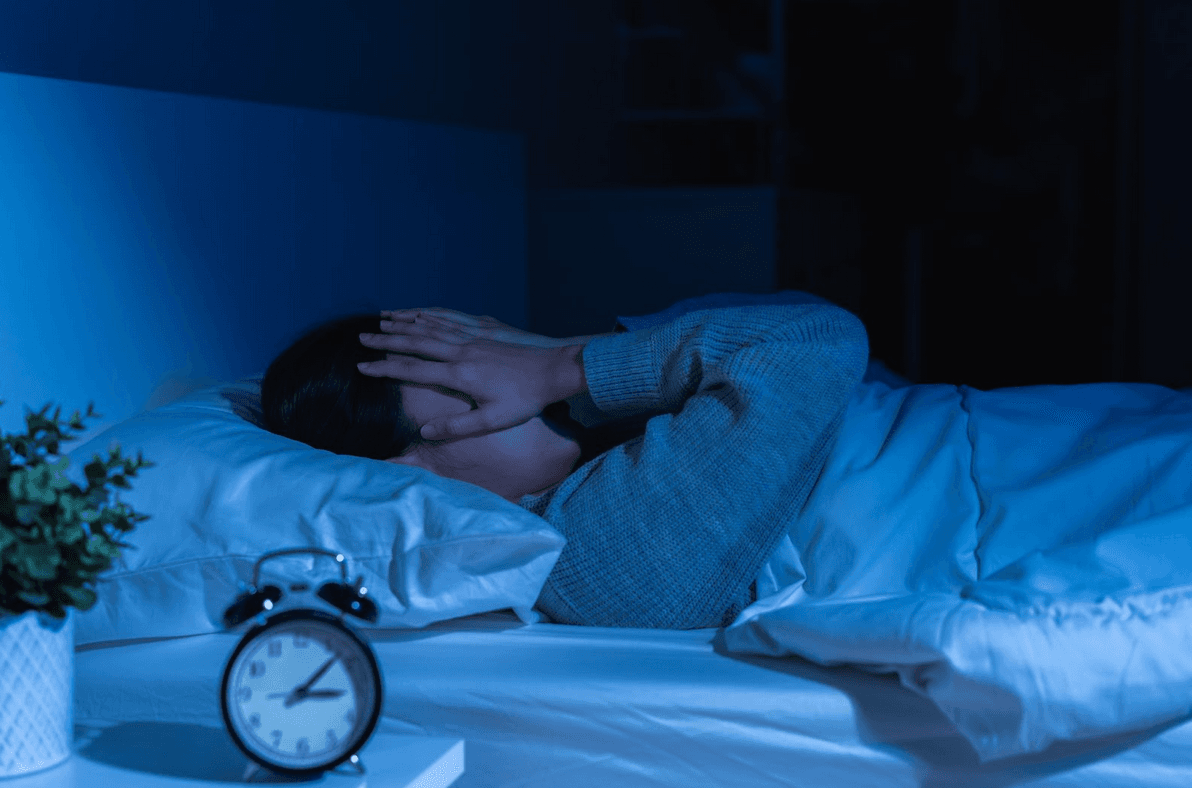「夜になると情緒不安定になったり、将来への不安が押し寄せたりする」
「なぜこんな気持ちになるのだろう?と、さらに不安が強くなる」
このように、昼間は平気なのに、夜になると急に不安感に襲われることはありませんか?
一晩だけのことであれば特に大きな問題ではないとしても、こうした状態が何日も続く場合、心や体に何らかの不調が隠れているのかもしれません。
この記事では、夜になると不安感に襲われる理由や、不安な気持ちをやわらげる方法について詳しく解説します。
また、考えられる病気や、つらいときに医療機関に相談すべきタイミングについても紹介していますので、同じような悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
夜になると急に不安感に襲われるのはなぜ?
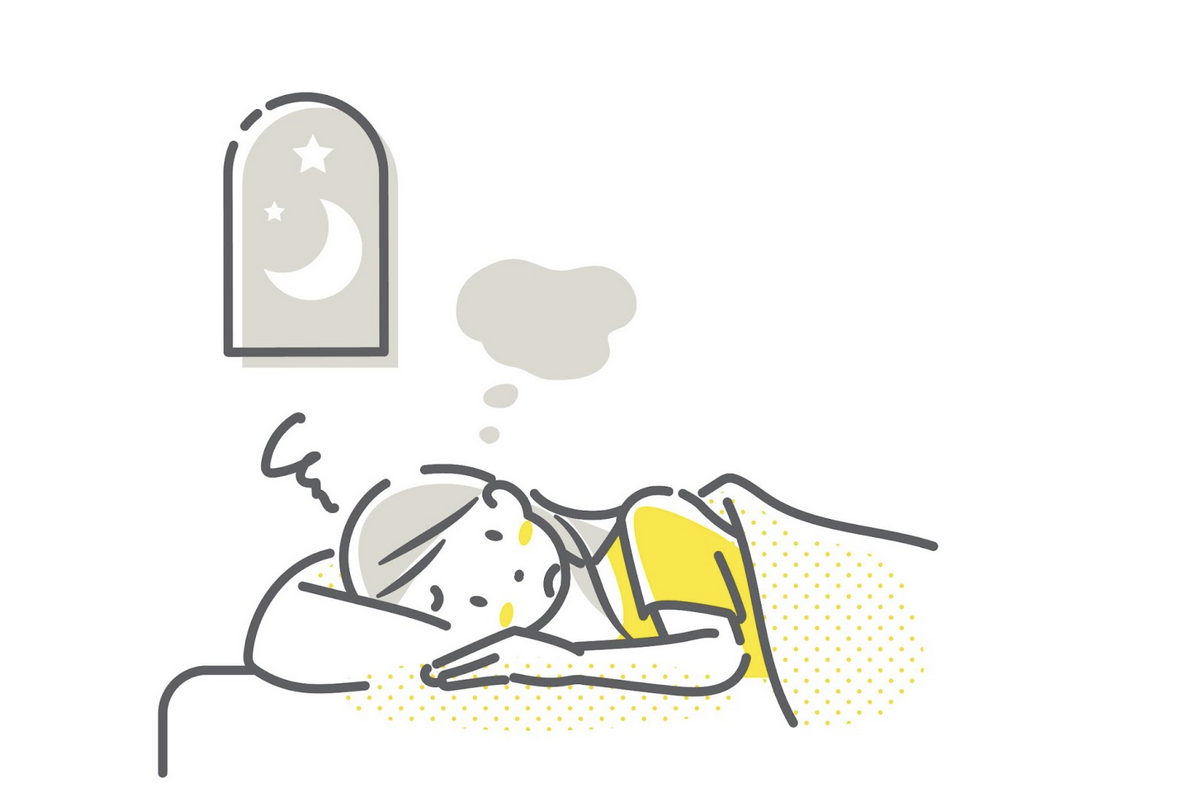
夜になると急に不安感に襲われるーそんな悩みを抱えている人は意外と少なくありません。
なぜ、夜になると不安を感じやすくなるのでしょうか。
心理的・生理的な観点から、夜になると不安になる理由について解説します。
夜になると不安になる理由①緊張がゆるみ、不安が出やすくなる
日中は仕事や家事、育児などで忙しく、やるべきことに追われている人が多いものです。
こうした日中の緊張状態から解放される夜は、心身がリラックスする一方で、ふとした瞬間に不安や孤独感が表面化しやすくなります。
1日の終わりにやっと一人になれたと思ったのに、何だか独りぼっちな気がして、急に不安感に襲われることはありませんか。
リラックスできるはずの時間帯に、不意に不安が押し寄せるというのはよくあることです。
夜になると不安になる理由②考える時間が増え、ネガティブ思考に陥りやすい
夜は一人で過ごす時間が増えることで、自然と1日の出来事を振り返る機会も増えます。
楽しかった出来事を思い巡らすのであれば、それも良い時間となりますが、実際には仕事のミスや人間関係のトラブルなど、ネガティブな記憶に意識が向きやすくなるものです。
「あれでよかったのかな」「あんなこと言わなければよかった」と、後悔や自己否定の思考に陥ることもあるでしょう。
こうした思考の繰り返しが、不安感を強める一因になります。
夜になると不安になる理由③セロトニンとメラトニンのバランスが影響している
日中は、神経伝達物質であるセロトニンが多く分泌されます。
セロトニンは『幸せホルモン』とも呼ばれており、感情や気分を安定させるのに重要な役割を担っている物質です。
朝日を浴びることで分泌が促されますが、夜になるとセロトニンの分泌量が減少し、睡眠を促す『メラトニン』の分泌量が増加します。
このセロトニンの減少が情緒不安定や不安感につながることがあり、特にもともとセロトニン分泌が少ない人は影響を受けやすいとされています。
現代人は屋内で過ごす時間が長く、意識しないと日光をほとんど浴びずに日々を過ごしてしまう方も少なくありません。
そのため、セロトニンの分泌が不足しがちで、夜になると情緒が不安定になりやすいという指摘もあります。
夜になると不安になる理由④自律神経の乱れにより、不安感が強まる
自律神経には、日中に活発になる『交感神経』と、リラックス時に優位になる『副交感神経』があり、この切り替えによって心身のバランスが保たれています。
しかし、ストレスや不規則な生活により自律神経のバランスが乱れると、夜になっても交感神経が優位のままになりやすくなります。
交感神経が過剰に働いていると、常に“戦闘モード”のような状態になり、心も体も休まりません。その結果、不安を感じやすくなるのです。
布団に入ってもドキドキが止まらない、呼吸が浅くて苦しい……そんなときは、自律神経のバランスが乱れているサインかもしれません。
夜になると不安になる理由⑤外的刺激が減り、内面に意識が向きやすい
昼間は音や光、対人関係など多くの刺激にさらされていますが、夜になると周囲は静かになり、外的な刺激が大幅に減少します。
その結果、自分の内面に意識が向きやすくなり、抱えている悩みや過去の記憶を考え込んでしまうことがあります。
「なぜ自分だけうまくいかないのか」「この先どうなってしまうのだろう」といったネガティブな思考が膨らむと、不安感も強くなりやすいでしょう。
夜になると情緒不安定・不安になるのは病気?考えられる心の疾患

夜になると情緒不安定になりやすく、急に不安感に襲われることが繰り返される場合、心の病気が関係している可能性もあります。
ここでは、夜の不安と関連が深い代表的な心の疾患について解説します。
不安障害
不安障害とは、日常生活に支障をきたすほどの過度の不安や心配を感じる精神疾患の総称です。夜になると不安感が強くなるタイプの不安障害には、以下のようなものがあります。
- パニック障害
- 社会不安障害
- 全般性不安障害
それぞれの病気の症状について紹介します。
パニック障害
理由もなく急に強い不安感に襲われて、動悸や息苦しさ、めまいなどの身体症状が現れるのが特徴です。
「このまま死んでしまうのでは」という強い恐怖を感じる方も多く、発作の再発を恐れて夜の睡眠にも影響が出ることがあります。
代表的なパニック発作の症状には以下のようなものがあります。
- 動悸・胸のざわつき
- 息苦しい、過呼吸
- 吐き気・腹部の不快感
- めまい、ふらつき
- 自分をコントロールできない恐怖
- 死への強い恐怖感
パニック障害について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
▶パニック障害とは?主な症状や原因、診断方法・治療法などを紹介
社会不安障害
人からどう見られているかを過剰に気にし、注目される場面で強い不安を感じる病気です。
人前でのスピーチ、初対面の人との会話などで強い緊張や不安が生じ、これを避けようとして対人場面を避けがちになります。
全般性不安障害
家庭、仕事、人間関係などあらゆる場面に対して慢性的な不安や心配が続くのが特徴です。
「常に何かに備えていないと落ち着かない」と感じる人もおり、不安の影響でイライラや集中力の低下、不眠などが現れることもあります。
強迫性障害
自分でも「やりすぎ」とわかっていても、確認や儀式的な行動を繰り返さずにはいられない病気です。
例えば、何度も戸締まりを確認したり、手を何度も洗ったりすることで一時的に不安を和らげようとします。
夜間に「何か悪いことが起きるのでは」と不安が強まり、寝つきにくくなることも少なくありません。
強迫性障害について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
▶強迫性障害で寝るのが怖いと感じる原因は?対処法や治療を解説
うつ病
うつ病は、気分の落ち込みや興味の喪失が続く精神疾患です。
夜になると、過去のつらい記憶を思い出して涙が止まらなくなったり、急に気持ちが沈んだりすることがあります。
不安感や情緒不安定さが発作的に現れることもあり、不眠や過食、自傷行為につながるケースも見られます。
更年期障害
特に40代後半から50代前半の女性に多く見られるもので、ホルモンバランスの変化により、心身のさまざまな不調が生じます。
自律神経の乱れから、不眠や強い不安感、イライラといった症状が出やすく、夜になるとそれらが強まることもあります。
夜、急に不安感に襲われる日が続くなら医療機関へ相談を

夜に不安を感じることがあっても、必ずしも病気が原因とは限りません。
疲労やストレス、ちょっとした心の揺らぎによって、誰でも一時的に気持ちが不安定になることはあります。
ただし、以下のような場合は、心の不調が進行しているサインかもしれません。
- 不安で眠れない夜が続いている
- 感情の波が激しく、日常生活に支障をきたしている
一人で抱え込まず、専門家に相談することが大切です。
夜の不安で病院を受診する目安
「夜に不安になっただけで、病院に行ってもいいのだろうか?」と迷う方もいることでしょう。
確かに一時的な不安や緊張が原因の場合、必ずしも受診が必要とは限りません。
しかし、次のような症状がある場合は、医療機関での相談を検討するようおすすめします。
- 急に不安感に襲われることが週に何度もある
- 不安のせいで眠れない夜が長く続いている
- 動悸・息切れ・めまいなどの身体症状を伴う
- 不安感が強すぎて仕事や家事に集中できない
- 死への強い恐怖や絶望感がある
- 少しずつ悪化しているように感じる
これらに当てはまる場合、早めに専門医のサポートを受けることで回復が早まる可能性があります。
何科を受診すればいい?
急な不安感や情緒不安定といった心の不調で悩んでいる場合、精神科や心療内科の受診が適しています。
どちらを選ぶべきか迷う方は、以下を参考にするとよいでしょう。
- 心療内科:ストレスによる体の不調(胃痛、頭痛、不眠など)が主な場合
- 精神科:不安や気分の落ち込みなど、心の症状が中心の場合
地域によっては「メンタルクリニック」「こころのクリニック」などの名称で専門外来があることもあります。
気になる場合は、ホームページや電話などで診療内容を確認してみるようおすすめします。
夜、急に不安感に襲われたときの対処法

夜になると急に不安感に襲われる場合でも、どうすればよいのか知っておくと、落ち着いて対処しやすくなります。
突然のパニック発作や理由のわからない強い不安感が起こったときは、まずは以下の方法を試してみてください。
深呼吸して呼吸を整える
不安や動悸、息苦しさを感じると、呼吸が浅くなりやすく、過呼吸のような状態になることもあります。
その結果、手足のしびれやめまいなどの症状が起こり、さらに不安が強まってしまうこともあるでしょう。
まずは、ゆっくりと深く呼吸することを意識しましょう。腹式呼吸を意識して、息をゆっくり吸って、長めに吐き出すようにします。
深呼吸は副交感神経の働きを高めることで、心身のリラックスを促す効果が期待できます。
不安な気持ちを紙に書き出す
心の中の不安を頭の中でぐるぐる考えていると、ますます不安感が強くなりがちです。
そんなときは、思い浮かぶ不安を紙に書き出してみましょう。
「何が不安なのか」「なぜそれが気になるのか」といった思考を言語化することで、気持ちの整理がしやすくなります。
書いてみると、意外と具体的な根拠がなかったことに気づいたり、問題を冷静に見直せたりすることもあるものです。
「大丈夫」と自分に声をかける
不安や恐怖が強まっているときは、頭の中でネガティブな想像がどんどん膨らんでしまうことがあります。
そんなときは、「大丈夫」「何も問題ない」などの言葉を、自分に繰り返し言い聞かせてみましょう。
自分にやさしく声をかけることで、不安に傾きそうな気持ちを落ち着ける効果が期待できます。
温かい飲み物で体をリラックスさせる
不安で眠れないときには、カフェインを含まない温かい飲み物をゆっくり飲むこともおすすめです。
例えば、ホットミルクやノンカフェインのハーブティーなどを飲むとよいでしょう。
温かい飲み物には、心を落ち着かせるリラックス効果があるだけでなく、体温を一時的に上げることで、その後の体温低下を促し、自然な眠気を引き出す働きもあります。
人の体は、深部体温がゆるやかに下がるときに眠気を感じやすくなるとされており、こうした温かい飲み物はスムーズな入眠をサポートしてくれるでしょう。
夜不安になる人が不安をやわらげるためにできること

夜、急に不安感に襲われることがしばしばある人は、日中の過ごし方や生活習慣を見直すことで、少しずつ心身の安定を図ることができます。
ここでは、不安の予防・軽減につながる日常の工夫を紹介します。
朝、太陽の光を浴びる
朝日をしっかり浴びることで、心の安定に関わる「セロトニン」の分泌が促進されます。
起きたらまずカーテンを開けて、太陽の光を浴びる習慣をつけてみましょう。曇りの日でも外に出るだけで一定の効果が期待できます。
十分な睡眠と休息をとる
睡眠不足が続くと、自律神経のバランスが乱れ、不安を感じやすくなることがあります。
十分な休息や睡眠をとるために、以下の点を意識してみましょう。
- できるだけ24時前に寝る
- できれば昼間も仮眠して疲れをとる
栄養バランスのとれた食事を意識する
心身の健康には、食事も大切な要素です。栄養バランスを考えたメニューにするとともに、規則正しい時間に食事をとることも意識してみましょう。
また、以下の成分は意識的に摂取するのがおすすめです。
成分 | 働き | 含まれる食品例 |
トリプトファン | セロトニンの材料となる | 肉、魚、大豆製品、乳製品など |
ビタミンB6、マグネシウム | セロトニンの合成に必要な成分 | B6:カツオ、マグロ、牛レバー、バナナなど マグネシウム:わかめ、とろろ昆布など |
また、夕方以降はカフェインやアルコールを控えることで、睡眠の質の改善につながります。
眠りやすい寝室環境を整える
睡眠の質を上げるためには、五感にやさしい環境づくりが大切です。
以下のポイントを見直してみましょう。
- 温度:夏は涼しく、冬は暖かく(エアコンなどを活用)
- 湿度:50~60%が快適な目安(加湿器などを活用)
- 光:照明をできるだけ暗くする。遮光カーテンの利用も効果的
- 音:静かな空間をつくる。耳栓やホワイトノイズを活用
快適な寝室は、夜の不安感を和らげ、入眠をスムーズにする手助けになります。
定期的に運動する
適度な運動には、ストレスの発散や不安の軽減・睡眠の質の向上など、心と体の両面にさまざまな良い影響があります。
運動によって分泌される『セロトニン』や『エンドルフィン』には、気分を安定させたり、心の安らぎをもたらしたりする働きがあります。
おすすめの運動は以下のようなものです。
- ウォーキング
- ジョギング
- ヨガ
- ストレッチ
- 水泳 など
まずは無理のない範囲で、週に2〜3回程度を目安に始めてみるとよいでしょう。
夜、急に不安感に襲われるのが続くなら、医療機関に相談を
夜になると急に不安感に襲われたり、情緒が不安定になったりすることは、誰にでも起こり得ます。
しかし、不安が続いたり日常生活に支障が出たりする場合は、心の不調が関係している可能性も考えられます。
「受診するほどではないかも……」と迷うときは、オンラインで気軽に相談できる窓口を活用してみましょう。
オンライン診療・オンラインカウンセリングに対応している『かもみーる』では、専門の医師やカウンセラーにご自宅から相談できます。
夜の不安をひとりで抱え込まず、気軽にご相談ください。
▶ カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶ 新規会員登録はこちら