強迫性障害の症状に悩んでいる場合、精神科と心療内科のどちらを受診すればいいのでしょうか。
両科とも心の健康を専門とする診療科ですが、それぞれに特徴があり、症状や状況によって適した診療科が異なってきます。
この記事では、強迫性障害の基本的な知識から、精神科と心療内科の違い、医療機関の具体的な選び方まで、実践的な情報をお伝えします。
強迫性障害の症状がある方はもちろん、ご家族や周囲の方々もぜひ参考にしてみてください。
強迫性障害(OCD)とは

強迫性障害は、自分の意思に反して不快な考えが頭に浮かぶ『強迫観念』と、それを打ち消すための行動を繰り返してしまう『強迫行為』が特徴の病気です。
不安障害の一種ともいわれますが、不安や恐怖よりも嫌悪感や道徳心と結びついた症状が多いため、思考や行動の病気として分類されることも増えています。
このような症状は日常生活にどのような影響を与えるのでしょうか。
強迫性障害の症状には、手が不潔に思えて過剰な手洗いを行う、戸締まりやガス栓を何度も確認してしまう、物の配置や対称性へのこだわりが強いなど、さまざまな形があります。
これらの症状により、仕事や学業に支障をきたしたり、人間関係が難しくなったりする場合もあります。
不安障害について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
▶︎不安障害の種類別の症状・診断基準┃セルフチェックや治療法も解説
医療機関を受診するタイミング
強迫性障害の症状に気づいたら、早めの受診をおすすめします。
なぜなら、これらの症状はうつ病や他の病気の初期症状である可能性もあり、また、適切な治療を受けることで改善が期待できるからです。
以下のような状況が当てはまるときは、医療機関への受診を検討しましょう。
- 日常生活への支障が出ている
- 家族や周囲の人を巻き込んでしまっている
- 不安や苦痛が強く自分ではコントロールできないと感じる
例えば、強迫行為に時間を取られ過ぎて睡眠時間が十分に取れない、仕事や学業に遅れが出る、約束の時間に間にあわないなどの問題が生じているケースです。
また、家族に確認行為への付き添いを求めたり、こだわりを押し付けたりして、周囲の人が疲弊してしまう場合もあります。
さらに、『おかしいと分かっているのにやめられない』という状態が続き、精神的な負担が増大することもあります。
このようなときは専門医による適切な診断と治療を受けて、症状の改善をはかることが可能です。
強迫性障害の診療科の選び方

強迫性障害の治療は、精神科と心療内科のどちらでも受診できます。
そのため、はじめて受診する方にとって『どちらの診療科に行けばよいのか』という疑問は自然なものといえます。
両科の違いを理解したうえで、ご自身の症状や生活スタイルにあう診療科を選ぶことが大切です。
精神科と心療内科の違い
診療科の特徴を以下の比較表にまとめました。
項目 | 精神科 | 心療内科 |
|---|---|---|
主な対象 | 精神疾患そのもの | 心身の関連性がある症状 |
治療アプローチ | 薬物療法中心 | 心身両面からのアプローチ |
得意とする症状 | 精神症状が明確な場合 | 身体症状を伴う場合 |
入院対応 | 可能な施設が多い | 原則外来のみ |
精神科は心の症状や病気そのものを専門に治療する診療科です。
強迫性障害をはじめ、うつ病、不安障害、パニック障害などの精神疾患の診療を行います。
一方、心療内科はストレスなどが原因で身体に症状が現れた際の治療を専門としています。
とりわけ不眠や食欲不振、頭痛などの身体症状を伴う場合や、ストレス要因が明らかな場合は心療内科が向いています。
それぞれの特徴と得意分野
精神科の主な特徴は、心の状態そのものに焦点を当て、薬物療法を中心とした治療アプローチを行うことにあります。
強迫性障害に限らず、精神症状が明確な場合は精神科での受診がおすすめです。
また、症状が重いときや入院が必要となる可能性があるときも、精神科での治療が適切です。
心療内科での治療は、心理的なストレスが引き金となって身体症状が出現している際に強みを発揮します。
とりわけ不眠や食欲不振、頭痛などの身体症状を伴う場合や、ストレス要因が明らかな場合は心療内科での受診を検討しましょう。
どちらを選ぶのがよいか?判断のポイント
診療科選びで重要なのは、ご自身の症状や状況にあわせて判断することです。
以下のポイントを参考に選択してみましょう。
【心の症状が主体で身体症状があまりない場合】
精神科を選択するとよいでしょう。
強迫観念や強迫行為が明確で、それらが日常生活に支障をきたしているケースも、精神科での受診をおすすめします。
【ストレスによる身体症状が強く出ている場合】
心療内科が適しています。
心身の関連性を重視した治療を希望する場合も心療内科を受診しましょう。
また、『精神科に抵抗感がある』という方も、心療内科から始めるのも一つの選択肢です。
現在では精神科と心療内科の両方を標榜している医療機関も増えています。
このような医療機関では症状に応じて柔軟な対応が可能となるため、診療科選びに迷うときは、両科をもつ医療機関を選ぶことも検討してみましょう。
強迫性障害を治療する医療機関の選び方
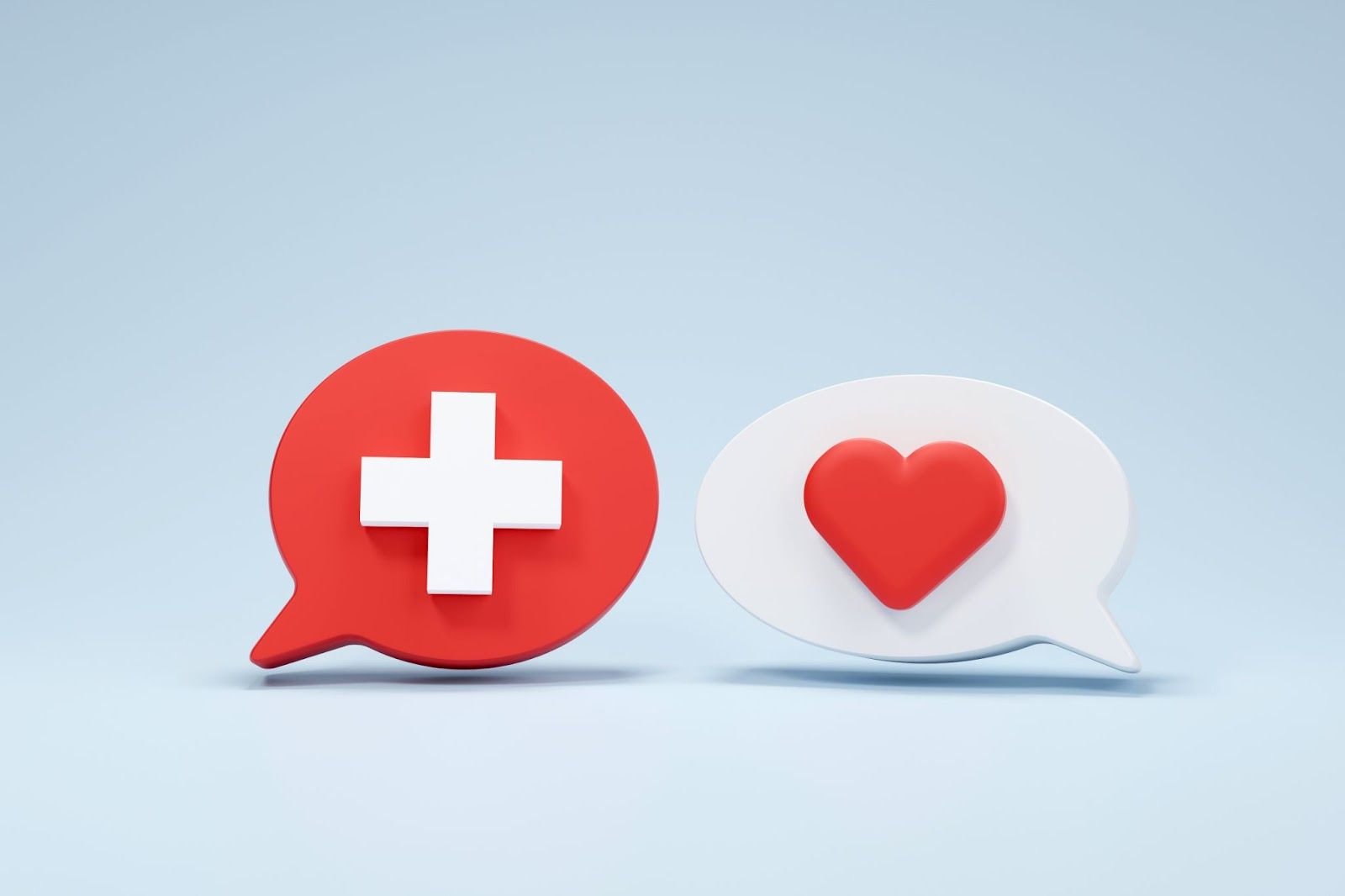
医療機関の選択は治療の成功を左右する重要な要素です。
ただし、心の治療は目に見えにくいため、医療機関の『よい・わるい』を外部から判断するのは簡単ではありません。
そのため、複数の観点から総合的に判断し、ご自身にあった医療機関を見つけることが大切です。
クリニックと総合病院の違い
クリニックは地域に密着した外来診療が中心の医療機関です。
アットホームな雰囲気で、医師とのコミュニケーションが取りやすい環境が特長です。
外来診療で対応可能な症状であれば、クリニックでの治療も十分な選択肢となります。
一方、総合病院や精神科病院は、より専門的な治療や入院治療が必要なケースに対応できます。
とりわけ症状が重い場合や自傷他害のリスクがある場合は、入院設備のある医療機関での受診が望ましいでしょう。
通院のしやすさを重視する理由
強迫性障害の治療では、定期的な通院が欠かせません。
週に1回〜2回程度の診察が必要になるケースも多く、通院の負担が大きいと治療の継続が難しくなる恐れがあります。
自宅や職場から通いやすい場所にあることはもちろん、診療時間がご自身の生活リズムにあっているかどうかも重要な判断材料です。
夜間診療や土日診療を行っている医療機関であれば、仕事や学業との両立がしやすくなるでしょう。
オンライン診療の活用
近年、オンライン診療を導入する医療機関が増えています。
働きながら通院する方や、遠方にお住まいの方にとって、オンライン診療は通院の負担を軽減する有効な選択肢となるでしょう。
例えば、『かもみーる心のクリニック』では、オンライン診察の新施設基準に対応し、厚生労働省の指針に沿った診療を提供しています。
さらに24時まで医師が待機する夜間診療体制や、当日初診への対応など、患者さんの生活スタイルにあわせた柔軟な診療体制を整えています。
強迫性障害の治療を受ける病院選びの5つのチェックポイント

医療機関を選ぶ際には、複数の観点から総合的に判断するのが重要です。
単なる評判だけではなく、実際の治療環境や体制を確認することによって、ご自身にあった医療機関を見つけられます。
以下の5つのポイントを参考に、医療機関選びを進めていきましょう。
1. 診療時間と予約システム
診療時間は治療を継続するうえで重要です。
通院には定期的な時間の確保が必要となるため、ご自身の生活リズムにあった診療時間を提供している医療機関を探しましょう。
夜間診療や休日診療の有無、予約制か否かも確認が必要です。
予約制の場合、予約方法や待ち時間の目安も確かめておくとよいでしょう。
2. カウンセリングの有無
強迫性障害の治療では、薬物療法に加えて認知行動療法などの心理療法が効果的です。
そのため、医師による診察だけでなく、心理士によるカウンセリングが利用できる環境があるかどうかも、選択の基準となるでしょう。
診察とカウンセリングの併用で、より包括的な治療アプローチが可能となります。
カウンセリングは保険適用外となる場合もあるため、費用面での確認も必要です。
3. 医師の専門性と経験
医師の専門性は治療の質に直接関わる要素です。
精神保健指定医や精神科専門医の資格を持っているか、強迫性障害の治療経験が豊富かどうかを確認するのも大切です。
医師の経歴や治療方針は、医療機関のWebサイトなどでチェックできる場合があります。
ただし、外来での治療経験やコミュニケーション能力も重要な要素となるため、実際の診察を通じて相性を確認することも必要です.
4. 設備や治療法の選択肢
医療機関によって利用できる治療法や設備は異なります。
薬物療法、認知行動療法、その他の心理療法など、どのような治療選択肢があるかを確認しましょう。
なかでも強迫性障害やうつ病の治療として注目されているのが、TMS(反復経頭蓋磁気刺激法)治療です。
この治療法は、従来の薬物療法とは異なり副作用がほとんどない点が特長です。
ただし、実施できる医療機関が限られていて、自費診療となる場合が多いため、治療費用や通院頻度などを事前に確かめる必要があります。
港区の『かもみーる心のクリニック』では、1回あたり2,980円でTMS治療を実施しています。
治療前に脳波検査を受けることも可能なため、詳しくはお問い合わせください。
将来的な治療の選択肢を広げるためにも、充実した治療体制をもつ医療機関を選ぶことをおすすめします。
TMS治療について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
▶︎TMS治療は比較的新しい治療法のため、研究結果によって効果があることは実証されていても、広く認知はされていません。
▶︎TMS治療は何に効く?効果や適応疾患&メリット・デメリットを紹介
5. 費用と保険制度の対応
治療費用も重要な検討事項です。
保険診療が基本となりますが、カウンセリングなど保険適用外の治療を行う際は追加の費用が発生します。
また、傷病手当や自立支援医療制度の利用が可能かどうかも確認しましょう。
これらの制度を利用すると、医療費の負担を軽減できる場合があります。
強迫性障害の治療についてのよくある疑問と注意点
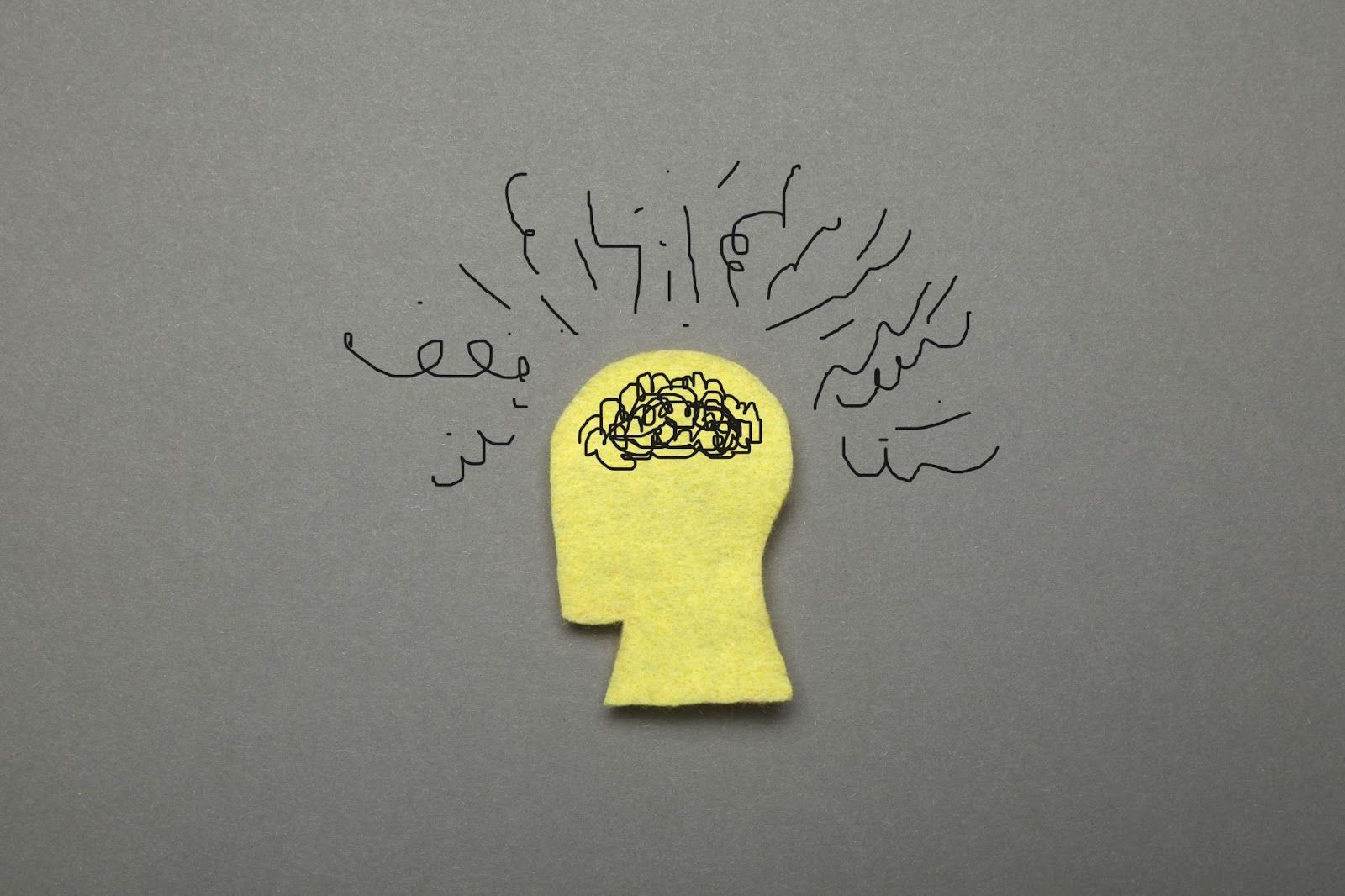
強迫性障害の治療を始めるにあたって、多くの方がさまざまな不安や疑問を抱えています。
ここでは、医療機関の受診に関する一般的な疑問と、知っておきたい注意点について説明します。
初診時に伝えること
初診では、医師にご自身の状況を正確に伝えるのが重要です。
強迫観念や強迫行為の内容、それらが日常生活に与えている影響について、具体的に説明しましょう。
【初診時の確認リスト】
- 症状の具体的な内容
- 症状が始まった時期
- 症状が出現する状況
- 日常生活への影響
- 現在服用中の薬
- 過去の治療歴
- 家族歴 など
事前にメモを準備しておくとスムーズです。
いつから症状が始まったのか、どのような場面で症状が出やすいのか、これまでの経過などを整理しておくとよいでしょう。
また、服用している薬がある場合は、その情報も忘れずに伝えましょう。
家族の同伴は必要?
家族の同伴については、状況に応じて判断するとよいです。
強迫性障害では、本人が気づいていない症状の変化を家族が把握していることがあります。
また、家族を症状への対応に巻き込んでしまっている場合は、家族からの情報提供が治療方針の決定に役立つケースもあります。
ただし、必ずしも初診から家族の同伴が必要というわけではありません。
一人での受診に不安があるときや、家族に症状を理解してもらいたいときは、同伴を検討してみましょう。
転院を考えるタイミング
医師と相性があわない、治療効果を実感できないなど、現在の医療機関での治療に不安を感じることもあるかもしれません。
このような場合、転院を検討するタイミングとなります。
ただし、すぐに転院を決断する前に、現在の主治医に治療に関する不安や疑問を相談してみるのをおすすめします。
コミュニケーションを通じて問題が解決するケースも少なくありません。
強迫性障害は自分に合った診療科で治療しましょう
強迫性障害の治療において、適切な医療機関を選ぶことは重要な第一歩です。
精神科と心療内科それぞれの特徴を理解し、ご自身の症状や生活スタイルにあった診療科を選びましょう。
また、通院のしやすさや治療体制、医師との相性など、複数の観点から医療機関を検討することによって無理なく継続的な治療が可能となるでしょう。
医師監修のオンラインカウンセリングサービス『かもみーる』では、強迫性障害をはじめとするメンタルヘルスの治療に対応しています。
オンライン診察だけでなく、港区虎ノ門の『かもみーる心のクリニック』で対面診療も行っていて、お仕事で忙しい方でも通院しやすい環境を整えています。
強迫性障害でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
▶︎ カウンセラー(医師・心理士)一覧 はこちら
▶︎ 新規会員登録 はこちら
