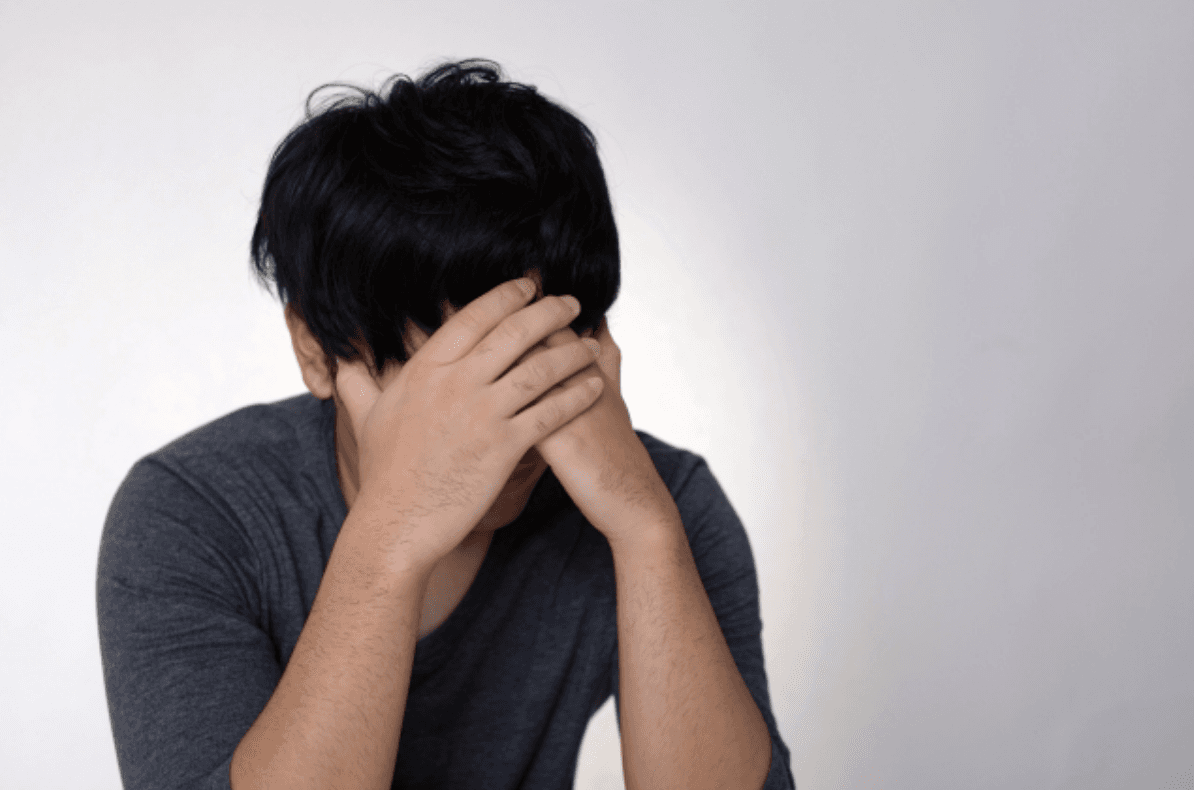ふとした瞬間に理由もなく不安に襲われると「自分はどこかおかしいのでは?」と不安になることもあるかもしれません。
このような急な不安感は誰にでも起こりうるものですが、もし頻繁に続いたり、日常生活に影響が出ているようであれば、原因を知り、適切に対処していく必要があります。
この記事では急な不安感にどう対処すればよいのか、不安の原因や落ち着くための応急処置、考えられる心の病気をご紹介します。
さらに、日常生活でできる予防法も詳しく解説します。
突然不安に襲われる主な原因

突然、不安感に襲われるとき、それは心や身体に負担がかかっているサインかもしれません。
過度なストレスや過去のつらい経験、身体の不調、自律神経の乱れなど、さまざまな要因が不安感を引き起こすきっかけになります。
ここからは、急な不安が生じる心理的・身体的な原因について、具体的に見ていきましょう。
限界を超えるような強いストレス
仕事の重圧や学業の悩み、人間関係のストレス、経済的不安、将来への漠然とした心配など、さまざまなストレスが積み重なると、心は常に緊張した状態になります。
こうした慢性的なストレスに加え、プレゼン直前や試験当日、苦手な人からの連絡といった突発的な出来事が加わると、不安感が一気に表に出てくることがあります。
不安は、心や身体がストレスに耐えきれなくなったときに「これ以上は無理」というサインとして現れるのです。
心に残る過去のつらい経験
過去に強い恐怖や苦しみを伴う出来事を経験した場合、その記憶が心の中に深く刻まれ、完全に処理されずに残っていることがあります。
例えば事故や災害、いじめ、家庭内での不和など、強い感情を伴った体験です。
日常の中のちょっとした出来事や言葉がその記憶を刺激し、突然不安感として現れることがあります。
普段は意識していなくても、特定の音や匂い、場所、状況などが引き金となって、当時の感情が突然よみがえり、不安感として現れる場合があります。
自分では乗り越えたつもりでも、心の奥で処理しきれていない場合、不安という形で再び浮かび上がってくるのです。
これは、脳がかつての危険を再び察知し、自分を守ろうとする防御反応の1つです。
自律神経の不調
自律神経は、心拍や呼吸、体温調節、消化など、私たちが意識しなくても身体のさまざまな機能をコントロールしている重要な仕組みです。
活動時に働く「交感神経」と、リラックス時に働く「副交感神経」がバランスを保ちながら、健康な状態を維持しています。
しかし、ストレスや疲労、生活リズムの乱れなどが続くと、このバランスが崩れ、交感神経が過剰に働いてしまうことがあります。
すると、動悸、息苦しさ、発汗、震え、めまい、吐き気などの身体症状が現れ、それを脳が「何か危険が迫っている」と誤って判断してしまい、不安や恐怖の感情が強まるのです。
自律神経の不調は目に見えにくいぶん、自覚しにくいのが特徴です。
不安感の背後には、こうした心身のバランスの乱れが隠れていることも少なくありません。
生活リズムが乱れている状態
生活リズムの乱れは、不安感を引き起こす大きな要因のひとつです。
夜更かしや不規則な食事、昼夜逆転の生活が続くと体内時計が乱れ自律神経のバランスが崩れやすくなります。
特に、夜勤の多い働き方や、海外旅行による時差ボケなどは、こうしたバランスの乱れを引き起こし、一時的に強い不安を感じる原因となることもあります。
その結果、ストレスへの耐性が下がり、些細なことでも強い不安を感じやすくなるのです。
日々の生活の中で、睡眠・食事・活動のリズムを整えることは、心の安定を保つためにとても重要です。
急な不安感を和らげるための応急処置

急に不安感に襲われたとき、どうすればよいかわからず戸惑ってしまう方も多いはずです。
そんなときは、これからご紹介する「すぐにできる応急処置」を試してみてください。
不安な気持ちに振り回される前に、できることから始めてみましょう。
呼吸を整える
不安やパニックを感じているときは、呼吸が浅く速くなりやすく、その状態がさらに緊張を強めてしまいます。
そんなときは、意識してゆっくりと深く呼吸をすることで、緊張状態を引き起こす交感神経の働きを抑え、リラックスを促す副交感神経の働きを高めることにつながります。
特に「腹式呼吸」がおすすめです。
- まずは、リラックスできる姿勢で座るか横になり、片手をお腹に、もう片方の手を胸にそっと当てる
- 鼻からゆっくり息を吸い、お腹が膨らむのを感じる(約4秒)。このとき胸はあまり動かないように意識する
- 次に、息を数秒止め(約7秒)、口からゆっくり息を吐きながらお腹をへこませていく(約8秒)
この「4-7-8呼吸法」を数回繰り返すことで、自然と心が落ち着いていきます。
安心できる環境への一時避難
突然強い不安に襲われたときは、今いる環境を見直してみましょう。
人混みや騒音、強い光など、周囲の刺激が不安を強めている可能性があります。
そんなときは、できるだけ静かで落ち着ける場所に一時的に避難することが効果的です。
自宅の一室やトイレ、車の中など、ひとりで安心できる空間に移動するだけでも、心が少しずつ落ち着いてくることがあります。
まずは安心できる環境を確保しましょう。
不安感が強いときに考えられる心の病気
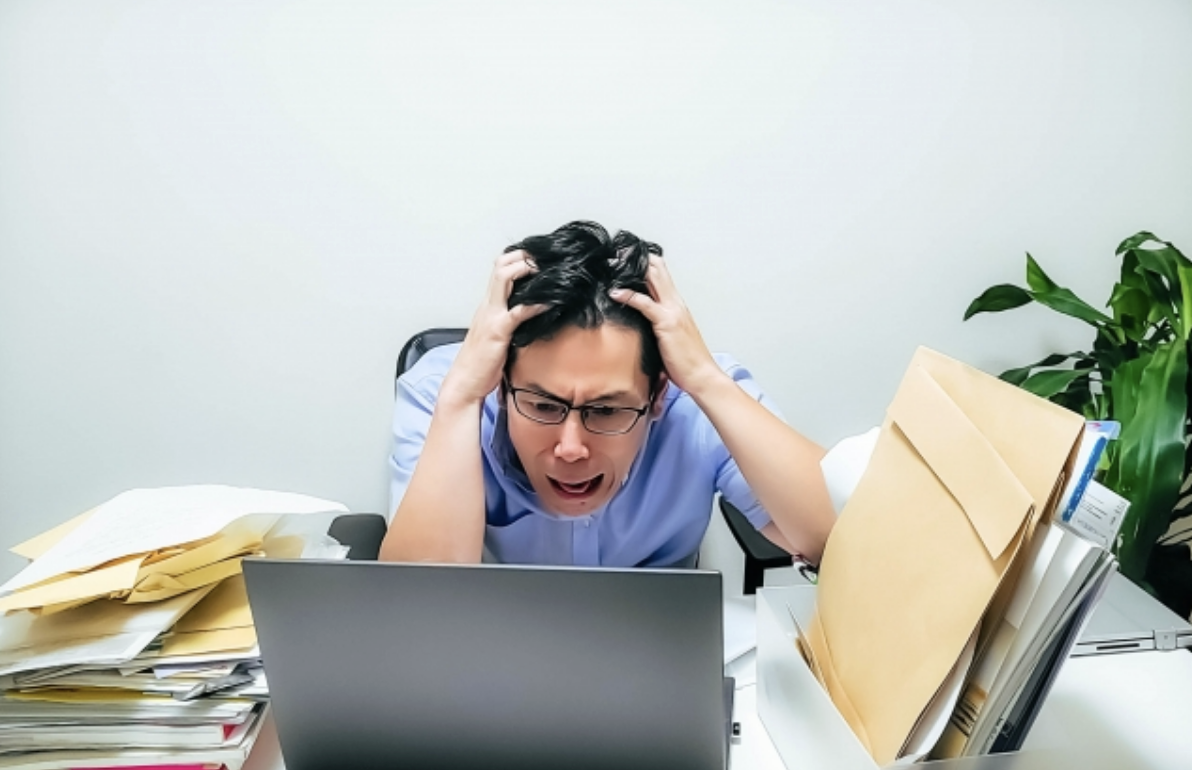
急に強い不安感に襲われる場合、その背景に心の病気が隠れていることもあります。
パニック障害や全般性不安障害、PTSD、強迫性障害、適応障害などは、不安を主な症状とする代表的な疾患です。
これらの病気は、日常生活に影響を及ぼすほどの不安や緊張を引き起こすことがあり、気づかないうちに心が悲鳴を上げているケースも少なくありません。
ここからは、不安感と関係が深い主な心の病気について解説します。
パニック障害
パニック障害は、ある日突然、強い不安や恐怖に襲われる「パニック発作」が繰り返し起こる精神疾患の1つです。
発作のたびに本人は「このまま死ぬのではないか」と感じるほどの激しい身体的・精神的苦痛を経験します。
パニック発作は突然始まり、短時間でピークに達するのが特徴です。
動悸や息苦しさ、めまい、吐き気、手足の震え、胸の圧迫感など、心臓発作や呼吸困難と似た症状が1度に複数現れるため、救急車を呼ぶ人も少なくありません。
しかし検査を受けても、身体には異常が見つからないことが多く、「何が原因か分からない恐怖」がさらに不安感を強めてしまうことがあります。
発作を1度経験すると、「また起きたらどうしよう」という不安(予期不安)が常に頭から離れなくなり、発作が起きそうな場所や状況を避けるようになってしまいます。
症状が進むと、電車やバス、映画館、美容室、人混みなど、その場を離れづらかったり助けを求めにくい状況に対して強い恐怖を感じるようになり、日常生活に支障をきたすこともあるのです。
このような状態を「広場恐怖」と呼び、外出が困難になるケースもあります。
全般性不安障害
全般性不安障害(GAD)は特定の出来事や状況に限らず、日常のささいなことに対しても過剰に不安や心配を抱き続けてしまう心の病気です。
パニック障害のように突然強い発作が起こるわけではなく、漠然とした不安が常に頭から離れず、それを自分でコントロールできないのが特徴です。
さらに、不安に伴って落ち着きのなさや疲れやすさ、集中力の低下、イライラ感、肩こり・頭痛などの身体症状、睡眠の問題などがあらわれることも少なくありません。
GADの方は「もし〇〇だったら…」といった現実には起きていない未来への過度な不安に悩まされる傾向があり、その状態が6ヶ月以上続き、生活に支障をきたす場合に診断されます。
慢性的な不安が続く中で、特定のきっかけにより不安感が一時的に強まることもあり、日常生活を安心して送るためには、専門機関への相談も重要です。
▶不安障害は治るのか?自力での対処法と病院での治療方法について解説
心的外傷後ストレス障害(PTSD)
心的外傷後ストレス障害(PTSD)は、命に関わるような重大な出来事を経験した後に発症することがある心の病気です。
例えば交通事故や自然災害、暴力や犯罪の被害、虐待、戦争などの強い恐怖や無力感を伴う体験が心に深く刻まれ、時間が経ってもその影響が続くのが特徴です。
PTSDの症状として代表的なのが「フラッシュバック」です。
これは、当時の記憶や感情が突然よみがえり、まるで今まさに同じ体験をしているかのように感じる現象です。
その際には、強い恐怖や不安だけでなく、動悸、発汗、息苦しさなどの身体的反応も現れることがあります。
また、トラウマとなった出来事を思い出させる場所や人、状況を避けるようになったり、常に警戒して気が休まらず、眠れない、集中できないといった状態が続くこともあります。
強迫性障害
強迫性障害(OCD)は、自分でも「やりすぎかもしれない」と分かっていながら、不安を抑えるために同じ行動を繰り返してしまう心の病気です。
例えば「鍵をちゃんと閉めたはずなのに、閉め忘れたのでは?」という不安にとらわれ何度も確認してしまう強迫観念や、「手にばい菌がついている気がして仕方がない」と感じ、何度も手を洗うといった強迫行為が代表的です。
こうした強迫行為は、一時的に不安を和らげるために行われますが、根本的な不安を解消することはできず、次第にエスカレートしていく傾向があります。
やめようとすると強い不安や不快感に襲われ、生活に大きな支障をきたすこともあります。
本人にとっては非常に辛く、周囲の理解も得られにくいため、1人で悩みを抱えてしまうケースも少なくありません。
強迫性障害は適切な治療で改善が見込めるため、早めの相談が重要です。
日常生活からできる不安の予防策

不安感を和らげるためには、応急処置だけでなく、日頃の生活習慣や考え方を見直すことも大切です。
睡眠や食事、運動などの基本的な生活リズムを整えることに加え、思考の癖や刺激の多い習慣を見直すことで、心が不安定になりにくい状態をつくることができます。
ここからは、日常生活の中で実践できる不安の予防法を紹介します。
生活リズム(睡眠・食事・運動の見直し)を整える
不安感を予防するためには、日々の生活リズムを整えることがとても大切です。
特に、睡眠・食事・運動の3つは、心と身体の健康を支える基本です。
まず、毎日同じ時間に寝て同じ時間に起きるなど、規則正しい生活習慣を心がけることで、体内時計が整い、自律神経のバランスも安定しやすくなります。
睡眠の質を高めるためには、就寝前にカフェインやアルコールを避けたり、スマホの使用を控えたりすることも効果的です。
また、ウォーキングやヨガなど、自分が無理なく続けられる運動を取り入れることで、ストレスホルモンの分泌が抑えられ、気分を安定させる脳内物質(セロトニンやエンドルフィンなど)の分泌が促されます。
さらに、栄養バランスの取れた食事も欠かせません。
血糖値の急激な変動を防ぐために、砂糖やカフェインの摂取を控え、たんぱく質や複合炭水化物、良質な脂質をバランスよく取り入れましょう。
野菜や果物などビタミン・ミネラルを含む食品を意識的に選ぶことも、不安を感じにくい身体づくりにつながります。
日々の小さな心がけが、心の安定に大きく貢献します。
思考の癖の修正
不安感は、出来事そのものよりも、それに対する捉え方によって強く左右されます。
例えば、「うまくいかなかったらどうしよう」といった悲観的な予測や、「〜すべき」といった極端な思い込みがあると、不安を感じやすくなります。
こうした思考パターンは、自分でも気づかないうちに身についていることが多く、無意識のうちに心を苦しめてしまうことがあるのです。
このような思考の癖を見直す方法として、認知行動療法が知られています。
これは、非現実的な思い込みに気づき、より現実的で柔軟な考え方に修正していく心理療法です。
思考の視点を少し変えるだけでも、不安に対する感じ方が和らぐことがあります。
考え方を整えることは、不安を予防し、心を軽く保つうえで非常に有効な方法です。
急な不安と向き合うために大切なこと
急な不安感に襲われるのは、決して珍しいことではなく、誰にでも起こりうる心と身体からのサインです。
原因を知り、適切に対処することで、その不安は少しずつ和らげていくことができます。
今回ご紹介した応急処置や原因、予防法は、日々の生活の中でも実践できるものばかりであるため、ぜひ実践してみてください。
しかし、不安が続いたり、程度が強くなったりする場合は、専門医のサポートが必要かもしれません。
『かもみーる』では、オンライン診療・オンラインカウンセリングを提供しており、専門の医師や公認心理師による相談が夜24時まで可能です。
通院が難しい方や、夜間に不安が強まる方でも、オンラインならでは柔軟さを活かして診察やカウンセリングが受けられます。
「自分がおかしいのかも」と悩まず、一歩ずつ取り組んでみましょう。
▶︎カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶︎新規会員登録はこちら