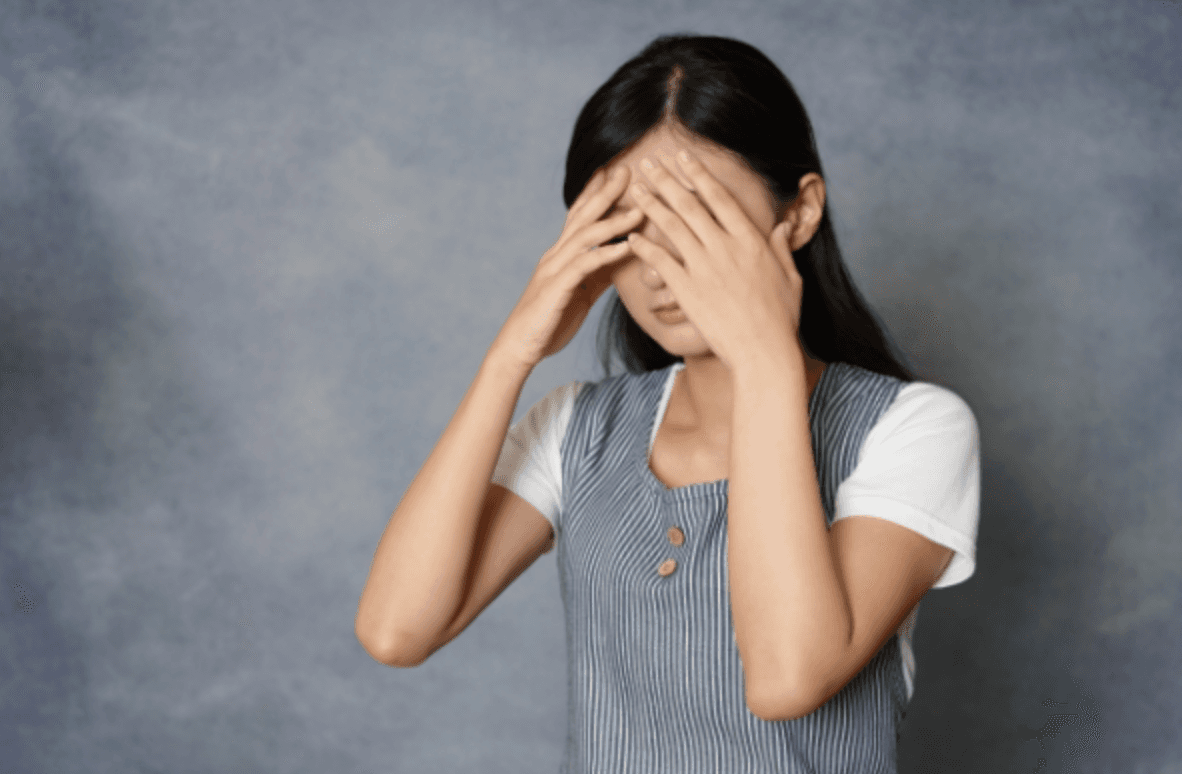「最近、涙もろくなった」「ふとした瞬間に涙がこぼれる」と思う方は、ストレスによって心や身体が限界を迎えているサインの可能性があります。
無意識にため込んでいる感情や疲れが、涙という形で現れることは少なくありません。
この記事では、ストレスによって涙が出る仕組みや背景、考えられる心の病気、すぐに試せる5つの対処法、医療機関を受診すべきサインを詳しく解説します。
「どうしてこんなに涙が出るのだろう」と感じている方は、自分を責めず、まずはこの記事を通して心の状態に気づくことから始めましょう。
なぜストレスで涙が出るのか?その仕組みと背景

ストレスには、脳の扁桃体や自律神経の働きが大きく関与します。
ストレスが高まると、感情の処理を担う扁桃体が過剰に反応し、副交感神経が優位になった瞬間に涙があふれることがあります。
これは身体がストレスから回復しようとする自然な反応です。
また、感情を抑え込んで我慢する生活が続くと、心の中に蓄積されたストレスや未処理の感情が、ふとした瞬間に涙として表れることもあります。
つまり、「涙が出る=心が弱っている」というよりも、心と身体がストレスに耐えてきた証でもあるのです。
この仕組みを知ることで、自分の涙を責めるのではなく、心の声に気づくきっかけにしていきましょう。
涙が出るのはストレスのせい?まずはセルフチェックしてみよう

ストレスが原因で涙が出ることが多いと感じたときは、まず自分の状態を簡単にチェックしてみるのがおすすめです。
厚生労働省では、職場におけるストレスの程度を確認できるセルフチェックリストを公開しており、57の質問に答えるだけで、現在のストレスレベルを把握できます。
所要時間は5分ほどで、すべて選択式なので気軽に取り組むことができます。
結果としてストレスが高いと出た場合はもちろん、数値が低くても「なんとなくつらい」「涙が止まらない」といった状態が続くようなら、無理をせず早めに医療機関への相談を検討してください。
自分の心の状態を知ることが、回復への第一歩です。
ストレスで涙が出るときにできる5つの対処法

ストレスで涙が出るときは無理に止めようとせず、自分に合った方法で心を整えることが大切です。
以下、すぐに実践できる5つの対処法をご紹介します。
- 泣くことを我慢せず「泣ける場所」を作る
- 心の中を紙に書き出して見える化する
- 呼吸法やマインドフルネスを取り入れる
- 生活リズムを整えて心の余白をつくる
- 信頼できる人に話す、話せないなら専門機関へ
詳しく見ていきましょう。
①泣くことを我慢せず「泣ける場所」を作る
涙が出そうなのに「ここで泣いてはいけない」と我慢している方は少なくありません。
しかし、涙を流すことには心を落ち着ける効果があるとされています。
人は強いストレスを感じたとき、涙を通じてコルチゾールなどのストレスホルモンを外に排出し、心のバランスを整えようとします。
これは「泣くこと」が感情調整機能の一部であることを示しています。
特に、感情を抑えがちな人は、意識的に安心して泣ける空間や時間をつくることが大切です。
誰にも見られない場所や、自分だけのリラックスできる空間で涙を流すことは、自分を守るセルフケアのひとつです。
無理に泣く必要はありませんが、「泣いていいんだ」と自分を許すだけでも、心は少し軽くなります。
感情を否定せず、受け入れることからはじめていきましょう。
②心の中を紙に書き出して見える化する
モヤモヤした感情や頭の中にある思考を紙に書き出すことは、ストレスの軽減や自己理解に効果があるとされています。
書き方に正解はありません。箇条書きでも、まとまっていなくても構いません。
大切なのは「感じたことを言葉にする」ことです。
「なぜ泣いてしまったのか」「何がつらかったのか」を紙に書いて見える化することで、自分でも気づけなかった本音や原因が浮かび上がることがあります。
続けるうちに、心の奥にあった不安やストレスの正体が見えてきて、涙のコントロールにもつながっていくはずです。
感情の整理ができると、同じような場面で涙が出そうになっても冷静に対応できるようになるでしょう。
③仕事の取り組み方を工夫してみる
仕事のストレスは避けられないものと思いがちですが、実はちょっとした工夫で軽減できることも多いです。
まずは、自分の働き方を振り返ってみましょう。スケジュールの立て方や作業の優先順位を見直すだけでも、無駄な負担が減り、効率がぐっと上がります。
また、1人で抱え込まずに、上司や同僚に相談してみるのも有効です。人に話すことで気持ちが整理されるだけでなく、新しい視点やヒントが得られることもあります。
さらに、自分の思考のクセを見つめ直すことも大切です。完璧を求めすぎたり、物事を極端に捉えたりする傾向が、知らず知らずのうちにストレスを強めているかもしれません。
仕事の進め方や考え方に少しずつ柔軟さを取り入れることで、心も軽くなっていきます。
④生活リズムを整えて心の余白をつくる
不規則な生活習慣は、心と身体のバランスを崩し、感情のコントロールを難しくさせる大きな要因になります。
毎日しっかりと睡眠をとり、朝は日光を浴びることで体内時計(サーカディアンリズム)が整い、自然なリズムで一日を過ごしやすくなります。
さらに、栄養バランスのとれた食事を意識することも、心身の安定には欠かせません。
また、ストレスを和らげるためには、ウォーキングやヨガ、軽いジョギングなどの無理のない運動を日常生活に取り入れるのがおすすめです。
運動によって分泌される「セロトニン」と呼ばれる脳内物質は、心を安定させる働きを持ち、気持ちを穏やかにしてくれます。
こうした習慣を積み重ねることで、心も徐々に落ち着き、前向きな気持ちを取り戻しやすくなるでしょう。
⑤信頼できる人に話す、話せないなら専門機関へ
ストレスで涙が止まらないときは、信頼できる人に話すことが大きな助けになります。
特に「もうどうしていいかわからない」と感じているときは、できるだけ早めに誰かに相談してみてください。
ひとりで抱え続けてしまうと、心身の不調が深刻化し、仕事や日常生活に大きな影響を及ぼすことも少なくありません。
そうなる前に手を差し伸べてもらうことで、回復にかかる時間や負担を軽減できる可能性が高まります。
身近に話せる人がいない場合、専門機関に相談しましょう。
外部の相談先を探したい場合は、公的な「相談窓口案内」などの情報を活用することができます。厚生労働省が運営する「こころの耳 相談窓口」も、心の不調に関する相談先として利用可能です。
急に涙が出るときに考えられる心の病気

涙があふれてしまう背景には、心の病気が隠れていることもあります。
ここでは、以下の精神的な不調や疾患について5つ、その特徴や関係性をわかりやすく解説します。
- 適応障害
- うつ病
- 自律神経失調症
- PTSD
- 双極性障害
詳しく見ていきましょう。
適応障害
適応障害は、仕事や人間関係、生活環境の変化などにうまくなじめず、強いストレス反応が出る心の病気です。
突然涙が出たり、気分が落ち込みやすくなることもあり、それがサインのひとつとされています。
ストレスの原因が明確で、それに対する反応として抑うつ・不安・涙もろさなどが現れるのが特徴です。
うつ病と異なり、原因となる状況から距離を取ることで改善が見られる場合があります。
ただし、そのままにしておくと慢性化することもあるため、注意が必要です。
▶適応障害とは?再発率や兆候・繰り返さないための対策・復職時の注意点を解説
うつ病
うつ病は、心のエネルギーが極端に低下した状態で、気分の落ち込みや興味の喪失、倦怠感などが続く病気です。
理由もなく涙が出る、感情をコントロールできないといった症状もよく見られます。
特に「なぜ泣いているのかわからない」と感じるときは、心の不調が深く進んでいるサインかもしれません。
症状が2週間以上続く場合、日常生活や仕事に大きな支障をきたす可能性があります。
食欲不振や睡眠障害などの身体的な変化が伴うことも多く、放置すると回復までに時間がかかることもあるため注意が必要です。
自律神経失調症
自律神経失調症は、ストレスや生活リズムの乱れによって、自律神経のバランスが崩れることで起こる不調です。
交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかなくなり、身体と心の両方にさまざまな症状が現れます。
涙が突然出る、感情の起伏が激しくなるといった状態も、その一環といえるでしょう。
不眠や動悸、胃腸の不調、倦怠感などを伴うことが多く、気分の落ち込みや不安感が強くなるケースもあります。
見た目には異常がわかりにくいため、周囲から理解されにくいというつらさを抱える人も少なくありません。
症状が長引くと日常生活に支障をきたすこともあるため、まずは休息と生活習慣の見直しから始め、必要に応じて心療内科や内科に相談するとよいでしょう。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)
PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、命の危険を感じるような強い衝撃や恐怖体験をきっかけに発症する心の病気です。
災害、事故、暴力、いじめなどが原因となり、時間が経ってから突然涙があふれる、感情が不安定になるといった症状が現れることもあります。
過去の出来事が何度も頭に浮かんだり、同じ状況を避けようとしたりする「再体験」や「回避」も特徴のひとつです。
日常生活に支障をきたすほどの不安や緊張が続く場合は、早期の受診が望まれます。
トラウマ体験が他人には理解されにくいこともあり、ひとりで抱え込んでしまう人も少なくありません。
双極性障害
双極性障害は、気分が高揚する「躁(そう)」の時期と、落ち込む「うつ」の時期を繰り返す心の病気です。
うつ状態のときには、突然涙が出たり、何をしても楽しめない、意欲がわかないといった症状が見られます。
一方で、躁状態では気分が異常に高ぶったり、考えが次々と浮かんで止まらなくなることもあります。
本人が病気を自覚しづらいケースも多く、周囲が異変に気づいて受診につながることも少なくありません。
双極性障害はうつ病と似た症状を伴いますが、治療法や薬の種類が異なるため、正確な診断が非常に重要です。
「急に涙が出る」といった感情の不安定さが続く場合は、無理をせず専門医に相談することが勧められます。
▶うつ病と双極性障害(躁うつ病)の違いは?症状・原因・治療法とセルフチェックリスト
涙が止まらないとき、受診を検討すべきサインとは?

涙が止まらない状態は一時的な反応ではなく、心の不調による可能性もあります。
特に感情の波が長く続く、日常生活に支障が出るなどのサインは、心からのSOSです。
ここからは、受診を検討すべき心のサインについて説明します。
涙もろさや感情の波が2週間以上続いている
感情の波が激しく、ちょっとしたことで涙が出たり、気分の落ち込みが続くようになった場合、それは一時的なストレスではなく、心の病気が隠れている可能性があります。
うつ病や適応障害の初期症状として、感情の不安定さが現れることは少なくありません。
特に、「理由もなく涙が出る」「普段なら気にならないことに過剰に反応してしまう」といった状態が2週間以上続いている場合は注意が必要です。
感情の不安定さは、自分でも気づきにくいものですが、日常生活や人間関係に支障が出始めたと感じたら、それは心が発している大切なSOSです。
自分の状態を軽視せず、早めに相談してみましょう。
仕事や家事、学業など日常生活に支障が出ている
涙もろさや感情の不安定さが原因で、仕事や家事、学業に集中できなくなってきた場合、それは心の不調が進行しているサインかもしれません。
例えば、仕事中に涙が出てしまい業務に支障が出る、家事をこなす気力がわかず部屋が荒れていく、授業や勉強に集中できないといった状態が続くようであれば注意が必要です。
こうした支障は、放っておくと社会的な孤立や自信の喪失につながり、回復までに時間がかかる恐れがあります。
特に「以前は当たり前にできていたことができない」と感じたときは、我慢せずに心療内科や精神科などの専門機関に相談することが大切です。
自分で気づきにくい場合もあるため、身近な人の指摘があれば真剣に受け止めましょう。
早めの対応が、心と生活を守る第一歩になります。
涙が出るのは心のサイン。無理せず、できることから始めよう
涙が出るのは、決して弱さや怠けではなく、心と身体の限界を知らせている大切なサインです。
無理に止めようとせず、「なぜこんなに涙が出るのか」と自分を責める前に、その背景にあるストレスや心の状態に目を向けてみましょう。
泣ける環境を整える、感情を書き出す、生活リズムを見直すなど、小さな対処を重ねることが、心の回復につながります。
もし日常生活に支障が出ていたり、不安や不調が続いている場合は、ひとりで抱え込まずに、信頼できる人や専門機関に相談してください。
とはいえ、自分に合う相談先がわからない方や、受診に不安がある方もいるかもしれません。
そんなときは、医師や臨床心理士・公認心理士といった有資格者のみが在籍しているオンライン診療・オンラインカウンセリングサービス『かもみーる』にぜひご相談ください。
オンライン診療は24時まで可能ですので、お忙しい方もご自身の都合に合わせてご利用いただけます。
▶︎カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶︎新規会員登録はこちら