「『うつ状態』と言われたけれど『うつ病』とは違うの?」「自分や身近な人の症状がうつ病なのかうつ状態なのか知りたい」などお悩みの方は少なくありません。
「うつ病」と「うつ状態」という言葉は似ていますが、実は意味には違いがあります。うつ病は「病気(病名)」であり、うつ状態は気分の落ち込みや憂鬱な気分が続く「状態」です。
この記事では、うつ病とうつ状態の違い、うつ病・うつ状態かもしれないと思ったときの対処法、うつ病と間違われやすい病気などについて詳しく解説します。
効果的な治療のためには、早期発見が大切です。うつ病やうつ状態について知って、適切な対処を取りましょう。
うつ病とうつ状態(抑うつ状態)の違い

うつ病とうつ状態(抑うつ状態)は同じだと勘違いされることがありますが、これらは別のものです。
うつ病は「病気(病名)」で、うつ状態(抑うつ状態)は気分の落ち込みや憂鬱な気持ちが続く「状態」を指します。
明確な基準や定義はありませんが、うつ病で見られるいくつかの症状が一時的に続く場合は「うつ状態」といいます。
そして、うつ状態が長く続き、生活や仕事に支障が出るほど症状が強く出る場合は「うつ病」と判断されることが一般的です。
ただし前述のとおり、両者に明確な基準はありません。うつ病かうつ状態かは専門家でなければ診断できないため、自己判断はせず医師に相談することが大切です。
うつ病とは

うつ病とは、気分の落ち込みや強い憂鬱感、睡眠障害などが現れる「病気(病名)」のことで、診断基準に沿って医師が診断します。
単なる気分の落ち込みではなく、以下のような精神症状と身体的症状が長期間続きます。
- 精神症状……憂鬱な気分、意欲の低下、興味や喜びの喪失など
- 身体症状……頭痛、肩こり、睡眠障害、疲労感など
うつ病の症状は通常、午前中が特に症状が強く、午後から夕方にかけて軽減する傾向があります。
うつ病の診断基準は主に「症状の重さ」と「仕事や日常生活への影響」で、症状が重く、2週間以上継続している場合にはうつ病と診断されることが多いです。
うつ病は日本人の約15人に1人が経験するともいわれ、多くの方が悩んでいる病気です。重症度によっては日常生活や仕事に支障をきたすこともあるため、早めに適切な治療を受けましょう。
うつ病については以下の記事で詳しく解説しています。
▶ うつ病を9種類に分けて症状・原因別に解説!重症度や間違われやすい病気も
うつ状態(抑うつ状態)とは
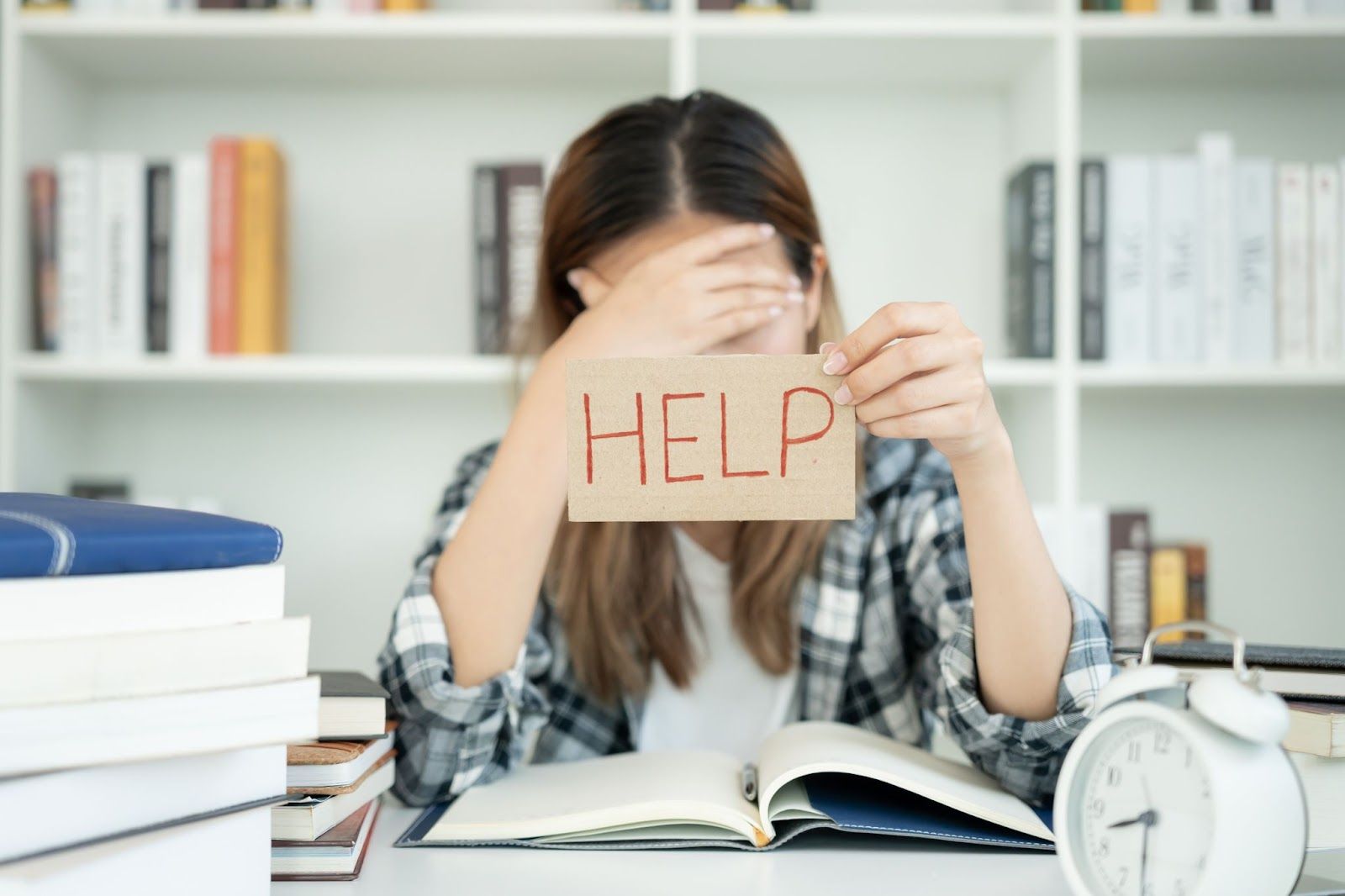
うつ状態(抑うつ状態)は、うつ病でも見られる気分の落ち込みや憂鬱な気分といった症状がある状態のことです。あくまで一時的で正常範囲の場合もあれば、うつ病などの病気が隠れている可能性もあります。
「抑うつ状態」と呼ばれることもありますが、うつ状態と意味は同じです。
では、専門家はどのようにうつ状態かを診断するのでしょうか?精神科・心療内科に限らず、医師は患者さんのお話を聞きながら病気について探っていきます。
- 「主観的症状(痛み、苦痛、悩みなど)」を確認する
- 「客観的症状(身体や表情など周囲からわかる変化)」を確認する
- ①と②の組み合わせから、「うつ状態である」と診断する
まずは、「主観的症状」の確認です。「気分が落ち込む」「自分なんていなくなればいいと思う」など、感じている苦痛や苦悩を挙げてもらいます。
次に、「客観的症状」として周囲から見える変化の確認です。例えば「家族から最近動作が遅いと指摘された」「職場の同僚から『ぼんやりしていることが多い』といわれた」などがあります。
そして「主観的症状」と「客観的症状」の組み合わせから、うつ状態であると診断します。つまり、うつ状態とは「(特定の疾患の診断につながる)特徴的な症状のセット」ともいえるでしょう。
うつ状態(抑うつ状態)と診断書に書かれた場合に考えられる可能性

うつ状態は、前述の通り「気分の落ち込みや憂鬱な気持ちなど、いくつかの症状のセット」のことです。
「うつ状態」と診断された場合や診断書に書かれた場合、以下の3つの可能性が考えられます。
- うつ病の可能性がある
- うつ病以外の病気の可能性がある
- 病気ではない可能性がある
1:うつ病の可能性がある
診断書に「うつ状態」や「抑うつ状態」と書かれていても、うつ病の可能性を完全には否定できません。
うつ状態では、気分の落ち込み、意欲低下、食欲減退、不眠などうつ病に似た症状が見られます。
現状では詳細な診断が難しい場合や、診断名がうまく当てはまらない場合、仮の診断として「うつ状態」としておき、医師が慎重に診断を進めている段階かもしれません。
2:うつ病以外の病気の可能性がある
うつ状態は、うつ病のみで見られる症状ではありません。うつ病ではなく、他の病気によって症状が現れている可能性もあります。
例えば、甲状腺機能低下症、副腎皮質ホルモンの異常、悪性腫瘍などもうつ状態が見られる原因となります。また、心筋梗塞、関節リウマチ、脳出血や脳梗塞の後遺症といった病気でも、うつ状態が見られることがあります。
ステロイド投与やインターフェロン製剤、βブロッカーなど薬剤の影響によってうつ状態が起こる事も知られています。(薬剤惹起性うつ病)
つまり「うつ状態で、うつ病ではないから大丈夫」と安易に判断することはできません。正確な診断のためには、専門家による詳細な評価が必要です。
3:病気ではない可能性がある
うつ状態は必ずしも病気を意味するわけではありません。一時的なストレスや環境の変化によって引き起こされることもあります。
例えば、仕事の責任や負担が大きすぎる、パワハラ、過労、大切な人との別れ、事故などといったショックな出来事が起こったときに気分が落ち込んでしまうのは誰もが経験する自然なことです。
しかし、症状が長引く場合や生活に支障をきたす場合は症状が悪化し、うつ病につながるリスクがあるため、早めに専門家に相談しましょう。
うつ病・うつ状態(抑うつ状態)で見られる症状

うつ病・うつ状態では、以下のような「精神症状」や「身体症状」が見られます。
【精神症状】
- 憂鬱な気分
- 悲観的なことばかり考える
- 意欲の低下
- 興味や喜びの喪失
- 思考力・集中力の低下
- 人に会いたくなくなる
- 罪悪感、不安感、焦燥感
- 自分は無価値だと感じる
- 死んでしまった方がいいと考える など
【身体症状】
- 睡眠障害(不眠や過眠)
- 食欲の変化(減退や増加)
- 疲労感、倦怠感
- 頭痛、頭重感、めまい
- 肩こり、腰痛、背部痛
- 手足のしびれ
- 息苦しさ、動悸
- 性欲低下
- 排尿困難
- 月経不順 など
一般的には、うつ病よりは症状が重くない状態を「うつ状態」と呼ぶことが多いです。
重症の場合は希死念慮(自殺念慮)や妄想が現れることもあり、このようなケースでは「うつ病」かもしくは他の病気の可能性が考えられるでしょう。
うつ病で見られる症状やサインについては以下の記事で詳しく解説しているのでよろしければこちらも合わせてご覧ください。
▶ うつ病の初期症状?12のサイン丨受診目安・対処法・顔つきの変化も解説
うつ病・うつ状態(抑うつ状態)の治療期間・治療法について

うつ病とうつ状態では、治療期間や治療法も変わってきます。
うつ病は脳の病気であり、原因と考えられている脳内神経伝達物質のバランスを整えるため、抗うつ薬を使用した薬物療法を行うケースが多いです。
うつ病の治療期間は個人差も大きいですが、完治までには1年ほどが目安といわれています。ただし、良くなった後もしばらくは薬の服用やカウンセリングを続けるなど、再発を防止するための対策が必要です。
うつ状態の場合、症状に合わせて、十分な休養や気分転換、認知行動療法(考え方のクセを分析し対処する)などを行います。治療期間も症状によって変わってくるため、詳しくは専門家に相談してみましょう。
うつ病と間違われやすい病気

うつ病と似た症状が起こり、うつ病と間違われやすい病気には以下のようなものがあります。
- 双極性障害(躁うつ病)
- 統合失調症
- 適応障害
- パーソナリティ障害
- 不安障害
- 認知症
- がん、心筋梗塞、関節リウマチなどの身体疾患 など
身体疾患の可能性が考えられる場合、画像検査などの検査を受ける必要があります。また、精神疾患の場合も、病気に合った薬を使って治療しなければなりません。
例えば、うつ病には抗うつ薬が使われますが、双極性障害の場合は抗うつ薬が効かないばかりか、躁転(うつ状態から急に躁状態になること)が起こるリスクがあり注意が必要です。
適切な治療を受けるためにも、早めに専門家に相談しましょう。
うつ病・うつ状態になりやすい人

誰しもうつ病・うつ状態になるリスクはゼロではありません。しかし、中には「うつ病・うつ状態になりやすい人」もいます。
まず、性格面では、真面目で責任感が強く、完璧主義の傾向がある人がうつ病になりやすいとされています。
このような性格の人は仕事や家事を人任せにできず、自分の許容範囲以上に頑張りすぎてしまう傾向があり、ストレスを感じやすいためです。
また、人からの評価を非常に気にする性格やストレス耐性の低さも、うつ病のリスクを高める要因です。
性別では、女性の方が男性よりもうつ病になりやすいとされています。これは、ホルモンバランスの変動(妊娠出産や更年期など)や社会的役割の多様さが影響していると考えられています。
ただし、これらの特徴がなくてもうつ病になる可能性はあります。誰もがうつ病のリスクを抱えているため、早めに自分の心身の変化に気づき、適切な対処をすることが大切です。
うつ病・うつ状態かもしれないと思ったときの対処法

「もしかしたら自分はうつ病かもしれない」「家族がずっと塞ぎ込んでいて心配」など、自分や身近な人にうつ病やうつ状態の兆候が見られたときは、思い悩んでしまうものです。
そんなときは、うつ病のセルフチェックや相談がおすすめです。
セルフチェックをしてみる
手軽にできるのが、簡単な質問に答えるだけでうつ病の可能性を診断できるセルフチェックです。オンラインで利用できるうつ病チェックリストなどを活用して、自分の状態を確認してみましょう。
あくまで参考程度であり、正確な診断には専門家の評価が必要ですが、クリニックでの診察時に医師に渡せば診断がスムーズになります。
身近な人や医師・カウンセラーに相談する
落ち込んでいることを信頼できる家族や友人に打ち明けられるのであれば、現在の自分の状態や想いを話してみましょう。
軽いうつ状態であれば、相談したり客観的な意見をもらったりすることで心が軽くなるかもしれません。
ただし、うつ病・うつ状態になりやすい人は真面目で頑張り屋な方が多く、なかなか周囲に自分のつらい気持ちを話せないこともあります。そんなときは、医師やカウンセラーに相談するのがおすすめです。
医師やカウンセラーは、うつ病やうつ状態に詳しい専門家です。一人ひとりの患者さんに寄り添い、悩みや症状を詳しく聞いて、的確な診断やアドバイスをします。
「どのような治療が必要か」「休職の必要はあるか」など治療の方向性がはっきりするだけでなく、自分の状態を把握することにつながります。
うつ病は早期に治療を開始した方が回復も早い傾向にあるため、迷っているのであればまずは相談してみましょう。
うつ状態で受診した方がいいケース

「これくらいの落ち込みはうつ病じゃない」と、つらい気持ちを我慢してしまっていませんか?クリニックを受診した方がいいかわからないときは、以下を目安にしてみましょう。
- 急激な変化があった
- 重くはないがうつ状態が長期間続く
- 「自分が生きている意味がわからない」「死にたい」といった気持ちが浮かぶ
急激な変化があった
ストレスを感じているかどうかに関係なく、気分や行動に急激な変化が見られた場合は、早めにクリニックを受診しましょう。
例えば「急に朝ベッドから出られなくなった」「突然仕事がひどく億劫になった」などの状態が見られた場合は要注意です。
重くはないがうつ状態が長期間続く
自覚している症状はそこまで重くないものの、気分の落ち込みが2週間以上続く場合は一度クリニックで相談してみましょう。
うつ病は、初期段階では本人も周囲も気付かないケースが多いです。長期化することで症状が悪化してしまう可能性があるため、注意しましょう。
「自分が生きている意味がわからない」「死にたい」といった気持ちが浮かぶ
「いなくなってしまいたい」「自分なんて生きている意味がない」など、希死念慮がある場合は、自殺のリスクがあります。なるべく早く専門家に相談しましょう。
うつ病やうつ状態が疑われる場合は早めに専門家に相談を
うつ病とうつ状態は似て非なるものです。うつ病は脳の病気であり、医師のもとで適切な治療が必要です。一方、うつ状態は一時的な気分の落ち込みを指すこともあり、必ずしも病気とは限りません。
しかし、うつ状態が長引いたり、症状が重くなったりする場合はうつ病に移行する可能性もあります。また、うつ病以外の病気が隠れているかもしれません。
自分や身近な人の状態が気になる場合は、早めに専門家に相談しましょう。
『かもみーる』では、医師によるオンライン診療・心理士によるオンラインカウンセリングを実施しています。
「自分や身近な人の症状が『うつ病』なのか『うつ状態』なのかわからない」「つらい気持ちを抱えていて、どうにかしたい」そんな不安を、まずはゆっくりお話してみませんか?
▶ カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶ 新規会員登録はこちら
