ストレス社会といわれる現代では多くの人がストレスを抱えており、それが頭痛の原因となることがあります。
しかし、頭痛の原因がストレスなのか、それとも他の病気なのか判断するのは難しいものです。
この記事では、頭痛の種類、ストレスが頭痛を引き起こすメカニズム、頭痛とこころの病気(精神疾患)の関係、ストレスによる頭痛の対策や解消法などについて詳しく解説します。
痛みはそれ自体がストレスになり、頭痛を悪化させる原因になります。つらい痛みやストレスで悩んでいる場合は、早めに対策してストレスや痛みを軽減することが大切です。
ストレスが原因と思われる頭痛に悩んでいる方、自分に合った治療法を見つけたい方はぜひ記事をチェックしてみてください。
ストレスと頭痛の関係

ストレスと頭痛には密接な関係があります。
ストレスで頭痛が起こる仕組みやメカニズム、ストレスが引き起こす悪循環などについて詳しく解説します。
ストレスは頭痛の原因のひとつ
仕事や人間関係、経済的な問題など、日々感じるストレスはさまざまです。そしてこのストレスは、頭痛の原因となることがあります。
慢性頭痛の中でも多く見られる「緊張型頭痛」は、別名ストレス頭痛と呼ばれていたこともあり、ストレスと密接な関係があります。また、片頭痛(偏頭痛)もストレスと関連があります。
ストレスで頭痛が起こる仕組み・メカニズム
緊張型頭痛と片頭痛はストレスが原因で起こることがありますが、痛みが起こる仕組みには違いがあります。
緊張型頭痛は、身体的ストレスと精神的ストレスが複雑に絡み合って起こると考えられています。
ストレスによって交感神経(自律神経の一つ)が優位になり、首や肩の筋肉が緊張して血流が悪化。疲労物質が蓄積してしまい、それが神経を刺激して頭痛が起こるという仕組みです。
一方の片頭痛にもストレスが関係していますが、そもそも片頭痛が起こるメカニズムはまだはっきりわかっておらず、三叉神経血管説・血管説・神経説など複数の説があります。
しかし片頭痛とストレスは関連が深く、頭痛にきっかけがある片頭痛患者の方のうち、約8割の人がストレスによる頭痛を経験したことがあるといいます。
また、ストレスは片頭痛が悪化する原因としても影響が大きく、転職や離婚などの環境変化によって片頭痛が軽くなるケースもあります。
ストレスが頭痛を引き起こし、痛みがストレスになる悪循環
頭痛による痛みは、それ自体がストレスになります。
頭痛持ちの方の中には「ストレスを受ける→頭痛が起こる→痛みがストレスになる」という悪循環に陥ってしまうケースも少なくありません。
ストレスは痛みを感じやすくさせる
ストレスは「痛みの感じやすさ」にも関係しています。ストレスがあると痛みの閾値(痛みの感じやすさ)が低下し、痛みに敏感になってしまうのです。
普段であれば痛みとして感じない刺激でも、ストレスが高い状態では痛みとして感じやすくなる傾向にあります。
頭痛の種類

頭痛は大きく「一次性頭痛」と「二次性頭痛」の2種類に分けられます。
一次性頭痛
一次性頭痛は原因となる病気が見つからない頭痛で、頭痛そのものが病気といわれるタイプです。
代表的なものとしては緊張型頭痛、片頭痛、群発頭痛(比較的珍しい頭痛で激しい痛みが特徴)といった慢性頭痛があります。
一般社団法人日本頭痛学会の調査によれば日本人の片頭痛の有病率は8.4%で、非常に多くの方が頭痛に悩まされていることがわかっています。
二次性頭痛
二次性頭痛は、なんらかの病気が原因になって起きている頭痛で、くも膜下出血や髄膜炎など緊急性が高い病気が隠れている可能性があるため注意が必要です。
また、こころの病気(精神疾患)が原因となって二次性頭痛が引き起こされることもあります。
ストレスが原因で起こる頭痛
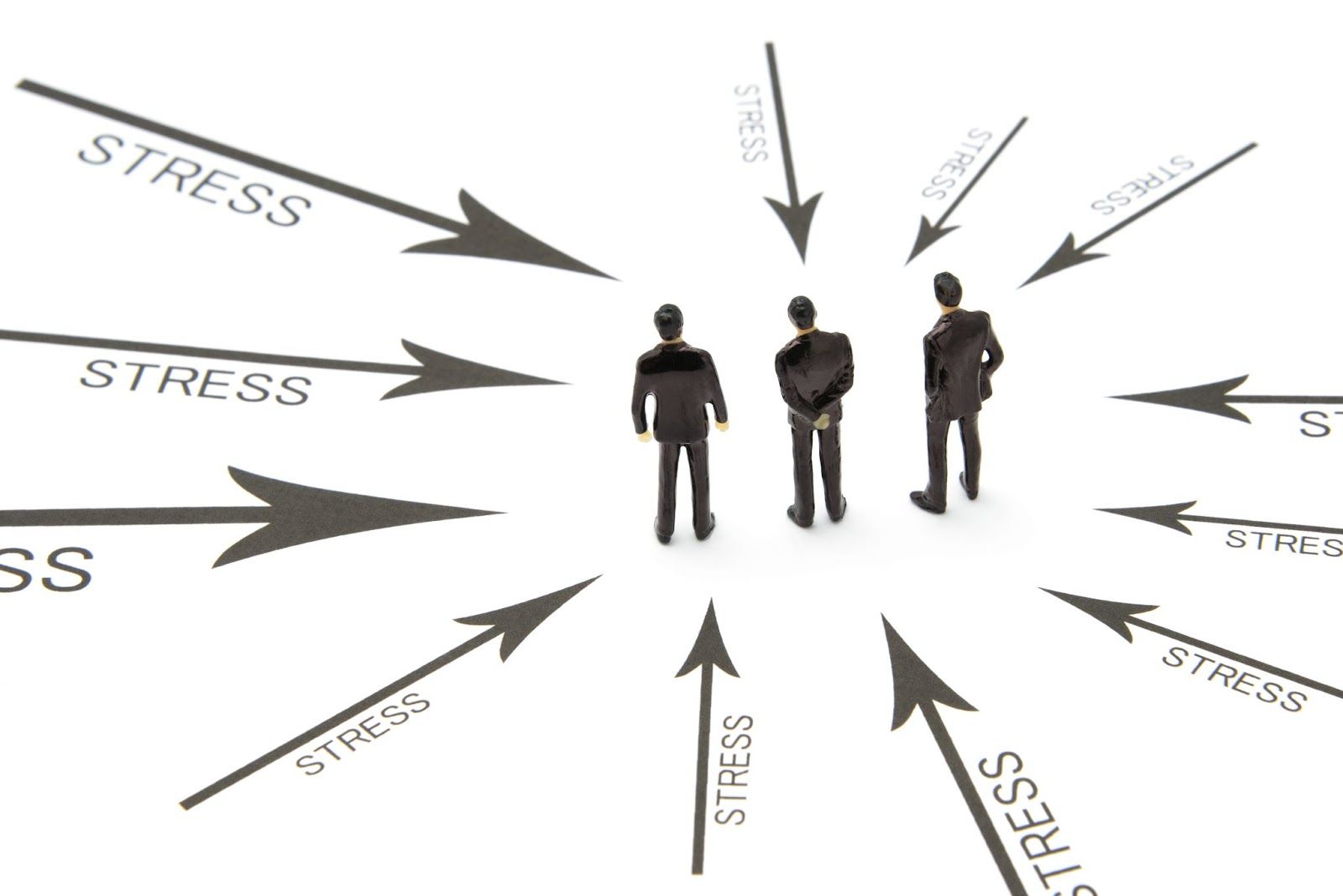
ストレスが影響する代表的な頭痛としては「緊張型頭痛」と「片頭痛」が知られています。ここからは、それぞれの頭痛について詳しく解説します。
緊張型頭痛
緊張型頭痛は、頭全体が締め付けられるような痛みが特徴の頭痛です。
無理な体勢を維持したり、長時間デスクワークを続けたときなどの「身体的ストレス」と、緊張や環境変化などの「精神的ストレス」が複雑に関係して起こると考えられています。
- 頭全体が締め付けられるような痛み、鈍い痛み
- 痛みの程度は軽度〜中等度(我慢できないほどではない)
- 肩こりや首こりなどがあることも多い(吐き気は感じないことが一般的)
- 数時間~数日の頭痛が繰り返し起こることもあれば、毎日続くこともある
- 動きによって痛みが悪化することはない
緊張型頭痛はストレスを受けている最中に起こる傾向にあります。
例えば「長時間スマホを見ていたら頭が痛くなった」「朝から作業をしていたら夕方になって頭痛が出た」といった現れ方です。
緊張型頭痛は筋肉のこりも原因の一つであるため、ストレッチやマッサージも有効です。
片頭痛
片頭痛は、ズキンズキンと脈打つような拍動性の痛みが特徴の頭痛です。頭の片側が痛む場合が多く、吐き気や光・音に対する過敏が見られることもあります。
片頭痛の原因には諸説ありはっきり解明はされていませんが、なんらかの「引き金(トリガー)」があって発生するケースも多いです。
ストレス、寝不足や寝過ぎ、気圧や天候、女性ホルモンバランスの変動(月経)、アルコール、カフェイン、脱水、空腹など日常生活のさまざまなことが引き金になります。
- ズキンズキンと脈打つような痛み
- 頭の片側に痛みが起こる(両側に起こる場合もある)
- 仕事や家事に支障をきたすほど強く痛むこともある
- 動くと痛みが増すことがある
- 吐き気や嘔吐が起こることがある
- 頭痛が起こる前兆や予兆が起こる場合がある
- 光・音・においに敏感になる
片頭痛は仕事のない休日など、ストレスから解放されたときに痛みが起こることがあります。
また、片頭痛は女性に多く見られることも特徴で、男性の3.6倍にもなるといいます。年代では特に20〜40代の女性に多いです。
頭痛とこころの病気(精神疾患)の関係

頭痛はこころの病気(精神疾患)と関わりの深い症状です。
例えば、片頭痛や緊張型頭痛といった一次性頭痛は、気分障害(うつ病など)や不安障害(パニック障害など)と密接な関連があるといわれています。
また反対に、うつ病やパニック障害などの病気が頭痛(二次性頭痛)を引き起こすこともあります。(参考: 『頭痛とは/頭痛がおこったら/頭痛の分類』(一般社団法人 日本頭痛学会))
ここでは、頭痛とこころの病気の関係について詳しく見ていきましょう。
片頭痛や緊張型頭痛があるとうつ病や不安障害を併発しやすい
片頭痛や緊張型頭痛がある方は、抑うつや不安を感じやすく、うつ病や不安障害(パニック障害など)になりやすい傾向にあります。
片頭痛における大うつ病の年間有病率は約8.6%、生涯有病率は18~40%程度と報告されており、片頭痛のある方はそうでない方の2〜4倍うつ病のリスクが高いといわれています。(参考:『頭痛の診療ガイドライン2021』)
パニック障害との関連も多数報告されており、片頭痛がある場合、パニック障害の生涯有病率は3〜7倍にもなるといいます。
また、「セロトニン」という脳内の神経伝達物質はうつ病にも片頭痛にも関わっており、セロトニンの代謝異常などの原因が影響しているのではないかという説もあります。
不安や恐怖感が薬物乱用頭痛につながることも
薬物乱用頭痛(薬剤の使用過多による頭痛)とは、頭痛薬の使いすぎによって引き起こされる二次性頭痛の一種です。
頭痛に対する不安や恐怖感から頭痛薬を過剰に使用してしまうケースがあり、薬物乱用頭痛につながる可能性があります。
「頭痛があるのはいつものことだから」と自己判断で市販薬を使い続けている方も多くいますが、薬物乱用頭痛のリスクがあるため早めにクリニックを受診することが大切です。
片頭痛・緊張型頭痛の予防に抗うつ薬が使われることもある
片頭痛や緊張型頭痛の薬というと痛み止め(鎮痛剤)を連想する方も多いですが、頭痛薬にはさまざまな種類があります。
三環系抗うつ薬として知られる「トリプタノール(アミトリプチリン)」も、その一つです。
トリプタノールは片頭痛にも関連の深いセロトニンの代謝を改善させて痛みの感じやすさを抑え、片頭痛の予防に効果を発揮します。
頭痛の症状が見られるこころの病気(精神疾患)

「うつ病」「双極性障害(躁うつ病)」「不安障害(パニック障害など)」などのこころの病気の中には、頭痛の症状が現れるものがあります。
こころの病気によって起こる頭痛には、以下のような特徴があります。
- 頭痛以外にもさまざまな症状が見られることが多い
- 痛みの出方など症状がはっきりしない
- こころの病気の調子が良くなったり悪くなったりするのに合わせて頭痛の状態が変化する
- 原因となったこころの病気が良くなるにつれて改善していくことが一般的
疲れや寝不足・寝過ぎなどによる一時的な頭痛であれば、頭痛薬で対処できることがほとんどです。
しかし、こころの病気によって頭痛が起きている場合は、原因となっている病気の治療が必要です。放置すれば悪化や治療の長期化などさまざまなデメリットが考えられるため、早めにクリニックを受診しましょう。
ストレスによる頭痛の対策・解消法

ストレスによる頭痛に対しては、以下のような対策や解消法が効果的です。
- 頭痛ダイアリーをつける
- ストレスマネジメントを実践する
- 認知行動療法を受ける
- 医師やカウンセラーへ相談する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
頭痛ダイアリーをつける
頭痛には種類があり、原因やきっかけも人それぞれ違いがあります。正確な診断のためにも、頭痛ダイアリーをつけて自分の頭痛を分析してみましょう。
頭痛ダイアリーとは、頭痛の頻度・強さ・持続時間、痛みが起きるきっかけ、ストレスの程度や種類などの記録のことです。
記録をつけることで自分の頭痛の特徴がわかり、適切な対策を立てやすくなります。また、診察で医師に自分の頭痛について伝える際にも役立ちます。
ストレスマネジメントを実践する
ストレスマネジメントとは、ストレスとの上手な向き合い方について考え、実践することです。ストレスマネジメントとして重要なポイントに「3つのR」があります。
- Rest(休息、休養、睡眠)
- Refresh(趣味や運動、旅行などの気分転換)
- Relax(本を読む、音楽を聴く、ゆっくりお風呂に入るなど)
また、ストレスについて考えないようにしたり、誰かとおしゃべりや相談したりすることもストレス解消法の一つです。
同じ方法ばかりではなく、自分なりのストレス解消法をいくつも持っておくと、ストレスに対処しやすくなります。
認知行動療法を受ける
心理療法の一つである認知行動療法を受けるのも効果的です。
ストレスは人によって受け止め方が大きく異なります。認知行動療法では、物事の捉え方や考え方(認知)に働きかけることで、ストレスやつらい気持ちを軽減します。
この他にもストレスの対処に役立つ方法があるため、一度クリニックで相談するのがおすすめです。医師やカウンセラーのサポートを受けながら、自分に合った対処法を学ぶことができます。
クリニックを受診する
頭痛が慢性化している場合や、仕事や学校、家事など日常生活に支障が出ている場合は何か病気が隠れている可能性があるため、早めにクリニックを受診しましょう。
例えば、うつ病の初期症状には頭痛や食欲不振など風邪に似た症状もあり、自分では気づけないケースも多いです。また、脳の病気が隠れている可能性もゼロではありません。
早めに医師に相談したほうがつらい痛みを緩和できるため、我慢せずに相談することをおすすめします。
ストレスによる頭痛がつらいときは何科を受診すればいい?

頭痛と精神疾患との関係は多様です。頭痛の原因を正確に診断し、原因に合った治療を行う必要があります。
これまで頭痛で診てもらったことがない場合は、内科や頭痛外来で身体に異常がないかをチェックしたほうがいいでしょう。
一方、頭痛のほかにも気分の落ち込み、不安、意欲低下、眠れない・寝過ぎてしまう、食欲がないなど精神的な症状が見られる場合は心療内科や精神科に相談するのがおすすめです。
つらい頭痛とストレスの悩みは我慢せずに相談しよう
代表的な頭痛である片頭痛や緊張型頭痛は、ストレスと深い関連があることが知られています。
ストレスは頭痛を引き起こし、さらに痛みがストレスとなって、頭痛を悪化させてしまう悪循環に陥ってしまうケースも少なくありません。つらい頭痛やストレスを抱えている場合は、我慢せずに専門家に相談することをおすすめします。
『かもみーる』では、ストレスでお悩みの方が気軽に相談できるようにオンライン診療・オンラインカウンセリングを実施しています。
お悩みに合わせてカウンセラーの選択も可能です。心に抱えているストレスや不安がある方は、気軽に医師やカウンセラーに打ち明けてみてください。
▶ カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶ 新規会員登録はこちら
