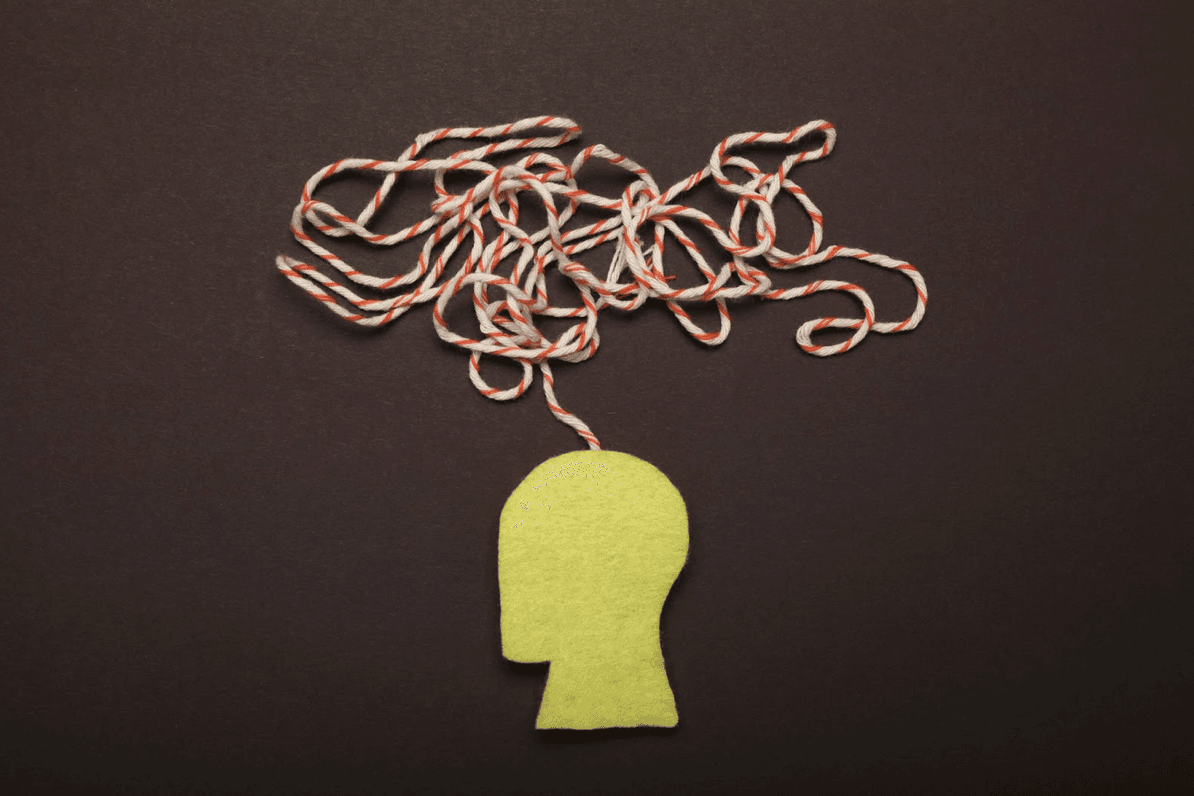ADHDとうつ病はそれぞれ異なる特徴を持つ疾患ですが、併発することも少なくありません。
ADHD特有の不注意・衝動性・多動性は、仕事や日常生活に支障をきたし、失敗の繰り返しや人間関係のトラブルを招くことで自己評価を低下させます。
このような状態が長く続くと、強いストレスや無力感からうつ病を発症する可能性が高まるのです。
この記事では、ADHDとうつ病を併発したときの症状や生活への影響について解説します。
具体的な治療方法や他の合併症などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
ADHDとうつ病は併発することがある

ADHDとうつ病は別々の疾患でありながら、同時に発症するケースが少なくありません。
ADHDの症状には、注意力の欠如・多動性・衝動性などがあり、これらは日常生活や仕事での失敗を招きやすくなります。
成人後は特に、仕事や家庭で複数の課題を同時にこなす必要があり、ADHD特性を持つ人にとっては大きな負担となります。
失敗の繰り返しや物事がうまく進まない状況が続くと、自己肯定感が低下して長期的なストレスや無力感につながり、これが引き金となって抑うつ状態からうつ病を発症する可能性が高まるのです。
ADHDとうつ病はどちらも集中力の低下、気分の変動、イライラ感などが見られますが、うつ病では抑うつ気分や活動への関心低下といった特徴が強く出やすい点で違いがあります。
診断や治療では、この違いを踏まえて判断することが重要です。
ADHDとは
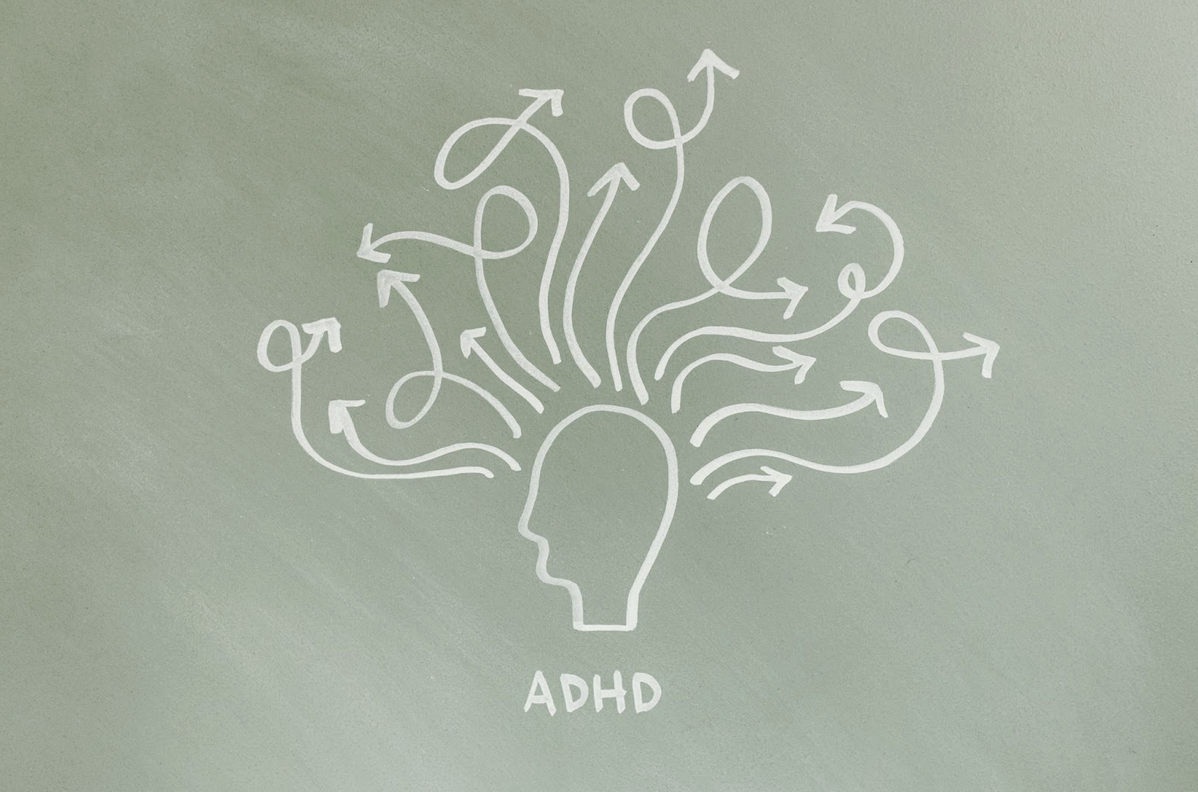
ADHDは不注意・多動性・衝動性の3つの特性が中心となる発達障害の一種です。
これらの特性は年齢や発達段階に不相応な強さで現れ、日常生活や学業、職場での適応に影響を与えます。
症状の現れ方は人によって異なり、不注意が目立つタイプ、多動性・衝動性が強いタイプ、そして両方を併せ持つ混合タイプの3種類に分類されます。
ここではADHDの症状と原因についてそれぞれ解説しましょう。
ADHDの症状
ADHDの症状は不注意・多動性・衝動性の3つに分けられます。
それぞれの具体的な症状は以下の通りです。
不注意 |
など |
多動性 |
など |
衝動性 |
など |
これらの症状は本人の性格や育て方の問題ではなく、脳の情報処理や行動制御に関わる機能の特性によるものです。
また、症状の強さや組み合わせは個人差が大きく、同じ診断でも日常生活での困難の現れ方はさまざまです。
ADHDの原因
ADHDの原因は完全には解明されていませんが、前頭前野や大脳辺縁系など注意や行動の制御を担う部位の機能差が関係していると考えられています。
特に、ドパミンやノルアドレナリンといった神経伝達物質の分泌量の調節不十分または機能不全が、注意力や衝動抑制の困難に影響しているとされます。
また遺伝的要因も大きいとされますが、必ず遺伝するというわけではありません。
出生前後の脳の発達過程での影響や、幼少期の環境的ストレスが症状の現れ方に関与する可能性も指摘されています。
ADHDはしつけや育て方が原因ではなく、生まれ持った脳の特性と環境要因が複合的に関わって症状が表れるものだと理解することが大切です。
▶ADHD(注意欠如・多動症)とは?発達障害との関係や特徴、対応法を解説
うつ病とは

うつ病は、強い気分の落ち込みや憂うつ感、意欲の低下といった精神的な症状に加え、睡眠障害や倦怠感、食欲の変化などの身体的症状を伴う精神疾患です。
日常生活の中での一時的な落ち込みとは異なり、うつ病では原因がはっきりしないまま気分の低下が長く続き、問題が解消されても回復が見られないことが多いのが特徴です。
早期に治療を受けることで改善が期待できるため、「気の持ちよう」と誤解せず、早期診断・治療を行うことが大切になります。
ここではうつ病の症状と原因について解説しましょう。
うつ病の症状
うつ病は心と体の両面に症状が表れる病気です。
精神面では、持続的な憂うつ感、何をしても楽しくない、意欲の低下、将来への悲観、自分に価値がないと感じる自己否定感、判断力や集中力の低下などがあります。
また、「死にたい」「消えてしまいたい」といった自殺念慮が見られる場合もあります。
身体面に表れる症状は、不眠や過眠、食欲の減退や過食、倦怠感、頭痛、吐き気、性欲の減退などです。
思春期や若年層では、これらが引きこもりやリストカット、攻撃的な行動として表れることもあります。
悲しく憂うつな気分や興味の喪失といった主要症状を含む5つ以上の症状が2週間以上続く場合には、医療機関の受診が推奨されます。
症状が多いほど重症度が高くなるため、早めの対応が重要です。
うつ病の原因
うつ病の原因は一つではなく、複数の要因が組み合わさって発症すると考えられています。
脳科学的には、感情や意欲を司る神経伝達物質の働きの乱れが関係しており、その分泌や受容が不十分になることで症状が出やすくなるとされます。
また、生真面目、完璧主義、責任感が強い、凝り性、他人に気を遣いすぎるといった性格の人も発症のリスクが高まるため注意が必要です。
発症のきっかけとしては、大切な人との別れや人間関係のトラブル、経済的困窮などのストレスだけでなく、結婚や昇進、引っ越しといった喜ばしい出来事も含まれます。
さらに糖尿病やがんなど長期的な身体疾患も心理的ストレスとなり、うつ病の引き金になることがあります。
うつ病はこうした要因が複雑に絡み合って発症するため、「性格の弱さ」や「怠け」といった誤解には注意しましょう。
ADHDとうつ病を併発した場合の仕事や生活への影響

ADHDとうつ病を同時に抱えている場合、仕事や生活のあらゆる場面で負担が大きくなります。
ADHD特有の不注意・多動性・衝動性によって業務の効率や正確さが低下しやすく、それが続くことで失敗や遅延が増加します。
その結果、自己評価が下がって自信喪失につながることが多く、うつ病の症状を悪化させる悪循環が生まれやすいです。
また、ADHDによる集中困難や計画性の欠如は、仕事の納期やタスク管理に直接影響を与え、職場での評価や人間関係にもマイナスの影響を及ぼします。
さらにうつ病の症状である意欲低下、強い疲労感、興味の喪失は、ADHDのパフォーマンス低下を加速させます。
もともと集中が苦手なところに、うつ病によるエネルギー不足が重なれば、業務遂行や自己管理はより一層困難になるでしょう。
生活面でも影響は大きく、人間関係の摩擦や誤解から孤立感が強まり、家族や友人との関係が悪化することがあります。
ADHDとうつ病を併発している場合は、両方の症状を理解した上で、まずはうつ病の治療を優先し、その後ADHDへの対応を行うことが重要です。
ADHDとうつ病を併発した場合の治療方法

ADHDとうつ病を併発した場合、複数の方法を組み合わせた治療が必要になります。
具体的な治療方法は以下の2つです。
- 薬物療法
- 心理療法
ここでは上記2つの治療方法についてそれぞれ解説します。
薬物療法
薬物療法は、ADHDとうつ病の両方に対応するために段階的に行われます。
まずはうつ病の症状を和らげることを目的に、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)などの抗うつ薬が処方されるケースが多いです。
これにより気分の落ち込みや意欲低下を改善し、生活の基盤を整えます。
その後、ADHDに対してメチルフェニデートやアトモキセチンなどの薬を使用し、注意力や集中力の改善、多動性や衝動性の抑制を図ります。
ただし、ADHD治療薬の一部には不安や睡眠障害を悪化させる可能性があるため、投薬量や組み合わせには細心の注意が必要です。
心理療法
心理療法の中でも代表的なのは認知行動療法(CBT)で、これは自身の思考パターンや行動習慣を把握し、より適応的な行動に変えていく治療方法です。
ADHDにより引き起こされる不注意や衝動性がうつ症状を悪化させる場合、認知行動療法を通じて課題の分解や優先順位付け、衝動の抑制方法などのスキルを身につけます。
また対人関係療法(IPT)も有効で、人間関係のストレスやコミュニケーションの問題を改善することで、うつ症状の軽減が期待できます。
うつ病以外にもあるADHDと合併しやすい病気

ADHDと合併しやすい病気はうつ病のみではありません。
具体的には以下のような病気も合併率が高いため、注意が必要です。
- 双極性障害
- 不安障害
- ASD(自閉スペクトラム症)
- 睡眠障害
- 過食症
ここでは上記の合併症についてそれぞれ解説します。
双極性障害
双極性障害は、躁状態とうつ状態を繰り返す気分障害で、ADHDと症状が似ている部分があります。
躁状態では多弁、多動、集中困難、衝動性などが見られ、これらはADHDの特徴と重なります。
ただし、双極性障害の症状は気分の波に合わせて出現し、寛解期には落ち着きますが、ADHDでは症状が持続的です。
診断の際には、気分の高揚や睡眠欲求の減少など、ADHDには見られない特徴を確認することが重要です。
併発した場合は、まず双極性障害の安定化を優先し、その後にADHDの治療を行うことが推奨されます。
▶うつ病と双極性障害(躁うつ病)の違いは?症状・原因・治療法とセルフチェックリスト
不安障害
不安障害は過剰な不安や心配が続く精神疾患です。
不安感が強いと落ち着きがなくなり、集中力が低下するため、ADHDの症状が悪化して見えることがあります。
ADHD治療薬の中には不安を悪化させる可能性がある薬も存在するため、薬の選択には注意が必要です。
▶不安障害とは?種類ごとの特徴や症状、治療法について詳しく解説
ASD(自閉スペクトラム症)
ADHDとASDは異なる疾患ですが、近年は両方の診断を同時に行うことが可能となり、併存するケースも少なくありません。
ADHDとASDの両方を持つ場合、不注意や多動性に加えて、対人関係やコミュニケーションの困難、行動の柔軟性の低さが見られることがあります。
両方の特性を理解した上で、心理社会的サポートや薬物療法を組み合わせた治療・支援を行うことが重要になります。
睡眠障害
ADHDは不眠症、過眠症、概日リズム障害など、さまざまな睡眠障害を併発しやすい傾向にあります。
睡眠の質やリズムの乱れは集中力や注意力をさらに低下させ、ADHD症状を悪化させます。
睡眠障害の治療は生活習慣の改善が基本です。
睡眠障害を改善することで日中の覚醒度や集中力が向上し、ADHDの症状軽減にもつながります。
過食症
過食症は衝動性の高さや感情調整の困難さと関連があり、ADHDとの併存がみられることがあります。
食欲のコントロールが効かなくなり、短時間で大量に食べる行動を繰り返すのが特徴です。
ストレスや感情の起伏が引き金になることが多く、ADHD特性がこれらの行動を助長する可能性があります。
過食症は身体的健康にも影響を与えるため、栄養指導や心理療法、場合によっては薬物療法を組み合わせて治療します。
ADHDとうつ病を併発した場合は適切な治療を受けましょう
ADHDとうつ病が併発すると、症状が互いに影響し合い、日常生活がより困難になります。
この2つを併発した場合は、まずはうつ病の治療を行い、その後ADHDの治療を行うケースが多いです。
また、ADHDは双極性障害や不安障害、睡眠障害といった他の病気の合併率も高いため、気になる症状がある場合は放置せず早めに医師に相談することが大切です。
『かもみーる』では、オンライン診療・オンラインカウンセリングサービスを提供しています。
発達障害やうつ病、適応障害の診察やカウンセリングにも対応しているため、気になる症状がある方はぜひ当院までご相談ください。
▶ カウンセラー(医師・心理士)一覧 はこちら
▶ 新規会員登録 はこちら