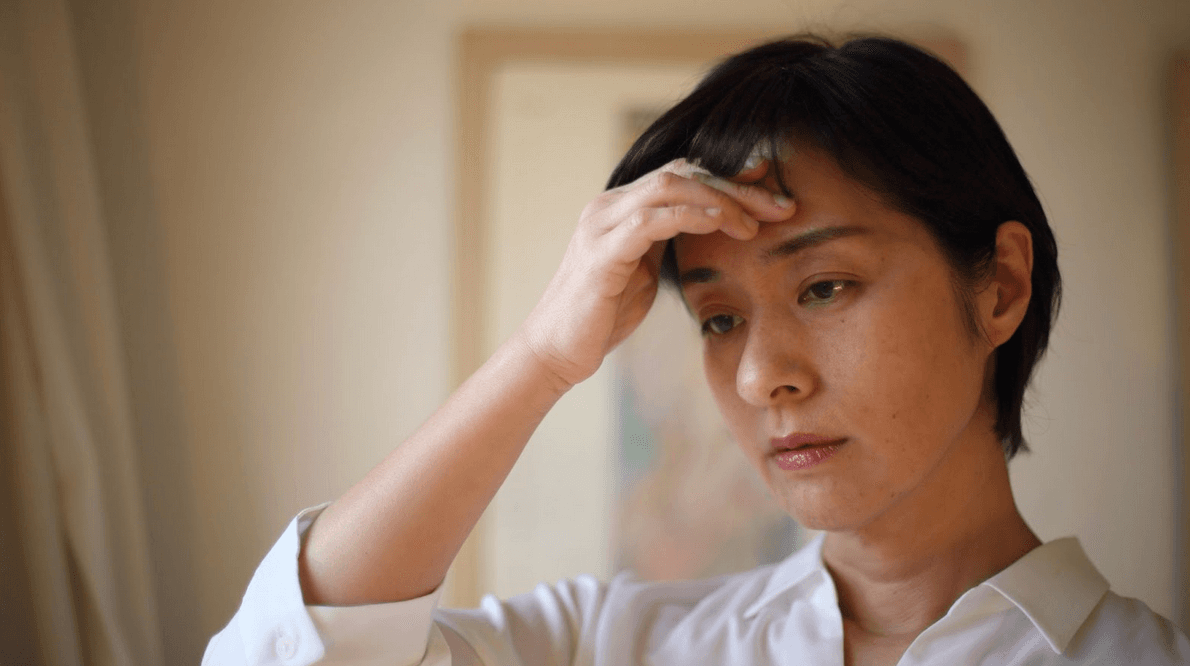「最近なんとなく頭がぼんやりする」「集中できない」「考えがまとまらない」といった状態が続いている方は、ブレインフォグの可能性があります。
ブレインフォグは医学的に定義された病名ではありませんが、思考力や記憶力の低下、注意散漫など、脳の働きが鈍くなっているように感じられる症状の総称です。
睡眠不足や栄養の偏り、ストレスなどが原因となることが多く、近年では新型コロナウイルスの後遺症としても注目されています。
この記事では、ブレインフォグの症状や原因について詳しく解説します。
具体的な治療方法やセルフケア方法などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
ブレインフォグとは?

ブレインフォグとは、頭の中がモヤがかかったようにぼんやりとし、思考が鈍くなったり、集中力や記憶力が低下したりする状態を指します。
医学的に正式な病名ではありませんが、日常生活に大きな支障をきたすこともあるため、無視できない症状の一つです。
「脳の霧」とも表現されるこの状態は、情報処理がうまくいかず、簡単な判断や会話すら困難に感じることがあります。
ブレインフォグの原因はストレスや脳への不可など多岐にわたりますが、近年では特に、新型コロナウイルス感染症の後遺症としても注目を集めており、「頭が回らない」「仕事が手につかない」といった相談が医療機関でも増えています。
本来、ブレインフォグは一時的な体調不良として捉えられることが多く、十分な休養や生活習慣の見直しで回復が期待できるケースも少なくありません。
しかし、うつ病や他の疾患が背景にある場合は専門的な治療が必要になることもあるため、安易に自己判断するのは避けるべきです。
このように、ブレインフォグは単なる「疲れ」や「気のせい」ではなく、心身の不調のサインとして現れることがあります。
特に長期にわたって症状が続く場合や、日常生活に支障が出ている場合は、早めに医療機関を受診し、正確な診断と適切な治療を受けることが大切です。
ブレインフォグの主な症状

ブレインフォグの主な症状は、思考力や集中力の著しい低下に加え、記憶障害や判断力の鈍化といった「脳の機能が一時的にうまく働かない状態」が中心です。
具体的には「頭がぼんやりする」「集中したくても思考がまとまらない」「物忘れが増える」といった状態が続き、まるで頭に霧がかかったかのような感覚に悩まされます。
具体的には以下のような症状が挙げられます。
- 思考が遅くなり、会話中に適切な言葉が出てこない
- 相手の話が頭に入らず、スムーズなやり取りが困難になる
- 何かを始めようとしても集中できず、行動に時間がかかる
- 一度に複数のことをこなすマルチタスクが難しくなる
- 短期記憶の低下により、直前の出来事や話した内容を忘れる
- 情報を整理してまとめるのが困難になる
- 目の焦点が合いづらく、視覚的な集中も妨げられる
このような症状は、日によって強さが変動するのも特徴です。
ある日は問題なく過ごせても、翌日は何も手につかないほど頭が働かないというような波があり、本人にも予測がつかないことが多いです。
そのため、周囲からは「怠けている」「やる気がない」と誤解されやすく、人間関係や職場での評価に悪影響を及ぼすこともあります。
また、ブレインフォグの裏には睡眠不足や慢性疲労、ストレス、目の疲れ、栄養不良など、心身の不調が隠れているケースが少なくありません。
こうした背景にある原因が解消されない限り、ブレインフォグの症状も慢性化し、社会生活に深刻な支障をきたす可能性があります。
そのため、日常の中で「最近、頭が働かない」「ミスが増えた」「人と話すのがうまくいかない」といった兆候が続いている場合は、早めに原因を見直すことが大切です。
放置するとうつ病などの精神的な不調にもつながる恐れがあるため、症状のサインに気づいたら適切な対処を行う必要があります。
ブレインフォグの主な原因

ブレインフォグの主な原因として、以下が挙げられます。
- 脳に負荷をかけること
- ストレス
- 栄養不足
- 睡眠不足・運動不足
- 抗うつ薬
ここでは上記5つの原因についてそれぞれ解説します。
脳に負荷をかけること
現代人はスマートフォンやパソコン、タブレットといったデジタル機器に長時間触れていることが多く、無意識のうちに脳に膨大な情報を送り続けています。
動画を見ているときなども、一見リラックスしているようで、脳を常に刺激し続けている状態です。
このような情報過多の状況が続くと、脳が過剰に働き続けることになり、結果として思考力や集中力が低下し、ブレインフォグの症状が現れやすくなります。
特にパソコンを使った作業が多い人や休憩せずに長時間ゲームをしている人は、脳が疲れやすいため注意が必要です。
ストレス
ストレスは自律神経のバランスを乱し、脳への血流を減少させる要因になります。
過労や人間関係のトラブル、家庭での問題などによって慢性的なストレスが蓄積すると、脳の処理能力が落ち、ブレインフォグを引き起こしやすくなります。
また、ストレスによって睡眠の質が低下したり、暴飲暴食や喫煙・飲酒などの不健康な行動が増えたりすることも、さらに脳の働きを鈍らせる原因となるでしょう。
心身ともにストレスを抱えた状態が長く続くと、ブレインフォグの慢性化につながる可能性があります。
▶ストレスとは?溜まったときに見られる症状や疾患・解消法などを紹介
栄養不足
脳の健康には、ビタミンB群、マグネシウム、オメガ3脂肪酸、鉄、亜鉛などの栄養素が必要不可欠です。
これらは神経伝達物質の合成やエネルギー代謝に関与しており、欠乏すると脳の働きが鈍くなります。
例えば、ビタミンB群が不足すると疲労感や集中力の低下が起こりやすくなります。
現代では、加工食品中心の食生活によってこれらの栄養素が不足しがちな傾向があるため、バランスの取れた食事を意識することが大切です。
睡眠不足・運動不足
ブレインフォグを引き起こす原因として、睡眠不足や運動不足が挙げられます。
質の高い睡眠は、脳の修復や老廃物の排出、記憶の整理などに欠かせません。
特にノンレム睡眠中には、脳内の不要物を取り除く機能が活性化されるとされており、このサイクルが崩れると翌朝の思考力や集中力に悪影響が出ます。
また、運動不足も脳の血流を低下させ、神経伝達物質の生成を妨げる原因となります。
適度な運動にはストレス軽減や睡眠の質の向上といった効果もあるため、日常的に体を動かす習慣を持つことが大切です。
▶なぜ寝不足だとイライラするの? 脳やホルモンなど身体に起きていること
抗うつ薬
抗うつ薬の服用中または減薬中に、ブレインフォグのような症状が出ることがあります。
これは、薬の影響で脳内の神経伝達物質のバランスが変化するためと考えられています。
しかし、ブレインフォグの症状はうつ病そのものの症状と重なる部分も多く、原因の特定が難しいのが現状です。
例えば思考が鈍くなる、集中力が落ちる、物忘れが増えるといった症状は、どちらにも共通してみられるため、専門医の判断が必要となります。
自己判断で薬の中止や変更を行うのは避け、医師に相談しましょう。
▶抗うつ薬は飲まない方がいい?副作用や種類別の特徴・対処法を解説
ブレインフォグを引き起こす可能性がある病気

ブレインフォグは病気ではなく、頭がぼんやりして思考がまとまらない、集中できないといった症状の総称です。
そのため、実際には他の病気が原因となってブレインフォグが起きていることも多く、注意が必要です。
特に精神的な疾患や神経に関わる病気、ホルモンバランスの乱れなどは、ブレインフォグの背景に潜んでいる可能性が高いといえます。
ブレインフォグを引き起こす可能性がある代表的な病気として、以下が挙げられます。
- 睡眠障害
- PMS・PMDD
- ADHD
- ASD
- 適応障害・不安障害・うつ病・双極性障害
- 物質関連障害
- 新型コロナウイルス後遺症
このように、ブレインフォグはさまざまな病気の一症状として現れることが多いため、安易に「ただの疲れ」と片付けてしまうのは危険です。
特に症状が長引く場合や日常生活に支障をきたしている場合は、医師の診察を受けることが大切です。
症状をうまく言葉にできない場合は、「集中できない」「記憶があいまいになる」「言葉が出てこない」など、具体的なエピソードを伝えると診断の手助けになります。
▶適応障害・不安障害・うつ病の違い&共通点│セルフチェックや治療法も解説
▶ADHD(注意欠如・多動症)とは?発達障害との関係や特徴、対応法を解説
ブレインフォグの治療方法

ブレインフォグの治療方法は原因によって異なります。
例えば、新型コロナウイルスの後遺症によるブレインフォグには明確な治療法が確立されていませんが、ストレスや生活習慣の乱れなどが原因の場合には対処の方向性が見えてきます。
まず基本となるのは、睡眠・食事・運動といった生活習慣の見直しです。
十分な睡眠を確保し、脳に必要な栄養素(ビタミンB群、鉄分、マグネシウム、オメガ3脂肪酸など)を取り入れることで、症状の改善が期待できます。
加えて、注目されているのがTMS治療です。
TMS治療は脳に磁気刺激を与えることで、神経ネットワークのバランスを整える治療方法です。
もともとはうつ病に対して承認されているものですが、集中力や思考力の改善効果が期待されることから、ブレインフォグにも応用されつつあります。
特にうつ症状を伴う場合に有効とされ、薬に頼らず治療できる点が評価されています。
ただし、TMS治療は専門の医療機関でのみ行われ、通院と複数回の施術が必要です。
また、ブレインフォグはうつ病や不安障害などの一症状として現れる場合もあるため、まずは精神科・心療内科での診察を受け、必要に応じて薬物療法や心理療法が必要となることもあります。
いずれにしても、症状を放置せず、原因を明らかにしたうえで適切な治療を進めることが大切です。
ブレインフォグを改善するセルフケア方法

ブレインフォグを改善するセルフケア方法として、以下が挙げられます。
- 十分な睡眠時間を確保する
- 栄養バランスの整った食事を心がける
- 水分を十分に摂取する
- 適度に運動する
- カフェインの摂取・飲酒・喫煙を控える
ここでは上記5つのセルフケア方法について解説します。
十分な睡眠時間を確保する
ブレインフォグを改善する上で大切なのが、十分な睡眠時間の確保です。
睡眠中、脳は情報の整理や老廃物の排出を行っており、このプロセスが妨げられると翌日の集中力や思考力に大きな影響を及ぼします。
特に深いノンレム睡眠中には、脳内の『グリンパティックシステム』が活性化し、神経に悪影響を及ぼす物質(アミロイドβなど)が除去されます。
適切な睡眠時間は個人差がありますが、7~9時間を目安に、毎日同じ時間に就寝・起床するのが望ましいでしょう。
また寝る直前にスマホやテレビなどのブルーライトを浴びる習慣は避け、深呼吸や軽いストレッチを取り入れると、入眠がスムーズになります。
栄養バランスの整った食事を心がける
脳の働きを支えるには、栄養バランスの取れた食事が欠かせません。
特にブレインフォグの症状が出ているときは、エネルギー不足や栄養の偏りによって、集中力や思考力がさらに低下しやすくなります。
脳に必要な主な栄養素には、ビタミンB群、鉄分、マグネシウム、オメガ3脂肪酸、亜鉛などがあり、これらは神経伝達やエネルギー代謝を支える重要な役割を担っています。
また、糖質過多やカフェイン・ジャンクフードの摂りすぎは血糖値の乱高下を招き、逆に脳のパフォーマンスを下げてしまうこともあるため注意が必要です。
食事は主食・主菜・副菜を基本として、栄養バランスの整ったメニューを心がけましょう。
水分を十分に摂取する
水分補給も、ブレインフォグ対策には欠かせません。
人間の体の約60%、そして脳の約80%は水分で構成されており、脳内の情報伝達やエネルギー生成にも水分は不可欠です。
水分が不足すると脳の活動効率が低下し、「ぼーっとする」「集中できない」「言葉が出てこない」などの症状が現れやすくなります。
特に夏場や室内での長時間作業時には、自覚がなくても水分が失われており、気づいたときには既に脱水気味になっていることもあります。
ブレインフォグを改善するためには、こまめに少量ずつ水や麦茶などを摂取するのが望ましいでしょう。
一度に大量の水を飲むより、1日を通してこまめに水分を補給する方が脳にも体にもやさしく効果的です。
また、利尿作用のあるコーヒーやアルコールは水分補給には適していないため、なるべく水を摂取するようにしましょう。
適度に運動する
運動をすると脳への血流が増え、神経伝達物質(セロトニンやドーパミンなど)の分泌が促されて思考がクリアになることが知られています。
特に有酸素運動は、ストレスホルモンの分泌を抑え、気分を前向きにする効果があります。
ブレインフォグに悩んでいるときこそ、ウォーキングやストレッチ、軽いジョギングなどを日常に取り入れるのがおすすめです。
また、運動による疲労は良質な睡眠にもつながるため、相乗的にブレインフォグの改善効果が期待できます。
無理のない範囲で少しずつ継続することが大切です。
カフェインの摂取・飲酒・喫煙を控える
カフェイン・アルコール・タバコといった刺激物は、一時的に気分をスッキリさせることがありますが、長期的には脳に悪影響を与える可能性があります。
カフェインは適量であれば集中力を高める効果がありますが、過剰に摂ると神経過敏や不眠の原因となり、結果的にブレインフォグを悪化させてしまいます。
特に午後以降の摂取は、夜間の睡眠に影響を与えるため注意が必要です。
また、アルコールも睡眠の質を下げるため、寝酒は避けた方が賢明です。
喫煙に関しては、ニコチンによる血管収縮が脳の血流を妨げ、集中力の低下や疲労感につながることがあります。
ブレインフォグの症状が続いている間は、これらの摂取量を抑えるか、一時的に控えるのが望ましいでしょう。
症状が続く場合は精神疾患の可能性も考え早めの相談を
ブレインフォグは生活習慣の見直しやセルフケアで改善が見込まれることもありますが、症状が長引く場合には、うつ病や不安障害、発達障害などの精神疾患が背景にあることも考えられます。
「いつもの疲れ」や「年齢のせい」と軽視せず、日常生活に支障が出ている場合は早めに専門医の診察を受けることが大切です。
『かもみーる』では、オンライン診療・オンラインカウンセリングサービスを提供しています。
「症状が気になるけど受診を迷っている」「受診すべきなのかわからない」といったお悩みを持つ方は、ぜひ当院まで気軽にご相談ください。
▶ カウンセラー(医師・心理士)一覧 はこちら
▶ 新規会員登録 はこちら