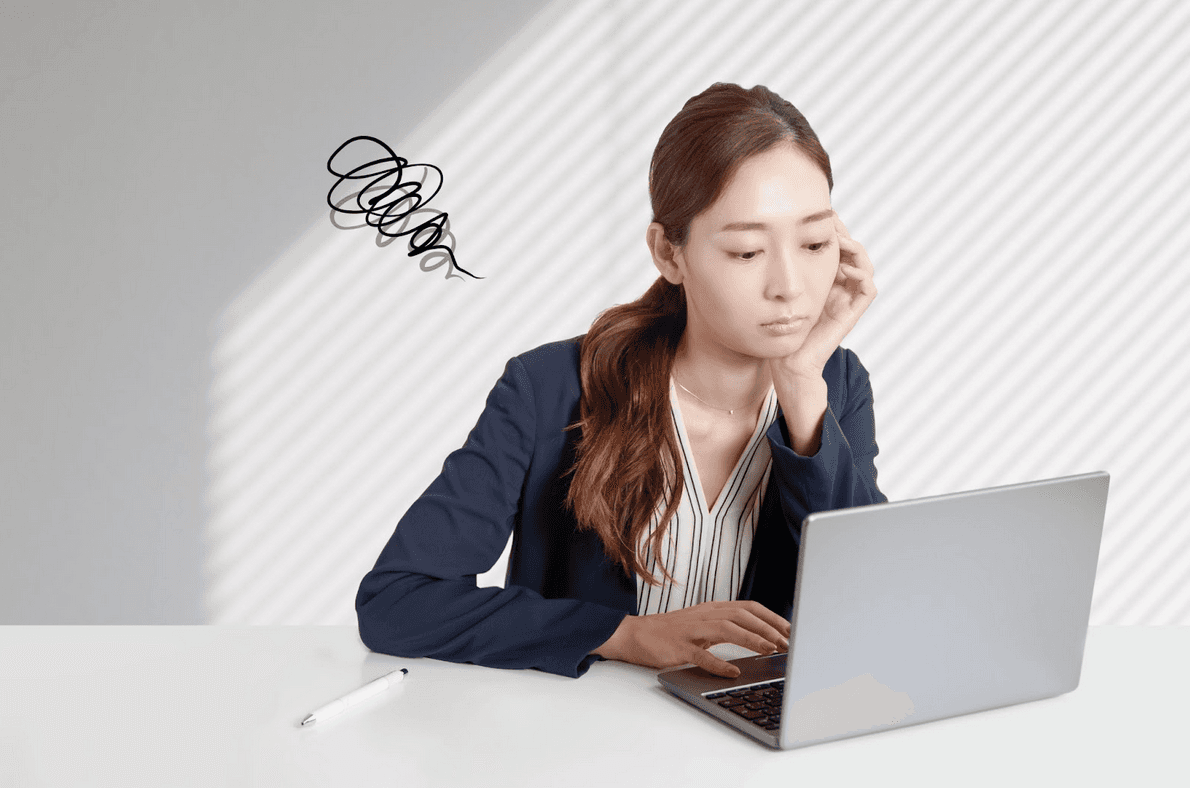仕事に集中できない、やる気が出ないといった悩みがある場合、甘えが原因のため自分で努力する必要がある、という結論に辿り着きがちです。
しかし実は「集中力がない」「注意力低下」という症状が現れる「集中できない病気」である可能性があります。
この記事では、仕事や勉強に集中できない原因や対処法、病気や障害の可能性などについて紹介します。
最近集中力がなくなった、頭に入らないなどで悩んでいる人はぜひご一読ください。
集中できない原因

まずは、仕事や学校などで集中ができない原因と思われる習慣や状況を紹介します。
自分の限界を超えた仕事量や労働時間
自分でこなせる量以上の仕事やかかる時間の長さによって、集中できなくなる、集中力が続かないなどの場合があります。
仕事量が多いと一口に言っても、以下のように状況はさまざまです。
- さまざまな仕事を並行して進めなければならない
- やることが多い、いつ終わるか分からない
- アクシデントが立て続けに発生して、自分だけでは対応しきれなくなった
- 締め切りや納期が迫っている
特に「ながら作業」は効率的に感じられますが、複数のタスクを同時に行うことで脳に過度な負担をかけるため、一つ一つの仕事に対する集中力が分散します。
仕事が許容量を超えるとモチベーションが低下することや、仕事があれこれあることも集中できない原因になります。
集中しづらい環境
自分は集中したいと思っても、周囲の環境に気が散るような要因が多い場合は、集中できない可能性があります。
例えば他人の話し声や足音、暑すぎる・寒すぎるなどの温度、視界や手の届くところにテレビやスマートフォンなど興味を引く要因があるなどです。
気が散る理由は見れば身近にたくさんあり、特に脳は新しい刺激に敏感に反応するため、無意識に注意をそらし、深い集中を妨げます。
脳のエネルギー不足
脳を働かせるためのエネルギー源はブドウ糖ですが、不足すると集中力低下を招きます。
脳のエネルギーは以下のような形で不足します。
- 朝食を食べていない、不規則な食生活など
- 過度なダイエットをしている(糖質制限)
- 糖質をエネルギーに変えるための栄養が摂れていない
- 水分不足
エネルギー源が不足すると脳の働きが悪くなるため、集中力が下がったり、注意力散漫になったりします。
睡眠不足や体調不良
睡眠不足は疲労が回復できないだけでなく、体調不良も招きます。
睡眠不足が続くと脳内にアミロイドβなどの老廃物がたくさんたまり、神経細胞の働きが鈍るため、情報処理能力が低下します。
また、体調不良は回復するために多くエネルギーが費やされるため、集中力の維持が難しくなります。
しかしこれらが原因の場合は対処法も明らかであるため、しっかり休息をとる、睡眠の質を上げるなどの判断が可能です。
悩みや不安などによるストレス
悩みや不安のためにストレスを感じると、ストレスホルモンと呼ばれている『コルチゾール』の分泌が急激に増えます。
これはストレスから身を守るための働きですが、ストレスに長期間晒されてコルチゾールが過剰に分泌されると、脳の海馬が委縮することが分かっています。
海馬の働きは、集中力や判断力、記憶などを司る重要な部位です。
また、コルチゾールの分泌は、免疫・中枢神経・代謝など身体のさまざまな機能にも影響を及ぼすことが知られています。
精神的ストレスによる海馬の萎縮や身体機能の低下は、目の前の仕事や学習に集中できなくなる原因となります。
集中できない病気や障害

仕事や勉強に集中できない原因を紹介してきましたが、これらが原因でない場合、なんらかの病気である可能性があります。
急に病気といわれると不安になるかもしれませんが、医療機関の診断によって治療だけでなく、サポートを受けられる・周囲の理解を得やすくなるなどのメリットもあります。
以下に病気や障害、治療法の一例を詳しく紹介します。ぜひ参考にして、受診について前向きに検討しましょう。
うつ病
うつ病は仕事や人間関係など日頃のストレスが原因で、脳内の神経伝達物質が減少しバランスが崩れ、引き起こされる疾患と考えられています。
うつ病の症状は以下の通りです。
- 抑うつ、気分が落ち込む
- 無気力、倦怠感
- 些細なことで不安やイライラを感じる
- 自信喪失、自分を責める
- 集中力や思考力の低下
- 眠れない
- 食欲低下、体重減少
- 午前中の調子が悪い
このような症状が2週間続いた場合、精神科や心療内科を受診しましょう。
うつ病の治療は薬物治療と精神療法・休養です。時間はかかりますが、治らない病気ではありません。
▶うつ病はどんな病気?特徴や重さごとの症状、なりやすい人の特性を紹介
注意欠陥・多動症(ADHD)
ADHDは発達障害の中の1つの疾患で、原因は遺伝や妊娠中の環境(父親の年齢や母体の健康状態・早産や低体重など)と考えられていますが、いまだにはっきり判明していません。
生まれつきに持つ特性からくる、以下のような症状が見られます。
- 目の前のことに集中力できない
- 興味があることには過集中する
- 物忘れ・忘れ物が多く、物を失くす
- 予定通りに行動できず、遅刻する
- ながら作業ができない、段取りが苦手
- 喋り過ぎるため対人関係が上手くいきづらい
- 浪費傾向がある
- 思いつきで走る、暴言を吐くなど衝動的な行動をする
- ソワソワと動いたり、ゆっくり歩けず常に走り回ったりする
大人になってから発覚する場合「きちんと振る舞えない人」とみなされることが多いですが、生まれつきの特性のためで、躾けの問題ではありません。
症状による日常生活への支障を抑えるカウンセリングや薬物治療などを治療として行いますが、集中力や発想力があるというADHDの強みを活かす方法などを探る相談も可能です。
▶ADHD(注意欠如・多動症)とは?発達障害との関係や特徴、対応法を解説
不安障害
不安障害とは、強い不安に襲われて日常生活に支障をきたす病気で、身体症状と精神症状の両方が見られます。
不安障害の種類には『社交不安障害』『全般性不安障害』『限局性不安症』『パニック障害』などがあり、症状としては以下があります。
- めまいや動悸
- 喉が詰まるような違和感
- 筋肉痛やこわばり
- 吐き気・下痢・便秘などの消化器症状
- 不安や恐怖がコントロールできない・落ち着かない
- 集中力の低下
不安障害は遺伝や環境・性格・身体的な状態などいくつかの要因が複雑に絡み合い発症すると考えられています。
治療法としては、まず薬剤を投与し症状を和らげることでカウンセリングなどに対する不安感を解消し、その後、不安障害の種類に合わせて適切な治療が行われます。
不安障害は、問題なく日常生活を送れる寛解を目指せる病気です。
▶不安障害は治るのか?自力での対処法と病院での治療方法について解説
認知機能障害
認知機能障害はいわゆる認知症ですが、65歳未満で発症する若年認知症もあり、働き盛りで発症するため家族の生活に大きな影響を与えます。
若年性認知症には原因となる疾患があり、症状の現れ方は高齢者認知症と変わりませんが、原因は身近なところでは遺伝要因の他、生活習慣病・喫煙や飲酒などがあります。
認知機能障害では以下のような認知機能が低下します。
- 集中力
- 注意力・判断力
- 記憶力
- 思考力・理解力
- 情報処理能力
- 問題解決力
若い人が認知機能障害になった場合、仕事のミスが増えたり家事が億劫になったりしても認知症とは考えない場合が多いため、診断が遅れることがあります。
病気の進行を緩やかにする薬物治療を行いますが、根本的な治療ではなく対症療法となるため、早期の治療開始が理想です。
睡眠障害
睡眠障害とは睡眠に関連した病気の総称で、入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠障害など4つのタイプがあります。
原因は複雑で、寝苦しい環境や心臓病・呼吸器疾患などの病気や、悩みや緊張からくるストレス、生活習慣などが考えられます。
睡眠障害に見られる症状は以下の通りです。
- 1ヶ月以上にわたる不眠状態
- 日中の眠気
- 倦怠感・意欲低下
- 集中力低下
- 食欲がなくなる
- 抑うつ
- めまい
- 不眠恐怖
まずは生活習慣や環境の改善を行い、効果が出ない場合に睡眠薬などの薬物治療が行われます。
睡眠薬といっても、睡眠・覚醒のリズムを整える薬、脳の過剰な覚醒を抑制する薬などが、上記の4パターンの症状や原因に応じて適切に処方されます。
薬だけでなく、神経症の治療として確立されている森田療法と呼ばれる精神療法も有効です。
慢性的な問題となりやすいため治療に時間がかかりやすいですが、適切な治療と生活習慣の見直しにより改善や完治が可能な病気です。
▶TMS治療は睡眠障害にも効果がある?原因別のアプローチ法や効果を紹介
適応障害
適応障害は、転勤や転校、離婚や引っ越し、経済的な問題や災害など、明確な出来事や環境変化でうつ病のような心身症状が現れるため、原因が解決すれば改善します。
適応障害の症状は以下の通りです。
- 抑うつ・不安
- 集中力低下・頭が働かない
- 怒り・焦り・緊張
- 攻撃的な行動
- 動悸・発汗・めまい
原因である問題を取り除けない、あるいは原因から離れることが難しい場合は、原因の受け止め方にアプローチする認知行動療法や問題解決療法などを行います。
それでも支障が大きく日常生活が十分に送れないような場合には薬物療法の選択肢もあります。
環境の調整や適応力の向上などで症状は改善され、問題が解決すれば完治は難しくない病気です。
▶適応障害について|タイプごとの特徴・発症の原因・予兆・治療法などを詳しく解説
自律神経失調症
自律神経失調症は、睡眠不足やホルモンの変化、食事や環境の変化、職場や人間関係のストレスなどをきっかけに、文字通り自律神経が失調して働きのバランスを崩した状態です。
自律神経は、心臓や血管、呼吸、消化、体温調節など、人が自分の意思で自由にできない機能を無意識のうちにコントロールしてくれる神経です。
自律神経失調症の症状の一例は以下の通りです。
- 倦怠感・疲労感
- かすみ目
- 汗をかく
- 痩せる
- イライラ・不安
- 睡眠障害
- 集中力低下
上記のような不調を感じても、さまざまな検査で異常が発見できない場合が多い疾患です。
治療では症状を抑えるための薬物を用いた対症療法や、ストレス・精神面へのカウンセリング、生活習慣の見直しなどが行われます。
長引くことが多い疾患ですが、ストレスと上手く付き合い生活習慣を整えることで症状が改善されます。
統合失調症
統合失調症はドーパミン系の神経伝達物質のバランス異常が関与していると考えられている疾患で、高血圧や糖尿病と同様の慢性疾患と位置づけられています。
原因は明確には分かっていませんが、遺伝要因に環境要因、ストレスや神経発達の脆弱性・脳の機能不全などが重なり合うことで発症すると考えられています。
統合失調症にみられる症状は以下の通りです。
- 思考の混乱・幻覚・妄想
- 不安・不眠・神経過敏
- 感情が平坦化する・口数が減る
- 意欲低下
- 不適切・奇妙な行動
- 記憶力・注意力・集中力の低下
- 情報処理能力・遂行機能の低下
前兆期→急性期→回復期→安定期・慢性期という段階を経て進んでいくため、段階にあった治療法と支援が重要となります。
薬物療法と精神療法・リハビリテーションを中心に行われますが、統合失調症は慢性化するため、再発を防ぎながらの長期的な視点で計画が立てられます。
症状をコントロールしながら生活していくことを目指して治療しますが、適切な治療によって安定した生活が送れるようになる人は多いです。
甲状腺機能低下症
甲状腺機能低下症とは、首にある臓器である甲状腺が分泌している甲状腺ホルモンの作用が低下し、体内でさまざまな機能低下を起こす疾患です。
原因は自己免疫疾患の橋本病や、脳腫瘍や薬剤の作用などによる中枢性甲状腺機能低下症、指定難病の甲状腺ホルモン不応症などの疾患によります。
甲状腺機能低下症の症状は以下の通りです。
- 寒がりになった
- 皮膚の乾燥
- 物忘れ
- 意欲・集中力低下
- 肥満・むくみ・便秘
- 脱毛
- 声がかすれる
治療法としては一般的に甲状腺ホルモンを補う補充方法が行われますが、少量から始めて定期的に様子をみながら投与量を増やしていきます。
ホルモンの維持量に達するまで数ヶ月かかるため、治療は長くかかります。
甲状腺機能低下症は多くの場合、甲状腺ホルモン補充療法によりおちついた日常生活を送れるようになる疾患です。
集中できない症状への対処法

集中できない症状への対処法を紹介します。
病気を疑って受診することを検討する前に、ぜひ以下のような改善策を心がけてみてください。
- 休憩を挟んで気分転換を取り入れながら仕事を進める
- 気が散る要因がなく集中しやすい環境かどうかを見直す
- 脳の栄養であるブドウ糖・ビタミンB群・オメガ3脂肪酸を摂取できるよう食生活を見直す
- 睡眠不足は集中できない大きな原因のひとつのため、十分な質の良い睡眠をしっかりとる
- ゴールが見えない場合は集中力が低下しやすいため、スケジュールや効率を見直す
- 原因が病気の場合は受診・治療して症状の軽減を図る
パフォーマンスが低下する要因に働きかけてみることで、集中できるようになる可能性があります。
これらの方法を試してみても改善がみられない場合は、専門家に相談しましょう。
病気が原因の場合は治療が必要です
集中できない原因がもし病気だった場合、早めに治療を開始する必要があります。
自分の甘えだと思ったり様子を見たりせず、早めに行動に移しましょう。
『かもみーる』は、医師監修のオンラインカウンセリングサービスを提供しています。
自分でできる改善策と並行しながらオンラインで相談することは、効率のいい対処法です。
医師のほか、臨床心理士や公認心理士を中心とした有資格者がお話を伺います。ぜひお気軽にご相談ください。
▶カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶新規会員登録はこちら