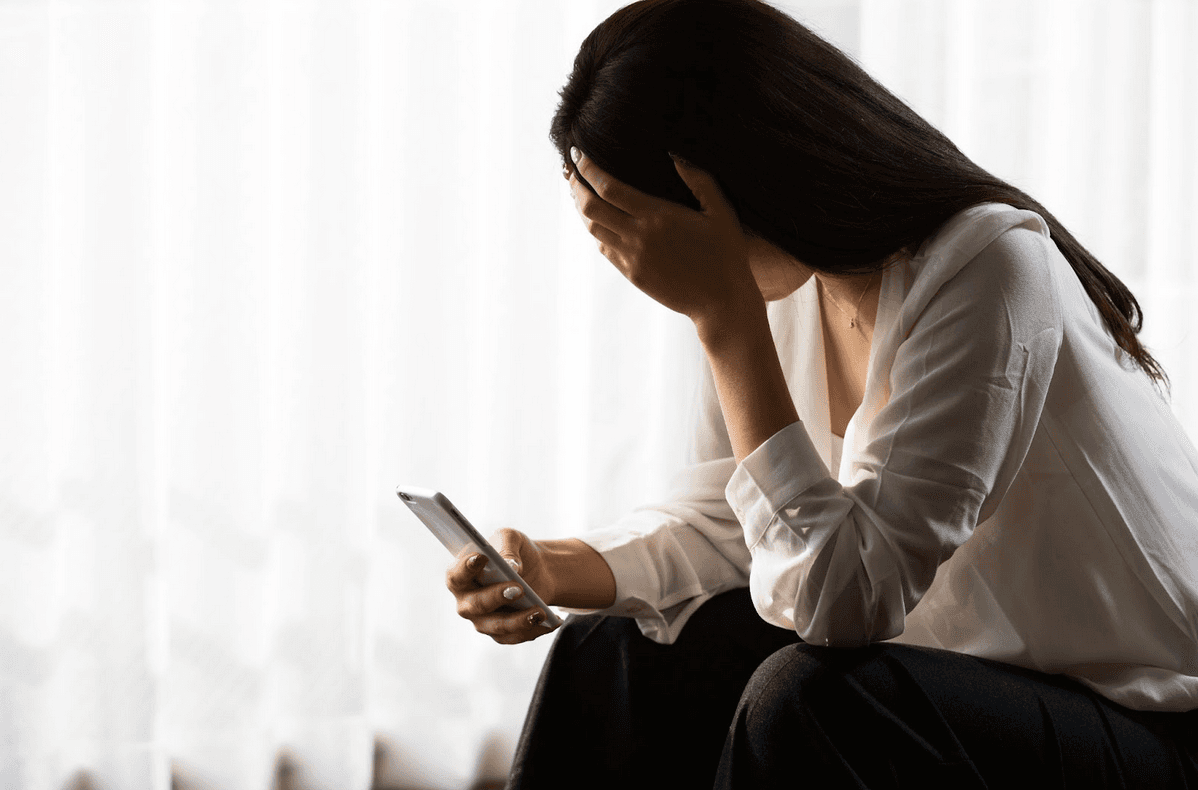「心がざわついて落ち着かない」「何かに追われているようで気が焦る」と感じたことのある人は少なくないでしょう。
こうした不安やイライラが入り混じった状態を『焦燥感』と呼びます。
焦燥感は一時的なものであれば大きな問題にはなりませんが、持続すると集中力の低下や不眠、さらには心の病気につながる可能性もあるため注意が必要です。
この記事では、焦燥感が起こる原因について詳しく解説します。
考えられる病気や対処法などもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
焦燥感とは
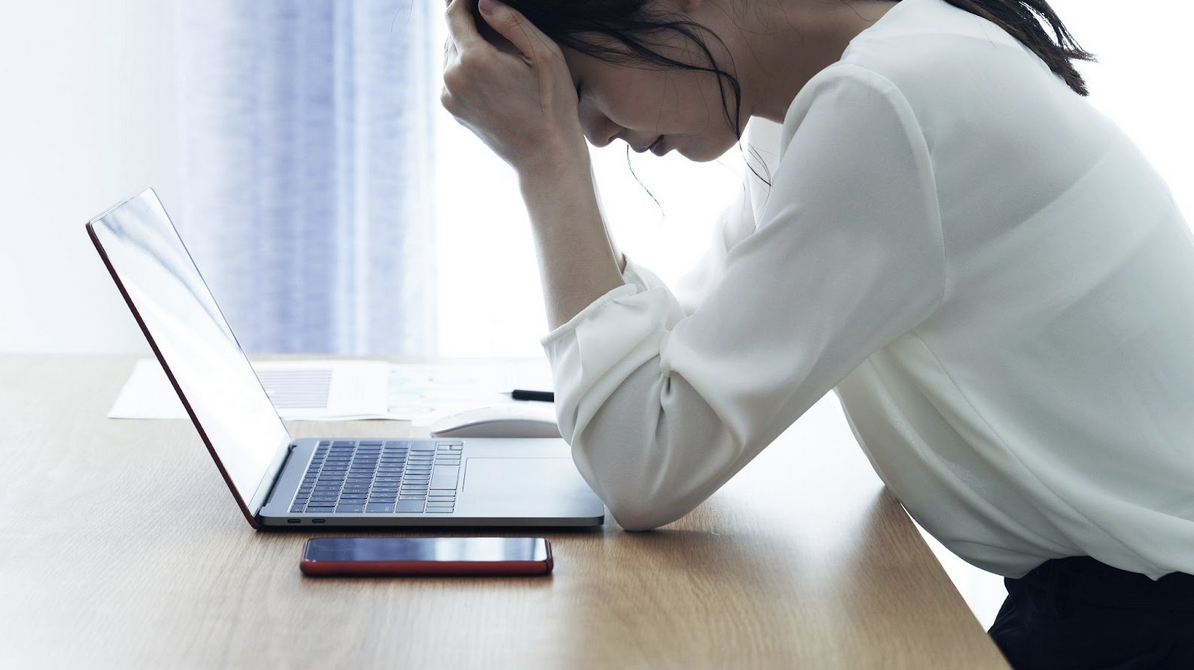
焦燥感とは、強い不安や焦り、苛立ちが重なり、心が落ち着かず、常に何かに追われているような状態を指します。
ただ単に「焦っている」とは異なり、精神的な圧迫感やストレスを伴うことが特徴です。
例えば何か大事なことを忘れている気がする、時間が足りないと感じて急かされる、上手くいかない苛立ちで気分が不安定になるといった状態が挙げられます。
焦燥感は精神的な緊張が長く続いたときや、過度なプレッシャーがかかっているときによく表れるものです。
この状態になると集中力が低下したり、判断ミスをしたり、感情のコントロールが難しくなったりと、日常生活にも支障が出やすくなります。
さらに焦燥感が続くことで自律神経のバランスが崩れ、動悸や発汗、胃の不快感、睡眠障害など身体的な症状が表れることもあります。
こうした症状が慢性化すると、うつ病や不安障害といった精神的な疾患につながる可能性もあるため注意が必要です。
焦燥感の主な原因

焦燥感の主な原因として、以下が挙げられます。
- 理想と現実にギャップがある
- やるべきことに追われている
- 他人と自分を比べてしまう
- ストレス
- 疲労・睡眠不足
- ホルモンバランスの乱れ
- 精神疾患
ここでは上記の原因についてそれぞれ解説します。
理想と現実にギャップがある
焦燥感の原因として多く見られるのが、自分の理想と現実との間に大きなギャップがある場合です。
「本当はもっと早く昇進しているはずだった」「今頃は結婚していたかった」といったような人生設計が思い通りに進んでいないと、焦りや不安が強まります。
こうしたギャップは人生設計のみでなく、日常的な場面でも起こります。
例えば「今日はここまで終わらせるつもりだったのに全然進んでいない」など、小さなつまずきが積み重なることで自己否定に繋がり、精神的な余裕を失いやすくなるのです。
理想を持つこと自体は悪くありませんが、現実とのバランスを見ながら軌道修正していく柔軟さも必要です。
やるべきことに追われている
日々のタスクや責任が多すぎると、やるべきことに追われて常に時間に追い詰められている感覚が強くなります。
このような状況では、「早くやらなきゃ」「終わらせないとまずい」という思いが焦燥感として表れます。
特に自分のやりたいことよりも義務や責任が優先される場面が多くなると、ストレスが蓄積し、心に余裕を持てなくなってしまうのです。
また、「締め切りが迫っているのに集中できない」といった状態が続くと、自分を責める気持ちが生まれ、さらに不安や苛立ちが増していく悪循環に陥ることもあります。
こまめなタスク整理や優先順位の見直しが有効です。
他人と自分を比べてしまう
他人と自分を比較することが、焦燥感の原因となるケースも少なくありません。
「友達はもう結婚している」「同期は昇進しているのに自分はまだ」といった周囲の状況を見て、自分の立ち位置に焦りを感じてしまうのです。
特にSNSでは他人の成功や楽しそうな様子が強調されやすいため、自分が取り残されたように感じてしまうこともあります。
比較を続けていると、次第に自己否定感や劣等感が強まり、自信を失う原因になります。
他人と比べるのではなく、自分の目標に意識を向けることが大切です。
ストレス
慢性的なストレスも、焦燥感を引き起こす大きな要因です。
職場での人間関係、家庭での問題、経済的な不安など、生活の中にはストレスのもととなるものが多く存在しています。
こうしたストレスが長期間にわたり蓄積すると、脳や自律神経が常に緊張状態となり、ちょっとしたことでもイライラしたり、落ち着きがなくなったりといった症状が表れます。
さらにストレスによって睡眠の質が下がったり、疲労が抜けにくくなったりすることで、焦燥感はますます強まってしまうのです。
ストレスと上手に向き合う工夫が必要になります。
疲労・睡眠不足
身体的な疲労や睡眠不足は、精神面にも大きな影響を与えます。
十分な休息がとれていないと、集中力や判断力が低下し、物事が思うように進まず「やらなきゃいけないのにできない」という葛藤が生じます。
その結果、焦りや不安が強まり、焦燥感へと繋がってしまうのです。
また、慢性的な睡眠不足は自律神経のバランスを乱し、気分が落ち込みやすくなったり、感情のコントロールがしづらくなったりすることもあります。
まずは規則正しい生活と質の高い睡眠を意識することが大切です。
ホルモンバランスの乱れ
ホルモンバランスの変化も、焦燥感の一因になることがあります。
特に女性では月経前症候群(PMS)や更年期障害の時期に、不安感やイライラ、落ち着かなさといった症状が表れやすくなるのです。
また甲状腺機能の異常がある場合も、情緒の不安定さや焦燥感を感じやすくなる傾向があります。
こうしたホルモンの影響は自分の意志や努力だけでコントロールしにくいため、症状がつらいと感じる場合は、医療機関を受診して適切な治療やアドバイスを受けることが大切です。
精神疾患
焦燥感はうつ病や不安障害といった精神疾患の症状として表れることもあります。
これらの病気では根拠のない不安や焦りが起こり、落ち着かない、イライラする、胸がざわつくといった感覚が強くなります。
また軽度の状態では見過ごされがちですが、本人にとっては日常生活に支障をきたすほどの苦痛となる場合もあるため、注意が必要です。
焦燥感が長期間続いたり、日常生活に支障を感じたりする場合は、精神科や心療内科など専門の医療機関で相談することが大切です。
焦燥感が見られるときに考えられる精神疾患

焦燥感が見られるときに考えられる精神疾患として、以下が挙げられます。
- うつ病
- 躁うつ病(双極性障害)
- 全般性不安障害
- パニック障害
- 強迫性障害
- 適応障害
- 摂食障害
- 注意欠如・多動症(ADHD)
ここでは上記の精神疾患についてそれぞれ解説します。
うつ病
うつ病では、気分の落ち込みや興味・意欲の低下に加えて、焦燥感が強く出ることがあります。
特に『焦燥性うつ病』と呼ばれるタイプでは、落ち着きのなさやイライラが目立ち、そわそわと無駄に動き回る、何かしていないと不安になるといった症状が見られます。
頭では休みたいと思っていても、体や心がじっとしていられず、疲れがたまっていく悪循環に陥ることも少なくありません。
うつ病に見られる焦燥感は放置すると症状が悪化しやすいため、早めに医療機関を受診することが大切です。
躁うつ病(双極性障害)
双極性障害は、気分が高揚する『躁状態』と、気分が落ち込む『うつ状態』を繰り返す精神疾患です。
躁状態では、エネルギーにあふれ、考えが次々と浮かんできて行動が止まらなくなり、それに伴って焦燥感や衝動性が強まる傾向があります。
一方でうつ状態に入ると、何も手につかないのに「何かをしなければ」と焦る気持ちに追われ、精神的に追い詰められるケースもあります。
特に躁と鬱が入り混じる『混合状態』では、焦燥感が顕著になり、情緒の不安定さが強まるため、周囲のサポートと適切な治療が不可欠です。
▶うつ病と双極性障害(躁うつ病)の違いは?症状・原因・治療法とセルフチェックリスト
全般性不安障害
全般性不安障害は、明確な理由がなくても慢性的な不安が続く状態になる精神疾患です。
この疾患では、あらゆる出来事に対して過度な心配や緊張感を抱きやすく、それに伴い焦燥感も強く表れます。
例えば「将来が不安」「ミスをしたらどうしよう」といった思考が頭から離れず、常に心がざわついた状態になってしまいます。
筋肉のこわばりや動悸、消化不良などの身体症状が出ることも珍しくありません。
不安と焦燥感が慢性化すると、仕事や家庭生活にも影響が出やすいため、早期の治療が勧められます。
▶不安障害の種類別の症状・診断基準┃セルフチェックや治療法も解説
パニック障害
パニック障害は、突然強い不安や恐怖が襲ってくる『パニック発作』を繰り返す精神疾患です。
発作中は動悸や息苦しさ、めまいなどの身体症状とともに、「このまま死ぬのではないか」という強い恐怖が伴い、激しい焦燥感が表れます。
さらに、また発作が起きるのではないかという『予期不安』により、人混みや閉ざされた空間を避けるようになり、生活範囲が狭くなることもあります。
このように焦燥感は発作時だけでなく、日常的な不安と結びついて慢性的に起こるため、早めに治療を受けることが大切です。
▶パニック障害になりやすい人の特徴│性格・年代・環境や遺伝など徹底解説!セルフチェックも
強迫性障害
強迫性障害は、自分でも不合理と分かっていながら、頭から離れない『強迫観念』と、それを打ち消すための『強迫行為』が繰り返される精神疾患です。
例えば「手に菌がついているのでは」と不安になり、何度も手を洗うといった行動が典型例です。
強迫観念を抑えようとしたり、強迫行為が中断されたときには、強い焦燥感やイライラ、不安が生じます。
この焦燥感は日常生活に大きな支障を及ぼし、時間や労力の浪費にもつながるため、早期段階でのカウンセリングや薬物療法が推奨されます。
▶強迫性障害は何科を受診?精神科・心療内科の特徴と選び方を解説
適応障害
適応障害は、環境の変化やストレスに適応できず、精神的な不調をきたす状態です。
転職、転居、離婚、学校の入学など、ライフイベントによる心理的ストレスが引き金となり、抑うつ気分や不安、焦燥感が表れることがあります。
「どうしてもうまく馴染めない」「頑張っても空回りしてしまう」といった苦しさが続くと、焦りやイライラが増し、日常生活のパフォーマンスが低下してしまいます。
適応障害の多くは一時的なものであり、環境への支援やカウンセリングによって回復が見込める疾患です。
▶適応障害とは?再発率や兆候・繰り返さないための対策・復職時の注意点を解説
摂食障害
摂食障害は食事に関する異常が続く疾患で、主に『拒食症(神経性やせ症)』や『過食症(神経性過食症)』が含まれます。
これらは食事や体重、体型への強いこだわりが精神的ストレスとなって表れる疾患で、食行動の異常とともに焦燥感が顕著に見られることがあります。
「もっと痩せなければ」といった思考が常に頭を占めており、それに対する焦りや不安が精神的な苦痛を増幅させてしまうのです。
自己評価の低さや人間関係の悩みが背景にあることも多いため、専門的な治療と心理的支援が必要とされます。
▶強迫性障害と摂食障害は併発することがある!診断・治療方法について解説
注意欠如・多動症(ADHD)
ADHDは、不注意・多動性・衝動性を主な特徴とする発達障害です。
特に成人期のADHDでは、日常生活におけるスケジュール管理やタスク遂行の困難さから、焦燥感が強く出ることがあります。
「やるべきことは分かっているのに進まない」「物事に集中できず空回りする」といった状況が続くことで、自己否定感やイライラが蓄積され、焦燥感が強まることがあるのです。
また、ADHDは他の精神疾患の併存リスクが高く、うつ病や不安障害などとともに焦燥感が複雑に絡み合うケースもあります。
適切な診断と支援によって症状の改善が期待できます。
▶ADHD(注意欠如・多動症)とは?発達障害との関係や特徴、対応法を解説
焦燥感や不安感があるときの対処法

焦燥感や不安があるときの対処法として、以下が挙げられます。
- しっかり休養をとる
- 深呼吸法を取り入れる
- マインドフルネス瞑想をする
- 適度に運動する
- やるべきことや不安を整理する
- 淡々と目の前の課題に取り組む
- 他人と比較することをやめる
- 不安につながる情報を遮断する
- 医療機関を受診する
焦燥感は睡眠不足や過労などが引き金になることが多いため、まずはしっかりと休養を取りましょう。
深呼吸法やマインドフルネス瞑想なども、心身を落ち着けるのに役立ちます。
上記の対処法を実践しても改善が見られない場合は、早めに精神科や心療内科などの医療機関を受診しましょう。
心がそわそわとして落ち着かないときは医療機関の受診も検討しましょう
焦燥感は、誰にでも起こりうる心の不調の一つです。
休息をとったり不安を整理したりといったセルフケアで改善することもありますが、症状が続く場合や日常生活に支障が出ている場合には注意が必要です。
精神疾患が原因で焦燥感が表れている場合もあるため、無理せず、早めに医療機関を受診しましょう。
かもみーるでは、医師監修のオンラインカウンセリングサービスを提供しています。
「医療機関の受診を迷っている」という方の相談も受け付けているため、ぜひ気軽にご連絡ください。
▶︎カウンセラー(医師・心理士)一覧はこちら
▶︎新規会員登録はこちら